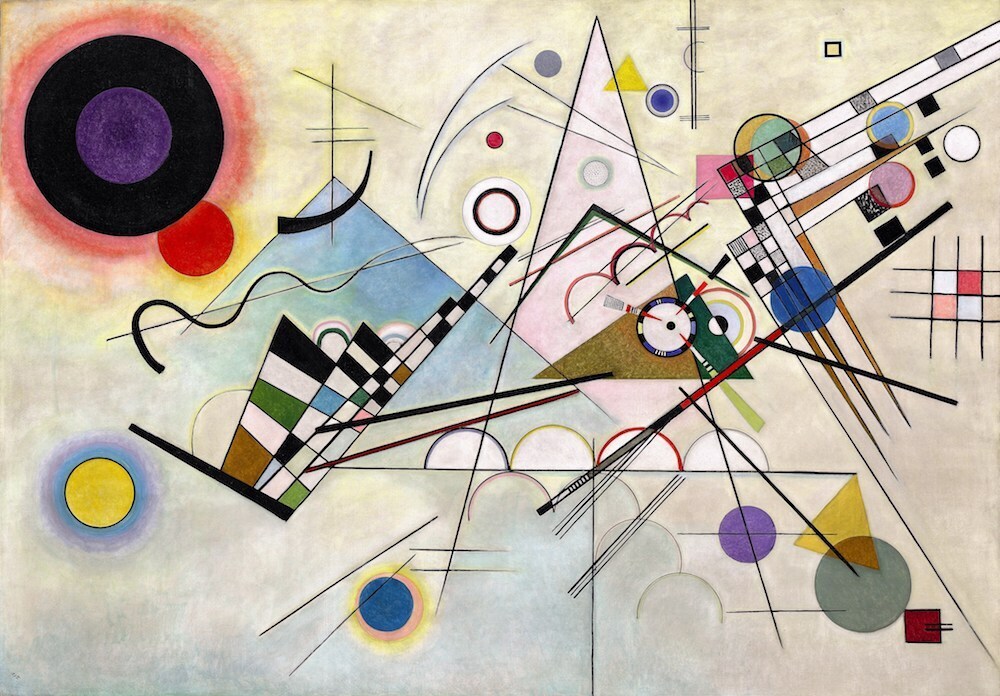
「AI業界のエバンジェリストevangelist」
少し前から「新しい技術」について説明してくれる人を「エヴァンジェリスト」と自称・他称するらしい。
しかし「説明してくる人」ではなく、「エヴァンジェリスト」であるから、ありがたい「福音」を伝道してくれる(してあげる)人というニュアンスがあるのだろう。
つまり、AI教ないしはデジタル教という宗教を「伝道」してくれる、という訳だ。
ま、この写真でI'm evangelist と黒地に青で書いたTシャツを着ている人が、伝道者なのだろう。それにしても随分「俗世」の香りがする気がするが。
しかし、この「伝道師」、AI搭載の「自律型致死兵器」システムのことは何も教えてくれないだろう。
ヴィスコンティ自身は、13世紀にはミラノの支配者であったヴィスコンティ家の傍流にあたる公爵家の出身。
ヴィスコンティ家はローマ教皇グレゴリウス10世を出すことでミラノの支配を確たるものとする。
しかし、盛期ルネサンス期には傭兵隊長出身のスフォルツァ家にミラノの支配権を奪われる。かのレオナルドのパトロンとなったのが2代目のルドヴィーゴ・スファルツァ(通称イル・モロ)。
ヴィスコンティ自身はWWIIの際、反ファシズム・レジスタンスに参加する過程でイタリア共産党に入党。その点ではやはり貴族出身でありながら、第5代PCI書記長となったE.ベルリンゲルと近い軌跡と言える。
ただし、ヴィスコンティ自身はバイ・セクシュアルであることを公言(イタリアの貴族階級では珍しくない)。
戦後の王政廃止の国民投票の際には、王を中心とする貴族階級の「性的倒錯」が廃止側の大衆動員の旗になったので、ヴィスコンティ自身は内心葛藤を感じながらも、尚「王政廃止」に一票を投じた。
『郵便配達は二度ベルを鳴らす』、『揺れる大地』など初期のネオリアリズモ的なスタイルから、PCI脱党後、『山猫』、『ルードヴィヒ』などの絢爛豪華な「滅びの美学」へと傾斜。
個人的には両者の接点となる『若者のすべて』が最高傑作だと感じる。
L.ヴィスコンティ『夏の嵐』(1954)
イタリア統一戦争の最中の、「イタリア統一」を支援するヴェネチィアの伯爵夫人とオーストリア青年将校の「敵同士」の「不倫」をベースとした、オペラ的メロ・ドラマ。
しかし、今見ると、俗物そのもの夫に満足できない伯爵夫人が、だからといって、体育会系の「頭の悪いアメリカ白人」にしか見えない青年将校に何故「魅かれるのか」が全くわからない。
と思ったら、将校を演じる俳優は米国人だった(ちなみにヒッチコックの『見知らぬ乗客』では被害者の有名テニス選手役、これはピッタリだった)。
それにしても、この将校、「政治」に何の幻想も抱けない、滅びゆく、洗練されたハプスブルク・オーストリアの美学を体現する位置を占めることが、最後の場面でわかるのだが、途中まであまりにもがっついた「ゴミ」なので、「滅びの美学」が宙に浮いてしまう。名前は音楽家G.マーラーから「マーラー中尉」としてあるのだが、「女を騙して金を貢がせる」ことしか頭にない。
このテーマだと、同じヴェネツィアを舞台にした「ヴェニスに死す」(マーラーと思しき主人公)の方がまだいい。
また「何も変えないためにすべてをかえた振りをする」というランペドーザの引用をB.ランカスターが呟く『山猫』は、さらにいい。
「オルタナティヴ」という言葉の投資会社による簒奪
下の日経一面広告、米の投資運用会社ブラックストーンの「オルタナティヴ」投資への呼びかけ。では大和証券が窓口となる。
ブラックストーンは共にリーマン・ブラザーズCEOを務めたピーターセン(故人)とシュバルツマンによって1985年に設立。シュバルツマンはイェール大の秘密結社でG.W.ブッシュと同期。この結社の卒業生は「ボーイズマン」と呼ばれ、歴代CIA長官はOB。
ウェビナーと称する講演会広告の文言がおもしろい。
「不確実性の高い投資環境における、プライベート・クレジット(直接投資)の潜在的な優位性に迫る」
なかなの修辞的と言えるかもしれない(ただし下品だが)。
最高投資ストラテジスト(戦略家)なる男と日本責任者の女性が解説してくれるらしい。
先ほどの修辞、要するに「リスク」が高いが、当たれば「大きい」と言っているだけ。「当たる」=「顕在化」。潜在性・顕在性というアリストテレス以来の哲学用語、こうも使えるのかー。
またケイマン籍であることを堂々と謳っているから「脱税」を前提。「プライベート・クレジット」とは非公開での投資。これを「オルタナティブ」投資と呼ぶ。要は一時世界をお騒がせした「ヘッジファンド」への超富裕層への勧誘用語。
いやはや。
「教養の再生のためにー危機の時代の想像力」加藤周一・ノーマ・フィールド、徐京植(影書房)
「戦争が絶えず、シニシズムが蔓延し、知性や理性、道徳性への信頼が脅かされている時代」という帯の文字、今年のものかと勘違いしそうになるが、2005年のもの。
しかし、韓国で収攬されている兄弟の釈放運動を通して、長く在日朝鮮人の運動を関わってきた徐京植さんが対話相手に、21世紀において最後の「戦後民主主義」者とも言える加藤周一さんと小林多喜二の研究者、『天皇の逝く国で』のノーマ・フィールドさんを選んだのは興味深い。
私が博士課程の時、ノーマさんの指導学生で米上院議員の息子さんと言う人が、1920年代の日本と朝鮮のプロレタリア文学運動の比較というテーマで在日していた。(韓国にもしばらくいた)。これは米国の東アジア研究の長所。本人も日本語と朝鮮語、両方できた。このまさに「トランスナショナル」な研究テーマ、日本の近代文学研究者にはかなり難しい。ま、現在はプロレタリア文学の研究者自体ほとんどいないのだが。
そう言えば、その人、ルームメイトは「CIA勤務」と言っていた。表向き「何の仕事をしているのは知らない」とも。こういうことは米上流階級の子弟にはよくあることらしい。
フローラ・トリスタンー19世紀の社会主義フェミニスト
フローラ・トリスタンは後期印象派の画家P.ゴーギャンの祖母。
19世紀前半の作家、社会主義者、フェミニストでもあります。
アステカ最後の皇帝の血を引く父をもつフローラは、フランスとペルーを往復。その経験を基に国際主義的な社会主義運動を構想し、C.フーリエとも協力します。
世代的には英国のメアリ・ウルンストンクラフトの娘メアリー・シェリー(『フランケンシュタイン』の著者、P.シェリーの妻)と同時期、ということになります。
ノーベル賞作家のバルガス・リョサ(政治家としてはろくでなしだが)が『楽園への道』でゴーギャンとフローラをともに主人公としているために、一般にも広く知られるようになりました。
フランスでは現在、リセで教えられる19世紀の大作家の一人となっていますが、日本ではどれくらい知られているのだろう?
フローラのボルドーに墓碑銘には、「自由・平等・友愛・連帯」が刻まれています。『労働者連合』の著者フローラ・トリスタンへの追悼碑として。
『古書発見 女たちの本を追って』久保覚(影書房)
ー本は、私たちの中にある凍った海を砕く斧でなければならない
-F.カフカ
著者の久保覚さんは『花田清輝全集』を事実上一人で完成させた名編集者。また在日コリアンとして朝鮮芸能史研究者でもありました。
本書は久保さんも関わった生活クラブ生協の『本の花束』に書いた書評エッセイをまとめたもの。
対象となっているのはすべて女性の書いた本です。
レィチェル・カーソン『われらをめぐる海』、イザドラ・ダンカン『わが生涯』、ルイーズ・ミシェル『パリ・コミューン』、ビリー・ホリディ『奇妙な果実』、ローザ・ルクセンブルク『ロシア革命論』、F.サガン『サラ・ベルナール』など。
日本人・朝鮮人としては崔承喜『私の自叙伝』、高井としお『わたしの「女工哀史」、幸田文『ちぎれ雲』、朴壽南『もう一つのヒロシマー朝鮮人韓国人被爆者の証言』、石牟礼道子『苦界浄土』、富山妙子『炭鉱夫と私』などなど。
S.ソンタグに関するついてのエッセイでは次のような言葉があります。「一見リアリスティックに見えて、実は高見から他人の努力をせせら笑っているに過ぎない、冷笑主義的対応ほど不潔なものはありません。」
この言葉、現代を真っ直ぐに射貫いている、と言えるのではないでしょうか?
日本と朝鮮半島の関係は、明治の初期から一方的な侵略・植民地化の歴史でした。
また日本国憲法制定の際には「国籍条項」が入れられることで、それまで「日本国籍」を持っていた朝鮮人・中国人が日本人から「排除」される準備が法制官僚によってなされます。
サン・フランシスコ講和条約とともに日本という「国家」は形式上独立しましたが、在日朝鮮人・中国人は国籍を失います。
また朝鮮半島では戦争で分断され、韓国籍を有しない朝鮮人の方も多く生まれます。
この他阪神教育闘争など、戦後の在日朝鮮人の歴史への入門として徐京植さんの下の本は、とても有益だと思います。はじめて徐さんの本を読む「日本人」の方にはやや「苦しく」なる箇所もあるでしょうけれども。それでも徐さんの本の中では「苦しくない」方だと思います。
フランス現代思想とポストコロニアル、あるいはフランス現代思想とマイノリティを語る方には是非読んでもらいたい。
おそらく、日本の80年代的なポストモダニズムが全く植民地支配の責任から眼を背けていたことが、自らの経験の喚起とともに理解できるでしょう。
尚、日本と朝鮮半島の関係はフランス・ドイツの二大国の関係とは異なります。フランスとアルジェリアの関係に相似と言えるでしょう。
G.ドゥルーズと「シャトーブリアンからの手紙」
「シャトーブリアンからの手紙」とは1941年ヴィシー・ナチに対するレジスタンスに参加した17歳の少年ギ・モケが仏警察に逮捕、海辺の街「シャトートブリアン」の収容所から銃殺の前日、母に書いた手紙のこと。これは涙なしには読めない。
17歳のギの処刑にあたってはド・ゴールがロンドンから追悼を、チャーチルとルーズベルトはそれぞれ非難を発表。
この事件をシュルレアリストにしてコミュニストとなったL.アラゴンは地下出版(Minuit)にて『殉教者の証言』として発表。
さて、この手紙2007年右派のサルコジ大統領が「共和国」を讃える詩としてギの銃殺の日、リセで歌うように法制化、その際左派は批判。マクロン与党が「共和国、前進」であるように、WWII以後は右派が「共和国」を掲げます(これが日本と政治軸がずれてわかりにくい所。)
しかしこうした政治的利用とは別にフランス人の多くは「シャトーブリアンからの手紙」を知っています。
ところで、実は哲学者G.ドゥルーズはこのギ・モケと同じクラスだった。また1944年23歳だったジルの兄ジョルジュ・ドゥルーズはレジスタンスに参加した廉で逮捕、ブーヘンヴァルト収容所に移送途中死亡。ジルの記憶には「英雄の兄」として刻まれます。
フォードがアイリッシュ、キャプラはシチリア系イタリア人。W.ワイラーはアルザスのユダヤ人でした。
ワイラーは1942年にドイツの空爆に抵抗する英国を描いた『ミニヴァ―夫人』でアカデミー賞監督賞・作品賞を受賞。その後、欧州大陸の航空戦を撮影。その際、聴覚障害となり、片耳は完全に聞こえなくなります。またWWIIに参加した黒人兵のドキュメンタリーも撮影します。
しかし、ミュルーズのワイラーの親族は全員ナチスによって殺害。
ワイラーの1946年『我らが生涯の最良の年』では復員兵たちの困難な「社会復帰」を描いています。片腕を失くしたもの、出征中に妻に出奔された者、PTSDに苦しむ者、職が見つからない者などなど。
ワイラーは戦時撮影に携わった監督の中で最も「赤狩り」に持続的に抵抗します。
いわゆる「ハリウッド・テン」の援護グループの世話人となり、『ローマの休日』ではD.トランボ、『友情ある説得』ではM.ウィルソン(「陽の当たる場所」、「戦場にかける橋」、「猿の惑星」)と「ブラックリスト」の脚本家を採用。前者はアカデミー賞。後者はカンヌ映画祭パルムドールを獲得。
しかし、『黄昏』は「レッド・パージ」の暗い時期を反映しており、商業的には失敗。しかし芸術的にはハリウッドの「文法」を逸脱した名画。
WWII中の戦場撮影班の責任者の一人はシチリア系移民のF.キャプラです。
キャプラは1939年に『スミス都に行く』を撮ります。これは地方の政治家のダム建設をめぐる不正、とそれと戦う「素朴なアメリカ人」(J.スチュアート)という典型的な「ニューディール」映画。
当初は脚本家が共産主義者であり、内容が「反米的」である、として上映禁止の可能性大、だったのですが、WWII勃発により、ニューディール+反ファシズムに揺り戻しが起こり、ぎりぎり上映できたものです。
「フィリバスター(議事妨害)」と言う言葉、日本では安倍政権の頃からポピュラーになったように感じますが、連邦議会で追い詰められたJ.スチュアートが最後の「あがき」として行うのが「フィリバスター」です。
そして日を跨ぎながら「フィリバスター」を続け、疲労困憊し今や倒れんとするところに、「デウス・エクス・マキーナ」が訪れ、相手側の「不正」は暴かれる、というストーリー。この時期の米英が、基本最後はHappy endが規則。
この頃は保守のJ.フォードでさえニューディール映画『怒りの葡萄』を撮りました。
しかし、ハリウッドのニューディール派はWWII後の「赤狩り」によって厳しい立場に追い込まれていきます。
『駅馬車』や『怒りの葡萄』で知られるアイリッシュ系の映画監督J.フォードは、WWII中海軍の戦時撮影班のリーダーとなり、ミッドウェイ海戦を現場で撮影、その際日本の戦闘機の機銃掃射で左腕を負傷。その障害は生涯続きます。
またフォードは日本では「玉砕」第一号で知られるアリューシャン列島の戦闘も現場で撮影。
これは米軍兵士の死傷者もフィルムに収められていたため、公開は見送られます。
ここに一つのエピソードがあります。フォードが現場撮影したフィルムを軍上層部に見せた際のこと。
映写が始まると、軍高官たちは一人去り、二人去りし「10分程でフォードだけ」になった。
フォードはこのエピソードを好んで語り、軍上層部は「現場」の戦場について「全くの無知」であることを強調しました。
フォード自身も戦後長くPTSDに苦しみました。超タカ派のJ.ウェインを可愛がってはおり、兵役経験なしのジョンを戦争映画の主役に抜擢はしましたが、「敬礼の仕方からしてなっていない」と罵倒し続け、その後「泣き崩れる」こともしばしばだったそうです。
フォード以外にもW.ワイラー、F.キャプラ、G.スティーブンス、J.ヒューストンがWWIIの戦時撮影に参加。この経験は4人の人生と映画を大きく変えていきます。
訂正と「戦間期の精神」、そして『勉強の哲学』の著者、千葉さんについて
『シュルレアリスム宣言』(正)
尚、日本のシュルレアリスム研究はブルトンとアラゴンがWWIの際、共に医学者として「地獄の西部戦線」に従事したこととシュルレアリスムの「(反)美学」の関係にほとんど着目しない。「西部戦線」では「人間の尊厳」、「生命の有機的統一」などは、霰のような砲弾の嵐によって、文字通り「バラバラ」の肉片へと砕け散っていたのです。
これこそがまさに「シュール」レアリスムたる所以。単なる「言語遊戯」ではない。この感覚がアルトーの「器官なき身体」を通じて『アンチ・オイディプス』にまで至る。
B.ウルフ(誤)
V.ウルフ(正)
『ダロウェイ夫人』かつては「意識の流れ」という小説手法の新技法の面から論じられた。
しかし内容的にはPTSD(友人の爆死のフラッシュ・バック)に苦しむセプティマスの飛び降り自殺とダロウェイの内面(死への衝動含む)との交差です。
ナチスの「ブラックリスト」にも入れられていたヴァージニアは1941年WWIIの最中入水自殺しました。
「戦間期の精神」とはブルトン、ウルフ、ジョイス、アルトーと向き合うこと。
さて、千葉雅也さん、これらのテクストについてどのくらい「勉強」されたのだろうか?
原爆ドームを背景に、岸田首相とゼレンスキーの「同盟」を視覚的に演出している(「日経」)。
キャプションには「平和の決意、今こそ」とある。
NHKでもゼレンスキーと岸田の映像をせっせと流していたらしい。
ゼレンスキーは演説で「バフムートと広島は似ている」と発言(うーむ)。
しかしノーベル平和賞受賞団体ICANと国連総長グテレスは、核禁止条約に加盟しようとしないG7(米覇権同盟)を強く批判。
サミットに招待されたインド、ブラジル、インドネシアもG7には同調せず、声明は別にした。
ブラジルのルラは元来今回の戦争の政治的責任はNATOにあるとの立場なので、ゼレンスキーとの会談も拒否。
何度も書いたが、ロシアのウクライナ侵攻は当然批判されるべき。
しかし、中ロとの対決を前提とした軍事同盟に加盟、改憲すべきかは別問題。また被爆地「広島」での「核不使用、通常兵器のみ」のデモンストレーションは悪質な「政治利用」です。
千葉雅也さん、「ゼロ年代という戦間期」とやや無邪気なことを言っているが、世界はもはや「第三次世界大戦」に入りつつある。
「哲学者・作家」として資本主義を最近はどうも「批判」されているけれども、この世界戦争の危機をドゥルーズを使って、どのように分析・克服できるのか、提示するべきだろう。
「千葉雅也さんにとっての第一次世界戦争」
千葉さんの「インターネットで旧来の世界が焼き払われていくというのが僕ら日本のロスジェネにとっての第一次世界大戦」という比喩に対して私は「いささか想像力を欠いているのでないか」と懸念を表明しました。
しかし「想像力」というものは意外とあてにならぬもの。そこでより具体的でアクセスしやすい資料を提示します。
例えば、前世代までは大学生の「常識」であったレマルクの『西部戦線異状なし』。これニ度にわたって映画化されている。また同じく西部戦線末期の仏軍の崩壊寸前状態を描いたキューブリックの『突撃』。尚、仏では徴兵忌避・命令拒否は法的に「敵前逃亡」と同じと見做されますので、原則「銃殺」。
インターネット時代に大量の若者が「銃殺」されたとは寡聞して知らない。
A.ブルトンは「地獄の西部戦線」に医学生として従軍、この経験からシュルレアリスムは誕生します。『シュルレアスム宣言』は1924年。
もう一つ付け加えると、近年再評価著しいB.ウルフの『ダロウェイ夫人』は1925年です。この頃にはドイツ語圏ではフッサール、ハイデガーの現象学が台頭。『存在と時間』1927年。
サルトル世代はこうした「戦間期の精神」の中で登場した。
少しでも参考になれば、ということで。
「知性の猛者たち」
いつもは新聞広告「不快」になるので、眼に入らないようにしているのだが、今日は運悪く視界に入ってきてしまった。
「創始者たちイーロン・マスクとピーター・テイル」これって見南アフリカ鉱山王の息子とその悪友、ネトウヨの世界の元締めとトランプの政策顧問、の組み合わせ。ピーター・テイル、右派リバタリアン、加速主義右派、投資家・コンサルというイーロン・マスクと同等の最悪のコンビではある。どちらも「何のリスク」もとったことない「詐欺師」だが。
それにしてもスプツニ子!も含めて、米国や英国の中朝教育での「数学の天才」(自称・他称)はやめてほしい。日本の高3生が米英に行けばほとんど全員「数学の天才」になるのです。
しかし「知性の猛者」たちが「絶賛」している、というので誰かと思ったら東浩紀・成田悠輔他詐欺師2名だった。
「知性の猛者」という表現ははじめて知った。イーロン・マスクを讃えるとはどんな「知性」だ?「痴性の猛者」の間違いじゃないのか?
BT)L.ブニュエル監督、ジャンヌ・モロー主演『小間使いの日記』、これはお勧めです。
現代日本の「極右」とほぼ「同じフレーズ」が連呼されているのに驚くと思います。
ブニュエルはゴダール、トリュフォーと並んでサルトルの大ファンだった。サルトルがノーベル文学賞を辞退した際には、「ブラボー」の電報を送っている。
尚ニザンは数ヶ月極右組織に加盟した後、離脱1926年アデンに向かいます。ここでの植民地主義と自らの経験を基にした小説第一作が『アデン・アラビア』です。
帰国後共産党に1927年に入党。サルトルとアロンの立ち合いの下、22歳で結婚(この両者は戦後は宿敵となる)。
ニザンの娘と結婚したのがアシュケナージ系ユダヤ人のO.トッド。オリヴィエは『現代』に協力しながら、27歳でサルトルの序文を得て小説を上梓。
このオリヴィエの息子がE.トッドです。ですから、ニザンの孫。なんだか意外ですねー
しかし、現代日本のリュシアン、もう50半ばで福田和也を賞賛してどうする?鵜飼哲さんを「強者」と讃えてすがるのか、福田和也を褒めたたえるのか、二つに一つではないのか?
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
