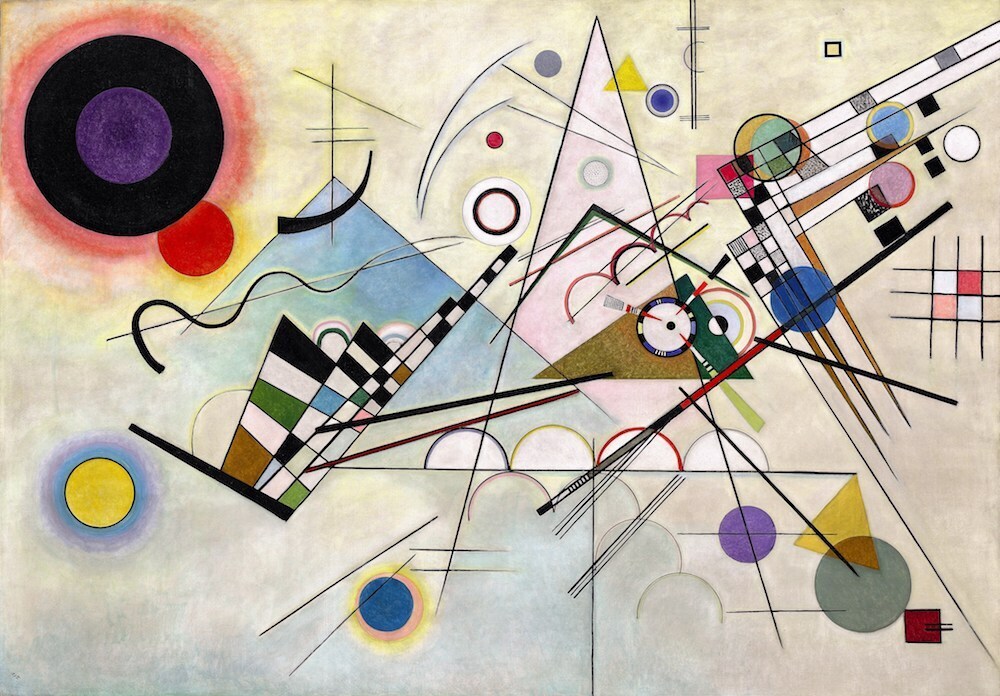
「お知らせ」
2020年に社会思想史学会のシンポジウムで行なった報告を基にした論考、
「社会批判は尚も可能かー「今」でなければいつ?」
が以下のホームページで閲覧・PDFダウンロードできるようになっているようです。
もしご関心のある方がいらしたら、ご笑覧下さい。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shst/45/0/45_51/_article/-char/ja
拙著『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会、2019年)です。
ここの所、ファシズムと冷戦に関する投稿が多いですが、もしより詳細な、思想的文脈にご関心の或る方はご笑覧いただければ幸いです。
いわゆる「戦後思想」と呼ばれている言説が「戦中」の「ファシズム」との思想的対決から生れ出た視点を強調しています。
またWWII以後の「グローバル冷戦 cold war」による世界空間の再編の中で、ユーラシアの両端で「独立左派」を模索したフランスと日本の思想を比較する視座を導入しています。
さらに言えば、日本は敗戦によって全ての海外植民地を喪失しますが、仏は形式上「戦勝国」となったため、インドシナ・アルジェリアで1965年まで「戦争」を継続しました。
サルトルと『現代』は、その過程で一貫して「植民地独立」を支持する篝火であり続けます。
また植民地独立後はマグレヴ(旧仏植民地)からの安価な移民労働者の導入(政府も関与)が生み出した所謂「郊外 banlieue」の問題、「クセノフォビア」の問題にも取り組みます。
FNのジャン・マリー・ルペンはアルジェリア戦争でアルジェリア人を拷問する立場にありました。
「記憶の戦争」は仏でもまだ終わっていないのです。
先週、参院会館で行った、「スラップ訴訟、言論の自由、民主主義」が週刊金曜日の今週号で取り上げられています。ご関心のある方は是非お読みください。
大学の新設計画という公的問題を動画にて突如公開するする以上、当然それは(多少の誤解を含む)論評が出るのは当然です。
それを自分の都合の悪い投稿をした人間に「日本財団・ドワンゴ学園」準備委員会が「法的措置を取る可能性がある」と内容証明で送って来れば、普通人は「心理的威圧」を感じます。
その企画の中心に安倍首相周辺の政治権力の中心や大富豪がいるとなれば尚更です。
法的訴訟となれば、時間はかかりますし、常識的に「スラップ」であって棄却と予想しても、この手のことに「絶対」はありません。
しかし、だからといって、誰もが「スラップ」を恐れ、また「忖度」して言論を自主規制すれば、民主主義は成り立ちません。民主主義は、構成員がある程度重要情報を共有してこそ成り立つシステム。であるから、「言論の自由」、「表現の自由」は民主主義にとっての死活問題。
私としては法的手続きはそれとして粛々と進める予定ですが、法的プロセスは別に「民主主義」と「言論の自由」について、(マスコミ政治家のみなさんも含めて)問題意識を共有していただきたく、記者会見を開きました。
今日、参議院会館で、「スラップ訴訟と言論の自由、そして民主主義」と題する記者会見を開きました。
研究者、ジャーナリスト、それに望外なことに参議院議員である宮本岳志さんが参加してくれ、活発な討論の場になったと思います。
宮本議員はかつて金融ローン会社武富士が週刊金曜日に対して行った1億数千万以上の賠償請求事件に関して、国会質問にたった経験があり、そのことから今日の会見に興味をお持ちになった、ということでした。ちなみにこの際の武富士側の弁護士が、現在の大阪維新の吉村市長です(勿論、武富士の要求は棄却)。
いやはや、20年たっても構図はあまり変わっていないのか・・・
というよりもジャーナリストの方たちのお話を聞くと、この手法は現在さらに多用されており、組織ジャーナリズムは「訴訟」になりそうな記事を自主規制、フリーの人は訴訟のリスク・負担を恐れてこれまた「自粛」という流れもあるように感じました。
「言論の自由」、少なくともこれがなければ民主主義はなりたちません。治安維持法でなくても、大富豪と権力者の企画を批判すること「スラップ訴訟」の圧力で「自主規制」されるようでは、日本の民主主義体制は風前の灯と云えましょう。
尚、今日の動画は近々、公開できると思います。
昨日、内科の待合室で午後5時代のニュースを見ていたら、延々と天気予報が続いて、次は「エンタメコーナー」だった。
しかし、私はもっていないが、近年はほとんどの人がスマホをもっている筈で、一日の内、何度も天気予報を、しかもかなり時間をとってTVで流す必要はないのでは?
「エンタメコーナー」に関しては「政治のエンタメ化」が指摘されて久しく、こうなるとTVニュースはほとんど天気予報とエンタメ・スポーツで構成されているのではないか?
あとはいわゆる視聴率が取れそうな犯罪報道。これに対し、パレスティナの惨状、第三次世界大戦につながりかねないイスラエルの暴走、韓国のクーデター未遂事件の背景、フランス、ドイツの内閣不信任案などは、ほとんど取り上げてないに等しい。
数年前まで私は知らなかった大谷翔平という野球選手にしても、どう考えても、騒ぎすぎである。
確かに、野球業界での数字はたいしたものらしいが、そんなものはイスラエルによるジェノサイドによって地獄の苦しみを味わっているパレスティナの人々の惨状を知らせる必要性に比較すれば「無に等しい」。せいぜいスポーツニュースで報道すればいいだけの話である。
こんなことだから、有事に「石丸」をエンタメ流に大演出すると、「コロリ」と行く人間が大量に出る。
仏の「新人民戦線」会派中の第一党「不服従のフランス France insoumise 」の党首、メランションのセカンドハウスが極右活動家達に襲撃された、とのこと。
家は荒らされ、壁には鉤十字(ハーケンクロイツ)と「マリーヌ万歳」、「アラブ野郎」などの落書きがあったと云ふ。
どうもフランスも物騒なことになってきたようだ。しかし、これこそフランス的、と言えるかもしれない。
韓国とフランス、「ユーラシアの両端」での右派の破綻、これからどのような転回を見せていくのか要注目です。
そう言えば、日本でも「あの」岸和田市長に対する「不信任決議」が今日可決されたらしい。
どうも、これも市長は、議会を解散、市長選・市議会選となるようだが、はてさて?
兵庫県知事選の文脈がどのように波及するのか、これも眼を離せません。
他方で、斎藤知事への公選法違反の捜査が次々と開始。Xデーは、年末年始か?
韓国ではクーデタ未遂の尹大統領が現在、逮捕を待っている状態。
他方、仏では内閣不信任を可決されたマクロン大統領が、バイルーを首相に任命して延命を図りつつ、野党を「国民の敵」などとクーデター前夜か、と思わせる発言を繰り返し、ルモンドなどマスコミに対する統制も進んでいる。
ところで仏も韓国と同じく最上部の権力闘争が表に出る国柄。
この度、元大統領サルコジが1年の実刑判決。これは大きくみれば同じ保守派(ド・ゴール派)の元大統領シラクの報復である。
というのも、ENA出身の「エリート」シラクとある種橋本徹的たたき上げのサルコジは、保守内部で激しい権力闘争を展開。シラクは大統領退任後、刑事事件で訴追、2011年執行猶予付き禁錮錮2年の有罪判決となる。
これに対しシラクは2012年の大統領選で同じENA出身のオランド支持を大々的な記者会見で公にし、サルコジは敗北、2013年直ちに刑事訴追された。
エナルク(ENA出身者)のエリート支配は現在のマクロンまで続く。同時に政治の内容は治安管理強化、米国追随、新自由主義とサルコジ路線を踏襲する形となる。この過程でかつて政権党だった社会党は実質的に解体。
マリーヌ・ルペンの極右の躍進もこの支配エリートのサルコジ化と連携したものと言えるだろう。
以前、「独占告白 渡辺恒雄」をレンタルDVDで見たのですが、おもしろかったです。
(NHKでの放送された番組をまとめたもの)
戦後、自民党が支配する体制を作ってきたときからその中心のちかくに居続けた人なので、戦後の歴史や今の政治を考える上で参考になると思いました。
むろん、自分を美化していたり、語っていないことも多いので、突っ込みいれながら見るべきところもあります。
あと、途中で挟み込まれる「政治学者」などのコメントには、どうでもいいお世辞めいたものがあったりもします。
それでも、見る前に予想していたほどは、「無駄」な部分は多くないです。
この「独占告白 渡辺恒雄」(昭和編、平成編)と、「NHK特集 日本の戦後」シリーズのDVDは、見ると戦後史理解に役に立つと思います。おすすめです。
あと、〔参照〕のところに、以前投稿した日本の戦後史関連の本のおすすめをつなげておきます。これらの本もどうぞ。 [参照]
石破との面会を「拒否」したトランプに、何故か「私人」として安倍明恵が面会に行き、そこでようやく「お目通り」の内諾を得たと云ふ。
これは、おそらくは一度内閣府の「中の人」が、トランプ当選を受けて、「日米地位協定を見直すよい機会」的な発信をしたことに対する「報復」だろう。
この「中の人」の発信はすぐに消去されていたが、当然これは米政府の目に留まる。(そのことに配慮しないで発信したとしたらーその可能性が高いがー日本の官僚達の「危機管理」意識の「甘さ」も相当である。)
そこで、一度安倍首相とともにトランプに「お目見え」している安倍明恵が、なんらかの「みやげ」をもってー当然外務省同行ー謝罪に行き、ようやく「お目通り」を許された、ということだろう。この「おみやげ」の中味は、秘匿されているが、またまた米国の軍需産業の「爆買い」の約束であった可能性もある。
しかし、トランプは究極の白人至上主義者であって、「黄色人種国家」日本からは「巻き上げる」ことしか考えていない。しかも、日本には「巻き上げる」金融資産だけは残っているのが悲劇的ではある。
今、金融資産が消滅したら、日本は韓国・台湾と違って「何もなくなる」。当然、円・国債・株式のトリプル安も来るだろう。それでなくてもバブルは近々崩壊するである。
スリランカ人ナヴィーンさんの裁判。
裁判所は、
政治的な理由の難民申請を退けたうえに、ナヴィーンさん・なおみさんが婚姻していることを理由に在留許可が出せないのかという点について
「婚姻関係は不法残留という違法状態の上に築かれたものだった」
として退けています。
現実に存在する、人と人の関係を「違法状態の上に築かれたもの」といいきる冷たさ。
作家の木村友祐さんがナヴィーンさん・なおみさんのことを取材した文章で
「仮放免状態の夫と暮らす/暮らした日本人の妻たちのお話をうかがっていて、あることに気づく」
「それは、国家および国家の意向に従う入管が家族の形を決めている疑いである」
「国家が上から家族の形を規定する。いわば「官製家族観」。その何が問題なのかといえば、そこから外れているという理由で、いつまでも夫に配偶者ビザも在留特別許可も出ないからだ」
https://imidas.jp/jijikaitai/F-40-241-23-05-G897
と指摘、
今回の裁判、まさにこの通りになっています。
基準から少しでも外れたらすぐ排除するのではなく、
なるべく、いろんな人が共に暮らせる社会をつくっていくための司法であってほしいです。
そういえば、京都の弾薬庫についてのMBSの特集番組、12月22日(日)の早朝に放送するようです。
「映像'24 ミサイル弾薬庫がやってくる 」(12月22日(日) あさ 5時00分放送)
「自衛隊の弾薬庫増設をめぐり、京都の街が揺れている。
1年前、京都府精華町と京田辺市にまたがる陸上自衛隊祝園分屯地に、弾薬庫8棟を増設する計画が発表された。2022年の安保関連3文書の改訂で、「反撃能力(敵基地攻撃能力)」の保有が明記されたことによるものだ。防衛省は約10年かけて全国で弾薬庫130棟を新たに整備する。
祝園分屯地は、「けいはんな学研都市(関西文化学術研究都市)」の真ん中にあり、半径5キロ圏内に10数万人が居住、企業誘致も進められている地域。防衛省は弾薬庫に保管される弾薬の詳細を明らかにしていないが、「トマホークや長距離ミサイルが保管される可能性は高い」と専門家は指摘する。
「有事の際に標的になるのではないか」「爆発の危険性はないのか」など、周辺住民からは不安の声が上がる。
全国で弾薬庫が急ピッチで建設されるのはなぜなのか、それは私たちの暮らしにどんな影響を及ぼすのか、安全保障政策の大転換の最前線をリポートする」
F.ボルケナウ『封建的世界像から市民的世界像へ』。1934年、フランクフルト社会研究所から出版された(序文M.ホルクハイマー)。
丸山眞男『日本政治思想史研究』に収められた第一論文(1940)及び第二論文「近世日本思想における自然と作為」(1941)は、このボルケナウのシェーマを下敷きに、ヘーゲル的叙述によって組み立てられたもの。
丸山自身は1929年に出版されたK.マンハイムの『イデオロギーとユートピア』の決定的な影響を強調する。確かに、未だに、イデオロギー論としてはマンハイムのこの著作を超えるものは出ていない、と言ってもいい。
しかし、ボルケナウの著作も現在再読すると、単なる「封建」ではなく「近世」思想への着眼的の独創性には驚嘆する。マキャヴェリ、ボダン、アルトジウス、グロティウスを扱った第三章「自然法と社会契約」、またリプシウスとモンテーニュ、リベルタン、ジェズイット、ジャンセニズムを分析した第四章など。とりわけリプシウスと新ストア主義の関係の重要性を指摘した箇所などは「先駆的」以上。
この時点ではディルタイが言及している程度で、WWII後G.エストライヒによって新ストア主義の重要性は再定位された。
晩年までストア主義に拘るフーコーは、エストライヒを読んでいたのか?
今回の尹大統領の「クーデター未遂」事件の日本のマスコミの報道、事態の重大性に終始一貫対応していなかった。
今日の「朝日」は「尹政権批判の「顔」李在明氏 小卒で工場勤務、弁護士に 日本に強硬」である。
この「日本に強硬」、「文在寅は反日」と並んで、韓国の民主派への日本マスコミの紋切り型のレッテリ貼り。
文在寅にしても李在明にしても、「反日本国」、「反日本人」なわけではない。「反日本帝国主義」・「反植民地主義」なだけ。
本来、WWI後の日本国は日本帝国主義の解体の上に建設されたもの。
であるから、日本政府も当然「反日本帝国主義」でなければならない。また制度や心性に継続する植民地主義については、政府・国民共にこれを克服していく努力をするのが筋である。
他方、韓国の右派は日帝時代の「協力者」がWWII後「反共」に鞍替えして、権力を維持して来た。故に、あまりに「植民地主義の清算」を進めすぎると、ブーメラン効果で自らの地位を動揺させかねない。
この事情を知ってか知らずか、右派政権を親日、民主派を反日とする報道がここ20年延々と反復されている。
この状況で「得をする」のは今やUSAのトランプ。白人至上主義者のトランプにとって、東アジアの分断支配は願ってもないことだからだ。
🔴 Mediapart décide de quitter X, à la date symbolique du 20 janvier #HelloQuitteX
🗞️ @mediapart : Contre la désinformation, Mediapart quitte X https://www.mediapart.fr/journal/france/171224/contre-la-desinformation-mediapart-quitte-x
弁護士の郷原氏と上脇教授が、公選法違反について提出していた告発状、神戸地検と兵庫県警が受理した、とのこと。
これは折田楓氏と斎藤氏の「金銭受理」の件。
「常識 common sense」で考えれば、N国の立花と斎藤の街頭での演説も、「示し合わせて」行ったとしか考えられない。ただし、これは「法的」には「あくまで偶然」として「推定無罪」を利用するつもりだろう。まさに典型的な「脱法」行為。
そう言えば、「社会心理学者」三浦麻子さんは、立花と斎藤の連携プレーに何も言及していなかった。
実際、選挙期間中、斎藤は実質何も発言していない。「全てが陰謀。斎藤氏は被害者」とがなり立てたのは立花氏。これもさすがに斎藤本人が「全てが陰謀」と叫び続ければ、普通人は「引く」。三浦氏は「心理学を専門とする」と称しながら、こんなことも理解できないようだ。
だいたい超テキトーな「常民性」で説明するなら、大阪小選挙区維新全勝も「常民性」が主因となる。なぜなら、常民とは「ナショナリズム」を前提とした概念であり、神戸と大阪には違いはない。石丸現象も常民性故、ということになる。
ま、関西電力の「研究所」の企画委員を務めているお人なので、確信犯で煙幕を張っているのかも、だが。でなければただの「あほ」。
BT
引用は、3月に京都の弾薬庫について書いた投稿です。
引用した記事のリンクがきれているので、同じ記事につながるリンクをはっておきます。
・「京都、本州の補給拠点に 火薬庫、陸・海自衛隊共同使用―増設に102億円計上・防衛省予算」(2023年12月24日)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023122300285
田淵さんがはってくださった2023年12月の赤旗記事では、
「防衛省は2024年度予算案に・・・弾薬庫を新設する建設費222億円を計上」
そして2025年度は、
「防衛省は弾薬庫の整備費として概算要求に358億円を計上」
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik24/2024-09-08/2024090801_03_0.html
だそうです。
今年度は222億円、
来年度は358億円も
ミサイルなどを保管庫をつくるために使う政府。
「お米も野菜も高くて買えない」と困っている私たちから集めた税金を、こんなふうに使うなんて。
#防衛省
#軍事費
QT: https://fedibird.com/@chaton14/112042126655447965 [参照]
この三浦麻子という人の兵庫県知事選についての「解説」、何か胡散臭いものを感じたけれども、どうもそういうことらしい。
美浜原発近辺の関西電力の「研究所」の企画会議委員を現在までつとめながら、「原発事故に関連する放射線不安は何故消えないのか?」などとふざけた共同研究を行っている。
「何故不安が消えないのか?」ー「そこに原発があり、政府が悉く嘘をつくから」
に決まっている。これはネットでアンケートを取るまでもない。
ま、要するに開沼博を少し「モデレート」にした線、と所だろう。
この人、「地元の警察を信頼する」を「常民性」としているが、「常民」的世界に「警察」はないの!
それでいて「警察の情報発信における信頼」なる共同研究はしっかりしている。
いやはや、日本の社会学どうなっていくのやら。誰か現在進行している岩波講座「社会学」の批評でもしてくれないかなー
ま、原発事故の風評加害の法的告訴を唱えている開沼博の登場する「環境」の巻を私自ら批判する予定だけれども。 [参照]
BT
記事を読んでから、この「社会心理学者」の方について調べたら、
関西電力が原発を推進・擁護するためにつくったらしき「研究所」(福井の美浜原発の近くにある)
の「研究企画会議 委員」をしたり、NTTがお金を出している財団から賞をもらったりされているような方でした。
大企業の「既得権益」側っぽい人ですね。
「原発事故に関連する放射線不安はなぜ消えないのか」という研究もしているみたいです。
企業や政府のやったことを等閑視して、人の「心理」の側にだけ着目してそこに原因を見いだすタイプの「心理学者」さんなのかな?と思いました。
それだと、兵庫県知事の再選の大きな要因となったと考えられる、知事後援者の朝比奈氏ら地元の建設業者など「既得権益」層が、SNSや御用マスコミなどをつかってイノセントで新しそうなイメージを見せながら、「ダーティ」な部分を外部委託した立花などと連携し、脱法的に疑惑ウォッシングして勝ったのではないか?といったことについて触れることは当然できないでしょうね。
統計など一見科学的に見える手法を用い、実際には考慮すべき重要な背景事情を考慮せず、権力側の責任が見えにくい「調査結果」を出す。
そういった「お仕事」と同じ方向性を、今回のインタビュー記事にも感じました。
BTs
こういうふうに有能な「パートさん」のやっていた仕事って
それに見合った待遇をしてないと思うし、それは結局搾取だし、
いままでは賃金以上の働きをしていた人たちに寄りかかって成り立っていた仕事は、たぶんもう今後成立しませんよね・・・。
あと、「パートさん」が「密なコミュニケーションや細かな配慮」ができていた背景事情として、
被扶養者の人向けの制度が存在していたということも大きかったと思います。
昨今、「ずるい」とかなんとかいって、被扶養者対象の控除とか3号被保険とかをどんどんなくす方向にもっていこうとしていく流れがありますが、
企業の側だってそういった制度があることで有形無形の恩恵をこうむっていたのでは?と考えてしまいます。
制度があることで搾取を温存していたという側面もあるわけなので、全面的によいものだともいえないわけですが、
経済的に追い詰めて、家庭がフルの二馬力の労働力でないと立ちゆかなくなるほど余裕がなくなると、今までその余裕の部分でなんとかやっていたものができなくなるというのは当然の帰結ですよね。
どういうわけか、今デジタル朝日の記事を確認したら、「常民」についての「解説」が「民主主義や法治国家を信用しない」に代わっている。
これは不思議なことだ。最近私は自分の短期記憶が信用できなくなくっているので、ここの部分は数時間前にコピペしておいた。
いずれにしろ、まず「常民」という柳田が提唱した概念は、現在は学問的には使えない。というのも、これは典型的な「近代の発明」だからだ。これは、歴史学的社会学的にももう決着がついたことと言ってもいい。
さらに、この三浦という人が酷いのは、21世紀の現代社会でまだ「常民性」などという概念を自明視していること。
ここでご本人が挙げている特徴は、基本的に現代社会論で言う所の「大衆」。
この大衆の「意識」をさらに階層別、地域別、年齢別に分けて「実証的」に調査するのが本来の社会心理学の仕事。
「斎藤氏は好きでない人でもえいや、と投票している人がいる」などと、呆けたコメントでは「心理学の専門家」という肩書は外した方がいいのではないか?
あるいは、この人、公開の研究者情報に趣味は「競馬の一口馬主、年間予約席を購入した阪神タイガースの応援」で自分で書いたいるだから、まずは自己の心理分析をしっかりと行った方がいいかもしれない。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
 朝日新聞デジタル
朝日新聞デジタル
