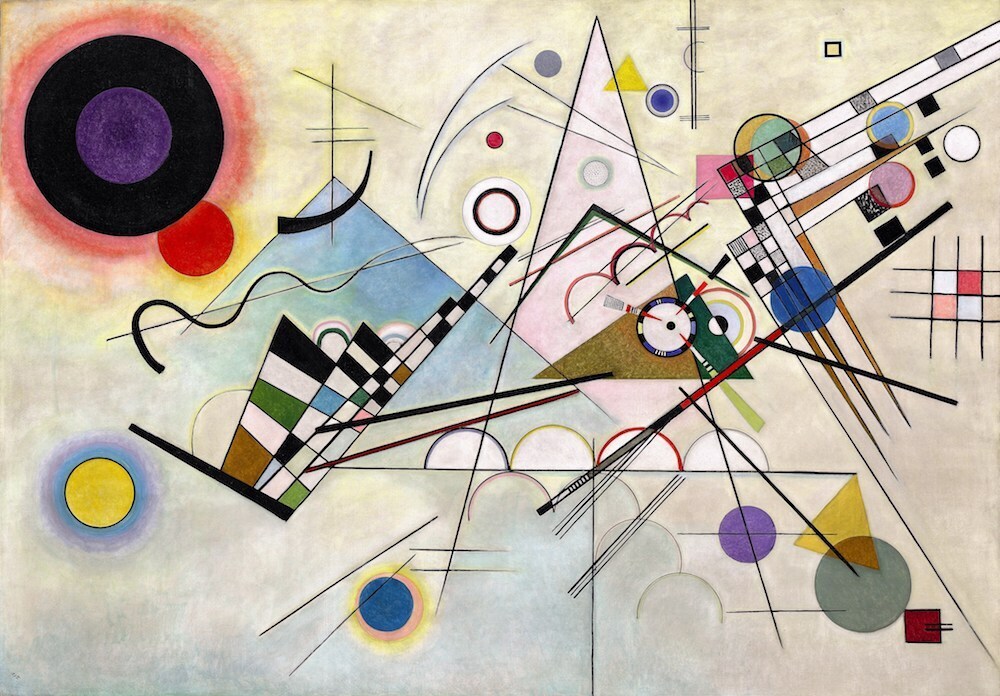
A.ヒッチコック(1899生)、イングランド生れのアイルランド人。『暗殺者の家』、『三十九夜』、『バルカン超特急』などのイギリス時代を経て、渡米。第っ作『レベッカ』以来、サイコスリラーの巨匠としての地位を確立。
このヒッチコック、実は1920年代、ドイツ表現主義の巨匠F.W.ムルナウの大きな影響を受けました。ムルナウの『最後の人』ーこれは現代に直結する悲劇を淡々と撮った映画史上に残る傑作です。
ヒッチコックの初期の映画『メリー』(1931)、『ウィンナーワルツ』【1934)、特に前者はドイツ表現主義かと見紛うまがりの光と影、人物の表情の演出です。
しかし、この頃からヒッチコック、カメオ出演をしており、さすがに若い。
ヒッチコックはS.モームやJ.コンラッドを原作としてスパイ映画、『間諜最後の日』、『サボタージュ』なども撮っています。
モームはMI6員です。MI6関係者はジョン・ル・カレにしろ、グレアム・グリーンにしろ、作家としてそれなりに評価の受ける人も多い。
対してCIA出身の作家というのはあまり聞いたことがない。
コンラッドに戻ると、彼はポーランド出身で、海員時代の経験を基にした、多くの作品を英語で出版。
E.サイードの最初の研究対象はコンラッドでした。
ネグリ=ハート派の「マルチチュード multitude」とルソーの「一般意志」はまず相容れない。
少なくとも、当人たちの理解はそうだ。
またもし、マルチチュードと一般意志を和解させるとすると、それは「マルチチュード」理論は崩壊することになる。
それにしても、佐藤嘉幸さん、廣瀬純さん、そしてスパルタカス君と面識がある人間ばかりが、東浩紀がらみで出てくるのはどういうわけだろう?
スパルタカス君について言えば、現在リュシアンのように、鏡の前で「髭を生やす」ことを決意すべきか、どうか思案中、ということだろう。
ところで、1930年代のフランスのファシズム・反ユダヤ主義、L.ブニュエルの「小間使いの日記」の主題でもあります。
排外主義の言葉は現代のものとほぼ「同じ」であることに驚かされます。
ルメイクもありますが、やはりブニュエルのそれが優れている、と言えるでしょう。
ブニュエルは、トリフォー、ゴダールとともにサルトルのファンでもあり、ノーベル文学賞辞退の際には「ブラボー」と祝電を打ったとされています。
R.ブレッソンの「抵抗」
ブレッソンはメルヴィルとともに「ヌーヴェル・ヴァーグ」の兄とも言える存在。
この映画は1943年にリヨンで囚われ、死刑宣告を受けたレジスタンスのメンバーが脱獄を試みる過程を追っていく。
当時リヨンには「レジスタンス」掃討担当者SS将校として、あのK.バルビーがいた。
しかし、この時期を扱った映画に限らず、フランス文学には「脱獄」のテーマが脈々と波打っている。
A.デュマの『モンテ・クリスト伯』やV.ユゴーの『レ・ミゼラブル』、バルザックのヴォートラン。『赤と黒』のジュアリン、『パルムの僧院』のファブリスは自ら「牢獄」への道を選択。
これは、つまり「世界」そのものを「牢獄」と見做し、そこからの「脱出」の試みを「生」と考える伝統とも言える。
この場合脱出の試みが「散文」による「この」世界での出来事として記述され、ドイツ浪漫派のような「別世界」への「憧れ」=「詩」でないことが特徴と言えるだろう。
こう考えるとカフカとフランス文学の「相性の良さ」にも得心は行く。この伝統はカミュ『シジフォスの神話』へと続く。
ただし、1848年革命の挫折により、フローベールの「偽の散文」・「反文学」(サルトル)も現れ、20世紀フランス文学を複雑にしていくのだけれども。
「別離」
ベルリン映画祭の金熊。監督、アスガル・ファルハーディーは、今もっとも優れた映画の作り手の一人だと思います。「サラリーマン」や「浜辺に消えた彼女」などでベルリンやカンヌの常連でもあるのでご存じの方も多いと思います。
かつて、イラン映画は当局の枠もあり、大人の社会の紛争、トラブルを描くことが難しく、結果として「子ども」の視点から見た優れた映画を輩出しました。
また皮肉にもアメリカとの関係で、ハリウッド映画がほとんど入ってこれなかったことが、国内の映画産業を保護し、次の世代を育てることにも成功しました。
かつてのイラン映画は「地方」の農村を舞台にすることが多かったのですが、ファルハーディは、都市中産階級の「女性」と社会の軋轢を、カフカ風のサスペンス・タッチで描きだすのがうまい。軋轢の結果、法廷闘争がわりと長く描かれ、イランにおける民事訴訟の在り方が垣間見えるのも興味深い。
日本では「悪の枢軸」、女性を抑圧する「イスラム共和国」と決めつける米国製のイラン像が強いようにも感じますが、例えば、イランは女性の大学進学率はとびぬけて高い。それを背景にファルハーディの描く中産階級の女性たちもごく自然に登場するわけです。
またドイツとイランの労働移動が必ず描かれており、これも興味深い。
『性的人身取引ー現代奴隷制というビジネスの裏側』シドハス・カーラ
社会主義圏崩壊以降、加速する国際的「性奴隷」ビジネスを綿密な調査と資料精査によって明らかにした書物。
性奴隷の供給源の一つは、社会主義崩壊以降、福祉が崩壊した旧東欧圏。ルーマニア、ブルガリア、ポーランド、チェコ、ウクライナ等から、「結婚詐欺」や文字通りの「誘拐」などによって大量の女性が西欧及び北米に拉致され、性奴隷ビジネスに従事させられています。
また、東南アジアではタイ、フィリピンなどの児童買春に「ペドフィリア」の多くの「北」側の男たちが訪れる。ただ、最近は観光に来た白人家庭の子供が誘拐され、性奴隷にされるケースもあるようです。またパキスタン、バングラデッシュからも「性奴隷」が国境を越えて「輸出」されている。
著者は、こうした調査を踏まえた上で、国境を超えた性奴隷制ネットワークが新自由主義グローバリズムによって急成長する分野になったことを指摘する。今や性奴隷ビジネスの「利益率」は麻薬ビジネスより大きい。
従って、著者はIMFが社会主義体制崩壊後の東欧の「社会保障」解体に果たした役割を強調し、自由主義グローバリズムの克服なくしては国際的「性奴隷制」の根絶はない、と主張します。
ご関心のある方は、ぜひご一瞥下さい
「法廷」
近年、新自由主義グローバリズムによる社会の変容(解体)に伴って、日本のみならず世界中で「極右原理主義」が台頭しつづけています。
インドでのヒンドゥー原理主義の台頭には、私は2002年の「ジャラードにおける「ムスリム」に対する「ポグロム」にショックを受けて以来、折に触れて不気味な関心をいただき続けていました。
このヒンドゥー原理主義政党(インド人民党)は、ある時期から国政を担当するようにもなり、一度下野しましたが、現在また政権に返り咲いています。モディ首相は、かつての「グジャラード虐殺」の際の州知事です。
米英日などはインド国内の「原理主義」に対して、「寛容」を示代わりに、中国包囲網に加われ、と誘っているのが現状です。
先日、 le monde でガンジーの暗殺者が、今やヒンドゥーの「英雄」として称揚されている、という記事を読んで驚きました。
「法廷」という最近のインド映画は、上記のような状況を背景にしつつ、アウト・カーストへの不当逮捕・判決を淡々と描いた作品です。
これは芸術的観点からも秀逸な作品で、昨今の世界レベルの映画風景では、トルコ、イラン、インドが先頭を走っている、という印象をも裏付けるものです。ヴェネツィア映画祭では2冠。
「A.エルノーとJ.クリステヴァ」
A.エルノー(1940生)は2022年ノーベル文学賞受賞。日本語訳もあり、2021年ヴェネツィア映画祭金獅子賞の「あのこと」の原作者でもあるので、あるいは現在の日本でもクリテヴァより知られているかもしれません。
クリステヴァ(1941生)はルーマニアのユダヤ人、故国での共産主義青年団時代を経て、パリではL.ゴルドマン、R.バルトに師事。ラカン派精神分析と文化記号論を武器として、パートナーのF.ソレルスと1960年代から『テルケル』を舞台に華々しく知的舞台で活躍。
他方エルノーは、ノルマンディーの田舎町に工場労働者の子として生まれ、大学で中等教育資格を取り、1974年作家デビュー。エルノーの小説は全て自伝的小説。
この点でも「作者の死」を唱えたパリの「文化エリート集団」と好一対をなす。
政治的には「文革礼賛」(わざわざ当時の中国に行った)から共和主義の「主権」(ラカンの父)に回帰したクリステヴァに対し、エルノーはフェミニズム、気候変動、反自由主義、反イスラエルなどの運動に参加する、典型的な「政治参加する作家Écrivain engagé」である。
階級的背景という点では「フーコー伝」で知られるD.エリボン(ゲイ)とも共通している。
2019年に出た、山内昌之・細谷雄一編「日本近現代史講義」、現在の政治史が如何にサントリー化しているかがよくわかる。いわば大学における「自由主義史観」である。
麻生太郎会長の中曽根平和研究所の研究本部長、川島真氏は毎度の御登場。またサントリー理事の弟子筋の人多数。しかし、いくら何でも中西寛が結論とは「やばすぎ」だろう。
明治維新を「立憲革命」とするのも従来の政治史の延長線上。
いわば歴研的なものと対極にある。これはさすがに対抗「日本近現代史講義」が必要なのでは?
序章 令和から見た日本近現代史(山内昌之)
第1章 立憲革命としての明治維新(瀧井一博)
第2章 日清戦争と東アジア(岡本隆司)
第3章 日露戦争と近代国際社会(細谷雄一)
第4章 第一次世界大戦と日中対立の原点(奈良岡聰智)
第5章 近代日中関係の変容期(川島真)
第6章 政党内閣と満洲事変(小林道彦)
第7章 戦間期の軍縮会議と危機の外交(小谷賢)
第8章 「南進」と対米開戦(森山優)
第9章 米国の日本占領政策とその転換(楠綾子)
第10章 東京裁判における法と政治(日暮吉延)
第11章 日本植民地支配と歴史認識問題(木村幹)
第12章 戦後日中関係(井上正也)
第13章 ポスト平成に向けた歴史観の問題(中西寛)
シェイクスピア史劇「嘆きの王冠」
リチャード2世から、ヘンリー4,5,6世、エドワード6世リチャード3世まで、百年戦争末期から薔薇戦争までを舞台にしている。
上左の写真はランカスター派を指揮するヘンリー6世の王妃マーガレット・オブ・アンジュー(マルグリット・ダンジュー)。黒人俳優であることは現代的演出と言えるのでしょう。(かつてピーター・ブルックは「ハムレット」で黒人俳優を主役ハムレットに起用した)。
ただし、王妃マーガレットは史実上も、ランカスター派の軍事的指揮を執ったとされています。
とは言え、王妃マーガレットがみずから前線で剣を振るい、血まみれになるところなどは現代的演出と言えるでしょう。
しかし、このシリーズでは総じて暴力による権力闘争の空しさを強調する演出となっている。
シェイクスピア史劇の映像化としては、総じて成功していると思います。私個人としては、マーガレット、それに最後の「リチャード3世」はとくに演技も含めてよかったと思います。
逆に、若き日のヘンリー5世(ハル王子)を描いた「ヘンリー4世 第二部」は20歳くらいの時から、オーソン・ウェルズのものも含めて4回くらい見ているのですが、年をとるにつれて、「王族・貴族」の傲慢さへの嫌悪が募るのは不思議です。
『ダントン』(監督A.ワイダ、1983)
このワイダのダントン、3度目か4度目だと思う。リマスター版であるから、画質はかなりいい。
また元来が戯曲であることもあり、演劇的な撮り方になっているが、それが決してマイナスになっていない。
ダントンとロベスピエールの権力闘争の最後の数日間であるので、ダントン、ロベスピエール、デムーラン、サン・ジュストなど限られた人物を近い距離からとっても不自然ではない。
活人画的な場面などは、P.ブルックの『マラー・サド』を思わせる場面もある。
ワイダは88年の『悪霊』の後、冷戦終結後は急速に緊張感を失ってしまった。
『ダントン』における各人物の描き方は基本ミシュレ以来の伝統的なもの。ただ、この映画、俳優の演技がパワフルである。ちょうど30年経った今、やはり映画界全体の衰退を感じる。
特に英米の白人男性俳優の演技のレベルが劇的に下がった。これはもう「時代」の問題だろう。
ところで、この映画を観た仏大統領ミッテランは非常に「不機嫌」だったとされるが、何故だろう?
ミッテランは青年期極右団体「火の十字団」のメンバー、ペタン崇拝者。個人的にダントンは愚かロベスピエールに親近感をもっていた筈もない。
ただ「ナショナリスト」故にということかも?
「AI業界のエバンジェリストevangelist」
少し前から「新しい技術」について説明してくれる人を「エヴァンジェリスト」と自称・他称するらしい。
しかし「説明してくる人」ではなく、「エヴァンジェリスト」であるから、ありがたい「福音」を伝道してくれる(してあげる)人というニュアンスがあるのだろう。
つまり、AI教ないしはデジタル教という宗教を「伝道」してくれる、という訳だ。
ま、この写真でI'm evangelist と黒地に青で書いたTシャツを着ている人が、伝道者なのだろう。それにしても随分「俗世」の香りがする気がするが。
しかし、この「伝道師」、AI搭載の「自律型致死兵器」システムのことは何も教えてくれないだろう。
ヴィスコンティ自身は、13世紀にはミラノの支配者であったヴィスコンティ家の傍流にあたる公爵家の出身。
ヴィスコンティ家はローマ教皇グレゴリウス10世を出すことでミラノの支配を確たるものとする。
しかし、盛期ルネサンス期には傭兵隊長出身のスフォルツァ家にミラノの支配権を奪われる。かのレオナルドのパトロンとなったのが2代目のルドヴィーゴ・スファルツァ(通称イル・モロ)。
ヴィスコンティ自身はWWIIの際、反ファシズム・レジスタンスに参加する過程でイタリア共産党に入党。その点ではやはり貴族出身でありながら、第5代PCI書記長となったE.ベルリンゲルと近い軌跡と言える。
ただし、ヴィスコンティ自身はバイ・セクシュアルであることを公言(イタリアの貴族階級では珍しくない)。
戦後の王政廃止の国民投票の際には、王を中心とする貴族階級の「性的倒錯」が廃止側の大衆動員の旗になったので、ヴィスコンティ自身は内心葛藤を感じながらも、尚「王政廃止」に一票を投じた。
『郵便配達は二度ベルを鳴らす』、『揺れる大地』など初期のネオリアリズモ的なスタイルから、PCI脱党後、『山猫』、『ルードヴィヒ』などの絢爛豪華な「滅びの美学」へと傾斜。
個人的には両者の接点となる『若者のすべて』が最高傑作だと感じる。
L.ヴィスコンティ『夏の嵐』(1954)
イタリア統一戦争の最中の、「イタリア統一」を支援するヴェネチィアの伯爵夫人とオーストリア青年将校の「敵同士」の「不倫」をベースとした、オペラ的メロ・ドラマ。
しかし、今見ると、俗物そのもの夫に満足できない伯爵夫人が、だからといって、体育会系の「頭の悪いアメリカ白人」にしか見えない青年将校に何故「魅かれるのか」が全くわからない。
と思ったら、将校を演じる俳優は米国人だった(ちなみにヒッチコックの『見知らぬ乗客』では被害者の有名テニス選手役、これはピッタリだった)。
それにしても、この将校、「政治」に何の幻想も抱けない、滅びゆく、洗練されたハプスブルク・オーストリアの美学を体現する位置を占めることが、最後の場面でわかるのだが、途中まであまりにもがっついた「ゴミ」なので、「滅びの美学」が宙に浮いてしまう。名前は音楽家G.マーラーから「マーラー中尉」としてあるのだが、「女を騙して金を貢がせる」ことしか頭にない。
このテーマだと、同じヴェネツィアを舞台にした「ヴェニスに死す」(マーラーと思しき主人公)の方がまだいい。
また「何も変えないためにすべてをかえた振りをする」というランペドーザの引用をB.ランカスターが呟く『山猫』は、さらにいい。
「オルタナティヴ」という言葉の投資会社による簒奪
下の日経一面広告、米の投資運用会社ブラックストーンの「オルタナティヴ」投資への呼びかけ。では大和証券が窓口となる。
ブラックストーンは共にリーマン・ブラザーズCEOを務めたピーターセン(故人)とシュバルツマンによって1985年に設立。シュバルツマンはイェール大の秘密結社でG.W.ブッシュと同期。この結社の卒業生は「ボーイズマン」と呼ばれ、歴代CIA長官はOB。
ウェビナーと称する講演会広告の文言がおもしろい。
「不確実性の高い投資環境における、プライベート・クレジット(直接投資)の潜在的な優位性に迫る」
なかなの修辞的と言えるかもしれない(ただし下品だが)。
最高投資ストラテジスト(戦略家)なる男と日本責任者の女性が解説してくれるらしい。
先ほどの修辞、要するに「リスク」が高いが、当たれば「大きい」と言っているだけ。「当たる」=「顕在化」。潜在性・顕在性というアリストテレス以来の哲学用語、こうも使えるのかー。
またケイマン籍であることを堂々と謳っているから「脱税」を前提。「プライベート・クレジット」とは非公開での投資。これを「オルタナティブ」投資と呼ぶ。要は一時世界をお騒がせした「ヘッジファンド」への超富裕層への勧誘用語。
いやはや。
「教養の再生のためにー危機の時代の想像力」加藤周一・ノーマ・フィールド、徐京植(影書房)
「戦争が絶えず、シニシズムが蔓延し、知性や理性、道徳性への信頼が脅かされている時代」という帯の文字、今年のものかと勘違いしそうになるが、2005年のもの。
しかし、韓国で収攬されている兄弟の釈放運動を通して、長く在日朝鮮人の運動を関わってきた徐京植さんが対話相手に、21世紀において最後の「戦後民主主義」者とも言える加藤周一さんと小林多喜二の研究者、『天皇の逝く国で』のノーマ・フィールドさんを選んだのは興味深い。
私が博士課程の時、ノーマさんの指導学生で米上院議員の息子さんと言う人が、1920年代の日本と朝鮮のプロレタリア文学運動の比較というテーマで在日していた。(韓国にもしばらくいた)。これは米国の東アジア研究の長所。本人も日本語と朝鮮語、両方できた。このまさに「トランスナショナル」な研究テーマ、日本の近代文学研究者にはかなり難しい。ま、現在はプロレタリア文学の研究者自体ほとんどいないのだが。
そう言えば、その人、ルームメイトは「CIA勤務」と言っていた。表向き「何の仕事をしているのは知らない」とも。こういうことは米上流階級の子弟にはよくあることらしい。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
