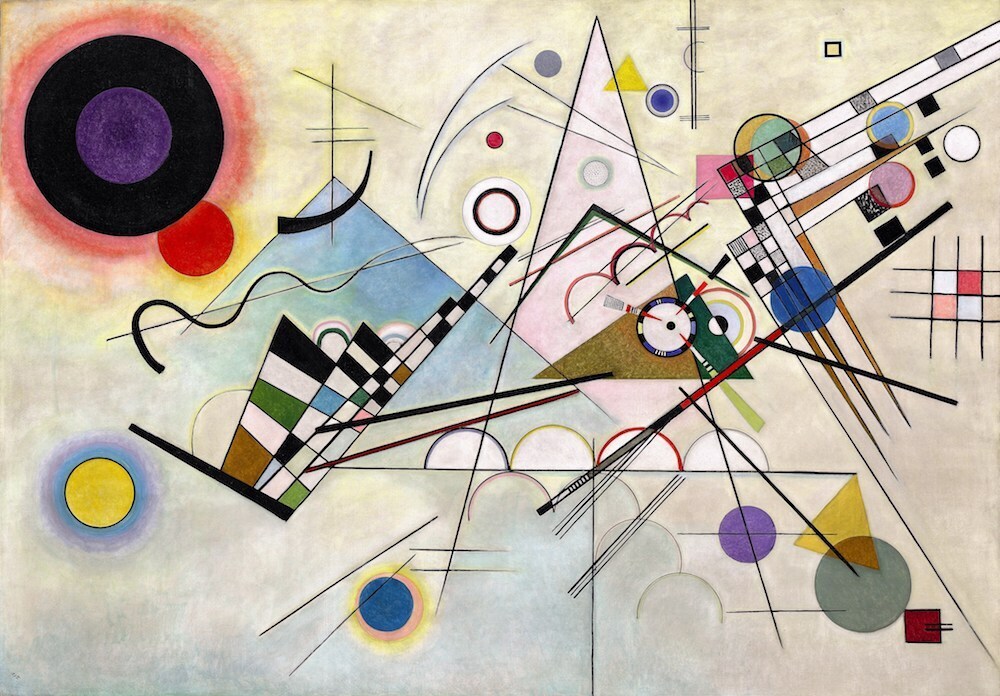
2000年代、ラテンアメリカで「反グローバリズム」が一定の広がりを見せていたころ、小沢健二は父親のドイツ文学者の主催する雑誌で、「うさぎ」という童話=政治評論を書いていた。
米国を基地帝国を命名し、それにチャベスのベネズエラやモラレスのボリビアの「反自由主義」を対置する、なかなかに要領よくまとまった評論だったので、1年生の学生にテクストとして読ませたりした。
「うさぎ」では新自由主義の問題だけではなく、ラテンアメリカの宿痾とも言うべき、大土地所有制と白人人種主義にも的確に触れられていた、と記憶する。
私もそこで小沢健二に一瞬期待したのだが、結局日本に戻ってコンサートもどきをやると、少し「左傾化」したと言われただけで、すぐに80年代「オリーヴ」的なものに撤退していった。
その時、やはり首都圏文化エリート2世の「ひよわさ」を実感した次第である。そもそも読者の少ない父親の主催する雑誌に連載する、という最初の選択からして「腰が引けている」。
なんとうちの大学の小さな抗議運動のテント村を、イスラエル支持のユダヤ系学生とその親らが殴り込む騒ぎがありました。教え子からの通報に急遽駆けつけ、大学警察に、学生から騒ぎを聞き、心配で見にきた教員である旨を伝え、抗議する学生らのバックには応援する教員が控えていることをアピール。なんと、親らが暴言を吐きながら、テントに入り、差し入れのランチなどと捨てたりする暴挙。私が到着した時点では、親の1人は逮捕され、一件落着のようだったんですが、5分くらいで、今度は子供ら(学生)も引きつれてまたやってきて、学生らに罵声を浴びせる騒ぎ。抗議学生らは全く無視して取り合わないので余計に腹が立つらしく、母親は、「テロリスト野郎!お前らは大バカだ!お前らは大学も授業料払わずタダ乗りしてるくせに。私は年間8万ドル払ってるんだぞ!(肌の色が茶色=貧乏=奨学生=タダ乗り野郎、という偏見)
で、「ガザの人間はガザの出入りは自由なのに自由の出入りできないのは私だ、何がアパルトハイトだ!」「イスラエルは敵のガザの人間にでさえ、寛容に医療提供しているのに、嘘っぱちを撒き散らしているのはガザの連中だろ!」とか、唾を吐きながら10分以上も絶叫してました。
もうなんだか異次元で、シオニストの世界観を垣間見ました。怖かった。😳😳😳
安彦良和に『ジャンヌ』という作品がある。山岸涼子にも「レベーレーション」というジャンヌ・ダルクを扱った漫画があり、日本では「オルレアンの少女」はなかなかの人気である。これが敵国だった英国では、シェイクスピアをはじめさっぱり不人気なのは、やはり百年戦争の敵国同士だからだろう。
ところで、安彦はすっかり「負け犬」モードだった仏の急転直下の勝利の要因として、長槍歩兵の密集隊形の登場をダイナミックに描いている。
長槍歩兵の密集隊形(パイク)が15世紀に急速に前景化したのは事実だが、ほとんど降伏寸前だった仏があっという間にイングランドをドーバーの彼方に追い払ったのは、砲兵隊。この仏砲兵隊の出現によって、従来の防御要塞は一旦その機能を失う。百年戦争終結の1453年が同時にコンスタンチノープル陥落の年でもあるのは、象徴的である。
火縄銃ないしマスケットは15世紀中には全欧州に普及したが、決定的な役割は果たさなかった。日本では1575年の長篠の戦が「火器の時代」への象徴とされるが、どうもこれは18世紀位につくられた伝説らしい(有名な屏風もその頃のもの)。
欧州では機動性のある騎兵と防御に勝る槍兵及び砲兵の兵科連合が緩やかに18世紀まで続くのである。ただし中世後期的な重騎兵は姿を消すけれども。
なんとなく、新聞の縮刷版を見ていたら、alcのEnglish Journal1987年4月号の広告が目にはいりました。
「中曽根発言にモノ申す 日本に来た初めての黒人大統領候補 ジェシー・ジャクソン師」と書かれていたのです。
English Journalといえば「ハリウッド人気俳優のインタビューで英語を学ぼう」みたいな記事ばかりだと思っていたのですがこんなふうに米国の黒人活動家が中曽根批判をするインタビューが載っていた時代もあったのですね。
現在、あまりにもいろんな表現物から「政治」が抜きさられてしまい、「政治」を扱うのが特別なことであるかのように肩肘張って考えられがちです。
でも、普通に私たちが生きているなかに当たり前に「政治」は存在しているのに、表現内容から消し去っているほうが不自然です。
この「中曽根発言」は、おそらく1986年の
「しかも日本はこれだけ高学歴社会になって、相当インテリジェントなソサエティーになってきておる。アメリカなんかよりはるかにそうだ。
平均点から見たら、アメリカには黒人とかプエルトリコとかメキシカンとか、そういうのが相当おって、平均的にみたら非常にまだ低い」
という発言と思われます。当時の英語学習者がこの発言の問題にちゃんと向き合うべきなのは当然ですよね。
アストル・ピアソラの「リベルタンゴ」を久しぶりに聴く。
かつて、ピアソラについてのドキュメンタリーで、息子が「父さんののスタイルはもう古い」と啖呵を切っているのを見て、「やれやれアルゼンチンでも同じ構図か😭 」と思って残念に思ったが、やはりピアソラは凡百の後続者よりもよい。
15年程前だったがフィギュアスケートで鈴木明子という選手が「リベルタンゴ」を華麗に滑っているのに感心して、ふと本屋で「自伝」を手に取ったことがある。
これは、非常に残念な経験だった。やはりスポーツ選手の言語による自己認識と身体の訓練は全く別物である、と思うことにした。
これは漫画家にも言えて、安彦良和は、なかなかに面白いテーマを扱い、またアニメ出身らしくダイナミックな絵もうまいのだが、「自己の全共闘時代」を自ら語った本読んだ時は脱力した。
この時も、バルトではないが、作者(の思想)とテクストは別、という典型的な例と言い聞かせることにした。
BT
与那国、そういう事情があるのか・・・。
石垣島も自衛隊ウェルカムな自民党市長みたいですね。
政府に「防衛体制強化」の要請をしたり、
わざわざ石垣市から尖閣諸島の調査船というのを出して自分も同行したり(中国にいやがられて最近も抗議されてる)、
市議会で基地反対派の野党議員が質問してる途中で「着ている服が派手でおかしい」とかいちゃもんをつけて話をさえぎったり。
地方がいろいろと財政が苦しかったりする事情もあるでしょうし、政府の「南西シフト」という名の軍備増強をこういう右派の首長が政府と一緒になっておし進められていくの、みんなで何とかしたいですね。
(参考)
・陸自 与那国島に「電子戦部隊」など 県内2か所に追加配備(NHK・3/21)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20240321/5090027098.html
・石垣市の尖閣調査に中国が抗議 「政治的挑発」などやめるよう求め(琉球新報・4/29)
https://ryukyushimpo.jp/news/politics/entry-3026983.html
・(社説)平和憲法と「戦争の影」 「国民を守る」を貫くためには(朝日新聞・5/3)
https://www.asahi.com/articles/DA3S15926228.html
@pandapanda
経済的な理由は大きいと思います…!
もうひとつ、「外国から攻めこまれる」という形での戦争への恐怖ばかりを繰り返し煽られているのもありそうです
もしも攻めこまれたら島民だけ見捨てられる、という不安が強くて(事実だと思いますし)、「軍隊がいて代わりに戦ってくれるべき」となっているのかも(いても島民が悲惨なのは変わらないし、むしろ戦争を呼び込むかもなのに…)
違う離島住まいですが、「外国が攻めてくる」形の戦争の脅威は日常会話の中で簡単に通じます
でも「日本から宣戦布告する」ほうは考えてない人が多いです
加害者になる危険は考えず、被害者になることだけ心配しているので攻撃的になるのかも…歴史教育のせいですかね…😢
与那国、2015年の住民投票で賛成多数になって自衛隊を招致、自衛隊員とその家族で島民の約2割(250人)占めるらしい(2017年内閣府)
2021年に自民公明推薦の前町長後継と争って、無所属の新市長が大差をつけて当選したけど、どっちも政策としては「自衛隊は必要」を主張してたらしい
さっきの記事を読むと防衛を超えて好戦派に見えるけど…
外からでは情報が少ないけど、反対派は選択肢がない選挙だな
離島民としては想像すると怖い
BT
小尻記者の事件。
あれからいろんなことがありつつも、ずっと大手マスコミは忖度・萎縮しつづけて、ここまで来てしまったという感じがしますね。
この記事に出てくる、在日コリアンの男性は、たぶん映画「1985年、花であること」という映画を撮った金成日監督だと思います。
映画は徐翠珍さんという神戸の華人2世の方の半生を撮ったもので、金監督自身も指紋拒否運動をいっしょに闘っていた仲間として、映画内に登場しています。
(そして、運動の成果が「特別永住者は指紋押捺しなくてよい」という法律として結実し、特別永住者の金監督とそうでない徐さんの明暗が分かれてしまったことも、徐さんのいわゆる「関西のおばちゃん」的な軽妙な口調で、ほろ苦い笑いとともに語られるのですが)
この映画を見ると、「あぁ、権利が保障されない立場で、こんなに頑張って闘っている人がいるんだな」と目が覚める思いがします。
たまに上映会が行われることもあるので(特に関西では)、そういう機会にはご覧になることをおすすめします。
(私自身は、数年前に文化センター・アリランで上映したときと、最近上智大学のウェブ上映会で見ました)。
いわゆる赤報隊が朝日新聞を襲撃した事件。先日在日コリアンの知人が、「左手人差し指1本だけでいいのにこの機械で10本取られるのだ」と話してくださった。それに憤った小尻記者の命日は、あす#憲法記念日 でもあります。
URLの有効期限は5月3日 18:07です
小尻記者が報じた指紋強制具の絵、30年ぶり当事者に
宮武努
2017/5/31 10:36 朝日新聞有料
https://digital.asahi.com/articles/ASK5Z536LK5ZPTIL01R.html?ptoken=01HWW8YMTJAAGG019NWKX2M3WH
能登半島地震4カ月 解体終了は想定の1%以下、建物の未登記が壁に
https://news.yahoo.co.jp/articles/27914d55cba60f9a5469c1cd71f674888ed89e4f
“解体するには、建物の所有者を確かめる必要/代々同じ場所に住み続けている家族が多く、名義が2~3代前のままという「未登記」のケースが/所有権が移転されていない場合、解体には相続の権利がある関係者全員の同意が原則必要なため、申請や審査に時間が”
“県構造物解体協会の幹部は、水道などのライフラインが十分に回復していない状況などから、600班が同時に作業できるようになるのは今秋とみており、「来年10月に解体をすべて終えるのはきつい」と”
国会図書館デジタルコレクションで調べてみたら、カート・ヴォネガットの『ジェイルバード』も入っていました。
https://dl.ndl.go.jp/pid/12708331/
サッコとヴァンゼッテイ事件のことを扱っている小説だそうなので、以前から読みたかったんですよね。
この国会図書館のサービス、ウェブで利用者登録をするだけで使えます。「本人確認書類」は、保険証をスキャンして、番号のところは「ペイント」で消して、登録しました(番号のところは消すように登録の案内で書かれています)。とても便利です。
ただ、ここまで便利だと、古本屋さんの商売あがったりなのでは、と毎回少しだけ心配になります。
ついに発売された#地平社 の本。いつのまにか電子書籍(Kindle)も用意されてますね。
『デジタル・デモクラシー』、『絶望からの新聞論』、『ルポ 低賃金』についてはすでに発売済み。
『世界史の中の戦後思想』、『経済安保が社会を壊す』、『NHKは誰のものか』は5/13発売みたいです。
電子書籍派の人にもアクセスしやすくなりますね。
「荒野のリア王」、木庭顕さんの近著、やはり各所にさざ波を起こしているようだ。これは、リア王の咆哮の「猛々しさ」からして当然ではある。
ただ、木庭さんの1970年代半ばから、戦後日本は激変、知的世界の風景も一変した、という見立てには私も同感である。
これは私の言葉で言えば「新自由主義的再編のはじまり」、ということになる。
1981年の第二臨調を大きな指標とすることも25年前から私が主張していたことである。
また1951年生れの木庭さんは、自分達の「世代」=「全共闘」ないし「団塊の世代」は、「戦後的言説」の継承に完全に「失敗」した、と位置づける。これも大きく見れば妥当な所だろう。
自分も含めたこの世代に関する木庭さんの総括はこうだ。
「高校時代以来周囲にあった彼らについて持った私の感触は、純朴だが夢想的で全然当てにならないということ・・それでいてしばしばぎらぎらした野心だけは光っていた。思考が雑で、深く考えることはなかった。すぐ行動に走り、乱暴であった。・・その後知ることになったのは彼らが無節操で簡単に豹変することことであった。リーダー達はあからさまに立場を変えて権力にすりよった。」
「例外」への留保はあるものの、かなり手厳しい。ま、強い反発があるのも当然ではある。
【大川原化工機事件】女性検事は「起訴できない。不安になってきた。大丈夫か」 裁判所に提出された生々しすぎる「経産省メモ」の中身(デイリー新潮)
#Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe467363bb9af4090379ef4add4835cb1cd1800e?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20240430&ctg=dom&bt=tw_up
原告側代理人である高田剛弁護士は、国と都が控訴してくることを予測していた。その理由について「(起訴を決めた東京地検の)塚部(貴子)検事は、最高検の決裁を取っていた。地方裁判所の判断を受け入れることはできないのではないか。他方、警視庁は、判決が偽計や欺罔(ぎもう)を用いた捜査だったと強く非難されたことを認めたくないのではないか」と見ていた。
いま、Jasper FfordeのRed Side Storyが、177円になっています。
発売してから初めての「うれしいお買い上げ」価格ではないでしょうか。
※ジャスパー・フォードはイギリスの作家で、基調に資本主義批判の要素があるファンタジー小説を書いています。
『最後の竜殺し』、『雪降る夏空にきみと眠る』などが翻訳されています。
#JasperFforde
#洋書 #kindle洋書 #うれしいお買い上げ
QT: https://fedibird.com/@marie__100/112334232511251573 [参照]
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
 朝日新聞デジタル
朝日新聞デジタル
 #入管法改悪反対
#入管法改悪反対
