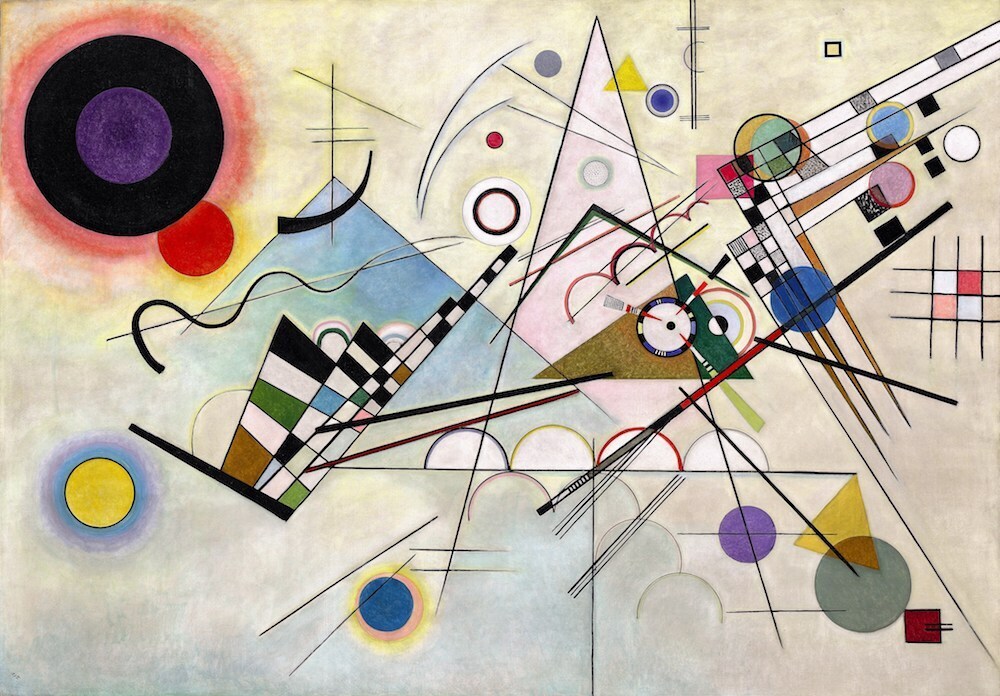
今からちょうど10年ちょっと前に当時「資本主義の終焉」論で有名な方と対談したことがある。
その方は、「利率から見て資本主義はもう終わっている」という見立てで、私は「資本主義は簡単には終わらないし、現に終わっていない。また資本主義は政治経済が複合したシステムであり、利率だけみて全体を判断できるものではない」という構図になった。
これは今から見ると、公平に見て私の主張に妥当性があったと思う。
また対談の終りで、私が資本主義の地球化に対して、「自由、平等、友愛」のフランス革命の理念は、今こそ輝きを増しているのでは?と話すと、お相手は「そういう近代の話はもういい、って感じなんですよ」と応じられ、このあたり絶望的なまでの世代ギャップを感じた。(ただし、本になる過程でフランス革命の理念はそれなりに評価するという文言に代わっていたが)。
現実はウォーラーステインが言うように、「自由」にして「平等」がほんとうに実現していたら、近代世界システムとしての資本主義はもう「この世」に存在していなかった筈である。
今でも広告的に「新しい資本主義」とか「資本主義の終焉」とかいうフレーズが広告的に流通している節があるが、これには警戒が必要だろう。
近代世界システムはそんなに「脆い」ものではないのである。
興味深いツリー。1978年、公害を研究しようとすると産業界から大学に圧力がかかり、研究を止めざるをえなかったという。
Kenji ShiraishiさんによるXでのポスト
“ 「私たちが問いたいのは、これほどの大事件でありながら、水俣病の本格的な化学研究が行なわれなかったのはなぜかということです。チッソが行なわなかったのは非道徳です。そして、企業の研究室でも、行政の研究機関でも、大学の工学部でも、水俣病の発生原因に関する研究は今日に至るまでタブーでした。これは、驚愕すべきことではないのでしょうか。日本には五万人を超える応用化学の研究者がおり、この四〇年間で多分二〇万報以上の論文が出たでしょう。しかし、水俣病に関する化学的な研究は皆無であり、本書が最初の、そしておそらく最後の本格的な研究なのです。
西村肇; 岡本達明. 水俣病の科学 増補版 (Japanese Edition) . 日本評論社. Kindle Edition. 」 ”
https://twitter.com/knjshiraishi/status/1789322914145488924?s=46&t=olpZ4O8cuV2yROWgx_c3Rg
LINEの経営から韓国のNAVER系をはずす話、もともとNAVERの子会社だったLINEを日本が取り上げようとしている、
日帝とおなじようなことをしているのにユン政権はなぜそれを止めないのか日本に甘すぎる、という感じで韓国では批判的に連日報道されているようですが、日本だとあまりそういう点からの報道がないような気がします。
この毎日新聞の記事では
韓国野党代表「松本総務相は伊藤博文の子孫」 LINE問題巡り
https://mainichi.jp/articles/20240511/k00/00m/030/140000c
「植民地支配とLINEヤフーを巡る問題を結びつけ、韓国内のナショナリズムをあおっ」て、野党がユン政権を批判するために利用しているかのように書かれていますが、これは因果関係が逆だと思います。
比喩ではなく、実際に初代韓国統監「伊藤博文の子孫」が、LINEなどを所管する総務省(前身は内務省。戦前は治安管理をしていた)の大臣をやっており、うまくいった韓国企業の日本での経営権をとりあげようとしているのだから、現に日帝の連続性の表れと考えるのは、当然ではないでしょうか。
LINEの話は措くとしても、いまだに「伊藤博文の子孫」が大臣をやっているような自浄作用のなさをなんとかしないとどうしようもないところまで、日本社会はきていると思います。
福島みずほ 参議院議員 (社民党 党首) 「X」2024/05/10 投稿
「国会に本屋さんがあります。その本屋さんで月刊誌を取ったり大変お世話になっています。その本屋さんに地平社の本が並べて販売されていました。とってもうれしかったです。ぜひ読んでください。」
https://twitter.com/mizuhofukushima/status/1788711745273667592?t=aojpuantX0HtD5yzCFbz5Q&s=09
逆境の人生に屈しなかった在日コリアン1世の女性たちの明るい闘争
https://japan.hani.co.kr/arti/culture/49970.html
川崎重工も、神戸製鋼も、ともに売上高過去最高、という一般市民にとってはわけがわからないニュースが出ているときだからこそ、署名を拡散させましょう!
このオンライン署名に賛同をお願いします!「川崎重工はイスラエルの軍需企業との輸入代理店契約を、ただちに破棄してください!」
https://www.change.org/p/川崎重工はイスラエルの軍需企業との輸入代理店契約を-ただちに破棄してください/exp/cl_/cl_sharecopy_490048988_ja-JP/2/1006765427?utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_490048988_ja-JP:2
イスラエルは、エルサレムの国連の難民援助する組織の事務所に放火。もう完璧な「ならずもの国家」。
https://www.axios.com/2024/05/09/israel-fire-palestinian-aid-refugee-jerusalem
琉球朝日放送「誰のために島を守る」。
公式配信はじまっています。
https://www.qab.co.jp/movie/episode/southwestshift
憲法記念日の「改憲して交戦権を」発言で話題になった糸数健一与那国町長も登場します。
この番組、ほんとうに見てよかったです。
日本最西端の島・与那国のことを全然知りませんでした。
そもそも二十数年ほど前の「平成の大合併」のとき、与那国も近隣の島と市町村合併するかどうか問題になったそうです。
そして、当時の尾辻吉兼町長を中心にみんなが一緒になって、近隣との合併はせずに、島の特産農作物を作り、近隣の島や台湾東部(花蓮市など)との連絡・交通を直に行いながら、自律的に島の運営をしていこう、という「自立ビジョン」計画がつくられました。
その案をつくるメンバーのなかには当時は農家だった糸数健一氏(今の与那国町長)も・・・。
しかし、いよいよ計画が動き出すときになって、中心人物だった尾辻町長が倒れ、亡くなってしまう。
その後、「地域振興策」として自衛隊基地を迎え入れる方針の町長が当選し、今に至っている・・・。
なんともやるせない気持ちになりました。
琉球朝日放送の力作です。
岩波から独立して新たな出版社「地平社」を立ち上げた熊谷伸一郎さんと一緒に那覇のジュンク堂でお話しする予定です。今のメディア環境であえて、6月から月刊誌『地平』を刊行する熊谷さんの挑戦についても聞きたいと思います。
南 彰 MINAMI Akira / 絶望からの新聞論(地平社)
https://twitter.com/MINAMIAKIRA55/status/1788332065978818974
2020年代に入ってのラテンアメリカでは、新自由主義のさらなる加速によって深められた矛盾が、いわゆる「急進左派」の巻き返しとなってあらわれます。
一度米国と資本家・大土地所有者の寡頭制の同盟によって覆されたブラジル、ボリビアでのルラ、モラレス派の復権、チリでの元学生運動家の大統領当選などはその象徴。
しかし、最も衝撃的だったのは、極右と米国にとって「難攻不落」の要塞であったコロンビアでの左派政権誕生です。
コロンビアは、地政学的に中米と南米を扼する位置にあり、WWII後常に親米右派政権が掌握してきた。
2000年代に仮にコロンビアが左派となっていたとしたら、ベネズエラとボリビア、エクアドルが連結する、まさにシモン・ボリバルが夢見た「大コロンビア」が成立していただろう。
勿論、そうはさせじとコロンビアでは長年CIAと麻薬カルテルに支えられた巨大な民間右派ゲリラが暗躍してきた。
しかし、2023年ついに急進左派のグスタボ・ペドロが大統領に当選。2018年のメキシコのロペスオプラドール(左派)に続いて、ラテンアメリカの左傾化は新たな段階に入る。
ただし、議会での右派の力は依然として強い。またブラジルのように福音派原理主義(プロテスタント)が極右の大衆的支持基盤となっている。
9 mai 1921 : Naissance de Sophie Scholl, figure de la résistance allemande face au nazisme.
Avec les autres membres du réseau étudiant « La Rose blanche », elle est arrêtée par la Gestapo en février 1943 et exécutée. #CeJourLà
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Scholl
「世界社会フォーラム」。
経済のグローバリゼーションをすすめる「ダボス会議」(世界経済フォーラム)に対抗するためのもので、だからこそ「もうひとつの世界は可能だ」(Alter-globalization)なんですよね。
最近、「ダボス会議」について書かれた本『ダボスマン』を少しずつ読んでいます。
少数の並外れたお金持ちの経営者たちによって世界経済が左右されるという傾向は、20年前よりもさらに強まっており、そういった資本主義の寡頭的支配ではない、搾取-非搾取ではない「もうひとつの世界」をいろんな国の仲間とともに指向していくことの必要性がさらに強くなっていると感じてます。
サッチャーは「社会なんてない」と言ったそうですが、なんでも民営化すればいいという彼女の考えが間違いだったことは、今でははっきりしています。
「社会的なもの」socialを消そうとしても、そんなことは無理なのです。
#ダボス会議 #DavosMan
#オルターグローバリゼーション
#Alterglobalization
#世界社会フォーラム
#WorldSocialForum
「外国人差別のルーツは日本の植民地支配」 川崎でシンポジウム、人種差別撤廃法のモデル案を公表
https://www.tokyo-np.co.jp/article/325527
外国人に対する差別の構造を解き明かそうと、在日コリアンが多く暮らす川崎市で「日本の植民地主義と奪われた外国人の人権」と題したシンポジウムが開かれた。同志社大の板垣竜太教授(朝鮮近現代社会史)は講演で、植民地支配で形成された朝鮮との関係性が戦後も克服されず、レイシズム(人種、民族差別)に根ざした法制度がつくられたと指摘。差別撤廃法や人権救済の制度が必要とした。
学者や弁護士でつくる「外国人人権法連絡会」(東京)が4月27日にシンポを開催し、オンラインと合わせ約100人が参加した。
板垣さんは裁判で関わった差別の事例として、在日コリアンが集住する京都・ウトロ地区で起きた2021年の放火事件や「祖国へ帰れ」との投稿が差別と認められ、在日の女性が23年に損害賠償を勝ち取ったネットヘイト訴訟などを紹介。差別を生み出す土壌として植民地主義を挙げた。
◆「外国人の人権擁護よりも管理を重視してきた」
1945年12月、日本では女性の参政権が認められる一方、在日朝鮮人、台湾人の参政権は停止。日本が主権を回復した52年のサンフランシスコ講和条約発効の際には朝鮮人、台湾人は日本国籍を剝奪された。「戦後日本では平和民主の流れの裏側で、外国人の権利は失われていった」
入国管理局幹部が60年代に自著で「外国人は煮て食おうと焼いて食おうと自由」と述べた言葉が象徴的とし、「差別撤廃に消極的で、植民地支配責任を否定し、外国人の人権擁護よりも管理を重視してきた」と政府の責任を問うた。
この日は、連絡会が策定した人種差別撤廃法モデル案も公表。差別犯罪を定義づけるとともにヘイトスピーチなどに刑事罰を設ける内容で、障害や性的指向を含め幅広い対象の差別を禁じた相模原市の人権施策審議会の答申などを踏まえた。事務局長の師岡康子弁護士は「国際人権基準に見合うものだ」と述べ、実現に向けて取り組むとした。
安倍氏、2013年参院選で候補者に現金100万円 「裏金」か
スイス 非正規滞在者「サン・パピエ」10万人。労働力として頼られる一方、世間から隠れて暮らす
https://bigissue-online.jp/archives/1083182369.html
#bigissueonline
2000年代、日本では「反グローバリズム」というやや誤解を招く表現が流通していたが、正しくは「オルターグローバリゼーション」である。
つまり、新自由主義グローバリズムを批判するが、移民排斥などを伴う「ナショナリズム」にも反対、ということだ。
世界的市民組織としては、世界社会フォーラムが代表的なもので、その中に欧州社会フォーラムもあった。哲学的には相いれないA.ネグリとデリダも共に政治的には「オルターグローバリゼーション」派だった。
私は2003年のパリ郊外での欧州社会フォーラムに出席して、その分科会(30人程)でネグリとカリニコス(英国の第四インター派)の討論でライブのネグリを始めてみた。その際は、欧州知識人らしく、両者とも相手の話を全く無視して自分の言いたいことを滔々とまくし立てていたが、全身を使ったネグリのパフォーマンスは印象的だった。
この時、ラテンアメリカでは、ブラジル、ベネズエラ、ボリビア、エクアドル、チリ、アルゼンチンで中道左派・左派政権を次々と誕生、「赤い米大陸」と呼ばれた。
この波は2010年代に一度押し返されるが、現在再び姿を見せている。一度は逮捕・収監されたブラジルのルラが再び大統領に返り咲き、南アとともにイスラエル批判の急先鋒となっているのはその象徴である。
今日は、中学・高校の同級生で、兵庫県弁護士会長を務め、現在「災害弁護士」として全国を飛び回っている人と十年ぶりにくらいに会う。
同じ中学・同級生で、「緩慢な自殺」とも言える孤独死をした人がいることを知る。
弁護士本人は至って元気で、「災害弁護士」として、阪神・淡路大震災、東日本大震災、能登地震などに飛び回っている。
地元神戸では、それなりに名が知られているらしく、神戸新聞の今年の憲法記念日の社説「災害と憲法」では、本人の名前が5回も引かれている。
今日は、維新の神戸侵略に対抗すべく、「神戸市長選に出ればどうか」という趣旨だったが、やはりそれはいろいろあって難しいらしい。
では、「地平社関西支部長はどうか」ということで話はまとまった。もちろん、この関西支部、現在は存在していない。
いずれにせよ、弁護士だけあって、拙著の「戦後改革と日本国憲法の制定」の箇所は読んできてくれていた。
いつもは「三宅の書いたものは難しくて、途中で投げ出すけど」と言われていたけれども、これも状況の切迫のなせる業だろう。
いずれにしても「維新と安倍派の連合に政権を獲らせるのはは絶対にダメ」という声は関西にもかなりあるようである。
その意味ではまだまだ戦略の余地はあるのである。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
 全体 : hankyoreh japan
全体 : hankyoreh japan
