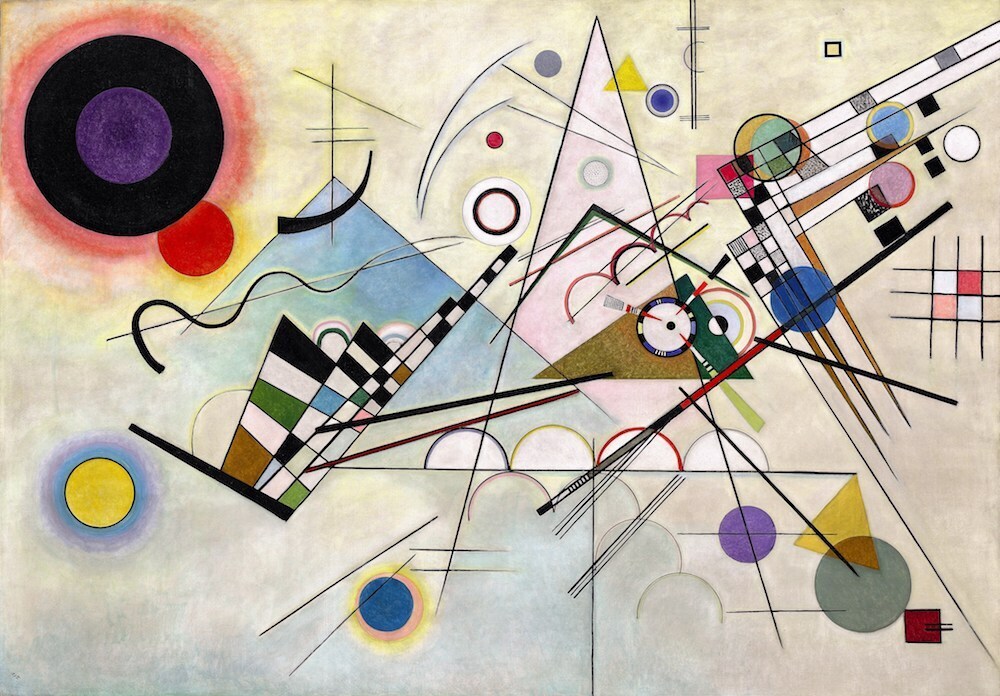
拙著『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会、2019年)です。
ここの所、ファシズムと冷戦に関する投稿が多いですが、もしより詳細な、思想的文脈にご関心の或る方はご笑覧いただければ幸いです。
いわゆる「戦後思想」と呼ばれている言説が「戦中」の「ファシズム」との思想的対決から生れ出た視点を強調しています。
またWWII以後の「グローバル冷戦 cold war」による世界空間の再編の中で、ユーラシアの両端で「独立左派」を模索したフランスと日本の思想を比較する視座を導入しています。
さらに言えば、日本は敗戦によって全ての海外植民地を喪失しますが、仏は形式上「戦勝国」となったため、インドシナ・アルジェリアで1965年まで「戦争」を継続しました。
サルトルと『現代』は、その過程で一貫して「植民地独立」を支持する篝火であり続けます。
また植民地独立後はマグレヴ(旧仏植民地)からの安価な移民労働者の導入(政府も関与)が生み出した所謂「郊外 banlieue」の問題、「クセノフォビア」の問題にも取り組みます。
FNのジャン・マリー・ルペンはアルジェリア戦争でアルジェリア人を拷問する立場にありました。
「記憶の戦争」は仏でもまだ終わっていないのです。
20世紀演劇をS.ベケットとともに代表するB.ブレヒト。
フランスにブレヒトを導入したのは、あのロラン・バルト(1915―1980)でした。
バルトはサルトルの影響下に『零度のエクリチュール』(1953)を著します。
その後、『記号学の原理』などで「構造主義」批評に分類されたりもしますが、『テルケル』でソレリスやクリステヴァに神輿に担がれたりしますが、毛沢東主義にはついていけず(「文革期」の中国には「行くだけ行ったが」)、晩年再び記号論からは離脱。
バルトの青年期の愛読書はジッド(プロテスタント・同性愛者でもある)、ブレヒト、サルトルだった。
バルトは1964年に上梓されたサルトルの幼年期の自伝『言葉 Les mots』を絶賛。「サルトルは近いうちに再発見されるだろう」と予言。
しかし、このバルトの予言はまだ
仏・英・日では広くは「実現」していないようです。
また、バルトのイメージ自体も同様に三カ国すべてで「歪めれたまま」。
バルトの弟子だったA.コンパニオンが「転向」してソルボンヌ教授に収まり『反近代』(19世紀仏における)などという「当たり前」の話を書いて「大物」と見做されている。
「ヨーロッパの心臓」いつ再鼓動してくれるのか?
「終電車」(F.トリュフォー、1980)
ナチス占領下のパリの演劇人の抵抗を描く。
ユダヤ人演出家の夫をモンマルトル劇場の地下に隠し、マリオン(C.ド・ヌーヴ)はベルナール(G.ドパルデュー)を相手役に「消えた女」を上演する。
極右=ナチス協力者の批評家(モデルあり)は芝居を「ユダヤ的」と難癖をつける。この批評家が所属する新聞「Je suis partout]
」は実際に存在した極右。映画では終戦後批評家は「世界中至る所に partout」逃げ回ることになった、と「落ち」が入る。
トリュフォーは、ブニュエル、ゴダールと同じくサルトルの熱烈なファンであり、サルトルの生前に自伝映画を撮り始めたが、これは完成しなかった。
フランス・レジスタンスと「影の軍隊 L' ARMEE DES OMBRES)」
レジスタンスを戦時中(1941)に鼓舞する、或る意味「プロパンガンダ」としての『カサブランカ』を紹介しました。
1941年と言えば、まだレジスタンスはJ.ムーランのような例外を除けば、ユダヤ系、亡命スペイン共和派が中心だった時代です。
ところで、映画としては『カサブランカ』は「物足りない」という方が居られるかも。
そういう方には1969年の『影の軍隊』がお勧めです。
監督J=P.メルヴィルはユダヤ人であり、英国に渡って自由フランス軍に参加しました。メルヴィルとは、ー米国の作家H.メルヴィルにちなんでいますがーこの時のコードネーム。メルヴィルは「ヌーヴェルバーグ」の兄とも呼ばれ、映画史的にも高く評価されている作家です。
WWII後、占領初期の静かな「レジスタンス」を描いたヴェルコール『海の沈黙』の映画化でデヴュー。
ちなみに「影の軍隊」とはヴィシーに忠誠を誓った軍隊ではなく、仏国内の「レジスタンス」組織こそ「共和国」正規軍という意味。ヴィシー政府は「影の軍隊」を「テロリスト」と呼び「法の外」に置く。
「テロリスト」の名称が政治的に大動員されたのは、この時期の仏がはじめて。
なかなかに政治語法というのは難しい。
現在の研究ではアメリカは共産党許すつもりはなく、万一選挙で保守連合が過半数をとれなかった場合、英とともにイタリアを軍事占領する予定だった、ことが明らかにされています。
結果はキリスト教民主党を中心とする保守の僅差の勝利でしたが、スターリンがイタリアに軍事介入する意志がないことを知っていた(であろう)、トリアッティを含めた共産党最高幹部はむしろ、ほっとしたかもしれません。
実際、ギリシアでは社会内部の力関係では優勢だった左派が英軍の介入で排除され、ソ連もそれを見捨てました(というか、チャーチルとスターリンはそのことについて合意していた)。
この映画「1951」では米国人で、イタリアの資本家の妻となったI.バーグマン演じる主人公は、子供の死とともに「社会問題」に目覚め、「イタリア共産党」の文化部長の親族としばらくともに行動するが、結局袂をわかち、半ば自分の意志ともとれる流れで精神病院に監禁される、ところで映画は終わりる。
日本では1951年と言えば堀田善衛の「広場の孤独」が発表された年です。ユーラシアの東端と西端で「国際冷戦レジーム」への抵抗としての「中立主義」が成立し、有意味な参照関係が成立したのは、このような文脈があります。
欧州でその立場をもっとも代表したのはサルトルと『現代』)でした。
R.ロッセリーニ「ヨーロッパ 1951
「無防備都市」、「戦火のかなた」、「ドイツ零年」のネオリアリズモ期のロッセリーニの作品はよく知られていると思います。実際、傑作でもあるし、ゴダールの「映画史」でも、もっとも登場回数が多い三作かもしれません。
1944―45年のイタリアは反ファシズムの内戦(中部・北部イタリア)を人民戦線的な構図をたたかい(ロッセリーニの前2作は、イタリア・パルチザンのたたかいが舞台)、戦後国民投票で王制を廃止し、共和国へと移行しました。
ところが、戦後ただちに地球規模での国際冷戦レジームの構築がはじまり、イタリアは、分断されたドイツ、ギリシアなどともに、ヨーロッパにおける最前線地帯の一つ、となります。
ただし、共産党の存在が認められたように、ドイツ、ギリシア、韓国と比較すると「緩衝地帯」としての要素も入ってきます。
この点、フランスと類似する面もあります。日本は同じく「前進基地」であると同時に「緩衝地帯」とされた点で、近い面もありますが、イタリアは長く共産党(PCI)が過半数に伺うほど強大な点が大きく異なります。
とくに内戦地域になった中部イタリアでは圧倒的。しかし、ロッセリーニは非「共産主義」左派であったため、冷戦の激化とともに、難しい立場に立たされていきます。
鶴見俊輔と網野善彦
鶴見さんと網野さんは、それぞれ1922生、28年生だから現在の感覚では同世代。
しかし、十代半ばで渡米、都留重人の下で批判的マルクス主義を学び、捕虜交換船で帰国後も「反ファシズム」の内心を持ち続けた鶴見さんと軍国少年であった網野さんの「戦争」経験はかなり異なる。
とは言え、ともに「民衆」を語る二人が、「対談」したのは1993
年がはじめて、というのは意外でもある。
これを読むと、網野さんにとって1950年代の「国民的歴史学」と石母田正が如何に大きな存在であったかがよくわかる。
他方、鶴見さんは認識論としてはカルナップ的論理時実証主義の脱構築としての「プラグマティズム」だから、戦後マルクス主義の「真理」論は、ほとんど意に介さず、石母田の当時の論文なども「おやおや」という印象だった。
この辺り、戦後歴史学と戦後思想の錯綜した関係を示すエピソードではある。
また近代日本は結局金時鐘など「在日」の詩人以外は「長詩」を書けなかった、という鶴見さんの指摘は鋭い。「明治以降、何故日本人が長詩が書けなくて、在日朝鮮人がかけたか・・在日日本人の場合、息が短い」。これは研究に値すること。
その他、気軽に読めながらも、知的刺激も満載の1冊です。
『陽の末裔』
私が読んだのは、単行本になってからだが、連載は1985年から。
「陽の末裔」とは平塚雷鳥の「原始女性は太陽であった」から来ている。
東北北部から紡績工場に出された二人の少女の人生を軸にした大河ドラマでもある。
一人はジャーナリストとして労働運動、女性解放運動に取り組んでいく。その中で社会主義運動の中にもある「女性差別」にも気づいていく。
とは言え、幸徳秋水の子である男(創作)と別れて、元特高刑事と結ばれるのは、プロットとして無理があると思うが。尚、前夫は別にDV夫ではない。
今一人は、子爵夫人として社交界の中心となり、実業にも乗り出す。
しかし、両者とも30年代の軍国主義には批判的。
家族内部の葛藤に関しては竹宮恵子、山岸涼子の方が詳細・リアルだが、大正・昭和の女性視点の大河ドラマとしては一読に値するのではないだろうか。
いずれにせよ、タイトル「陽の末裔」はうまい。
(承前)
このインドネシアの1965年の虐殺の「マニュアル」は60年代半ばから70年代にかけてのラテンアメリカの軍事クーデターに転用されていきます。
典型的な例が、73年のチリのアジェンデ政権をCIAとピノチェト、そして民間右翼が連携して打倒したクーデターです(当時民社党幹部は「天の声」と讃えた)。クーデター直前にはサンチャゴ(首都)の至る所に「ジャカルタが来る」というグラフィティが突如現れ、住民たちをパニックに陥れました。
このクーデターの指揮棒を振ったニクソン=キッシンジャーはベトナムに見切りをつけて、すでに大きな亀裂の入っていた中ソの間に楔を打ち込む、という戦略を採用していく。
ちなみに「全体主義」と「権威主義的独裁」という対比は、米国にとってアジェンデ(全体主義)とピノチェト(権威主義的独裁)を比較して、後者が「まし」という(屁)理屈として多用されます。
選挙で選出されたアジェンデをどう定義すれば「全体主義」になるのか不明ながらも、この語用は東アジア・東南アジアにも適用されます。
つまり韓国の軍事政権や日本の自民党は「権威主義的独裁」ではあるが、「左派」=「全体主義」に政権を奪われるよりはまし、という発想。
インドネシアをはじめ、タイやシンガポールなども同様の位置付けで米国は支援。
「アクト・オブ・キリング」と「Look of silence」(上)
1965年ーベトナムへの北爆が始まった年ーインドネシア、スハルト派軍部とCIAの連携、民兵集団の動員により、数百万ともよばれるインドネシア共産党員及び関係者が虐殺されました。
ジョシア・オッペンハイマー(ユダヤ系)監督による、この二つのドキュメンタリーは、加害者(とくに民兵集団)にインタビューを進める過程を映像化しています。
後者には被害者の関係者も登場します。
恐ろしいのは、この大虐殺は未だインドネシアでは公的に批判の対象になっておらず、関係者の処罰も行われていないこと。むしろ被害者側のサバイバーが、身を潜めて生きていかなければならない。
スハルト政権自体は倒れたとは言え、インドネシアのエスタブリッシュメントが、「虐殺」に加担した側との連続性が強いことが根本的な原因でしょう。
本来、インドネシアを研究フィールドにしていたB.アンダーソンはこの事件に関してスハルト政権を強く批判したため、長く入国を拒否され、結果として広く東南アジア全体を研究対象としたため、「比較の亡霊」という名著も生まれました。
日本ではどうも「想像の共同体」を文脈抜きに使いまわす時期が長すぎた。誤訳もかなり多い。
「米ソの宇宙開発競争と映画」
A.タルコフスキー「惑星ソラリス」、ゲルマン「神々の黄昏」、A.ゲルマンJr「宇宙飛行士の医者」。個人的にはA.ゲルマンが初期のものを含めて好きなのですが、
趣味とは関係なく、ソ連時代の米国との宇宙開発競争を背景とした枠の映画が多いです。
ロシア時代に入ると現実では「宇宙開発」というよりは、「宇宙戦争」テクノロジーを競い合っています。映画でもゲルマンJrが枠としては「宇宙開発」(この場合はスプートニク時代を背景にしている)を使っているのを見て、やはりつづいているのだなぁと。
ちなみに一時代話題になった火星の地球化(プロジェクト「テラ・フォーミング」)は、米国でも当面無理だと判断されたようです。
私も、素人ながら、重力、気象などからして数十億年かけて地球の条件で進化した脆弱な「ヒト」が移住するのは不可能だと思います。
その前に地球の生態系が破壊されてしまう可能性の方が高いので、そちらの方が直近の問題でしょう。
こうした流れを反映してか、SF本場のハリウッドでもF..K.ディック原作の「トータル・リコール」第一作は火星を舞台にしていましたが、リメイクバージョンは近未来地球の超階級社会を舞台にしていました。
シモーヌ・ド・ボーヴォワール『第二の性』改訳版
『第二の性』、生島遼一訳を1994年に改訳、さらに加筆修正の上、この3月河出書房新社から出版されました。
訳者あとがきによれば、1988年に「第二の性を原文で読み直す会」に参加した際には、日本でもボーボォワールに対する評価は芳しくなく、その背景の一つに「ポストモダン思想の流行」があったとある。
1988年であれば、おそらく訳者の実感は正しいだろう。
評価が芳しくなかったもう一つの理由は明らかに戦略的なもので「ボーヴォワール」が「男性的主体」を目指す「近代主義」というものだった。
この後者の批判、上野千鶴子さんもいつもしていた。私は上野さんのゼミでこの点を巡って―険悪ではなくー論争したのをよく覚えている。
ところが機を見るに敏な上野さんは、最近すっかりボーヴォワール派になったようだ。これは仏本国のクリステヴァでも同じだが。
フランスでも女性に参政権が与えられたのはWWII以後であり、1949年出版の『第二の性』が影響力をもつのは70年代を待たねばならなかった。
『第二の性』、サルトルの「実存的精神分析」と深い関係があり、現在の英語圏でのクィアーセオリーとも交差する(同じではない)。初読・再読・三読されるに値するテクストです。
著者の酒井隆史さんからご恵贈いただきました。ありがとうございます。
「賢人と奴隷とバカ」、なかなかに挑発的なタイトル。
ただ、中身を読むと、「賢人」=左右の対立を「ない」とする中道学者。事実上サントリー・笹川・上廣財団の提灯学者。
「奴隷」=「賢人」たちの文化ヘゲモニーの下、破滅へと自らひた走るレミングの群れ。
「バカ」は頑固なまでに、「賢人」という指揮者の振る狂騒曲に加わらないリア王のような狂人。
いつもながら刺激的な問題提起。レイシズムを考える上ではサルトルの『ユダヤ人』を再読すべし、と序文で長く引用している。
これは別に私へのエールではない。実際サルトルの『ユダヤ人』にはレイシストの心理が類のない鋭利さで分析されている。
「歴史学研究会」について
どうも最近またまた私が全方位に砲撃しているような誤った印象を与えているような気がします。
マスメディアに関しては「致し方ない」とマストドンの読者の方もご納得いただける筈。
問題は研究者です。確かにここまで私は人文社会科学のほぼあらゆる分野に砲撃を加えてきたように映るでしょう。
しかし現在はほとんどの分野において権力に距離を取りながら社会、思想、哲学を分析する、というスタイルはほぼ崩れ去りました。勿論、例外的に優秀な方は数多くいらっしゃいます。ただ、それは個人であって、「学会」としての「コンセンサス」があるわけではない。
しかし、ここに一つ例外があります。「歴史学研究会」です。通称「歴研」、この研究会は「プロ」の研究者だけでなく、「アクチュアリティ」と歴史記述との関係を常に問いただし、アマチュアの方とも交流するスタイルを保持している唯一の「学会」と言えるでしょう。
ここで急いで付け加えると、私は歴研メンバーでもなければ歴研大会にも行ったことがなく、決して歴研の「回し者」でないことは保証します。
21世紀現在、我々が大分岐点に立たされていること、これは間違いない。ここから未来を構想するためにこそ「過去」から学ぶこと、つまり「歴史」を学ぶことが不可欠になるのです。(続く
アキ・カウリスマキ、27歳のデビュー作「罪と罰 白夜のラスコーリニコフ」
ヌーヴェルバーグと小津安二郎の影響がきわめて強く、まだ後年のカウリスマキの作風ではないとは言え、映像的完成度は非常に高いです
。
ただ、最後は微妙な流れながら、結局ラスコーリニコフが自首(懲役8年)する点は、ブレッソンの「罪と罰」ではイギリスに亡命して、恋人ものち合流、そのまま逮捕もされず、「暮らしました」という落ちとは異なりました。
ブレッソン(これもヌーヴェルバーク的映像)の方はいかにもフランス的ですが・・・
とは言え、カウリスマキ・バージョンでも「大地に接吻して許しを請う」という流れではなく、監獄でもあくまで「反社会的」な姿勢を崩さず、というラストです。
カウリスマキやドストエフスキー、あるいは小津安二郎がお好きな人にはお勧めです。
先日、BBCとガーディアンが岸田ウクライナ訪問を小躍りして報道していることを投稿しました。
他方、仏の月刊誌「Le Monde diplomatique」3月号では1面トップ、計3面使って「軍事費倍増」を「平和主義の終焉へ」と批判的に報道・分析しています。
ここではロシア・北朝鮮を「敵」と見做し中国を「戦略的競争国」と区分していることまで紹介されています。
下に貼り付けた地図は現在の東アジアの地政関係。「米国の保護下にある海軍大国」という皮肉なタイトルつき(たしかに経費では世界2位)。
星印は米軍基地。首都圏以外には沖縄に集中していることが一目でわかります。在日米軍53973、在韓米軍25372、と一桁まで記してある。これに日本・韓国には戦略核を配備(原潜)している訳だから、核を実戦配備していない中国との非対称は明らかです。
ちなみにLe Monde diplomatiqueは日刊紙のLe Monde とは全く別。近年ネオリベラル化著しいLe Mondeと対照的な「左派」の雑誌。
Mediapartは右傾化するル・モンドと袂を分かった記者たちが2008年に創刊したメディア。こちらは新自由主義に批判的な記事を多く掲載。
ただ国際的な記事・論説はDiploが有益です(尚両誌とも英語版あり)。
「人文学と社会科学の架橋」
何度か、人文学と社会科学の架橋の必要性について投稿してきました。
2000年代に「ディアスポラ」と「新自由主義グローバリズム」双方について、この視点から思想史、文学、歴史学、政治学、経済学など専門を異とする人々と共同研究を行いました。
「ディアスポラ」研究は、ポストコロニアル研究の延長線上でもあり、当時の日本としては先駆的なものであったと思います。ただ、栗田禎子先生の「伝説の締め切り破り」のために発刊1年半は遅れましたけれども。
こちらの研究に参加、ご寄稿いただいた多くの方が「歴史学研究会」編の「歴史学のアクチュアリティ」に参加していらっしゃいます。
人文学の細分化と社会科学の体制化の中、現在直面している新自由主義グローバリズムと近代世界システムの危機を長期・中期・短期それぞれの次元において、分析・叙述する中で、新しい学問、批判理論を練り上げることが求められている、と思われます。
シェイクスピア史劇「嘆きの王冠」(下)
逆に、若き日のヘンリー5世(ハル王子)を描いた「ヘンリー4世 第二部」は20歳くらいの時から、オーソン・ウェルズのものも含めて4回くらい見ているのですが、年をとるにつれて、「王族・貴族」の傲慢さへの嫌悪が募るのは不思議です。
このシリーズでリチャード3世を演じたB.カンバーバッチ、実際にリチャード3世の遠縁にあたるらしい。
1485年のボズワースの戦いで斬死したと伝えられていたリチャード3世、それらしい遺体をDNA解析したところ、本人だと確定した。こういうこともあるのだなー。
リチャード3世に代わり、王位についたヘンリー・チューダーが「小ブリテン主義」を採用、ここに英仏政治権力は最終的に分離していくことになります。
ちなみにシェイクスピアはチューダー朝ルネサンスの芝居なので、基本チューダー家の人間に好意的、逆にリチャード3世を可能な限り「悪」に描く必要あり、それが現代にも通じる「悪」の結晶の造形の成功に繋がったとも言えます。
日本では「リチャード3世」、あまり上演されないようだが、英語圏では実はシェイクスピア劇の中で最多の上演だとか。
いずれにせよ、英国のシェイクスピア俳優にとっては「ハムレット」より「リチャード3世」が栄誉です。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
