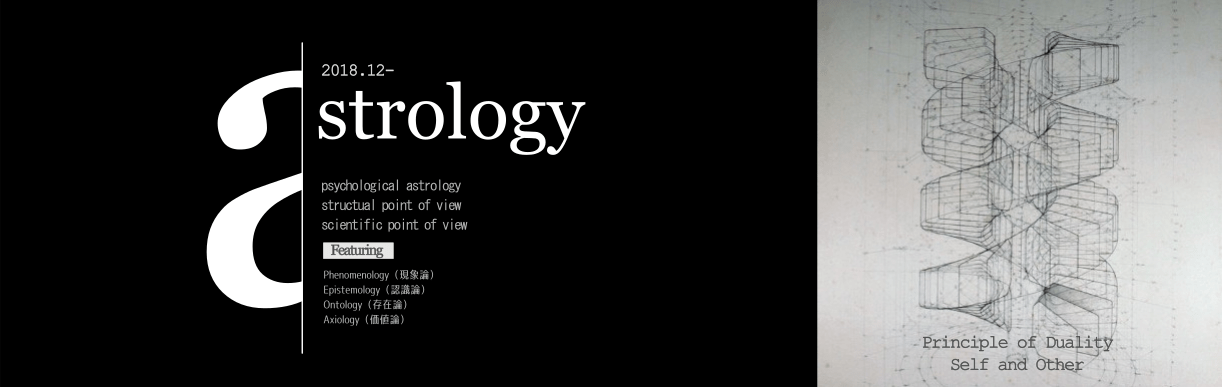
記憶というのは、自分が選択した(注意を向けた)部分の映像を、そこに自分が感じた印象を加えながら、部分部分として取り上げ、まとめあげたもの。だから、それらは人によってすべて異なる。
客観的映像なんていうものは、私たち個々人においては存在しておらず、それは別次元のあり方になる。
例えば、以下の動画は街を歩いている映像だが、こういう客観的映像は私たちが日常の中で見ているものとは違う。なぜなら、
・どこに注意を向けているのか?
・その注意を向けた視野にどんな印象を持っているのか?
について、何も語っていないからだ。
●Night Walk in Tokyo Shibuya (東京散歩)
https://www.youtube.com/watch?si=Y-FvpkcT0f_77pPG&t=680&v=0nTO4zSEpOs&feature=youtu.be
本当はそこにこそ、それぞれの人の個性が現れるものなのに、それらがまったく伝えられない。そして、記憶というのは「このシーンとこのシーン、それからあのシーン…」と印象に残ったものの総合としてあるものだから、こういう連続的な、延長的なもの(映像)としては存在しない。
【視覚映像と記憶 -ドラマ「ブラックミラー 人生の軌跡のすべて-】
面白い記事を見つけたので、そこで取り上げられていたドラマを見た。
●NETFLIX ブラックミラー〜人生の奇跡の全て〜評論
https://note.com/kinajosouri/n/nee9aa58a09e8
近未来、人は体内にチップを埋め込むことにより、自分の網膜に映った映像をすべて記録するようになる。いわば「カメラやビデオの進化版」といったもの。それにより、その映像を客観的証拠(事実)として他者と共有するようになる。
このテーマ自体はとても奥が深く、いくつも考察の余地があるが、一旦脇において、ここでは「視覚映像と記憶との違い」について書いてみたい。
写真(カメラ)や動画(ビデオ)として撮った映像は、網膜に映った視覚映像を表しているが、私たちが実際に見ている映像(感じている映像)は実は同じではない。
感覚心理学・知覚心理学が示しているように、私たちは網膜(光の反射をとらえたもの)に映った映像のすべてを見ているわけではない。自分が注意を向けた部分(興味をひかれた部分)を選択し、そこを主に見ている。それ以外の情報は脳内でカットされている。
●見えているようで,見えていない?(選択的注意)
https://www.youtube.com/watch?si=eIzac8tptDrHvC2R&t=15&v=yu4ZU3YrMdU&feature=youtu.be
⑤ 母性の自立
変な表現になってしまったが、「母性」にも自立した表現というものがある。一般化と言ってもいい。自分が望む、特定の子供に、好きなやり方で母性を表現する―のではなく、誰に対しても、どんな人に対しても、受け入れられるような「母性(慈しみの心)」を表現すること。
映画では、このあたりを端折って表現してしまった。
あんなに身勝手で、横暴で、わがままだった義母が、最後は寝たきりになり、認知症になる。その義母が言うのだ―「ルミ子さんは私の大切な娘なの」と。
そこには、それまで散々義母に尽くしていた(大切にしていた)ルミ子の行動がある。例え、義母が私を嫌いでも、私が義母を好きではなくても、つながりのできた人を思いやっていこう。
おそらく、母性(父性も)の本質はこういう慈しみの心であり、ルミ子はこの境地にたどり着くために、これまでの苦難を味わってきたのだと思う。本当ならその軌跡こそ、しっかり描いてほしかった。
母性とはなにか?―その本質を探るなら。
⑥ 女優さんの演技力
最後に。戸田恵梨香さんと高畑淳子さんの演技が圧巻だった。
●映画『母性』 予告
https://www.youtube.com/watch?si=x4mfcZhidNoorFLd&t=16&v=UEiLnMfa3xU&feature=youtu.be
④ 親と子の相性
この映画では母が自分の娘を愛することをなかなかできない―その葛藤を描いていた。それは母が「下のものを慈しむ気持ち」がなかったからではなく、その気持ちが娘の求めるものと一致していなかったからと言える。
これはホロスコープにおける相性問題と同じで、「上の者が下の者を慈しむ気持ち」にもスタイルがある。火的であったり、地的であったり、風的であったり、水的であったり。その自分が表現しようとするスタイルが、子供の求めるスタイルと一致しないと、母は(娘も)葛藤することになる。
自分は風的に子供を慈しもうと思っているのに、子供は水的に慈しまれたいと思っている。そうなると、子供は親の思っているように行動(考え)してくれなくなり、不満・イライラを感じるようになる。
・ なんで…?どうしてなの?ねぇ、どうしてなのっ!!!!
これは親となった人が誰しも経験することではないだろうか。自分が思い描く理想的な親子関係にならない。
だが逆に、もしそういう理想的な親子関係だったら、人は健全な自我を形成できなくなる。母子一体化という執着的意識によって。
※ それは母(ルミ子)にとっての実母への想い=関係性に現れている。
③ 母性とは
この映画のテーマは「母性とは何か?」だと思うが、占星学的な観点で言えば、母性とは「上の者が下の者を意識すること」だと思う。母性というからややこしくなるのであって、上の者が下の者を意識するとは、父性も同じだし、母性も同じだし、祖父母が孫を想うのも同じ。
上次元意識と下次元意識の関係性。父性と母性なら「木星と土星」、祖父母性なら「天王星と海王星」といったところだろうか。
私たちは下の存在(子供・孫・後輩…etc)を見るとき、そこにかつての自分を見る。「あぁ、そうだよな、私も昔はこんなだったな…」。そこから長い道のりを経て、様々な経験をしてきたからこそ、そのかつての自分に「与えたいもの」がたくさんあると感じる。
・ あのとき、これを知っていたなら
・ あのとき、こういうことに気づけていたなら
・ この子には、あの頃の自分よりもっと幸せになってほしいな
・ この子には、あの頃の自分の経験をもっと活かしてほしいな
子供(孫)を慈しむ気持ちは、そういう上からの視点を伴う。能動的な視点(木星・天王星)もあれば、受動的な視点(土星・海王星)もあるが、それらすべてが「下のものを慈しむ気持ち」から生まれる。
だから、それをどう解釈するかという視点によって、記憶(出来事の意味付け)は変化する。
典型的なのが年齢による記憶の印象変化。
若い頃は「ひどく、辛い、苦しい出来事(記憶)」だったものが、歳を経て様々な経験をし、幸せをたくさん味わうようになると、その頃の記憶がとても優しく、温かいものになったりする。
例えば、殺したいほど憎んだ親に対して、自分が歳を取って振り返ると「確かに苦しかったけど、親も辛かったんだろうな」と思いやるようになり、甘酸っぱい記憶に変わったりする。
客観的事実は変わらない。それに対する自分の印象(意味づけ)が変わる―。
主観世界とはそういう印象(意味づけ)で構成されていて、だからそれは人それぞれ皆違っているということ。
② 記憶の改ざん
こういう記憶の改ざんは私たちの生活でもごく普通に行われている。それは記憶の本質に関わるテーマであり、記憶とはあくまで「自分の主観世界を形作る意味付けの体系」にすぎないから。
・自白の研究(浜田寿美男著)
・自白が無実を証明する(浜田寿美男著)
母は「世界が美しくあること」が何よりも大事だった。母は娘のことを思い、娘は母のことを思う。そこに齟齬などあってはならず、一心同体の存在として、考えも感情も価値観もすべて一致していなければならないと。それが彼女にとっての「美」であり、そのためにすべてを捧げると。
娘は「世界が正しくあること」が何よりも大事だった。愛しあっていない父と母、自分(娘)よりも祖母を愛している母、母を裏切って浮気する父、精一杯尽くす母に感謝のかけらもない義理の祖母、娘なのに愛してくれない母。理不尽で、正しさのない世界に、強い義憤を感じていると。
そういうそれぞれの価値観を投影して世界(人・モノ・出来事)を見るから、そこで起こった出来事に対して、自分の色付けをしてしまう。
記憶とは起こった事実に対して、自分がそれをどう思ったか、どう感じたか、どう味わったか―という主観的な印象のこと。
【映画:母性 -記憶の改ざんと主観世界-】
戸田恵梨香さん主演の映画「母性」を見た。この映画は「母と娘の主観世界の違い」を描いていると知って、ブログ記事に良いと思って鑑賞したのだが、ちょっと内容が重すぎて(見ていてあまり面白くない)取り上げづらいと思った。
なので、ここでのつぶやきでいいだろうと。以下思ったことを書き出してみる。
① 母の主観世界と娘の主観世界の違い
これは羅生門効果を使ってうまく表現していた。
・母が弁当箱を落とすシーン
・娘がひざまずいて「ごめんなさい」と謝る際に、抱きしめた(or 抱きしめなかった)シーン
母と娘でまったく異なるシーンとして描かれている。
客観的事実がどうだったかは別にして、これは母と娘それぞれの主観世界(記憶)を描いているのであり、母は「ショックを受けて弁当箱を落としてしまった」との印象を持ち、娘は「自分に対する怒りでわざと弁当箱を落とした」との印象を持ったということ。
最後の謝るシーンにしても、母は「愛しさから娘を強く抱きしめた」との印象を持ち、娘は「愛おしさはあっても私を抱きしめるのは躊躇した」との印象を持ったということ。
これは母と娘それぞれが持つ主観世界によって「意味づけられた記憶」であり、それぞれの価値観が反映されたものにすぎない。
【追記】
以前書いた記事でも同じテーマを考えていた。この頃はまだ深く考察できておらず、単純にナラティブ・アプローチの「語りと聞き」を構造論的に当てはめただけだった。ただ「自他の双対性」として捉えているところは参考になる。
●【語りと聞きの関係性】2022.06.07
https://lean-paste-7c0.notion.site/2022-06-07-5af221d920074f3398f06f5cf3e859ac
[自己側] [他者側]
天秤座(7)=語り手(語るもの) 蠍座(*8)=聞き手(語れれるもの)
蠍座(8)=聞き手(語られるもの) 天秤座(*7)=語り手(語るもの)
人は自分の内部でも自己語りする際に「語り手」と「聞き手」の両方を発生させる。と同時に、その関係性を他者との間にも発生させる。
個体構成(アイデンティティ化)には、こういう2重の仕組みがあるようで、自己としてのアイデンティティを実体化させる(自己内での語りと聞き)仕組みと、他者によってそのアイデンティティを承認される(他者に向けての語り)仕組みの2つがあるのではないかと。
そう考えると、蠍座(8)としての意識が「自己アイデンティティとしての実体化・生命化」であるのと同時に、「他者アイデンティティを承認(理解)・それによって自己内部に他者を存在化させる」作用を持つのかもしれない。
この両者は不可分の存在であり、自己構成しよう(アイデンティティ化しよう)とした瞬間、自己構成された自分(アイデンティティ化した自分)が発生するのと同時に、語るものと語られたもの、語り手と聞き手が同時発生する。
(7):語るもの=個体構成する意識
(8):語られたもの=個体構成された実体(生命としての存在)
(7):語り手=個体構成する意識
(8):聞き手=個体構成された実体を承認する意識
おそらく、これが天秤座(7)と蠍座(8)の意識だと思われる。だが、問題は蠍座(8)としての聞き手側の存在。聞き手とはただ単に承認するだけの存在なのか?ナラティブ論が示すように、そこには語り手に影響を与える相互作用性があるのではないか?
もしそうだとすると、語る行為(個体構成する意識)とは自分ひとりで成されるものではない―ということになる。聞き手(他者が持つ価値観・社会通念など)を意識した上での語り。むしろ、聞き手を意識しないで語ることなどできない―と。
他者(他者認識)の本質はここにあり、自己(自己認識)と切っても切れない不可分のものだと。
蠍座(8)があれほどまでに他者を求めるのは、このあたりに本質があるのではないだろうか…。
そういう全体性(関連性)を作り上げるには、自分を客観的に捉え、これまで経験してきた出来事の1つ1つを、そこで味わってきた想いの1つ1つを、外在的な視点でまとめあげる(意味づける)ことが必要。
そういう意識作用のことを象徴的イメージで表したのが、あのキョンや岡部の外在的視点。そして、この外在視点は「自己を物語る意識」として作用する。自分自身のことを語るとは、それまでの出来事すべてを関連づけ、意味付けを与え、1つの構成物(作品)としてまとめること。この語りの作用がなかったら、自分が体験してきた出来事はすべてバラバラの脈絡のない断片物にすぎない。
この語り=ナラティブは、個体にとってはアイデンティティ化を促進する意識であると同時に、語られたもの(あるいは語りを聞くもの)という反映意識を作り出す。
これは自分が心の中で語ることを想像してみると分かると思うが、内言(外言でもいい)で、自分自身のことを語ろうとした瞬間、その語り(内言)を自分の耳で聞いていることに気づくはずだ。
・語り=語られたもの
・語ること(語り手)=聞くこと(聞き手)
●臨床心理学におけるナラティヴ分析
https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/2007615/files/dcp46005.pdf
このイメージは例えば、アニメ「涼宮ハルヒの消失」でのキョンがタイムリープをして過去の自分を見つめるシーン、あるいはアニメ「シュタインズ・ゲート」最終話で、岡部がクリスを救い出したあとに過去の自分を見つめるシーンにあたる。
キョンが過去の自分を客観的に(客体として)眺めているシーンにしても、岡部倫太郎が過去の自分を客観的に(客体として)眺めているシーンにしても、こんなことは実際にはありえない。つまりこれはあくまで象徴(イメージ)としてのものであり、この外在的な視点にこそ(それが表す意識にこそ)重要なポイントがある。
この意識とは何なのか?
自己を外部的な客観視点で捉えようとする意識とは何なのか?
それがその主体(キョンや岡部)をより大きなものとして構成しようとする意識=自己アイデンティティを構成する意識と言える。私たちは自分というのを考える時、そこにそれまで経験してきた想い・感情・考えといったものをすべて含めて”自分”だと思っているはずだ。その全体性こそが「わたしとしてのアイデンティティ=他の誰でもない”このわたし”」だと認識している。
【語りと語られたもの】
天秤座(7)と蠍座(8)の意識を、「個体としての構成と実体化を行う意識作用」と考えている。問題は「ここにどうやって他者が関わってくるのか?」だ。この他者問題(他者認識)について、ずっと考えを巡らせている。
以前まとめた視野空間の視点から考えると、獅子座(5)としての主体認識と乙女座(6)としての客体作用を統合したものが、天秤座(7)としての個体構成意識(自己アイデンティティを構成する意識)だと思われる。それはエルンスト・マッハの自画像的なPOV視点(一人称視点)だったものが、視点を外部に移すことによって(外在視点)、主体を客体化させた「人間(わたし)」というイメージを作り出す。
本来、私たちが持つPOV的な一人称視点では、「身体を持った客体化した人間」というものは生まれでてこない。この人間としての身体イメージ(そこには主体としてのイメージも含まれる)の元になるイメージがどこからやってくるのか?―それが天秤座(7)の個体意識を構成する意識だと。
この作品ではあくまで「女性の社会的立場(射手座・山羊座)」という視点だから、個々の女性が持つ女性性(ホルモンを始めとする女性性的な資質)の変換を扱っているわけではない。
※これには天秤座・蠍座の視点が必要
そういう意味で男性に女性性そのものを体験させることにはなっていないが、それでも教育・慣習といったこれまでの社会が作り上げてきた世界観の変換(反転)を、見事に表現している。
こういう(自分が抱いている)世界そのものの変換こそが、水瓶座的な精神といえる。1つの世界(社会=価値観)から別の世界(社会=価値観)へ場所を移す。異国・異民族・異文化・異世界といった水瓶座のキーワードは、そういう異なる世界観(価値観)へ自らを放り込むことによって、他集団のことを理解し、それによって自集団のことをより深く理解させる。
それにより、集団と集団を止揚するより上位の超集団(より一般化された上位の集団)を作り上げる。国際機関に象徴されるもの。男性も女性も、大人も子供も、白人も黒人も黄色人種も、金持ちも貧乏人も、健常者も障害者も、人間も動物も。すべてが含まれるより上位のあり方を見出そう…と。
●軽い男じゃないのよ 予告
https://www.youtube.com/watch?v=2bFHdkzqSZA
【世界の変換(入れ替え) 水瓶座の精神】
映画「軽い男じゃないのよ」を見た。とても素晴らしい作品だった。最初は「なんだ、よくある女性の男性性化(悪い意味での男性性化)か…」と思ったが、そうではなく、男性に女性の社会的立場を実感させる見事な演出だった。映像だけで、女性の社会的立場を男性に実感させてしまうことが可能なんだ…と、ただただ脱帽した。
最初はコメディーっぽい雰囲気だったのが、だんだんと女性が味わっている理不尽な思いを、見ている視聴者に植え付けていく。「あぁ、女性ってこんな思いをしていたんだ…」と、男性なら誰しもが実感させられるのではないだろうか。
映画のラストシーンのシニカルさも見事だった。男性優位→女性優位→男性優位と、世界そのもの(価値観そのもの)を変換させることによって、見ている人は自分のそれまで抱いていた常識がぐちゃぐちゃにされてしまう。
映画を見終わったあとには、自分の価値観がまったく新しいものへ変えられているのに気づくだろう。
【追記】
ちなみに、ちょうど今私のホロスコープでは「トランジット海王星がネイタル月にアスペクト」を取っている。この配置が起こる時、なぜか私は映画を猛烈に見るようだ。図ったわけではないのだが、自然とそういう風に導かれる。
【1996/01~1997/01】
トランジット海王星とネイタル月の60度
大学の図書館で映画を見漁る
街のレンタルビデオ(VHS)を借りまくる
【2010/02~2011/01】
トランジット海王星とネイタル月の90度
ゲオでレンタルDVDを借りまくる
【2024/02~】
トランジット海王星とネイタル月の120度
Netflixに加入
こういうのは本当に興味深い。自分の資質(興味・才能)がこの分野にある―というのを星が教えてくれているわけだ。そして、それはどうやっても表に出てきてしまうものだと。
そして、存分にそれを体験したあと、新たな覚醒が起きる。自分の世界(意識体験)に飽き、他人の世界(意識体験)に興味を持つようになる。他人が経験したものを、他人の視点(意識)で体験するように。そうなると、わたしもあなたも彼も彼女も、みんな同じような感覚になり、自我の崩壊が起きる(個体意識の終わり)。
そして、個体的な意識から集団的な意識へと進化する。
※おそらく、これが映画「2001年宇宙の旅」でのスターチャイルドの誕生、小説「地球幼年期の終わり」でのオーバーマインドとの一体化
と、いろいろ想像の羽を広げてしまったが(笑)、物質的なあの世イメージ・天国地獄イメージを取り払うと、もっと違ったものが見えてくる。そういう視点で見えてくるものもあるのではないだろうか。
- 占星学と心の探求
- http://astrologia89.blog.fc2.com/
- 占星学と科学の探求
- http://astrologymemo.blog.fc2.com/
占星家です。占いではない心の内面を見つめる占星学、意識の構造を解き明かす占星学を目指しています。日々感じたことや思うこと、読書記録や研究内容などを書いています。よろしくお願いします。
