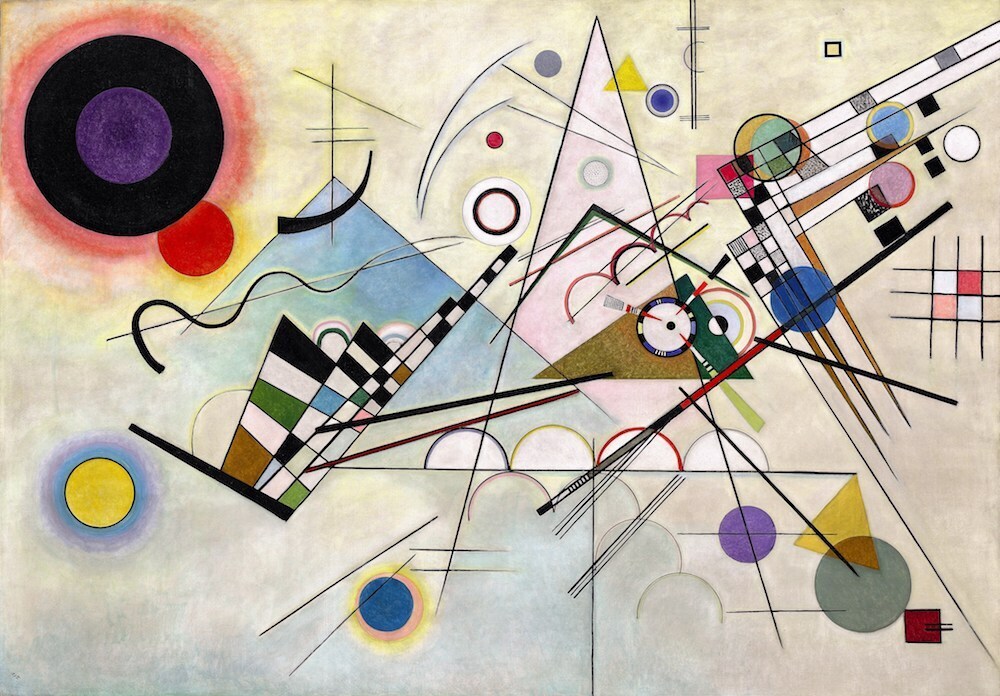
1983年が丸山眞男への組織的攻撃の年だったとすると、1984年の埴谷ー吉本の間の「コム・デ・ギャルソン」論争も当然、偶然ではない。
論争の争点は、この時点で「消費社会」段階に突入した日本社会をどう見るか、というもの。
埴谷は、「消費社会」の現象をあくまで世界資本主義の中の一局面に過ぎず、例え「日本が豊かにになったように見える」としても、それは「第三世界からの搾取」と表裏一体とした。
それに対し、吉本は「大衆が支持しているのであれば、それを批判するのは、スターリン主義」などという譫言で反論。「アン・アン」にコム・デ・ギャルソンの服を着て登場することまでした。
新左翼・吉本ファンから、消費社会の「犬」とも言える「広告屋」に転じ、30年前から表舞台に出てきて悪事をまき散らしている典型が糸井重里である。
浅田彰は一見吉本と相性が悪いように見えるが、「消費社会」肯定論の点では、実は相通じている。ここからネトウヨ大王東浩紀が飛び出してくるのは、個人的な関係は別にしても、筋が通っているのである。
こうしてみると、江藤淳、吉本隆明、福田和也、西部邁、当時の柄谷行人、蓮実重彦そして浅田彰、中沢新一とニュアンスの違いはあれ、戦後民主主義、戦後文学を「共通の敵」としていたの歴然としている。
広島市と逆に長崎市は平和式典にイスラエル代表を招待せず。(尚、広島がパレスティナ代表を招待せず。これは全く理解不能)。
すると、英スターマー政府は駐日本大使に欠席を支持。つまり、スターマー政府はイスラエルを招待しないような「反ユダヤ主義」的都市には、「断固たる姿勢」を示す、というパフォーマンスをしている。
これが英国の誇る「法と秩序」であるから、聞いて呆れるとはこのことだ。
この調子ではイスラエルがレバノン、イランと戦線を拡大し、中東大戦争になった暁には、これ幸いと「法と秩序」の名の下に、イラン討伐に参加するのだろう。
ちなみに私は、今回のスターマー労働党の政権復帰は、単に保守党が自滅しただけに過ぎず、「リフォームUK」の躍進こそ、注目すべき論点、と何度か書いてきた。
英国をバランスを取り戻すには、J.コービンを中心とした新労働党がヘゲモニーを取るしかないだろう。
そう言えば、加藤尚武、去年の「現代思想」にも駄文をよせているのだった。
それはそれとして、1983-86というのは中曽根政権下で国鉄解体が推し住められていた。
後に中曽根自身が、「社会党を解体するために総評を解体する、総評を解体するために国労を解体する」という戦略を語った政治プロセスが作動していた時期である。
この中曽根の国労解体が総評解体、連合結成、そして社会党の解体へと繋がっていく。それは同時に小選挙区制を導入することでもあった。
この時期の山口二郎や佐々木毅などの東大政治学者は「小選挙区制」=「政治改革」として旗を振っていたのである。これに対し、加藤周一は「守旧派」としてそれを批判する、という構図にされていた。
それはともかく「ニューアカ」の連中はドゥルーズ・ガタリにはやしゃぐのはいいが、彼らの口から「国労解体」が意味するものを聞いたことがない。
それで「ドゥルーズ=ガタリの政治哲学」などという本を書いてしまうのだがら、臍で茶が湧く、とはこのことである。 [参照]
ファシズムの再来を危惧する丸山眞男を
加藤尚武(当時、千葉大学文学部教授)という人が「狼少年」呼ばわりしたのが1986年。
バブル経済のなかで、中曽根政権が新自由主義的で復古的な政策を推し進めていた1980年代。
臨教審設置(1984年)、国鉄民営化(1987年)など、「公」を解体する動きが加速するなか、
それを批判するようなまともな「批評」を、加藤のようなアカデミズムのなかにいる人が、内側から壊し、世間の雰囲気に迎合するものに作り替えていく、権力のアシスト的な働きをしていた・・・。
いろんなことが、いろんな場所で、数十年かけて行われてきたのだなぁと、つくづく思います。
(そして、この加藤という人はいま現在も、雑誌などに出つづけているのです)。
今の1960-1970年代生の人文・思想系のインテリの「貧困」は、基本的に、『現代思想』・『批評空間』によって自己形成を遂げたことに拠るとしておいて大過ない。
『批評空間』、就中、浅田彰が最も精力的にプロデュースしたのが、「かの」ネトウヨ大王、Z大学教務部長就任予定だった東浩紀だったことはそのことを証明してあまりある。
昨年秋の「痴愚神礼賛」祭りの事務局長をはじめとする、「駒場の神々」6人衆などは、「僕は批評空間」発売日に本屋に行って買ってます」などと言って当時の私をうんざりさせていたものである。
その内の一人の「政治と美学の関係をやりたい」などと宣っていた御仁などは、後輩の女性院生イジメの精を出す「政治」、美学と言えば「僕は服と時計合わせて十万円以下では大学にこないことをエチケットを心得てます」という調子である。この男が今は早稲田で漫画批評などを教えていると仄聞した。要するにただの「オタク」。
福田和也に戻れば、SFCの教え子で最も有名なのが、先日都知事選後に「朝日」で蓮舫批判をしていた鈴木某という女性「評論家」である。この人はジジェックの翻訳などをしている大学教授の娘である(ちなみにこれは公開情報)。
駒場の「神々」の掉尾を飾るのが千葉雅也氏ということになるだろう。
1990-2000年の間、浅田彰・柄谷行人編集の『批評空間』という雑誌があった。
人文・思想系の院生のほとんどは、基本この雑誌に引きづられて自己形成をした、と言ってもよい。傍目から、私などはそれを苦々しく見ていた。
ところで、この雑誌に何故か西部邁やあろうことか福田和也が登場することがあったが、これは勿論柄谷と西部の学生時代からの関係に拠る。何か「保守主義」についての戯言の特集だったように記憶している。
柄谷さんは、ブントから出発して文芸批評家としては、元来江藤淳のファンから出発した言ってももいい。
江藤淳は戦後暫くは「左派の振り」をして「作家は行動する」というサルトルの『文学とは何か』の劣化したコピーを発表したりしていたが、潮目を見計らって「戦後文学批判」、とくに埴谷雄高を攻撃するようになった。それに対する埴谷の反論の中に若き日の柄谷行人が江藤の「手下」的に登場する。
それはそれとして慶応仏文科の博士課程に進学できなかった福田和也をSFCの教員に「押し込んだ」のは江藤淳の政治力だとその筋から聞いたことがある。
福田はその頃「1万人の労働者の命より一杯の上等のワインの方が価値がある」などと嘯いて「文学」的な身振りをアピールしていたが、この福田と妙に相性が良かったのが浅田彰である。
さて、加藤尚武は「落ちた偶像丸山眞男」(1986)のなかで、日本社会が戦前のファシズムがある部分連続していることを憂慮し、また別の形で「ファシズム」が来るのでは、と批判する丸山を「狼少年」と呼ぶ。
蓮実重彦と同じ1937年に生まれ、戦後改革の「恩恵」しかしらない世代が、学校教育・大学教育という最も「守られた場所」から加藤尚武はファシズムへの警戒を呼び掛ける丸山を「狼少年」と罵倒しているのである。
その後の加藤はと言えば、「眠たい」エッセイと「マルクスからデリダへ」(PHP新書)などただの環境破壊にしかならない行為を続け、遂には「月刊日本」などに登場して今に至る。まさに最悪の「転向」である。
盟友西部はこの加藤の醜悪な駄文を新聞の論壇時評で「本年最高の学術的評論」と激賞、さらに1983年にサントリー学芸賞を与えられた中沢新一を東大駒場に押し込もうとして事件化する。
この際「文明としての家社会」の著者、村上泰亮、佐藤誠三郎、公文俊平は西部に加担。関係者の多くは中曽根が設立した日文研に移る。
ちなみに死後出版されたインタヴュー(聞き手みすず書房・小尾俊人)で丸山は、「1983年は私に対する凄まじい攻撃の年だった。信頼していた筈の編集者の多くが背を向けて立ち去った」と振り返っている。
引用したのは、5月16日の投稿。ここではタイプミスで3万円」前後となっているが、この時点では4万円前後。
先週末、東証史上2位の大暴落があったが、今日は4千4百円暴落しして、現在3万2千円を割った。
しかし、これでも日本の現在の実体経済からすればまだ高い。何と言っても、安倍政権前は1万円前後だったのである。これを「アベノミクス」などとカタカナを並べて、株価上昇至上主義、「我が亡きあとに洪水は来たれ」で日銀に大量の株価を所有させ、海外投資家を「よびこむ」とした。
当然、これは持続不可能であり、いずれ「暴落は避けられない」と私は何度も警告して来た。
しかし岸田政権になってもこの方針は変わらず、ロンドンで「Invest in Kishida です」などと呆けたことを言い続けた。「です」は「death」に通じ、このまま一般市民が大量にdead するとすれば、政府の責任は重大である。
朝日の報道では大手証券アナリストに「驚きだ。いつ反発してもおかしくない」などと言わせている。
これで「逆張り」で一儲け、と素人がさらにNISAにつぎ込むと、身ぐるみ剥がれることになりかねない。
どうも情報操作の毒、政治だけでなく経済にも回りきっているようだ。 [参照]
加藤尚武の「下品な」エッセイ、国会図書館で確認してみたら、「中央公論」ではなく、「諸君」1986年12月号だった。題して「落ちた偶像 丸山眞男」。
そしてこれに呼応して西部邁が「東京新聞」11月の論壇時評で、「本年度最高の学術的評論あるいは評論的学術」と持ち上げている。「語るに落ちた」とはこのこと。
加藤尚武と西部邁は東大駒場寮の同室仲間であり、学生自治会選挙では、「ブント」側の候補が「負けそう」だということで、投票用紙を偽造して民青の候補を落選させた「ギャング」仲間である(西部の回想による)。
実は、「ブント」は自治会選挙で負ける見込みの際は、この手の「実力行使」はお手の物だった。
千葉大で学生達から「インテリヤクザ」と呼ばれていた中央大学のブントのボスは、何故かネトウヨの金融工学、経営学、「南京大虐殺」否定論の経済学者などを手下にして学部を内乱状態に陥れていた。
手下達には「俺が中大のボスの時には親衛隊がいてよー俺に睨まれた奴は夜道を一人で歩けなかった」などと怪気炎を上げていたらしい。
この「ファシスト」達には、私を始めとする「常識」派が鉄槌を下し、粉砕することで内乱は収束した。
しかし加藤尚武、この後日本哲学会長、受勲まで受けているのだから、恥知らずもいい所である。
加藤尚武(1937生)は、ヘーゲル研究者。学部学生時代、西部邁とともにブントに参加。68年の東大闘争の時は文学部助手だった。
先に挙げた加藤の「下品極まりない」文章は、学部生に囲まれ、小突かれながら、つるし上げられている丸山眞男を、助手の加藤が横から「ほくそえんで見ている」という趣向である。
私は学部学生の時に友人に進められて加藤の「汚らしい」文章を読んだ時の感触をいまでも覚えている。
この文章を書いた時、加藤は千葉大文学部教授ではなかっただろうか?
私が千葉大に赴任した時、加藤尚武は、京大に移り、なにやらあやしげ且つ「眠たい」エッセイを書きなぐるPHPお抱えのような存在になっていた。
日本のヘーゲル学会のボスとして『ヘーゲル大事典』の編集責任者の一人となっているが、私が彼の仕事を全く認めていないことは言うまでもない。
ついでいうと、柄谷行人はブント時代、たしか駒寮で加藤、西部と同室(基本3人一部屋)だったと記憶している。
月刊「地平」三号が届いたので眺め始めて、大特集「ジャーナリズムをさがせ」がなんとp44からp131までの圧巻(まさに)。まだパラパラ見ただけだが、出口を失っていたジャーナリスト魂が突破口を見つけた、という趣である。「さがせ!」といいつつ、ここにある、われをみよ、という気概があるのであるな。すばらしい。朝日の吉田調書問題の背景から始まり、トリは花田達朗さんの「第三のジャーナリズム」連載の最終回。この脱藩記者・編集者に注目した連載がこの特集をアジャイルに生み出したのではなかろーか。
なお、他にも読んだところでは、佐藤学さんによる「学術会議への権力介入」、学術総動員化を目指す権力側の実名入りで資料価値ありまくりである。岸田弱体化のスキをついて正統性なき法制化を目論み跋扈する官僚。ひでえものだ。
なお、佐藤さんの危機感に賛同する一方で、学術会議も原発事故の対応とか考えたら腰抜けだったので、この危機を奇貨として行政をしっかり批判する存在に生まれ変わってほしいと思う。もう30年前近いが、オウム真理教のテロに科学者が関わっていることが次々と明らかになった時にも、今こそ学術会議は声明を出すべし、と思ったが、ずっと黙っていて、お前ら仕事しろよ、と私は憤懣やる方なかったのである。
ローマ法講座、東大のリア王の後もなくなったそうなので、もう日本では研究者の再生産はあ止まった、ということなのだろう。
イタリアでは100以上の大学でローマ法講座があり、これは本場であるから当然としても、欧米でローマ法講座がゼロ、ということは考えられない。
日本でも最低、ヨーロッパ古典学の一部門として10講座は残すべきだろう。財政的裏付けを言うなら、研究者でもない「コンサル」系・企業経営者・官僚、落選した政治家の天下りの分を充てれば十二分でまだおつりが来る。
なんといっても、欧州は勿論米国も「アインデンティティ」は体制派も含めて「ローマ」である。何かと公の場ではローマの故事の引用が入る。
であるから、外交にしても、最低限のローマ史・ローマ法の知識は必要になる。でないと、いつまでも「文明外の輩」と見下されたままになる。
これは絶滅しつつある中国法制史に関しても言える。何と言っても、唐の律令は7世紀に日本に国家が創設される時に、ほぼそのまま輸入されたもの。その後、時代に合わせて変遷したものの、基本的には幕末まで続いたのである。
大江の「新しい人よ、目覚めよ」は、現代文学に読み慣れていない人にも広がりのある「カタルシス」型の作品で、それはそれとしていいと思う。
ここで大江が伴走しているのは、ダンテの神曲の挿絵を描いた18世紀末のイギリスの詩人、W.ブレイクである。ブレイクの周辺には近代アナーキズムの創始者にして「政治的正義」の著者、W.ゴドウィン、妻のM.ウルストンクラフト、娘のメアリー・シェリー、そして夫のP.Bシェリーたちがいた。
要するに、イングランド急進派としてフランス革命を支持した知識人達だ。メアリウルトンクラフトはバークの『フランス革命に対する省察』を批判して『女性の権利の擁護』を書いた。
言論の自由で有名な筈の英政府は彼らを弾圧。表現活動を不可能にした。ワーズワース、コールリッジは転向、前者は桂冠詩人となった。
元来とりたてて政治思想がなかったバイロンはオスマン帝国領ギリシアの削り取るための「独立運動」に参加、病没。「ギリシア独立の英雄」と讃えられたバイロンの軌跡などは今日では典型的な「オリエンタリズム」とされるだろう。
加藤さん曰く「大江君は勿論小説家としては才能あるよ。でも政治的なことは脇に置いて、とにかく日本国内の知的流行に弱い。例えばクンデラとブルクハルトを同列に置いて語ったりする。これは欧州の基準からは考えられない。」
つまりクンデラはそこそこ才能はある作家ではあるが、「かの」ブルクハルトととは同列に並べる、などは「あり得ない」ということ。
ブルクハルトは歴史家ではあるが、著書「イタリア・ルネサンスの文化」は芸術作品でもあって、これを超えるような小説は早々出ない。
ちなみにニーチェがトリノで発狂した際に、バーゼルに引き取って精神病院への入院手続きをしたのも理解者であったブルクハルトである。
大江に戻ると、21世紀に入り、日本の極右化がさらに進むと、加藤さんがリーダーとなって「憲法9条の会」が結成、大江もそれに参加。このあたりから、大江は「戦後民主主義」を自分の原点として語るようになる。
「サルトルを読む」=最後の小説にする、という構想は加藤さんの死後、練り上げられたようだ。この場合、おそらくサルトルの「政治的」とされる文章と「アンガジュマン」についての小説になったのだろう。
実は私は最初の著書、『知識人と社会 J=P.サルトルにおける政治と実存』(2000)を大江に献呈していたのである。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
