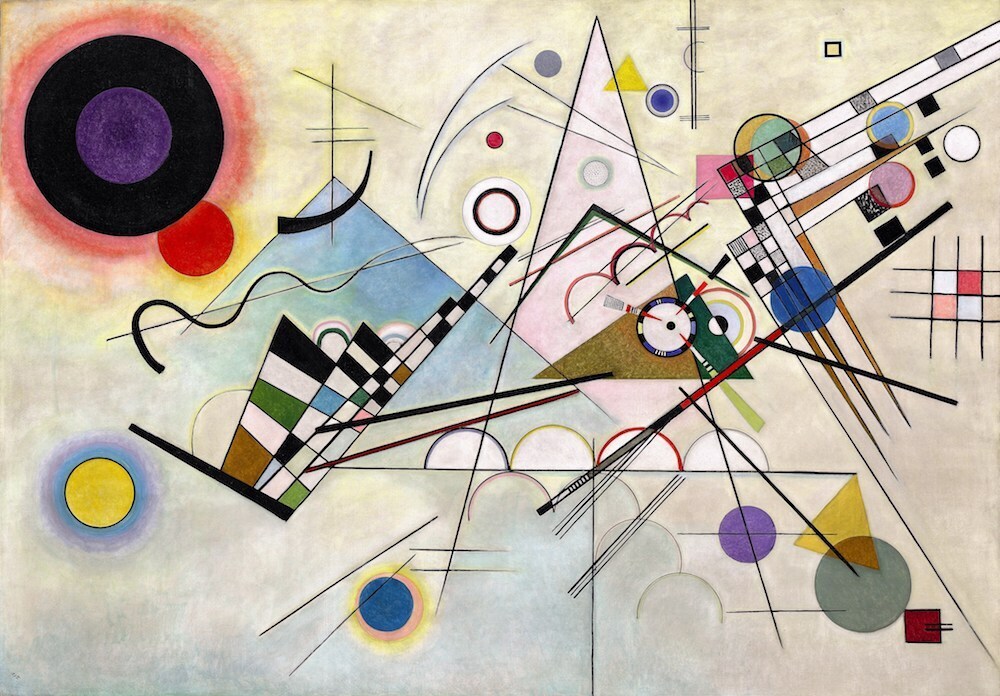
訂正と補足)
ディエン・ビエン・フーの陥落は1954年、この年、仏、米国・ソ連・中国も参加したジュネーヴ協定において、北ベトナム側は中ソの圧力に最終的に譲歩して協定に調印。
すでにこの段階では、米と中ソの地球スケールの「冷戦」の論理に植民地解放のベクトルは歪められつつありました。
米国との正面衝突を避けたい中ソの圧力で、ベトナム政府軍はすでに国土の大部分を制圧していましたが、北緯17度線まで撤退。
しかも、この合意を米国は土壇場で調印拒否。つまり最初から南の傀儡政権を支援して、「北」を倒す腹積もりだった。協定で定められた統一選挙も拒否(「北」が勝つのがわかっていたため)。
しかし、南ベトナム政府は、米軍の膨大な軍事援助にも関わらず劣勢となり、ついに米国は1964年トンキン湾事件をでっち上げて直接介入を開始、最大時55万人の地上軍を派遣。また「北爆」には、B52が嘉手納から出動します。
そしてインドネシアの「血のクーデター」が1965年です。まさに「グローバル冷戦」ドミノです。その上、この頃から中ソ対立が激化、ベトナム政府は間に挟まれて苦境に陥ります。
しかし1975年、ついにベトナムは統一されました。
下画像『ベトナムから遠く離れて』(ゴダール、K.マルケルなど)
BT)欧州では1945年5月8日、ナチス・ドイツが降伏し、終戦。しかし同日に、アルジェリア北部のセティフとゲマラでは、独立を求める何千もの市民をフランス軍が虐殺します。
この「セティフの虐殺」からフランスは1962年まで続くアルジェリア独立戦争にまさに「切れ目なく」のめりこんでいく。
戦争は次第に拡大し、遂にアルジェリアに60万以上の兵士を投入、徴兵動員体制となる。ちなみにデリダとブルデューもこの際徴兵され、アルジェリアに駐屯している。
ゴダールの『勝手のしやがれ』、日本公開時は「刹那的」で「無軌道」な若者を描いた、とまるで「新人類」映画のような扱いだったが、これは「大義」が感じられない「戦争」に動員される仏青年の焦燥を背景にした映画。ゴダールの2作目「小さい兵隊」はさらに踏み込んでフランス軍の「拷問」を告発する内容になっている。
自由フランス軍に動員されたアルジェリア兵はFLN(民族解放戦線)と仏傭兵(ハルキ)側に分かれて殺戮し合うことになる。独立時には10万人以上の「ハルキ」が殺された。
仏はインドシナでも1965年まで旧SS隊員を大量に動員してまで戦争を継続、しかし要塞ディエン・ビエン・フーをグエン・ザップ将軍に攻略され、降伏。
この後、米国が10年に渡りベトナムに介入することになる。
「機械人間 machines」(インド、ドキュメンタリー)
インド、グジャラート州の、ある繊維工場と労働者たちを、映像としての完成度を徹底して追求しながらフィルムに収める。
インドと言えば、バンガロールなどのIT産業のお話しがよく報道されていますが、労働者の圧倒的多数は、むしろこの映画で描かれるような、労働法・労働規制を排除した19世紀的な環境に置かれている。
組合をつくろうとする試みが稀にあっても、リーダーたちは暗殺されること示唆されます。
劣悪な労働環境の中、子どもたちは化学物質にまみれながら、働いてる。エンゲルスが描いた19世紀における「イングランド労働階級」とほとんど相似的です。
グジャラート洲と言えば、2002年、時のBJP州政府、警察の暗黙の支持の下に行われた、ムスリムに対する「ポグロム」でも知られます。この際、少なくとも数千人規模の犠牲者が出ました。この時の州政府首相が現在、インド共和国首相のBJP党首のモディです。
マクロに見れば、新自由主義グローバリズムと極右原理主義との結合、というありふれたものでありながらも、危険きわまりないブロックが世界中でせりあがっていることになる。
このドキュメンタリー、それほど入手困難なものではないので、ご興味のある方にはぜひお勧めします。
「ウォーターゲート事件(ニクソン辞任)は何故可能だったか?」
スパルタカスくん、「ウォーターゲート事件告発をしたのはNYT」と書いているが、これは誤り。正しくは1972年にワシントン・ポストのボブ・ウッドワードとカール・バーンスタインが「すっぱ抜いた」。
NYTは前年1971年に国防総省の機密文書(ペンタゴン・ペーパーズ)を報道した。
前者は『大統領の陰謀』、後者は『ペンタゴン・ペーパーズ』として映画化もされている。
「新左翼」気取りの、この東大准教授、この告発が可能であったのは「社員持ち株制」が云々と思いもかけぬ「ナイーブ」さを曝け出している。
この「告発」がニクソン辞任の大事件にまでなったのは、米国のもう一つの「エスタブリッシュメント」である民主党本部への「盗聴」事件であったため。また直接の工作員多数がCIA関係者であったこともあり、FBI副長官の協力も得ていた。1972年のフーバー死後のFBIとニクソンの関係も背景にある。
米共産党、ブラックパンサー、はてはキング牧師の個人電話まですべて「盗聴」されていたが、これは何の問題にもならなかった。
ブラックパンサーに至っては、パブリック・エネミー」としてFBIによる暴力的弾圧に晒され、指導部も含め、多くのメンバーが「違法」に殺害された。
また、ユーゴ含めロマン派は一般にプロテスタンティズムよりも、「原罪」の観念を希薄化したカトリックに近く、その点この映画はやはりアングロ・サクソン的。
社会理論として考えた場合、プロテスタンティズムはカトリックと異なり、「自己」論中心で「政治秩序」論は希薄。
(ただし、ロックを国教会「寛容派」理論と考えると別。またヘーゲルを世俗化した最大のプロテスタンティズムの思想家と見ることもできる。)
「危機の17世紀」にはカルヴァン派の「抵抗理論」や「寛容論」なども仏語圏では現れましたが、その後衰退。
ドイツのルター派はむしろ世俗の国家への服従を説きました。E.フロムやH.プレスナーは「ナチズム」の起源をルター派まで遡らせますが、これはやや無理があります。
いずれにせよ、プロテスタント諸国では世俗国家が社会を管理するようになり、国家論はこの地域では衰退した、とは言えます。
これに対し、カトリックは中世においては地域・国家・国際社会の秩序の管理者であって、個人の「信仰」は二の次。ローマ教会の高位者も「聖書」などは読んだこともない人が多数派、むしろ教会法に精通。
教会法、つまり当時の行政法の専門化、ということ。
であるから、仏で世俗国家とカトリックの対立が最も激しくなるのは自然の成り行きだったかも。
ヴィクトル・ユゴー「レ・ミゼラブル」について
「レ・ミゼラブル」は今までに、何度も映画化されてきました。小説の映画化、はジャンルの違いもあって、成功するとは限らない。失敗の典型はトルストイの「戦争と平和」。しかし、「レ・ミゼラブル」はこれだけ、映画化されるのは、やはり人気が高いのでしょう。
フランスでは大詩人とされるユゴーですが、日本では詩人としてというよりは、やはり「レ・ミゼラブル」の作者として知られている印象。
私も、J.ギャバン、ベルモンド、ドバルデューなどがジャン=ヴァルジャンを演じたものを見てきましたが、最近の英語版ミュージカルも、わりにテンポよくつくられていた印象です。
J=ギャバンのヴァルジャンはやはり少し年を取り過ぎていて、その点映画版ミュージカルのヴァルジャンは、活力、という点では、よかったのでは。
この映画、最後ヴァルジャンの死の場面で、「現世の罪」から洗い流されて昇天する、というメッセージになっている。
原作では、あるいはフランス版映画では、ジャン=ヴァルジャンは、社会的に「罪」を犯したとは本人も小説内でもされておらず、むしろブルボン王政復古と産業革命の進展によって生み出された「悲惨」と「不正」の犠牲者にして犯行者という位置づけです。
「核・原発と米軍」・・・東日本大震災の際、最悪のシナリオは米軍による日本再占領だった
昨年、とある書評会でとりあげられ、たいへん好評だった本。
東日本大震災の際、状況の展開次第では、350キロ圏退避(首都圏全部含む)、米太平洋軍司令官指揮・自衛隊下請けによる、軍政の可能性があったことが、当時の関係者への聞き取りによって明かされていきます。
この過程で、いまだに日本が軍事的には完全に米国の管理下にあることが炙り出されていきます。
ETV特集でも放映されたので、ご覧になった方もおられるかと思いますが、書籍化され新たな情報も追加されていますので、ご関心のある方はぜひお読みください。
この本の中で、アメリカ側が「自衛隊は英雄的行為を示せ」、「英雄的精神が求められている」、というメッセージを送ってきたことが明らかにされています。これってつまりチェルノブイリの時のように、「超法規的」に自衛隊員が「全身被ばく前提で原子炉に突入しろ」、ということなのです。
著者・NHKディレクターの石原大史さんは、大学院の時の後輩。修論は「鶴見俊輔と思想の科学」でした。
今のNHKでよく生き残れたものだ。偉い!某プロデューサーも感心していた。
しかし岸田政権、「原発全面回帰」法、何考えてる?
WWII中のユーゴスラビアー坂口尚とE.クストリツァ(下)
チトーのパルチザンは、ソ連の援助ゼロ(これはチトー=スターリン書簡でスターリン側が医療・食料援助も拒否したことが確認されています)という状況において、ドイツ軍8個師団、クロアチア軍、ブルガリア軍を引き受けることとなりました。
この結果、ユーゴは東欧圏で唯一ソ連から自立した国家として戦後出発します。
また「解放」後、連邦制として再編された新ユーゴスラビアを、クロアチア人であったチトーがまとめ上げることで、その後半世紀ユーゴは「連邦制」として「平和」を維持しました。
その意味でも、以前の投稿で批判した「民族的個体性」に依拠した「ロマン主義的ナショナリズム」は、ユーゴスラビアでも、破滅的な役割を果した、と言ってよいでしょう。
このような歴史を振り返るにあたっても、『石の花』は再読に値する、数少ない日本のサブ・カルチャーの作品の一つである、と思います。
WWII中のユーゴスラビアー坂口尚とE.クストリツァ(中)
ただし、安彦の場合、『神武』など古代を扱ったものは当然として、前述の『王道の狗』でも、妙な「平和主義」者「天皇」を「尊崇」するメッセージが常にあります。まあ、一種の『平成天皇、平和へのメッセージ』の漫画版、というところでしょうか。
『石の花』の方は、そうした疑問点はほとんどなく、いわば完全に「大人用の漫画」です。
強制収容所の長い描写のエピソードなどは、かなり「リアル」で、これは、「15歳以下」にはちょっときついかも、です。
それにしても、この漫画が描かれて5年余りで冷戦は崩壊。続いて、今日からは時期尚早であったとされるドイツの「スロヴェニア」、「クロアチア」独立承認からはじまった戦争によって、ユーゴスラビアは再び悲惨な内戦に突入、解体。
現在、経済的には完全にドイツの支配下に入ったことを考えると、感慨深いものがあります。
ちなみに、WWII中、ナチス・ドイツは「クロアチア」を「ユーゴスラビア」から独立させ、枢軸側に国家として「同盟」させていました。チェコから「スロバキア」を独立させたのも同じ文脈です。
クロアチア、スロバキアは、ハンガリー、ルーマニア、ブルカリアとともに、ドイツの同盟国としてソ連に侵入していました。(続く)
WWII中のユーゴスラビアー坂口尚『石の花』とE.クストリツァ『アンダーグラウンド』(上)
1939-1945年、大陸ヨーロッパ全域をナチス・ドイツが制覇する状況下において、ユーゴスラビアでのパルチザン闘争を扱った漫画。複数の「言語」、「民族」、「宗教」が、複雑に交錯する中での「抵抗」、「暴力」、「憎しみ」、「平和」などの様相をかなり丁寧に描いている。
扱っている時代的にはE.クストリッツァの『アンダ―グラウンド』中盤までとほぼ重なっている。
作品化にあたり、作者と「偶然」小学校で同級生であった、駒場のバルカン現代史の柴宜弘さんが、ユーゴの複雑な歴史に関して、かなり全面的に協力した、とのこと。
作者坂口尚は1946年生なので、1947年生の安彦良和とは、虫プロでのアニメ製作を経て、漫画に転じた、という意味では、ほぼ同じキャリアを辿った。
ただし、弘前大学全共闘のリーダー格であった安彦と異なり、坂口尚は、東京の下町育ちで高校中退。
安彦良和は、現在のアニメーターたち、例えば庵野秀明などと比較すると、一応「カウンター・カルチャー」的な要素もあり、明治初頭を扱った『王道の狗』などでは、朝鮮の「開化派」を利用した、日本の「アジア主義」や福沢諭吉の双方を批判する視点もある。(続く)
「イル・ポスティーノ」の監督マイケル・ラドフォードがアルパシーノ主演で撮った『ヴェニスの商人』【2004)
半世紀ほど前から英米文学では「ポストコロニアルスタディーズ」の方法が盛んになり、さまざな古典、特にシェイクスピアの再解釈が映画の演出にも応用されてきました。
特に多いのは『テンペスト』のキャリバンとプロスペロの関係。英ではD.ジャーマン、P.グリーナウェイの両人、米国ではプロスペロを女性とするバージョンもあります。
さて、この2004年の『ヴェニスの商人』では強欲金貸しのシャイロック(A.パシーノ)に対するヴェニスの貴族たちの「反ユダヤ主義」がかなり詳細に描かれます。
有名な「証文」へとシャイロックを追い込む、恥辱、法廷での「出来レース」などに焦点が合わせられます。
ユダヤ教の「正義」に対するキリスト教の「慈悲」の優位を説く「欺瞞性」にも光が当てられます。
最後はキリスト教への改宗を強制され、ユダヤ共同体からもキリスト教会からも排除されるシャイロック。
ヴェネチィアの「ゲットー」を破壊し、ユダヤ人を「解放」したのはナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍でした。
ライン川のフランクフルト、トリ―アなども同様。この「解放」からH.ハイネ、K.マルクスが次世代に登場するのです。
「ミッシング」(1982 )と「イル・ポスティーノ」(1994)ー「グローバル冷戦」下のチリ
以前投稿したように、1964年のブラジル及び1965年のインドネシアで確立された「ジャカルタ・メソッド」は、世界中で応用されていきます。
日本で有名な例は1973・3・11のピノチェトによるクーデターでしょう。
「ミッシング」は自身、冷戦下のギリシア軍事政権から亡命したコスタ=ガブラス監督のもの。米国・カナダ製作でカンヌでパルムドール。
「イル・ポスティーノ」は1950年代共産党員であったためにチリを追われたP.ネルーダとイタリアの子島の青年の交流を描いています。ネルーダはアジェンデ政権の下駐仏大使。1971年にノーベル文学賞
を受賞した後、72年に帰国。クーデターの際、急死(死因については諸説あり)。
『百年の孤独』で有名なコロンビアのガルシア=マルケスはチリ出身のシネアスト、ミゲル・リティンと協力した『戒厳令下チリ潜入記』を著しました(岩波新書あり)。
南太平洋の両岸での軍事クーデター、「アクト・オブ・キリング」、「ルック・オブ・サイレンス」と並んで、この二つの映画を観ることでより具体的にイメージできると思われます。
「敵こそわが友 K.バルビー」
K.バルビー(1913生)、SS情報将校としてWWII中、ヴィシー政権の下、リヨン、ディジョンで「レジスタンス」組織の摘発、拷問、虐殺を担当。
バルビーの指揮下で「自由フランス」国内最高司令官J.ムーランをはじめとする大量のレジスタンス参加者が拷問、銃殺された。
WWII後、アメリカ陸軍情報部(CIC)は「反共」工作のため、バルビーを匿い、雇用。しかしフランスがそれに気づき、引き渡しを要求したため、バルビーはカトリックやイタリアの反共組織(旧ファシスト党)の手引きで、ラテンアメリカに亡命。
ボリビアで軍事政権の顧問となり、大きな役割を果す。1967年のゲバラ捕縛、処刑にはCIAとともに関与。
しかし1982年ボリビアで文民政権が成立すると同じ社会党政権である仏ミッテラン政権に引き渡される。
1984年からリヨンで公判で最高刑である終身刑(仏は死刑廃止)。
1991年刑務所内で77歳で死亡。
しかし、アイヒマン、バルビーはむしろ例外で、多くのナチス、イタリア・ファシズム関係者は亡命先のラテンアメリカで右派軍事政権の下、優雅な暮らしを全うした。
「別離」
ベルリン映画祭の金熊。監督、A・ファルハーディーは、現代を代表するシネアスト。「サラリーマン」や「浜辺に消えた彼女」などでベルリンやカンヌの常連でもあります。
かつて、イラン映画は当局の枠もあり、大人の社会の紛争、トラブルを描くことが難しく、結果として「子ども」の視点から見た優れた映画を輩出しました。
また皮肉にもアメリカと関係から、ハリウッド映画が入ってこれなかったことが、国内の映画産業を保護し、次の世代を育てることにも成功しました。
かつてのイラン映画は「地方」の農村を舞台にすることが多かったのですが、ファルハーディは、都市中産階級の「女性」(イランの女性大学進学率は極めて高い)と社会の軋轢を、カフカ風のサスペンス・タッチで描きだすのがうまい。軋轢の結果、法廷闘争が長く描かれ、イランにおける民事訴訟の在り方が垣間見えるのも興味深いです。
またイラン映画には、ドイツに出稼ぎに行っている人物が頻繁に登場するのも、ここ数十年のイランとドイツの移民労働の関係を背景にしていて、これもおもしろいです。
総じて、日本では「悪の枢軸」、女性を抑圧する「イスラム共和国」と決めつける米国のつくりあげるイラン像が強いですが、「別のイラン」を垣間見ることができるのは貴重です。
拙著『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会、2019年)です。
ここの所、ファシズムと冷戦に関する投稿が多いですが、もしより詳細な、思想的文脈にご関心の或る方はご笑覧いただければ幸いです。
いわゆる「戦後思想」と呼ばれている言説が「戦中」の「ファシズム」との思想的対決から生れ出た視点を強調しています。
またWWII以後の「グローバル冷戦 cold war」による世界空間の再編の中で、ユーラシアの両端で「独立左派」を模索したフランスと日本の思想を比較する視座を導入しています。
さらに言えば、日本は敗戦によって全ての海外植民地を喪失しますが、仏は形式上「戦勝国」となったため、インドシナ・アルジェリアで1965年まで「戦争」を継続しました。
サルトルと『現代』は、その過程で一貫して「植民地独立」を支持する篝火であり続けます。
また植民地独立後はマグレヴ(旧仏植民地)からの安価な移民労働者の導入(政府も関与)が生み出した所謂「郊外 banlieue」の問題、「クセノフォビア」の問題にも取り組みます。
FNのジャン・マリー・ルペンはアルジェリア戦争でアルジェリア人を拷問する立場にありました。
「記憶の戦争」は仏でもまだ終わっていないのです。
20世紀演劇をS.ベケットとともに代表するB.ブレヒト。
フランスにブレヒトを導入したのは、あのロラン・バルト(1915―1980)でした。
バルトはサルトルの影響下に『零度のエクリチュール』(1953)を著します。
その後、『記号学の原理』などで「構造主義」批評に分類されたりもしますが、『テルケル』でソレリスやクリステヴァに神輿に担がれたりしますが、毛沢東主義にはついていけず(「文革期」の中国には「行くだけ行ったが」)、晩年再び記号論からは離脱。
バルトの青年期の愛読書はジッド(プロテスタント・同性愛者でもある)、ブレヒト、サルトルだった。
バルトは1964年に上梓されたサルトルの幼年期の自伝『言葉 Les mots』を絶賛。「サルトルは近いうちに再発見されるだろう」と予言。
しかし、このバルトの予言はまだ
仏・英・日では広くは「実現」していないようです。
また、バルトのイメージ自体も同様に三カ国すべてで「歪めれたまま」。
バルトの弟子だったA.コンパニオンが「転向」してソルボンヌ教授に収まり『反近代』(19世紀仏における)などという「当たり前」の話を書いて「大物」と見做されている。
「ヨーロッパの心臓」いつ再鼓動してくれるのか?
「終電車」(F.トリュフォー、1980)
ナチス占領下のパリの演劇人の抵抗を描く。
ユダヤ人演出家の夫をモンマルトル劇場の地下に隠し、マリオン(C.ド・ヌーヴ)はベルナール(G.ドパルデュー)を相手役に「消えた女」を上演する。
極右=ナチス協力者の批評家(モデルあり)は芝居を「ユダヤ的」と難癖をつける。この批評家が所属する新聞「Je suis partout]
」は実際に存在した極右。映画では終戦後批評家は「世界中至る所に partout」逃げ回ることになった、と「落ち」が入る。
トリュフォーは、ブニュエル、ゴダールと同じくサルトルの熱烈なファンであり、サルトルの生前に自伝映画を撮り始めたが、これは完成しなかった。
フランス・レジスタンスと「影の軍隊 L' ARMEE DES OMBRES)」
レジスタンスを戦時中(1941)に鼓舞する、或る意味「プロパンガンダ」としての『カサブランカ』を紹介しました。
1941年と言えば、まだレジスタンスはJ.ムーランのような例外を除けば、ユダヤ系、亡命スペイン共和派が中心だった時代です。
ところで、映画としては『カサブランカ』は「物足りない」という方が居られるかも。
そういう方には1969年の『影の軍隊』がお勧めです。
監督J=P.メルヴィルはユダヤ人であり、英国に渡って自由フランス軍に参加しました。メルヴィルとは、ー米国の作家H.メルヴィルにちなんでいますがーこの時のコードネーム。メルヴィルは「ヌーヴェルバーグ」の兄とも呼ばれ、映画史的にも高く評価されている作家です。
WWII後、占領初期の静かな「レジスタンス」を描いたヴェルコール『海の沈黙』の映画化でデヴュー。
ちなみに「影の軍隊」とはヴィシーに忠誠を誓った軍隊ではなく、仏国内の「レジスタンス」組織こそ「共和国」正規軍という意味。ヴィシー政府は「影の軍隊」を「テロリスト」と呼び「法の外」に置く。
「テロリスト」の名称が政治的に大動員されたのは、この時期の仏がはじめて。
なかなかに政治語法というのは難しい。
現在の研究ではアメリカは共産党許すつもりはなく、万一選挙で保守連合が過半数をとれなかった場合、英とともにイタリアを軍事占領する予定だった、ことが明らかにされています。
結果はキリスト教民主党を中心とする保守の僅差の勝利でしたが、スターリンがイタリアに軍事介入する意志がないことを知っていた(であろう)、トリアッティを含めた共産党最高幹部はむしろ、ほっとしたかもしれません。
実際、ギリシアでは社会内部の力関係では優勢だった左派が英軍の介入で排除され、ソ連もそれを見捨てました(というか、チャーチルとスターリンはそのことについて合意していた)。
この映画「1951」では米国人で、イタリアの資本家の妻となったI.バーグマン演じる主人公は、子供の死とともに「社会問題」に目覚め、「イタリア共産党」の文化部長の親族としばらくともに行動するが、結局袂をわかち、半ば自分の意志ともとれる流れで精神病院に監禁される、ところで映画は終わりる。
日本では1951年と言えば堀田善衛の「広場の孤独」が発表された年です。ユーラシアの東端と西端で「国際冷戦レジーム」への抵抗としての「中立主義」が成立し、有意味な参照関係が成立したのは、このような文脈があります。
欧州でその立場をもっとも代表したのはサルトルと『現代』)でした。
R.ロッセリーニ「ヨーロッパ 1951
「無防備都市」、「戦火のかなた」、「ドイツ零年」のネオリアリズモ期のロッセリーニの作品はよく知られていると思います。実際、傑作でもあるし、ゴダールの「映画史」でも、もっとも登場回数が多い三作かもしれません。
1944―45年のイタリアは反ファシズムの内戦(中部・北部イタリア)を人民戦線的な構図をたたかい(ロッセリーニの前2作は、イタリア・パルチザンのたたかいが舞台)、戦後国民投票で王制を廃止し、共和国へと移行しました。
ところが、戦後ただちに地球規模での国際冷戦レジームの構築がはじまり、イタリアは、分断されたドイツ、ギリシアなどともに、ヨーロッパにおける最前線地帯の一つ、となります。
ただし、共産党の存在が認められたように、ドイツ、ギリシア、韓国と比較すると「緩衝地帯」としての要素も入ってきます。
この点、フランスと類似する面もあります。日本は同じく「前進基地」であると同時に「緩衝地帯」とされた点で、近い面もありますが、イタリアは長く共産党(PCI)が過半数に伺うほど強大な点が大きく異なります。
とくに内戦地域になった中部イタリアでは圧倒的。しかし、ロッセリーニは非「共産主義」左派であったため、冷戦の激化とともに、難しい立場に立たされていきます。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
