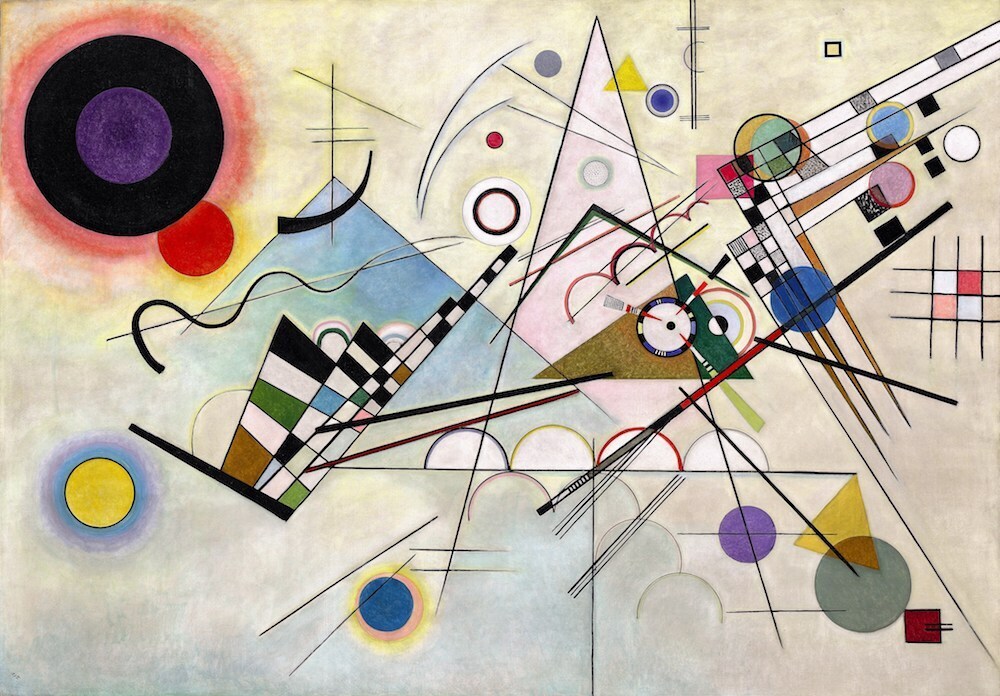
A.ゲルマン「わが友イワン・ラプシン」を観る。
これでゲルマンが監督をした映画は全て観たことになる。
1938年生のゲルマンは「道中の点検」(1972)が検閲で上映禁止になって以来、ペレストロイカまで映画上映を禁止。1998年の「フルスタリョフ、車を」がロッテルダム映画祭が上映されるまで沈黙を強いられた。「神々の黄昏」(2013)の撮影後死去。この映画は死後上映ということになる。
ロシアの映画監督としては、タルコフスキー、ソクーロフなどが著名だが、ゲルマンは別格の貫禄がある。
やはりポルトガルのサラザール独裁政権時代、沈黙を守り、その後105歳まで映画を撮り続けたオリヴェイラと相通じるものがある。
オリヴェイラ、晩年は駄作も多かったが、1991年の「神曲」や95年の「メフィストの誘い」は傑作である。
1575年の「長篠の戦」での三段射撃は現在の研究では疑問視されており、明治に入ってからの教科書記述で人口に膾炙したようだ。
これは近世欧州の軍事史と比較しても納得がいく話ではある。
そもそも当時の火縄銃はライフリングがされていないため、命中率が極めて低く、有効射程距離は最大100メートル。
これは百年戦争の際のイングランド(ウェールズ長弓隊)の射程距離より遥かに短い。また1分あたりの射撃頻度も圧倒的も長弓隊が優る。ただし、長弓隊は子供の頃からの長期の訓練がないと育成できない。
対して火縄銃・マスケット銃は長くて数ヶ月の訓練で習得できた。
従って、いわゆる「足軽」に火縄銃を担当させることは「合理的」と言える。
16世紀末の日本に大量の火縄銃が普及したのもそういう背景があるのだろう。
いわゆる「武田の騎馬隊」が存在したのかどうかも疑問のようだ。実際当時の日本の馬はポニー程度の体躯で重武装した突撃に耐えられたかどうか疑問。
それに対し13世紀の仏重騎兵を乗せた馬はかなりの大きさ。ただし、逆に弓や銃の的になりやすい。
とは言え、18世紀まで決定的な火力となったのは大砲。
明はすでに大砲を16世紀には導入していたので、朝鮮侵略した秀吉軍はそれに敗れたとも言える。
「週刊金曜日」でNHKディレクターの石原大史さんが、公安警察による「大川原化工機事件」と経済安保の関係を、リークされた警視庁公安部の未公開資料を基に論じている。
この資料は、警視庁公安部外事一課が、「事件」の成果を総括するために作成したものと見られる。
ここでは「事件」を中国脅威論・経済安保の文脈の中で位置づけ、次のように外事一課長が「総括」している。
「本事件はマスコミでも大きく報道されるなど社会的反響も多きく、我国の先端技術保有企業等にも注意喚起を促す等の効果があった」
要するに、公安外事一課は、この「冤罪事件」を経済安保体制への貢献、と自画自賛していたわけだ。大河原社長は、「自分達はスケープゴートにされた」と主張していると言う。
また匿名の警察関係者によると、この事件の担当幹部は「この事件は”政治”だ。「報道にうまくアピールすればモノになる」と語っていた。
しかし警視庁公安部が確信犯で捜査を「政治」と位置づけるようになれば、それは「法の支配」の終焉を意味する。
経済安保法案、ほぼ審議なしで衆院通過したが、参院で徹底した審議することは必要だろう。
それにしても、この法案を後押しする「朝日」、立憲に無抵抗を指示する連合、どの口で「立憲主義」を唱える?
なんと、新出版社地平社、6月には月刊総合誌「地平」を創刊するそうです。
しかし、レセプションで紹介されていた社員は5,6人である。
これで月刊、というのは大丈夫なのだろうか?勿論、現在世界も日本も風雲急を告げ、それを批判的に捉える「言論」がない、という危機感はわかる。
季刊などと悠長なことを言っている内に、経済安保法案も国立大学大改悪法案を通ってしまうのは事実である。
ここは熊谷社長、全退職金を資本金につぎ込んで、乾坤一擲の大勝負に出たということなのだろう。
走り始めたからには、私としては応援するしかない。何と言ってもスピーチで「臥竜から雲を掴み、天翔ける龍となることを疑わない」と煽ったのは私でもありますし・・・
尚、1年定期購読は地平社のページからできるようです。
先日、お知らせしたインタビュー、「民主主義は「スラップ訴訟」に屈してはならない」のタイトルで「ZAITEN」6月号(5月1日発売)に出るようです。
私は実は、この「ZAITEN」という雑誌を知らなかったのですが、取材を受けて、「基本方針は権力の批判です」と説明を受け、2,3冊拝読すると確かにそうだった。
少なくとも今の「朝日」よりは、三菱重工などの軍需産業や「経済安保マフィア」などを持続的に批判している。
というわけで、インタビューを受けることにしました。
編集長さんの説明では、「普通の本屋さんに置いてある」とのことでしたので、ご関心のある方はご一瞥いただければ幸です。
今、気づいたのだが、ホームページには新刊拙著の写真まで載せてくれている。ありがとうございます!
目次で野田と並んでいるのはやや複雑な気持ちだけれども。
去年の『現代思想』4月号で、現代日本の「教育と社会」討議のお相手をして下さった大内裕和さんが、早速拙著の読後の感想をXにUPしてくれています。ありがとうございます。
https://twitter.com/ouchi_h/status/1782026043492290947
本屋に並ぶのは月末、と聞いていたけれども、東京堂さんは地平社の立ち上げに協力してくれた、ということだろうか?
尚、前述の去年の『現代思想』の討議も戦後日本社会の推移と言説、それに学歴を通じた階層移動システムの機能不全の問題など幅広く扱っています。もし、ご関心のある方はご一瞥下さい。
集英社の『アジア人物史』、著者の一人、栗田禎子先生からご恵投いただきました。ありがとうございます。
栗田先生の担当は、ジャマールディーン・アフガーニー。アフガーニーは、西洋帝国主義列強、とりわけ英国によるアラブ・イラン・インドへの侵略に対して、立憲主義・法治主義に基づいた、「近代化」したイスラム主義と、アラブ、イラン、インドのイスラムの連帯を説いた思想家。
このアフガーニー、1980年代の私の高校時代は教科書にも掲載されていなかったように思う。
史上初の黒人共和国ハイチの指導者、「黒いナポレオン」トーサン・ウーヴェルチュールとともに、研究が教育に徐々にではあれ、フィードバックしていった例だろう。
それにしてもこの大部な書物、いくら荒木飛呂彦の装画とは言え、4000円台、とは集英社もかなり大胆な賭けに出た、という感じはする。
東大出版会から刊行された『女性/ジェンダー』、著者の水溜真由美さんからご恵投いただきました。
水溜さんは、日本近現代思想史専攻で森崎和江研究の第一人者。現在北海道大学教授。
他にも石牟礼道子、堀田善衛など数多くの作家・思想家に関する研究・著作があります。
今度の出版会の本は、女性/ジェンダーに関する、近代日本のテクスト、例えば与謝野晶子、平塚雷鳥、高群逸枝、そして山川菊枝。また田村俊子、湯浅芳子、松田解子、さらに田中美津、松井やよりなどのテクストを4つのテーマに分けて収録、それに現代的視点から解説をつけたものです。
また上野千鶴子さんの世代に典型的な「第一波/第二波フェミズム」という進歩・段階史観を脱構築している点でも画期的、と言えるでしょう。
このテーマに関心がおありの方は、是非お読みください。
14-16世紀の所謂「ルネサンス」期において、ネーデルランドはフィレンツェなどの北イタリアと並ぶ文化の中心地。
ルネサンス期の特徴である(哲学者ではなく)文献学者はと言えば、最初に上がるエラスムスはロッテルダム出身、バーゼルで死去。「ユートピア」のトマス・モアはネーデルランド大使としてエラスムスと親交を結ぶが、最後はヘンリー8世の離婚に反対して処刑。
「ユートピア」で出てくる「羊がヒトを食べる」エピソードはイングランドが当時、ネーデルランドの毛織物産業の原料である羊毛を供給地であったことを示す。領主達は羊の放牧地の確保のために小農民を土地から追い出した(所謂第一次囲い込み)。
この北方の人文主義者達は、フィレンツェのフィチーノやピコ・デラ・ピランデルラのネオ・プラトン主義に多いに影響を受けた。
人文主義者はカトリック内部での改革を志向していたが、ルター、さらにカルヴァンが出るに及び、宗教対立は決定的となり、ユマニスムの目指した「調和」の世界はマニエリスムへと滑り落ちていく。ネーデルランドではヒエロニムス・ボスの祭壇画などがこの「不安の時代」を象徴するとも言えるだろう。
フーコーは『狂気の歴史』では、「大いなる監禁」のエピステーメーの「以前」として、ボスの絵画に長々と言及している。
J.ホイジンガに『中世の秋』という書物がありますが、ここで扱われているのは、パリのヴァロア王権に対抗したディジョンを中心とした傍系のブルゴーニュ家の領域。ほぼ、カロリング朝が分裂した際のロートリンゲンにあたる。
このブルゴーニュ公国は、当時北イタリアと並ぶ欧州の2大経済中心地であったフランドル地方をも支配。
ところがパリの王権との闘争に敗れて、フランドルの南部は仏に、最後の女伯はハプスブルク家のマキシミリアンと結婚することで、北部はハプスブルク領となる。このマキシミリアンの孫が神聖ローマ皇帝カール5世=スペイン国王カルロス1世。
カール5世と次のフェリペ2世は新大陸から強奪した貴金属をセビリアからアントワープに運び、そこで欧州統一のための大傭兵団を編成。同時にアントワープは覇権国家スペインの金融センターとなる。
しかし、ホラント州を中心としたネーデルランド連邦共和国が16世紀末から海洋覇権を奪い取り、総督派と共和派の内部対立を抱えながらも文化的にも欧州の一大中心地となる。
オラニエ総督派がカルヴァン派、共和主義派がアルミニウス派と大まかには分類できる。
国際海洋法の父とされるグロティウスは、カルヴァン派(総督派)に追われ、パリで「戦争と平和の法」(1625)を著すのである。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
