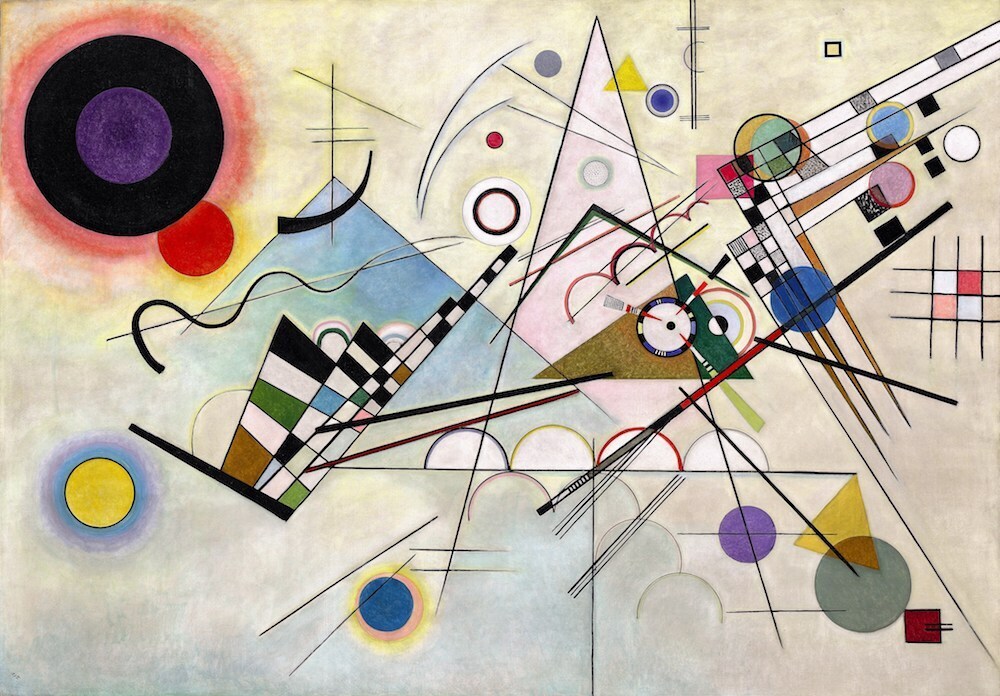
J.ルノワール『ラ・マルセイエーズ』(1938)。ジャンは有名なA.ルノワールの息子。この映画では、兄ピエールはルイ16世役で出ている。
ルノワールは1930年代、「トニ」(35)、「ランジェ氏の犯罪」(36)「ピクニック」(36)、「大いなる幻影」(37)、ゲームの規則(39)など映画史に残る傑作を立て続けに監督。「トニ」、S.バタイユが主演した「ピクニック」ではビスコンティ、「ラ・マルセイエーズ」ではベッケルが助監督を務めた。
この映画は「人生は我らがもの」と同様、反ファシズム人民戦線への連帯として撮影された。
最初は1789年7月14日、バスティーユ襲撃を知らされたルイ16世が「暴動か?」ー側近「陛下、これは革命です」の有名な場面で始まる。
映画では南仏のプチ・ブルジョアのインテリ、マッソン(石工だが、フリーメーソンの意味も掛ける)、貧農、下層都市民の4人に焦点があてられる。
最後は、共和国の存続をかけてヴァルミーでプロイセン軍に立ち向かう場面で終わり、「ここから、そしてこの日から新たな世界史が始まる」というゲーテの有名な言葉が引用される。
この場面で「自由」=「恋人」の比喩が用いられる。レジスタンス中のエリュアールの有名な「自由よ、僕は君の名を書く」はここから来たのだろう。
1951年と言えば、日本では堀田善衛の「広場の孤独」が発表された年。また、サン・フランシスコ講和条約(日米同盟)に反対して、平和4原則、非同盟中立路線が社会のかなりの部分の同意を得る。
欧州ではサルトル、メルロー=ポンティ、ボーヴォワールの『現代』を中心とした独立左派が朝鮮戦争の勃発のアルジェリア独立問題で、四分五裂へと追い込まれていく。
この中であくまで「中立」と植民地独立を堅持したのがサルトルと『現代』です。メルロー=ポンティとカミュは、朝鮮戦争とアルジェリア問題にある意味「躓き」、冷静な状況判断能力を失って脱落していきます。
そうした意味でユーラシアの東端と西端で「国際冷戦レジーム」への抵抗としての「中立主義」が成立し、ある期間までは有意味な参照関係が成立したのは、こうした世界空間の再編、という背景があったと思います。
ロッセリーニ自身はその後、アッシジのフランチェスコの伝記(?)映画(「神の道化師 フランチェスコ)を撮り、ある意味、キリスト教左派的な社会主義に向かっていきますけれども(「殺人カメラ」)・・・
現在の研究では米国は伊共産党に政権にわたすつもりはなく、万一選挙で保守連合が過半数をとれなかった場合、英とともにイタリアを軍事占領する予定だった、ことが明らかにされている。
結果はキリスト教民主党を中心とする保守の僅差の勝利。スターリンがイタリアに軍事介入する意志がないことを知っていたトリアッティを含めた共産党最高幹部はむしろ、ほっとしたかもしれません。
実際、ギリシアでは優勢だった左派が英軍の介入で排除され、ソ連もそれを見捨てた。(というか、チャーチルとスターリンはそのことについて大戦末期に合意していた)。
この映画「1951」では米国人で、イタリアの資本家の妻となったI.バーグマン演じる主人公(米国人)は、子供の死とともに「社会問題」に目覚め、「イタリア共産党」の文化部長の親族(イタリアでは上流階級出身のコミュニストはかなりいた)としばらくともに行動するが、結局袂をわかち、半ば自分の意志ともとれる流れで精神病院に監禁される、ところで映画は終わる。
日本では1951年、と言えば堀田善衛の「広場の孤独」が発表された年(続く)。
ロベルト・ロッセリーニ「ヨーロッパ 1951」
「無防備都市」、「戦火のかなた」、「ドイツ零年」のネオリアリズモ期のロッセリーニの3作品はよく知られていると思います。
実際、傑作でもあるし、ゴダールの「映画史」でも、もっとも登場回数が多い三作かもしれません。
1944-1945のイタリアは反ファシズムの熾烈な内戦(中部・北部イタリア)を経て、(ロッセリーニの前2作は、イタリア・パルチザンのたたかいが舞台)、戦後国民投票で王制を廃止し、共和国へと移行。
ところが、戦後た直ちに地球規模での国際冷戦レジームの構築が始まり、イタリアは分断されたドイツ、ギリシアなどともに、ヨーロッパにおける最前線地帯となる。
ただし、共産党の存在が認められたように、ドイツ、ギリシア、韓国と比較すると「緩衝地帯」としての要素も入っては来る。
この点、フランスと類似する面もあります。日本は同じく「前進基地」であると同時に「緩衝地帯」とされた点で、近い面もある。ただし、イタリアは長くイタリア共産党(PCI)が野党第一党である点が大きく異なります。とくに内戦地域になった中部イタリアでは圧倒的。
しかし、ロッセリーニは非「共産主義」左派であったため、冷戦の激化とともに、難しい立場に立たされていく(続く)。
A.ゲルマン「わが友イワン・ラプシン」を観る。これで公開されたゲルマンの映画は全て観たことになる。
1938年生のゲルマンは「道中の点検」(1972)が検閲で上映禁止になって以来、ペレストロイカまで映画が創れなくなる。
作家は、まだ「密かに書く」ことができるが、チームと最低限の資金を必要とする映画監督にとっては撮影禁止はつらい。
結局ゲルマンは1998年の「フルスタリョフ、車を」がロッテルダム映画祭が上映されるまで沈黙を強いられることになった。
「神々の黄昏」(2013)の撮影後死去。この映画は死後上映ということになる。
ソ連・ロシアの映画監督としては、タルコフスキー、ソクーロフなどが著名だが、ゲルマンは別格の貫禄がある。「宇宙飛行士の妻」などで知られる映画監督のA.ゲルマンJrは息子。
ゲルマンのキャリアは、やはりポルトガルのサラザール独裁政権時代、沈黙を守り、その後105歳まで映画を撮り続けたオリヴェイラと相通じるものがあるように私は感じている。
オリヴェイラ、晩年は駄作も多かったが、1991年の「神曲」や95年の「メフィストの誘い」はやはり傑作である。
アイスランドが国民の遺伝子情報を一企業に委託していることはご存じの方も多いのでは。
映画「湿地」はこの状況を背景にしたサスペンス映画。サスペンスとしても良くできていますが、その過程で「生命倫理」的な問いを浮かび上がらせている、という点でもうまい映画だと思います。
それにしても、「新生児医療」に携わっている友人から、アイスランドでは、現在、ほぼ「ダウン症」がゼロで移行しており、おそらくそのままの率で進むだろう、という話を聞いて複雑な気持ちになったことを思い出しました。これはもちろん、「出生前診断」によるものです。
昨今、「確信犯」のメディアのみならず、世間、あるいは学生のなかにも、むやみに「遺伝」ですべての問題を語ろう、とする傾向が強まっていることには危機感を感じます。
とくに医学部系の学生は、ほぼ完全にそれがデフォルトになっており、ほとんど優生思想と区別がつかない場合も多い。
現在の優生思想は新自由主義による格差の正当化に明らかに寄与しており、新自由主義と優生思想との共犯関係を批判する必要性を強く感じます。
とりわけ、分子生物学者や遺伝学者(の一部)はみずからの「学問」の「エビデンス」を逸脱して事実上「優生思想」に踏み込んでいる場合も多く、きわめて深刻な問題だと感じます。
大岡昇平原作、溝口健二監督の『武蔵野夫人』を数十年ぶりに観る。
文学と映画は全く別ジャンルの芸術なので、文芸映画というのは難しい。大河ドラマ的な構成にやすいトルストイの『戦争と平和』でさえ、何度も映画化されているが、成功作はない。
ところで、この溝口の『武蔵野夫人』全くの駄作である。溝口は1930年代と50年代の時代物で海外映画祭狙いの作品は、相当水準が高い。小津と並んで、映画史的には1950年代を「日本映画の時代」と言わしめる位である。
しかし、戦後の混乱期を描く「現代」を舞台にしたものはからっきし。
成瀬と比較して、溝口には花柳界の女性しか描けない、という決定的な弱さがある。成瀬は多様な職業の女性を描くことができた。
ところで、この映画を「失敗作」にした要因は「潤色」の福田恒存にある。福田は小説「武蔵野夫人」を「失敗作」と断じたらしいが、いくらなんでもこの映画のシナリオはひどい。
福田は小林秀雄ともに『正論』を73年にサンケイから創刊。70年代後半はフジテレビで「世相を斬る」などと小癪なことする。朴正煕との密接な関係。
早稲田英文教授の弟子にシェクスピアの翻訳をやらせ(名義は自分)、その弟子は自衛隊と密に交流していた「ど右翼」。最後は小林よしのりの神輿となった。
A.ドロン死去(88歳)。
フランスの俳優にしては珍しい「イケメン」だった。
同世代のもう一人のスター、J=P.ベルモンドが「勝手にしやがれ」などの役柄とは異なり、ブルジョア出身の「インテリ」だったのに対し、アラン・ドロンは、家庭環境が安定せず、海軍兵士としてインドシナ戦争に従軍もした。
実際、アランは「インテリ」とは言えず、マフィアとの関係も「公然の秘密」だったとされるが、若い頃は「繊細で知的な青年」を演じることが多かった。
例えば、ゲイであったL.ビスコンティに愛され、『若者のすべて』や『山猫』などに出演できたことは、ドロンにとって幸運なキャリアだった。またJ=P.メルヴィルの映画にも複数出演、これらはすべて歴史に残るだろう。
他方ヌーヴェル・ヴァーグからは目の敵にされたルネ・クレマンの『太陽がいっぱい』では「現代のジュリアン・ソレル」を演じ、大衆的にも一挙に大スターになる。
実際これは、今見てもアラン・ドロンの俳優としての潜在力を引き出したよくできた映画だと思う。
この美的センスは日本の「太陽族」を演じた代表とも言える石原裕次郎とは全くレベルが違う。
その上、ゴダールの「ヌーヴェル・バーグ」にも出演しているのだから、まさに時代に恵まれたと言えるだろう。
J=L.ゴダールの最後の長編、「イメージの本 Le livre d'image 」(2018年)を観る。これで三度目位くらいだが、記憶とさして変わらなかった。最近「短期記憶障害」に不安を抱えているので、少し安心した。😀
映画の構成は、基本「晩期」ゴダールの基調である「新ドイツ零年」、「映画史」に連なる。
ただし、2点ほど大きな変化がある。
まず、ロシア革命ではなく、むしろフランス革命への回帰が見られること。
68年以降、ゴダールは一時期は共産主義、とりわけ毛沢東主義への批判的近接性が前景化する。
その後毛沢東主義への言及はほぼなくなり、ロシア革命とナチズム、ホロコーストに焦点が移る。
しかし、21世紀に入ると、さらに時代を遡りフランス革命への言及が増えてくる。これは決して「フランス・ナショナリズムへの回帰」ではなく、フランス革命の特異性を問題化していると見做せる。
2点目はイスラエルによるパレスティナへの暴力への言及が急激に前景化していること。特に映画の後半はほとんどこの問題に費やされる。ゴダールの立場は明快で「私はアラブ(イスラムではなく)の側に立つ」というもの。
ホロコーストからパレスティナへ。ゴダールは90歳に至るまで深化し続けた作家と言えるだろう。
今週の「週刊読書人」にて、『地平』創刊に寄せて、ということで熊谷編集長、内田聖子さん、武田徹さん、の鼎談が掲載されています。
しかし、この鼎談、2号校了終了後に行われた、ということだけれども、さすがに熊谷さん、ちょっとお疲れのご様子。何と言っても、ちょうど校了の日は2時間睡眠といっていたからなー
「68年5月、サルトル、ゴダール」
1958年にクーデターで政権を掌握したド・ゴールは1962年にエヴェイアン協定でアルジェリアの独立を認めます。ただし、アルジェリア領内での核実験場所の確保など、さまざまな条件をつける。
国内ではテクノクラート主導の経済成長を採用するも、クーデターから10年後の1968年5月、パリ大学ナンテール校(私は2002-2004客員研究員だった)から火の手が上がった学生運動がパリのカルチェラタンに飛び火、これにCGTを始めとする労働組合が呼応して「ゼネスト」に入ることで、首都パリは「権力の空白」状態へ。
ド・ゴールは一時国外に出て、軍の支持を確保して後、帰国。秩序を概ね回復した後、「信任選挙」に打って出て何とか勝利するが、69年に辞任。
言説界では、当時「構造主義」が一世を風靡していたが、五月革命では「構造はデモをしない」というグラフィティが溢れる。
サルトルはこの際、学生叛乱を断固支持。すでにノルマルに勤務していたデリダもビラの編集作業など「慣れない」仕事をした。
またF.トリフォー、G=L.ゴダールなどサルトルに私淑する映画監督も運動に参加。
写真上はビラを配るサルトル、後ろの女性がボーヴォワール。下はゴダール、サルトル、ボーヴォワールである。
「仏で人民戦線(左派連合)大勝利」
都知事選と同日7月7日に行われた仏国民議会選挙では、当初の予想を大きく覆し、新人民戦線が182議席で第一党、マクロン党が168、極右(RN)は143で、過半数どころか三位に沈みました。
政治危機において、「左か右か」の二択しかなければ「左」が勝利する、という「フランスでは左翼は無敵 En France ,pour la gauche , il n'y a pas d'ennemi」の政治文化、 三度に渡り裏付けられた形です。
ちなみに一度目はドレフュス事件から第三共和制、二度目は30年代の反ファシズム人民戦線。
ただし、今後の政局は混乱が予想されます。なんといってもマクロンは「人民戦線よりはルペンがまし」という男。また新人民戦線には「政治屋」R.グリュックスマンを始め、日和見中道も多くいる。36年に勝利したブルムの人民戦線も内部の「いざこざ」で崩壊しました。
しかし次の焦点はまずは来週7月14日の革命記念日。この日は巨大なデモが予想される。今まで強行突破してきた悪法の撤廃は勿論、マクロンが辞任に追い込まれる可能性さえある。
ただし、「右側(右翼)に気をつけろ Soigne ta droite」(J=L.ゴダール)
20世紀前半の「社会的カトリック」は資本家と労働者の間の支配・搾取関係を批判し、労働運動に参加する人々も現れます。
これは主に日常的に民衆と接する機会が多かった「村の司祭」(教会内部での地位は最下位)が中心になります。日本で『出る杭は打たれる』を書いたA.レノレ神父も極東にまで志願してやってきた労働神父です。
しかし仏における「社会的カトリック」にはナチスによる「占領」という試練がありました。
多くの司祭はレジスタンスを匿い、また自ら参加さえしました。ルイ・アラゴンの詩に「神を信じる者も、神を信じないものも」という句があるのはそのためです。
現在の歴史的調査では占領中、はっきり「レジスタンス」派は人口の1割、「対独コラボ派1割」、残りは最後まで「なだらかな日和見のスペクトル」だったとされている。
とは言え、この時のレジスタンスの犠牲と神話によってWWII以後仏では「ファシズム」・「極右」はタブーとされて来た。この「共和国の神話」がついに破られるのか、または守られるのか、明日日本時間7月8日未明には判明します。
下の映画は『影の軍隊』で知らせるJ=P.メルヴィルの『モラン神父』。レジスタンスに参加する神父をJ=P.ベルモンドが演じます。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
