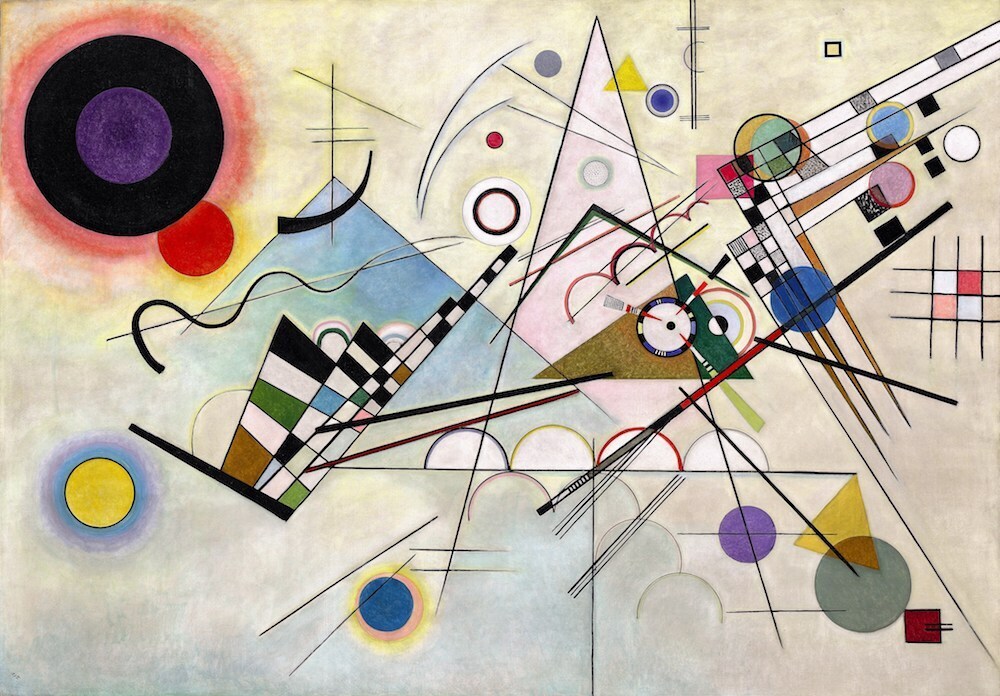
続き)
判事に関しても、最高裁事務局が定期的な研修と人事権によってコントロールしているのは周知のとおり。
もし、仮に日本で司法権力が独立していたとすれば、冷戦後イタリアでキリスト教民主党、社会党など政権担当与党が軒並み構造汚職で逮捕され、崩壊した事態と類似の様相を呈したと思います。
にも関わらず、日本では検察・警察と政治権力・財界の関係を映像化したものが極端に少ない(とくに劇映画)と感じます。
逆にタレントに「型破りの検察」をスター化して描いたり、公安側から撮っているアニメなどがある。
近年の韓国映画では、ノワールの形式をとったもの(江南ブルース)、あるいは弁護側から撮った「法廷闘争」もの(「国選弁護人」)、両方の要素があるもの(「インサイダーズ」)など、複合的なパワー・エリートの構造を娯楽物として仕上げる劇映画が続出しています。
都市開発・地上げとマフィア、検察、財界・政界との関係など、日本に類似した構造が筋になっていることも興味深いです。
決していわゆるフォトジェニックな映画ではありませんが、やはりパワーで圧倒する昨今の韓国映画の勢いを感じさせます。
「支配階級 ruling class」ー合法化された暴力の管理者ー検察
近年の韓国映画は、検察と財界・政界のつながりを描くものも多い。
検察・警察は、軍隊と並ぶ「合法化された暴力」の管理者でありまがら、一般的に組織としてあまり表に出ることを好みません。
日本など、自衛隊、防衛省などよりも、警察庁、検察の方が実質的にははるかに権力を持っていると言っていい。
特に安部前政権、経産省+警察キャリア公安組によって固められていた。
日本では、元来三権分立、とくに司法の独立が機能していません。
いわゆる「統治行為」論をはじめとする「政治案件」は言うまでもなく、刑事案件でも、圧倒的に検察優位であり、起訴された場合の、世界に類を見ない99%前後の有罪判決率などは、この検察優位の一つの表れと言えるでしょう。
賛否両論ある「裁判員制度」も一審だけのことであって、二審、三審には関与できません。
いずれにしても、現在のところ、裁判員制度が検察に歯止めをかけるようにはなっていないようです
また「死刑執行」に関しても法務大臣に圧力をかけるのは、検察です。
つまり法務次官よりも検事総長の方が上なのです。
判事に関しても、最高裁事務局が定期的な研修と人事権によってコントロールしているのは周知のとおり。
ロベール・ブレッソン「ジャンヌ・ダルク裁判」
当時の裁判記録を忠実に再現したとされるブレッソンの「ジャンヌ・ダルク裁判」。他の多くのジャンヌ・ダルクを扱った映画と異なり、啓示や戦闘のシーンは一切なし。
ジャンヌ・ダルクについては、いままでかなりの映画監督が取り上げてきました。ドライヤー、ロッセリーニ、リヴェットなど。シェクスピアの「ヘンリー6世」では、英側から描かれるので、かなり「好戦的」な女性として描かれます。
ブレッソンのこの映画では、「人を殺すのは本意ではなく、剣よりもむしろ旗をもつことを好んだ」と法廷で述べています。
記録に残っているわけですから、実際そう述べたのでしょう。
いずれにしても、ジャンヌ・ダルクは延々と著述でも描かれてきたので、ジョレス(社会主義者、第一次大戦に反対して暗殺)、バレスのダルク、近年ではFNのダルクなど、語り手によって、「ジャンヌ」にはかなり違う意味を担わされてきました。
この映画の最後には「有罪が確定している刑事裁判」の欺瞞、拡大すれば「すべての刑事裁判の欺瞞」を描くことを意識した、という趣旨のコメントが流れます。
これは「スリ」で最後ラスコーリニコフが司直の追求を振り切ってしまう、というブレッソンの姿勢にも通じるところでしょう。
「ブレッソン、フーコー、サルトル、そしてアナーキズム」
私見では、ブレッソンの刑事裁判、国家機構への正統性への疑問は、M.フーコーの立ち位置に通じるものがあると思われます。
「監獄の誕生」、「ピエール・リヴィエールの犯罪」、あるいはコレージュ・ド・フランスの監獄、刑事権力の知的正統性の誕生などを扱ったものではさらにはっきりと近接性が窺えます。
ただ、もっと言えばこのブレッソンやフーコーの視点はある世代までのフランスの「アナーキズム」と呼ばれる空間ではかなり共有されたものだったとは思います。
例えばこの点ではサルトルとフーコーでは違いはありません。むしろ、サルトルの方が一貫してアナーキズムの側に立っていた、と言えます。
ただ、ブレッソンのこの映画の時代的文脈で言えるのは、15世紀フランス北部を占領していた英軍とブルゴーニュ派の同盟が、第二次大戦中フランス北部を占領していたナチスとコラボの関係を想起させざるを得ない、ということです。
おそらく当時の観客の多くはブレッソンの示唆とは別に、そのように観たのでは、と推測されます。
その点では当時、この「ジャンヌ・ダルク裁判」はレジスタンスの映画としても受容されたのでしょう。
これもブレッソンの傑作の一つだと思います。
V.ユーゴー『レ・ミゼラブル』
フランスでは大詩人とされるユーゴーですが、日本では詩人としてというよりは、やはり「レ・ミゼラブル」の作者として知られている印象です。
僕も、複数のフランス映画バージョンを見てきましたが、近年の英語版ミュージカルも、テンポよくつくられていたと思います。
ただ、別の意味で印象に残ったのは、最後J.=ヴァルジャンの死の場面で、「現世の罪」から洗い流されて昇天する、というメッセージになっていたことです。
原作では、あるいはフランス版映画では、J.ヴァルジャンは、「罪」を犯したとは見做されておらず、むしろブルボン王政復古と産業革命の進展によって生み出された「悲惨」と「不正」の犠牲者にして抵抗者という位置づけです。
また、ユーゴーも含めロマン派一般はプロテスタンティズムよりも、「原罪」の観念を限りなく希薄化したカトリックに近く、ードイツ・ロマン派詩人たちもほぼすべてカトリックに回帰したーその点も映画版ミュージカルは、原罪とそこからの救済、というプロテスタンティズムの様式に従っていて、その点、やはりアングロ・サクソン的で興味深かったです。
いずれにせよ、この映画、近年の英語圏の若年層の「左傾化」の感性と共振していることは間違いないと思われます。
「文学と映画・・・ユン・ドンジュとエミリー・ディキンソン」
昔からいわゆる「文芸」映画、というものがありますが、文学と映画はまったく別のジャンルなので、いわゆる名作を原作にした映画が成功するとは限りません。
典型的なのは、トルストイの「戦争と平和」。これはアメリカ、ソ連どちらの映画化も失敗だったと言ってよいと思います。
とくにアメリカ映画の場合、かならず登場人物に英語を話させますので、これはちょっと苦しい。第二次大戦時を扱った映画でもSSやドイツ国防軍の将校が英語を話すのはやはり無理があります。
詩人の伝記映画、となるとさらに難易度は上がると思うのですが、エミリー・ディキィンソンとユン・ドンジュの二つの伝記映画は、どちらもよかったと思います。
後者の作品、ほとんどの部分をモノクロで撮っているのですが、これはとくに詩人を主役にする場合、冒険だと思うのですが、全体に抑制の効いた画面になっていたと思います。
あと、当然ながらユン・ドンジュを描く場合、日本の植民地支配の暴力とそれへの抵抗、というきわめて「政治的な」テーマと「ポエジー」のバランスというか、交差(「抵抗」が「ポエジー」になる場合もある)がデリケートな問題になりますが、僕はそこも基本的に成功しているのでは、と感じました。
「主婦マリーがしたこと」下
パクストンは米国人であるが故に、コラボの実態を体系的に明らかにできたという側面があるのですが、フランス国内でヴィシー期をタブーなしに描くことができるようになったのはかなりあとになってからです。
映画では、ルイ・マルがわりにはやくこの問題を題材にしていましたが・・・
実際、戦後初の社会党大統領となったミッテランでさえ、戦間期は「極右団体」の積極的メンバーであり、ペタンの墓には自らの死の年まで献花を怠らなかったことを考えても、フランスにおいても「記憶」操作の難しさが長期存在したことがわかりまず。
現在は「植民地帝国」フランスの記憶と、「共和国」フランスの歴史の衝突・対話が「移民」問題と絡んで常に言論界の紛争を巻き起こしています。
映画の世界でも「コラボ」やフランス警察が進んで行った「ユダヤ人狩り」は頻繁に取り上げられるようになりましたが、アルジェリア戦争、インドシナ戦争の映像と記憶の試みははじまったばかりという感じでしょうか?
「主婦マリーがしたこと」中
ともあれ、降伏したフランスはpペタン元帥を首班とするヴィシー政権となり、1789年以来の「自由・平等・友愛」にかえて「家族・労働・祖国」をスローガンにした「国民革命」を主導した。
戦後直後の「神話」と異なり、旧フランス共和国の高等行政官(警察はとうぜん)は、ジャン・ムーランを除いてすべてヴィシーに忠誠を誓った。
ヴィシーの「政党」、「官僚」、「知識人」の「コラボラシオン 協力」を体系的に明らかにしたR.パクストンの「ヴィシー・フランス 1940-44」はその意味でまさに「パクストン革命」の名にふさわしい名著だった。
ちなみに戦争末期に拷問によって殺されたジャン・ムーランはド・ゴール派の「英雄」とされ、今に至るまでフランスではやたらと有名人です。
パンテオンに入る際のアンドレ・マルローのむやみに「荘重な」演説もフランス映画で・・・しばしばアイロニーのニュアンスで・・・引用されています。サルトルとマルローを自らの「守護天使 ange gardien」と称するゴダールの「映画史」にもムーランは頻繁に登場します。
「ヴィシー・フランス」の「家族・労働・祖国」とC・シャブロル「主婦マリーがしたこと」
第二次大戦の際、自称「ヨーロッパ最強の陸軍」を擁していたフランスは世界を驚愕させる潰走をし、6週間でナチスに降伏した。
もし、フランスが自称通りの実力を発揮していれば、フランス国内のユダヤ人殺害は阻止できていただろう。
実際、日本で思われているほどナチスの電撃戦(Blitz Krieg)の勝利は確実なものではなかったのです。
戦車、戦闘機、兵力、そして兵士の練度のすべてにおいて、標準的な基準からは英仏連合軍の方が上でした。
また、英仏連合軍がドイツ軍を押し返した場合、ドイツ国防軍はヒトラーを倒すクーデターを立案していた。
その場合、ポーランド、バルト、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアのアシュケナージの「ホロコースト」はなかっただろう。
また、そうであれば、戦後パレスティナに「イスラエル」建国が認められることはなかった筈。
その意味でもWWIで「三枚舌」外交によって、「イスラエル」建国と「アラブの独立」、そして英仏の分割統治を「合意」した英仏帝国主義の責任は、極めて大きい。
パレスティナは、英仏の2度の世界戦争での行為の「つけ」を未だに払わされている。
「別離」下
またファルハーディの映画だけではなく、イラン映画には、ドイツに出稼ぎに行っている人物が頻繁に登場するのも、ここ数十年のイランとドイツの移民労働の関係を背景にしていて、これもおもしろいです。
総じて、日本では「悪の枢軸」、女性を抑圧する「イスラム共和国」と決めつける米国のつくりあげるイラン像が強いようにも感じますが、実際のイラン(とか言って僕は行ったことはないのですが)の一部だけであれ、見ることができるのは貴重だと思います。
例えば、イランは女性の大学進学率はとびぬけて高く、それを背景にファルハーディの描く中産階級の女性たちもごく自然に登場するわけです。
また現在のイランのフェミニズムの活発さにも、こうした背景があります。
ですから、政権保守派の「反フェミニズム」は早晩挫折せざるを得ないでしょう。
唯一の不確定要因は、ほとんど根拠のない、欧米のイラン包囲網です。
これによって国の存立が脅かされれば保守派の「原理主義的」反動が、フェミニズムを抑え込むことはあり得ます。
現在は、その分岐点にある、と思われます。
「別離」
この映画はベルリン映画祭の金熊。監督、アスガル・ファルハーディーは、現在もっとも優れた映画の作り手の一人だと思います。
「サラリーマン」や「浜辺に消えた彼女」などでベルリンやカンヌの常連でもあるのでご存じの方も多いと思います。
かつて、イラン映画は当局の枠もあり、大人の社会の紛争、トラブルを描くことが難しく、結果として「子ども」の視点から見た優れた映画を輩出しました。
また皮肉にもアメリカとの関係で、ハリウッド映画がほとんど入ってこれなかったことが、国内の映画産業を保護し、次の世代を育てることにも成功しました。
かつてのイラン映画は「地方」の農村を舞台にすることが多かったのですが、ファルハーディは、都市中産階級の「女性」と社会の軋轢を、カフカ風のサスペンス・タッチで描きだすのがうまい。軋轢の結果、法廷闘争がわりと長く描かれ、イランにおける民事訴訟の在り方が垣間見えるのも興味深いです。
それにしても映画に限らず中国は、作家・芸術家はかならず「政治」に強い関心をもつ、というか、「政治」に関心のない「文人」・「芸術家」は存在しない、という「伝統」を強く感じます。
これはいわゆる「士大夫」的な伝統だけではなく、魯迅あるいは莫言など近現代作家にも明瞭に受け継がれています。
その逆の面として国家権力が過剰(外からは見える)なほど「知識人」・「作家」の批判的発言に反応する側面もあります。
ただ、であるからこそ、「文化」に支出される予算も超巨額で、分野によってはそれによって成り立っている、という側面もあるのですが・・・
いずれにせよ、1980年代の映画シーンは台湾・中国の時代とも言われましたが、「第五世代」と言われるジャ・ジャンクーを見ても中国映画は健在なんだなぁと思います。
最近だと次の世代(もう)と言われる(と記憶している)「長江画」を見ましたが、これもアンゲロプロスを想起させる霧と水(しかも長江なのでスケールがすごい)それこそフォトジェニックな散文詩とも言えるよい映画でした。
「ジャ・ジャンクーと現代中国の20年」(上)
ジャ・ジャンクーの作品は初期の「青の稲妻」から最近の「山河ノスタルジア」まで、映像的にも優れていますが、現代中国の大きな流れにも敏感な、その意味で「社会」派的な要素をもつ大作家の一人だと思います。
初期の「青の稲妻」などは蓮実的「シネ・フィル」コードでも評価されるようなフォトジェニックな作品(たしか蓮実本人もどこかで誉めていた記憶があります)ですが、次作「世界」(2004)ですでに都市部の「ポスト・モダニズム」的空虚さへ対象を移行させ、「四川の歌」、「長江エレジー」では「改革・開放」以降の中国社会の激変と、取り残される人々への節度を保ったキャメラ、「罪の手ざわり」では新自由主義の矛盾を具体的な人格に凝縮させ、その怒りを爆発させることで社会への問いを浮上させる、といったそれぞれの作品のニュアンスを微妙に変えながらも、高い質の映像を創りあげてきた作家だと私は思います。
(しかし、「罪の手ざわり」は結局中国では上映禁止になったらしい)
R.ロッセリーニ「1951」(下)
しかし、ロッセリーニは非「共産主義」左派であったため、冷戦の激化とともに、難しい立場に立たされていきます。
現在の研究ではアメリカはイタリアの共産党政権にわたすつもりはなく、万一選挙で保守連合が過半数をとれなかった場合、イギリスとともにイタリアを軍事占領する予定だった、ことが明らかにされています。
実際、ギリシアでは社会内部の力関係では優勢だった左派が英軍の介入で排除され、ソ連もそれを見捨てました(というか、チャーチルとスターリンはそのことについて合意していた)。
この映画「1951」では
米国人で、イタリアの資本家の妻となったI.バーグマンは、子供の死とともに「社会問題」に目覚め、PCI文化部長の親族としばらく共に行動するが、結局袂をわかち、半ば自分の意志ともとれる流れで精神病院に監禁される、場面で映画は終わります。
日本では1951年、と言えば堀田善衛の「広場の孤独」が発表された年です。
ユーラシアの東端と西端で「国際冷戦レジーム」への抵抗としての「中立主義」が成立し、ある期間までは有意味な参照関係が成立した(欧州でその立場をもっとも代表したのはサルトルと『現代』)のは、こうした世界空間の再編、という背景がありました。
R.ロッセリーニ「ヨーロッパ 1951」(上)
「無防備都市」、「戦火のかなた」、「ドイツ零年」のネオリアリズモ期のロッセリーニの作品はよく知られている。
実際、傑作でもあるし、ゴダールの「映画史」でも、もっとも登場回数が多い三作かもしれません。
1944-45年のイタリアは反ファシズムの内戦(中部・北部イタリア)を人民戦線的な構図にてよって戦い、戦後国民投票で王制を廃止し、共和国へと移行しました。
ところが、WWII後ただちに地球規模での国際冷戦レジームの構築がはじまり、イタリアは、分断されたドイツ、ギリシアなどともに、ヨーロッパにおける最前線地帯の一つ、となります。
ただし、共産党の存在が認められたように、ドイツ、ギリシア、韓国と比較すると「緩衝地帯」としての要素も入ってきます。
この点、フランスと類似する面もあります。日本は同じく「前進基地」であると同時に「緩衝地帯」とされた点で、近い面もなくはないですが(とくに「知識人の言説」)、イタリアは長くイタリア共産党(PCI)がキリスト教民主党に次いで第二党(自民党と社会党の議席数より僅差)である点が大きく異なります。とくに内戦地域になった中部イタリアでは圧倒的な力を誇りました。
ラウル・ペック「I am not your negro」
ラウル・ペックはハイチ出身、主にフランスで活動する黒人の映画監督です。
ルムンバ政権をアメリカ、フランス、ベルギーによるクーデターによって倒した「ルムンバ」で知っておられる方も多いと思います。
「私はあなたの二グロではないI am not your negro」は、ゲイの黒人作家J.ボールドウィンが公民権運動の際に米国に取材した未完成のテクストをもとにしたドキュメンタリーです。
動く(?)ボールドウィンを多くみられる、という点でも貴重な映像です。
ラウル・ペックは最近日本でも公開された「マルクス・エンゲルス」の監督でもありますが、映画としては上記二作の方が優れていると感じます。
黒人の監督、というのは女性監督と同じくーー俳優はもちろんたくさんいるのですが(それでもフランスは最近)--稀な存在なので、その意味でも重要な存在では、と思います。
ロベール・ブレッソン「スリ」
ドストエフスキー「罪と罰」
inspire by の映画なのですが、最後主人公が身近にいた女性への愛に目覚め、国外に逃亡して「幸せ」(?)に暮らす、というオチがフランス映画らしくおもしろい。
ラスコーリニコフが「大地に接吻して許しを求め、ロシアへの愛」に回心する、原作と比較すると、反社会的な(と設定されている)「スリ」の主人公は、社会への反省や大地への愛などへの身振りを一瞬たりとも垣間見せることなく、身近にいた「個」としての女性への愛に目覚め、孤独から脱出する。
もちろん、そのために主人公の犯す犯罪は「殺人」から、「スリ」に変更されてはいるのですが。
「犯罪」に対する社会的規範も、フランスらしい。つまり「人」に対する殺人・傷害は「罪」と見做されるが、「物」特に「不労所得」ないし「搾取」よる財産に対する「盗み」は基本的には「罪」とは見做されない。
プルードンの「所有とは盗みである」の感覚が民衆のなかで共有されている、と言えるでしょう。
ただ「現実」ではフランスは強力な警察国家ではあるので、暴力的に取り締まります。
1789年の革命以来フランスは支配に対する「同意」がいわめて脆弱な国家であるために、それだけ強力な治安権力が必要とされました。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
