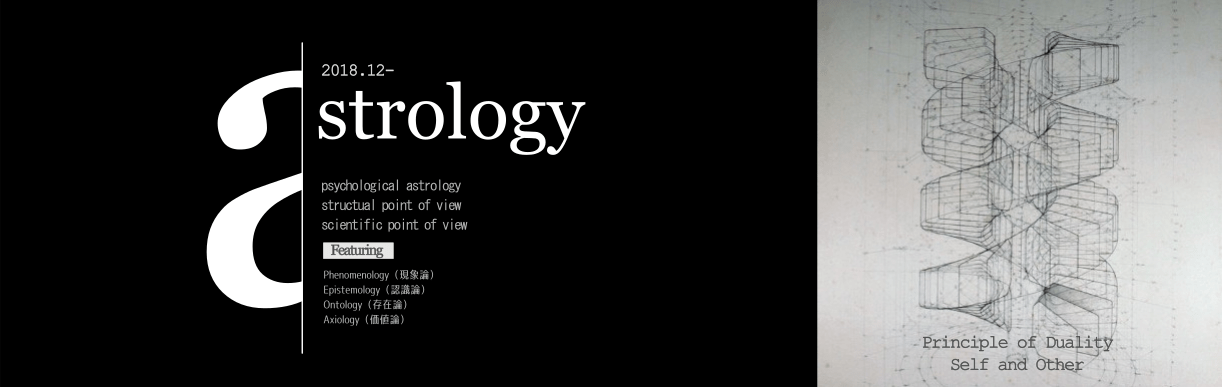
肉体的な性機能の低下が起こる中年期とは、逆に心理的な性意識の向上が起こる時期のことなのではないだろうか。それは性意識の上昇であり、自己(自我)を超えた、本当の意味での他者とのふれあいを求め始める時期。
それには一種の妥協の気持ち(強すぎる自我に対する制限)が必要で、なんでもかんでも自分の思い通りにすること・なることを、制限することが必要になる。
中年期における様々な心理的・肉体的困難(老化をはじめとする出来事)は、そういう妥協=諦めの気持ちを生み出すためのものではないだろうか。
※もちろん、その妥協=諦めの気持ちを受け入れるためには、30代40代までに「自分ひとりの世界(自分の思い通りになる世界)」を存分に味わうことが必要になる。その自信が「もうそんなに無理しなくてもいいかな…」という心の余裕を与える。
わたしという主体と、あなたという主体。2つの別の主体が、お互い別の存在だと理解した上で、わかり合おうとする。
考えてみれば、これはものすごいことだ―。
自分だけの世界だったものに、もう1つ別の世界を並べる。そのもう1つの別の世界は自分の思い通りには決してならない。そちら側の主人公は自分ではないのだから。その別々の世界の、別々の主人公が、それぞれの別々の物語(世界)を持った上で、つながりあおうと努力する。
私一人だけの努力では決してできない。あなたも同じように努力して、2人で成し遂げる。
人間は「自己意識=わたし」の存在だから、放っておくと、1人だけの世界に行こうとする。もちろん自分1人で作る自分だけの世界は楽しい。だが、それと同じくらい自分と自分以外の2人で作る世界も、きっと楽しい。
それは自分の思い通りにいかない世界。主人公が2人いて、それぞれにそれぞれの想い・希望を持っている。その別々の想いが様々に交差して作り上げる世界。
だからこそ、楽しい。なぜなら、そこには常に未知(自分の知らないこと)があるから。私一人では決して知らなかった喜び・楽しさ・面白さ・豊かさ。私とは別の主人公である「あなた」がいるから、それを教えてもらえる。
心理的な性欲の低下は、肉体的な性機能の低下として現れる。最近ではオナニーするときの粘液がすっかり枯れて、無理にやると痛みが出るようになった。「もう、そんなに無理にやることもないのかな…」。そんな気持ちになっている。
だが対照的に、他者(女性)に対する興味はこれ以上ないほど強くなっている。若い頃のような肉体的な興味ではなく、その人がどんな気持ちで、どんな人生を、どんな風に歩んでいるのか、歩んできたのか―。少しでもその人の内面にふれたい、そして、その人と心を通わせたいと。
30代までの「自分!自分!」の頃なら、相手と肉体的・実際的につながること(付き合う・結婚する・一緒に暮らす)=自分の欲求を叶えることだけで満足していただろう。
だが、今はもうそんな程度では少しも満足できない。肉体的につながろうが、実際的につながろうが、それがイコール相手の心とつながりあうことではないと分かっているから。
【中年期における性意識の変化】
ここ数年で一気に自分の身体的変化・心理的変化が進んでいる。変な動きをすると体の筋がピキッとなって痛みが起きたり、白髪が増え、髪の毛の抜けは進み、老眼も出だし、悪かった視力はさらに落ちだした。精神的に無理もできなくなった。
様々な身体的劣化だけでなく、祖母の認知症、母親のがん→死去、(息子くらい年の離れた)親しかったネットの友達の親離れ(?)。自分の力ではどうにもできない変化を受け入れることを、次々とさせられていく中で、「諦める」ということを学んでいった。
中年期における変化とは、そういう「諦め」の気持ちから始まるのではないだろうか。30代までは「我を通すこと・自分らしくなること・自分の思い通りにすること」に意識が向いていた。だが、ある程度それを達成し、自己満足も得て、40代からの諦めの時期を迎える。
それは人に謙虚さを与え、物事をありのままに受け入れる、あるいは自分以外の他者に関心を持つことへと、気持ちを向かわせる。
この個体性意識は、自己を物語り、アイデンティティ化するために、外在的な視空間認識を与える。自己を客観視することがそれには必須の要件だから。自分を1つの個体として外側から観察し、理解し、まとめあげるような意識。小説やドラマではそれを作者の視点=神の視点と呼ぶ。
この外在視点こそが3人称的な視点を発生させる。
つまり、3人称視点こそが人間という、1つの物語性を持った、自己同一化したアイデンティティ性を与えると。この自己同一性・物語的自己というのは、他の個体との差異によって意味づけされるものなので、この3人称視点には自己も他者もみな「人間」という個体物として存在可能になる。
この個体という原型的な人間イメージが、意識の流動性・重畳性により、下位に降ろされ、乙女座(6)の客体として出現する空間に流れる。人間という姿かたちをしたモノ、話し・聞き・触り・見ることができるモノ、わたしが「あなた(他者)」として認識することができるモノ。
そういう客体物として。
だが、このよく見る1人称視点(主観ショット)には大きな誤解があって、そこに映る他者像(人間の姿)を当たり前のように捉えているが、この元となる原型イメージはまた別の次元で発生していると思われること。
知覚正面としての客体空間(乙女座:6)とは、「そこに客体として、モノとして、認識可能物として顕現させる」ということであって、その本体(原型)は様々なレベルで別々に発生しているのだと思われる。
人間という原型イメージは、獅子座(5)乙女座(6)を統合した天秤座(7)蠍座(8)レベルで発生していると思われ、それは天秤座(7)が獅子座(5)と乙女座(6)と統合した意識として存在するから。
それは図で表すと以下のようになる。
認識する主体と認識される客体を1つのものとして統合して捉える意識。そのとき生まれるのは「主体が客体との相互作用によって生み出す、思考・感情の認識によって得た感覚を、まとまりのある個体としてアイデンティティ化する意識。自己同一性とも言える意識。
ある一定のまとまりのある存在として、そこに物語性を与える意識。
私たちが「人間」と呼ぶものは、皆そういった自分だけのアイデンティティ=物語性を持った存在といえる。
【人間という原型イメージ】
今まで考察してきたことを視野空間認識からまとめてみる。
私たちが普段意識している(知覚している)視野空間は、POV的な1人称視点だ。エルンスト・マッハの自画像に表されるような、自分の姿は見えず、目の前に映るモノの景色(客体が集まった世界)を見ている=認識している世界。
わたしはこう思った
わたしはこう感じた
わたしはこう考えた
そういった主体としての主観認識(獅子座:5)は、この1人称視点のあり方と深く関わっている。そこには主体としての認識する意識(獅子座:5)と客体としての認識される意識(乙女座:6)が存在している。
私たちはこれらを別のものとして理解することによって、主体(わたし)と客体(モノ)を別々に捉えることができている。
自己(自)=獅子座・太陽というのは、「”絶対的な今”という瞬間において、この場所において、意識の焦点をあわせている場」という意味であり、それ以外の焦点(場)はすべて「別の主体」あるいは「別の個体」といった存在になるのではないか。
一人称視点(POV)というのは、この”絶対的な今ここ・今この瞬間”を表す視野認識のことだと。3人称視点(客観視点)というのは、この”絶対的な今ここ・この瞬間”から離れ、すべての今ここを1つにまとめて捉える意識のことだと。
それは自分の内部でも存在していて(ホロニック構造)、分かりやすい例では年代別の自己プロフィール画像を見るといい。個体としての姿形は皆違っている(個体性)。10代の自分、20代の自分、30代の自分、40代の自分、50代の自分、60代の自分。どの自分も、その時々で生きていた自分の主観世界(一人称視点=POV世界)があって、それらは皆違っているのにも関わらず、すべてまとめて「わたし(の物語=人生)」だと認識している。この全体認識が3人称的な客観視点といえる。
どこに焦点を合わせるかで「自(自己)」は代わり、その自は他の個体(別の年代のわたし=他)との差異によって意味付けが行われる。
https://piximus.net/celebrities/age-catches-up-with-everyone-even-celebrities
【客観視点(3人称視点)の原初② -メモ-】」
以前のメモのつづき。
自己側の主体世界(獅子座:5)+他者側の主体世界(獅子座:*5)= 自他両方の主観内容の差異によって生まれる関係性世界(天秤座:7)
それを外在視点によって観察(構成)する神の視点=3人称視点
自己側の客体世界(乙女座:6)+他者側の客体世界(乙女座:*6)= 自他一体化した客観世界(蠍座:8)
それを1つの物語として構成する客観空間=3人称空間
おそらく、3人称視点と自他を包含した客観空間は同一の意識によって発生していると思われる。この3人称視点の客観空間では「自己」だけということはありえないし、「他者」だけということもありえない。
外在的な3人称視点の客観意識(あるいは空間)を意識した瞬間、そこには自己と他者が同時に存在可能な形式が生まれている。
※これを視野空間認識、個体を構成する物語性、アイデンティティを構成する意識と絡めて説明すること。とくに視野空間認識においては、この3人称視点(客観意識)を獲得することで、私たちが「人間」と呼ぶ姿形をしたものの原型イメージが作られると思われる。
自己側の意識と他者側の意識が逆向きで重なっていることにより、こういう作用が可能になっている。人が自分自身のことを見つめよう・振り返よう(乙女座6=内省)とすると、必然的にそこに重なっている他者側の意識(獅子座*5)にふれることになり、
他者が認識している相手(他者側の獅子座*5)
↓
他者に認識されているわたし(自己側の乙女座6)
という意識のつながりが生まれる。自我意識=獅子座5が強くなる10代・20代の頃に、やたらと「人の目」を気にするのはここからくる。人から見られている自分を強く意識することによって(自意識過剰)、自分自身の客体像を強くイメージする。さらに承認欲求も同じで、他者に認められているわたし(他者に認識されているわたし)を強く意識することによって、自分自身の肯定感(客体化された自分)を高める。
それは他者側のPOV的な一人称視点であり、そこに客体として映っている自分の像になる。以前のトヨタのCMを思い出してほしいのだが、父親と娘では、POV的な一人称視点でも、そこに映っている像が違う。父親は自分自身の姿を見ることはなく、娘の姿を客体として見ている。娘は自分自身の姿を見ることはなく、父親の姿を客体として見ている。
父親を自己側としたとき、娘が他者側となり、その他者側(娘の一人称視点)に映っているであろう自分自身の姿を想像する。
その際に
・私は娘に見られている
・私は娘に認識されている
という意識が生まれ、これを自分自身に向けることで自己内省・自己反省・自己分析といった内省的意識を与える(乙女座6の意識)。この意識によって客体として反映された自己像を具体化させる。これが象徴的に現れたのが鏡映像(鏡に映った自分の姿)。
[意識の双対性 -例①-]
この意識の双対性を、獅子座(5)乙女座(6)レベルでまとめてみよう。
獅子座(5)は認識する主体としての自己意識を与える。わたしが想っている・私が考えている・私が感じている―主体としての「(認識している)自己感覚」。視野空間としては、それはPOV的な一人称視点になる。この一人称視点には自分は映らない。なぜなら客体としての姿がなくても認識は可能だから。むしろ、客体としての姿は別の意識作用を与えるものとして、次の乙女座(6)で生まれる。
意識が乙女座(6)の段階に達すると、客体としての身体を持った自己身体感覚が生まれる。それは認識される客体としての自己感覚。手があり、目があり、足があり、歩くことができ、話すことができ、触ることができるわたし。
この客体感覚には「意識の双対性構造」によって、他者側の認識する主体意識―他者側の獅子座(*5)―が重なっている。
自己側 他者側
乙女座(6) 獅子座(*5)
- 占星学と心の探求
- http://astrologia89.blog.fc2.com/
- 占星学と科学の探求
- http://astrologymemo.blog.fc2.com/
占星家です。占いではない心の内面を見つめる占星学、意識の構造を解き明かす占星学を目指しています。日々感じたことや思うこと、読書記録や研究内容などを書いています。よろしくお願いします。
