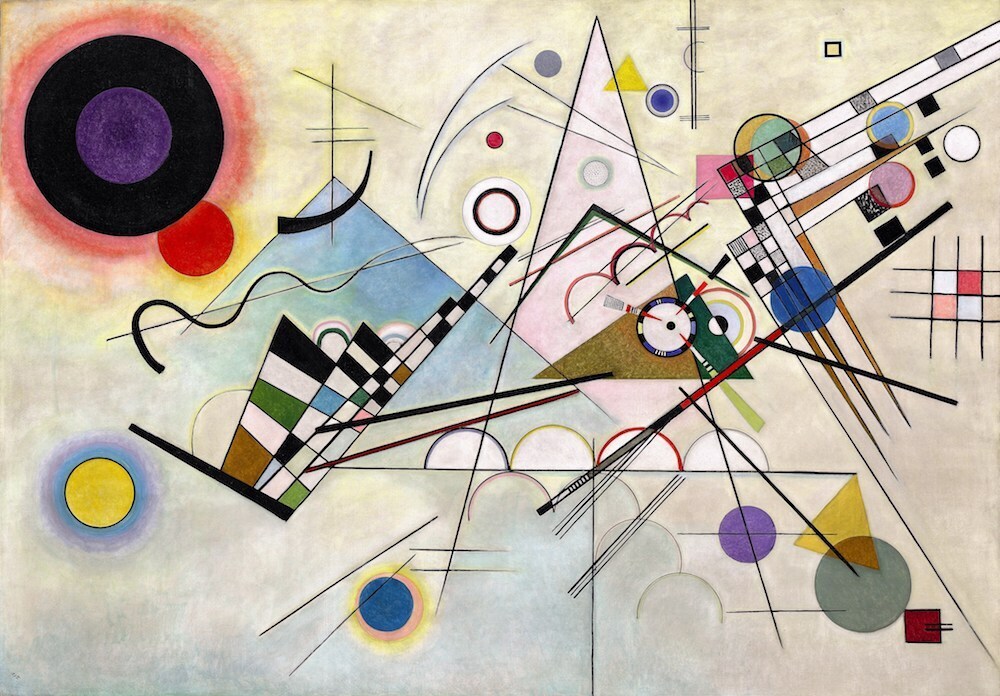
最近田中優子さんと上野千鶴子さんをよくみかける。
内容は今の自公政権批判であったり、現在開催中の「大吉原展」に関する解説であったりする。
私は自公政権批判については、田中さんや上野さんの側であって、「後ろから弓を引く」意図は毛頭ない、ことを断っておきたい。
さて、それを前提とすると、田中さんも上野さんも80年代の主張と今現在の主張が全く異なることに驚く。
二人とも「人権」という言葉を頻りに口にするが、「人権」とはまずもって法的概念であって、まさに「近代」のもの。お二人とも「人権」を含めた「近代」を超える、という主張だった筈である。
であるからこそ、「近代」の視点からネガティヴに捉えられる江戸の消費文化を再評価しよう、という話だった。勿論田中優子さんは広末保の弟子であって、その「悪場所の思想」をより感覚的に展開にしたに過ぎない。左か右かと問われれば迷わず「左」の人。ここは今やサントリー芸人になった佐伯順子さんとは明確に異なる。
上野さんに至っては、この世代特有の「流行り好き」そのままに論じる対象の評価を次々と変えてきた。「一波フェミニズム」の矮小化や福祉国家批判だった筈が近年は擁護に回っていることなどはその典型。
いずれにしてもこの分野も世代交代が切に望まれる所ではある。
中国の学歴社会は近世宋代に科挙というシステムで完成され、基本的には清代末期まで継続した、とされます。
このシステムによって、中国では皇帝(と皇族)以外の世襲の身分は消えました。勿論、高級官僚の子供は教育投資によって科挙に受かりやすいとされますが、落ちれば「ただの人」となる。
この中国の科挙システムと能力主義と非身分制社会という点で評価したのが18世紀急進啓蒙のレナル。
他方、皇帝専制主義として激しく攻撃したのがモンテスキューです。
J.イスラエルの分類では「穏健啓蒙」に入れられるヴォルテールは儒学の「現世的な」(反パスカル)的な部分を評価。
また中国の特徴はこの時代にすでに均分相続だったこと。従って、一代で財を成したものも子供、孫の代になると、小型化し、市場を独占するアクターが生まれにくかった。
さらに言えば、近世中国では日本でいう「村」はほとんど機能せず、地縁による紐帯はないに等しい。また住民の移動が激しいので、一世代ですっかり入れ替わることも。
朝鮮では、この移動率は中国と日本の間とされる。
甲午農民戦争のも指導者、チョンボンジュンもそのような移動する民でした。
従って、中国では宗族・結社の同調圧力は強いが、村の同調圧力はほぼない。ここは地縁優位の日本と大きく異なる。
来週投票の衆院東京15区、酒井氏リードは「わずか」で、維新・教育の金沢、保守(百田)党の「あの」飯山陽氏が「激しく追う」展開と報道されている。
飯山氏は「敵の背中が見えてきました!」と意気盛んだという。やれやれ。
乙武氏(国民民主・都民ファ)は圏外のようだ。
しかし、極右がある意味三つにわれても、「リード」が「わずか」しかない、とすればこれはたいへんなことである。
維新はすでに横浜までは東進しており、いずれ近いうちに多摩川で迎え撃つこになるだろう、と思ってたが、江東区がこの状態では、後詰が必要だなー。
しかし、それとは別に日本の政党システム、いよいよ激変の日は近い予感はする。
それは必ずしもいい方向になるとは限らないけれども。
野党指導者の中にフォルトゥーナを摑めそうな人もいないしなー
みなさま、ご存じの通り私は米中の直接軍事対決は「ない」という見立てです。
今日は、逆に日本・韓国と共通する中国資本主義の「危機」について。
現在、中国の最大の問題は日本と同じく少子高齢化と福祉の危機。
少子高齢化のスピードは、日本は実は東アジアで最も緩慢。
中国は革命後2世代ほど「一人っ子」政策を採用していたため、劇的に少子高齢化が進みました。
元来、中国は国家と社会の分離がはっきりしており、伝統的に福祉は宗族と言われる拡大大家族の担当。しかし、都市化と核家族化の進行とともに単純に言うと、2人で4人を支えることになる。
この10年の中国の政府予算の内、福祉予算の割合が急拡大している理由があります(軍事費は横ばい)。
また中国は宋代に原型ができた超学歴社会でもある。現在でも親が無理をしてでも子供を大学に進学させる。
しかし、日本・韓国と同じく大卒の就職率ないし雇用の中味は平均すると急激に低下している。また、結婚圧力が強い中で、若い男性の独身率が高まっている(元来男の数が多い)。
これは日・韓とも共通する資本主義的近代化と学歴を通じた階層上昇システムの危機、と言える。
とは言え、今中国の資本主義が倒れれば、日本も崩壊する。
その意味でまさにグローバルな危機、と言えるでしょう。
私はまだスマホをもっていない。しかし、緑色部分がもう薄くなってきたスイカはさすがに使っている(切符を買う手間が省けるから)。
しかし、昨日はーよくあることだがー駅に着いたところで、スイカを入れた財布を家に忘れてきたことに気がついた。
「しょうがないなー」と思いつつ、自動券売機の方に向かうと何やら行列ができている。何事かと思えば、自動券売機が2台しか動いていない。
快速が止まる駅なので、住民はそれなりに多く、2台しかなければ行列になる。多くは高齢者の方だった。
待っている間に駅構内を見渡すと、何やら緑の窓口がなくなって、そこにやたらとJRのコンビニが入っている。しかし、コンビニは駅周辺にすでに4つもあるので、もう十分だ。
結局、列に並んでいる間に予定の列車は出発してしまい、結果的に目的地には随分と遅れて到着することとなった。
最近はスマホで電子決済する人が多いようだが、私のような「忘れん坊」にはリスクがある。現金の入った財布とスイカの入った財布、それに前ポケットに小銭を入れておけば、どれかを忘れてもなんとかなることが多い。少なくとも家に取りに帰らなくても済む。
なんでもリスクは分散しておいた方がよいのである。しかしJRは何も一斉に緑の窓口を閉鎖する必要はないのではないか?
尚、ネットでは下の版元ドットコムの予約ページで買えるようです。
去年の『現代思想』4月号で、現代日本の「教育と社会」討議のお相手をして下さった大内裕和さんが、早速拙著の読後の感想をXにUPしてくれています。ありがとうございます。
https://twitter.com/ouchi_h/status/1782026043492290947
本屋に並ぶのは月末、と聞いていたけれども、東京堂さんは地平社の立ち上げに協力してくれた、ということだろうか?
尚、前述の去年の『現代思想』の討議も戦後日本社会の推移と言説、それに学歴を通じた階層移動システムの機能不全の問題など幅広く扱っています。もし、ご関心のある方はご一瞥下さい。
「ル・モンド」などでは10年程前から時折記事になっているが、日本の受刑者の中で高齢者の割合が増加し続けている。特に女性の場合が顕著である。
22年は、男性受刑者の23.1%、女性のなんと33.2%が高齢者(70歳以上)である。
検挙数に至っては、22年度の82,5%が女性高齢者である。ここまでは今日の東京新聞に出ている。
しかし、その背景の分析がない。
勿論受刑者、特に女性の受刑者・検挙者のここ10年(20年)の急増は少子高齢化社会の「反映」などではない。
単身・低学歴の女性の貧困が最大の背景である。つまり、これらの人々にとっては刑務所が老人ホームの「代わり」となっているのだ。
つまり、刑務所は家賃もいらないし、診療施設もある。また「孤独ではない」=「仲間」がいる、ことも重要だ。
元来、万引き・窃盗などの軽微な犯罪なので、刑期は短い。従って釈放された後、途方に暮れて「自発的に」再犯して、また戻って来る人も多いという。
この状況程日本の「福祉の貧困」を象徴するものはない。
従って、軍事倍増で福祉予算を削減している場合ではないのだ。
メディアなどではやはり高学歴の若者ないし子供が「絵になりやすい」。
しかし単身高齢女性の貧困にももっと目を向けるべきだろう。
「 あの」竹田恒泰氏が社長をつとめる令和書籍の歴史教科書が検定を合格したと云ふ。
しかも、日本史研究者でもない竹田氏が自ら執筆した、というのだ。
中学・高校の歴史教科書は、普通各時代、各地域の専門家たちが、数年かけて作り上げるもの。
竹田氏は、日本の中学の歴史教科書が「反日的」として自ら「国史」の執筆に乗り出した、と伝えられる。
ところで、「国史」という表現、とっくの昔にアカデミアでは使われないようになっている。通常、「日本史・日本語文学」である。
ま、東大法学部の紀要のようにまだ「国家学会雑誌」という名前に所もあるけれども。
今回提出した竹田版教科書では「現存する世界最古の国家は、わが国」という明らかなデマもあったらしい。
しかし「後白河天皇の院政」と書くようでは、著者自身が中学歴史教科書を「学び直し」した方がよいのではないか?
日本の建国の成り立ちを「子供たちが知らない」とも主張しているようだが、本人も「知らない」ようなので、まずは網野善彦「日本とは何か」を読むのがよいだろう。
しかし、この手の出版事業、WILLでもHANADAでも同じだが、一体どこから資金を調達しているのか、それがなんとも謎である。
4/25(木)経済安保についての院内集会があるようです。
地平社の新刊『経済安保が社会を壊す』も買えるみたい。
https://kojiskojis.hatenablog.com/entry/2024/04/17/215613
以下転載
【緊急集会】
<参議院で実質審議を!>
経済安保が社会を壊す
民間企業の従業員にも身元や思想にかかわる調査を義務づける「セキュリティ・クリアランス」を含む、経済版の秘密保護法というべき法律が、衆議院で、十分な議論もされないまま、通過してしまいました。
多くの野党も、「反対の声が広がっていない」などとして賛成してしまっています。この法案の問題点を共有するため、専門家の分析を聞き、議論します。
4月25日(木)
午後5時開会(午後4時30分開場)
※午後4時30分よりロビーにて通行証を配布します。
参議院議員会館・講堂(永田町駅)
参加費無料
<報告>
井原 聰(東北大学名誉教授)
海渡雄一(弁護士)
天笠啓祐(ジャーナリスト)
坂田雅子(名古屋経済大学名誉教授)
主催:経済安保法に異議ありキャンペーン
協賛:地平社
=============
<当日、会場にて販売します>
【緊急出版】
『経済安保が社会を壊す』
(島薗 進、井原 聰、海渡雄一、坂本雅子、天笠啓祐/地平社)
民営化の話で最近恐ろしかったのは、英国のテムズ川の汚染の話。
私のテムズ川の知識は、「産業革命以降、工場排水などがそのまま流されて汚染されたけど、その後がんばってまたきれいにした」っていうところでとまっていたのですが、きれいになったあと、80年代に水道会社が民営化されて、ちゃんと処理していない下水をそのまま川に流したりすることも起きるようになって、再び危険なレベルにまで汚染されてしまったみたいです。
最近は、水道会社を国営に戻す話もすすんでいるけど、そうするとその会社の巨額の負債を政府が丸抱えすることになるし、80年代に保守党のサッチャー首相がやった民営化が失敗だったと認めることになるし、選挙で保守党に不利になるから、とかで政府はやや二の足を踏んでいる、みたいな報道が出ていました。
こうしたことは、すでにいろんなところ(経団連副会長など)にヴェオリア・ジャパンに入り込まれている日本でも、人ごとではない気がします。
やはり、インフラの民営化をすると、してはいけない「コストカット」をしてしまい、あらかじめ予測できた以上の社会的コストとなって跳ね返ってくる可能性が高いのではないでしょうか。
日本も水道の民営化をこれ以上すすめるのはやめて、鉄道も郵便も再度国営に戻してほしいです。
国連安保理事会は、パレスティナの正式な国連加盟(現在はオブザーバー加盟)を勧告する決議案は否決。
理事会は15カ国、フランス、日本など圧倒的多数の12カ国は賛成しましたは、米国が例によって拒否権を行使。英国、スイスは棄権。
しかし、よりによってパレスティナ問題に歴史的に最も責任がある米国が拒否権発動、英国が棄権、とはこんな道理に合わないことはない。
バングラデッシュは、「2国家案が最終解決と言いながら、加盟拒否は完全なダブルスタンダード」と批判。
それにしても国連安保理の「ラマダン停戦」決議も少なくとも短期的には何の役にも立たなかった。ただし、中期的には国連が正式にイスラエルの「戦争犯罪」を調査・処罰する形に発展させることは可能かもしれない。
いずれにしても、イスラエルは公然と「反国連」の立場を選択、米国も実質それを支持した。
これでは、現在の世界は米国の一極支配、と見做すことが合理的(特にグローバルサウスにとっては)。
リビア、イラクと核開発を放棄した国家は破壊された。一方North Korea は米国に届く核を数発保有するだけで持ちこたえている。
これではイランが核開発に走ることを止める大義名分がない。最悪の場合はロシアの核の傘の下に入るだろう。
『疑惑』
松本清張原作。
過去に有罪になって服役した女が出所後に金持ちの男と結婚したが、男と一緒に乗っていた車が海に落ちて男が死んでしまう。保険金目当ての殺人を疑われた女とその弁護士の法廷劇。
法廷劇って単調で退屈になりがちだけどこれは面白かった。被告と、証言台に立つ証人の振る舞いがなかなか自由。
世間は女が犯人と決めつけてるけど弁護士が冷静に一つ一つ覆していく。
被告と弁護士を演じる桃井かおりと岩下志麻がすごい。
#マストドン映画部
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』、地平社刊、ついに刷り上がったらしい。やれやれ。
昨年度(2023年度)は、ほとんどこの仕事にエネルギーをつぎ込んだので、なんだか「ほっとした」気持ちが先に立つ。
しかし、私もたいへんだったが、やはり新しい出版社(企業)をゼロから立ち上げるのは、これはまた超人的なエネルギーを必要とする。しかし、現在超斜陽産業とされる出版社であるから尚更である。
ここはあえて岩波を退社して、全退職金を資本金につぎ込み、新出版社設立にこぎつけた熊谷伸一郎さんの気概を讃えたい、と思う。
小池百合子都知事の学歴詐称疑惑事件に関わっている可能性があると言われる千代田区の区長。
調べてみたら警視総監の子息で、大学卒業後は電通総研→政治家(都民ファ)という経歴。
つねづね、警察とか電通とか政治家って、なんらかのかたちで繋がっているのだろうなぁとは思っていましたが、ほんとにそのままの人脈ネットワークのなかで存在している人がいて驚きました。
こういう○○の子弟みたいな人が政治家になったり、
大企業がお互いの取締役会に役員を入れあって「風通しがいい」ふうにしたりして、
内輪のネットワークで仕事を回し合って独占して、なにか不祥事があってもかばいあう、という不健全なやり方がまかりとおりすぎて、社会全体がまともに機能しなくなっているような気がします。
本当にそろそろ、いろんなところを全面的に刷新しなければならない時期にきているのではないでしょうか。
17日の参院本会議で岸田首相は森喜朗と裏金システムの関係について、「結論とし具体的関与は確認できなかった」と答弁したと云ふ。
しかし、この答弁、一体誰が「信じる」?さすがに世論調査でもほとんどの人が「信じていない」ようだけれども。
常識で判断すれば、「関与がなかった」という主張は無理すぎる。一般人なら間違いなく「クロ」とされるだろう。
「被疑者」が元首相、自民党派閥の大物だからと言って、「シロ」と言い募り、一国の最高権力者・首相までそれを認めるようでは、「法の支配」の理念、一体どうなるのか?
これは五輪収賄疑惑にも全く言えることである。
これは安倍の友人だった元TBS記者山口敬之の事件に関しても、同様である。
権力者とその取り巻きであれば、「法に縛られない」となれば、法治国家の理念は成り立たない。
これでよく米国で「自由民主主義体制のためにデッキにのる覚悟はできている」(デッキ=海軍の主力として中国と対峙する)と吠えられたものだ。
「法の支配」とは自由主義にとっての要である。まず「隗より始めよ」とはこのことではないか?
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
