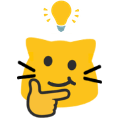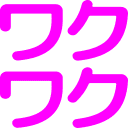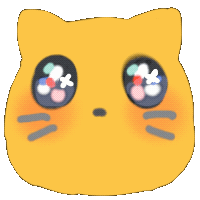小川洋子 著『まぶた』は不思議で風変わりな8つの短編集。
眠りの物語、少女と中年男の逢瀬、不安な一人旅、匂いの収集の話など、繋がりのない短編集で設定もさまざまなのに、どこか共通したものがあった。
印象としては、どの登場人物もまるで音もなくゆっくりと崩壊していくようだった。
彼らがまとう空気には確実に死のにおいが感じられる。生きているからこそ死が感じられるのだろうか?その二つには大きな違いがないように思えてくる。
物語全体に色褪せたフィルターがかかっているようだ。生と死がそんなに遠いものではなく、誰もそれを恐れていないように見える。
それぞれに悲しい出来事や上手くいかなかった人生を抱えながら、今多くを求めず穏やかに生きている人々を見ると、心が静けさに満ちてくる。
大事にしているものを壊さないように、細心の注意を払って丁寧に扱っているような生活を、こちらも息をひそめて見守る。その静けさによって、わずかな空気の震えさえも聞こえてきそう。
かつての美しい記憶と、現在手の届く範囲のものを愛していくという生き方をして、いつかの死へ向かっていく様子が不思議と心を落ち着けるのだ。
その一瞬を閉じ込めた標本のような短編集だった。
『暗い越流』を読んでいます。
短編集なんですが、探偵・葉村晶の短編から始まって嬉しい!
葉村晶37歳とあるので、シリーズでいうと4番目にあたるのかな。読む順番が前後してしまったけれど特に問題はなさそう。
これで20代後半から40代までの彼女の活躍を全部読み終えることになります。読み終わりたくないなー 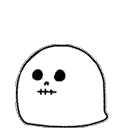
#マストドン読書部
彩瀬まる 著『骨を彩る』を読んだ。
病気や死別や家庭の事情などの、自分ではどうしようもない問題が降りかかってきた人、知らなくてもいい苦労を知ってしまった人がこの作品には多く登場する。
その苦労の形は人それぞれで、一口には言えない感情が渦巻いていた。
でも読んでいて苦痛ではない。おそらく誰しもが感じたことのあるような馴染み深い感情だから。
人間の複雑さがよく書かれているところが良かった。生きていれば色々あるのが楽しくて苦しい。
他者に見せている顔が人間の全てではなくて、別の顔だってきっと内側に持っている。心には普段は守っている柔らかい部分もあり、消化できないものの一つや二つは持っているのだろうと思った。それは別に悪いことではない。
立っていられない自分を、強がりや逃避で支えることだって時には必要。とことん自分を守って、そこから自分を解き放つのも自分しかいない。でも他者とのコミュニケーションのなかでそのきっかけを見つけられるかもしれない。
現実はそんなに上手くはいかないかもしれないけれど、生きていくことに希望は持っていたいと思わせてくれる物語だった。
みんなが初めての人生を送っているのだと当たり前のことを思った。
レイ・ブラッドベリ 著『火星年代記/新版』(小笠原豊樹 訳)を読んだ。
目次は年表になっていて、主人公の違う短編が時系列で27おさめられている。
新版は、年代記の始まりが1999年から2030年に改められ、著者の序文と2短編が加えられているそうだ。
最初は一体何が起きているのだろうと思うけれど、このいくつもの短編を読むうちに火星や地球の全体像が見えてくる。
科学技術などの難しい話はほぼ書かれておらず、SFらしくないと言えばそうかもしれない。あくまでもこれは年代記なのだ。
喉元にナイフを突きつけられたような恐怖を味わう話もあったし、心を押しつぶしてくるような話や、神秘であったり、詩的で美しい話もある。
目線が変われば当然見えてくるものも違っていて、それぞれの主人公の立場で真実を見せてくれるのが良かった。
この作品の中で描かれている火星移住の過程は、人類全体で見ると酷く愚かでどうしようもない行為のように見える。
でも一人一人の感情や生活、人生に焦点を当てると、また感じ方が変わってくる。その複雑な気持ちを抱えながら読んでいくうちに、これ以降の年代記も読みたくなった。
現在にも置き換えて考えることのできる物語だった。
小学生の頃に親に買い与えられて読んでいた『ああ無情』が私の特別な一冊!
これはヴィクトル・ユーゴー『レ・ミゼラブル』の児童書バージョンで、社会情勢などの詳しい記載部分は省かれていたと思う。大人になってから完全版を読んで、やはり私にとって大切な作品だと再認識した。
小学生の私は、ミリエル司教の高潔な行いと、ジャン・ヴァルジャンの正しい人であろうとする精神に衝撃を受けた。
その頃はまだ本を読んで泣くということは無かった気がするけれど、今読んだら大号泣。  この二人のように生きることは本当に難しいことなのだと分かる大人になりました。
この二人のように生きることは本当に難しいことなのだと分かる大人になりました。
三津田信三 著『首無の如き祟るもの』を読んだ。怪奇幻想作家・刀城言耶シリーズの第三弾。
調べてみるとシリーズ最高傑作と名高いので、第三弾までは順番に読もうと決めていた。一も二も面白くて好みだったというのもあるし。
本作は古くからの怪異が伝承されてきた村が舞台。旧家の跡取りをめぐって起こる事件に焦点を当てたホラーミステリー小説である。こういう話、大好き。やはり思い浮かぶのは横溝正史。
でもこの作品は個人的にホラー要素はそこまで強くなかったので、事件の謎解きや人間関係の部分に集中して読めた。
読みながらなんとなく推理をしてはいたけれど、読み終わってみればその推理がことごとく外れていて笑ってしまった。真相を見破るのは至難の業。
ミステリを読み慣れていないとはいえ、想像すらしなかった種明かしに新鮮に驚いた。ラストの伏線回収が見事であることに拍手したい気分だ。恐ろしさに身震いしながらも爽快に読み終えられた。
複雑に事情が絡み合うと、こういう怪異めいた事件になってしまうのだ。
絶対に当事者にはなりたくないけれど、因習村のミステリーってどうしても惹かれるものがある。シリーズ第四弾も読みたくなってきてしまった。
またいずれ。
子どもの頃はそこまで読書をしていなかったけれど、私はファンタジー小説が主に好きだった。物語の世界に入っていって、現実には起きない不思議なことの連続にワクワクして、夢で胸をいっぱいにする子どもだった。
深緑野分 著『この本を盗む者は』は、そんな子どもの頃の懐かしい感覚が蘇るような作品だった!
本の町「読長町」に住む高校生が主人公。読書好きとしては本当に羨ましい設定が盛り沢山。
書物の蒐集家の曾祖父を持ち、建てられた巨大な書庫は町の名所でもあり、ぎっしりと蔵書が並んでいる。私がここに住みたいと思ってしまうけれど、有名な一族のもとに生まれた主人公が苦労しないわけがない。
物語は後半から加速して終盤に面白くなってくる。世界観に慣れてくると、軽やかに飛翔するようにスルスル読んだ。頭が固くなった大人なので「ファンタジーってこうだったな」「最近こういう読書体験してないな」と何度か思ったのが切ない。
次々と場面転換していくような勢いのある内容が詰まっているので、一冊で終わるのが勿体ない気がした。主人公や家族や町の人たち、この町の事も深く知りたかったな。
森見登美彦氏、推薦とのこと。読んでいる間ずっと頭に浮かんでいたので納得!
『死にたくなったら電話して』(李龍徳 著)
この印象的なタイトルに惹かれて購入した小説。
きっとたぶん人間の内面を繊細に書いたような話だろうと思い込んで読み始めたら、まぁそれも間違いではないけれど、もっと強烈なインパクトのある話だったから驚いた。
浪人生の主人公が、バイト仲間と行ったキャバクラで悪女に出会ってしまうところから物語は始まる。
私は主人公よりもそのキャバ嬢のことが気になって仕方がない。「悪女」と書くのが分かりやすいけれど個人的には悪女とは思っていなくて、それどころか最後まで読んでみても彼女は何も悪くない気がしているので始末に負えない。破滅的だからこそ好きにならずにはいられないのだ。
彼女の口から出てくるのはいつでも自信たっぷりの正論で、思わず何もかも肯定してしまうような説得力がある。関西弁との相性もよく、彼女の淀みない喋りに快さすらおぼえてしまう自分がいた。
ただ、彼女の意見を全面的に支持した先には何があるのか、それを突き付けられて読み手もほとんど主人公と同じような状態に陥る。
例えば何にも希望が持てない時、精神的に落ち込んでいるような時には読んではいけない。それくらい、誘い込む力を持つ小説だった。
『余と万年筆』を読んだ。
短いエッセイだけれど面白かった。
当時の万年筆の価格とか需要、なかには"万年筆狂"がいたりだとか、そういう話が気楽に綴られていた。
『彼岸過迄』を書いていた時のエピソードや、漱石自身はセピア色を好んでいた話が読めて嬉しい 
#マストドン読書部
(時々TLを覗きにきてリアクションするのを楽しんでいます。普段は個人サーバーのほうにいます)
 @erin@fedibird.com
@erin@fedibird.com