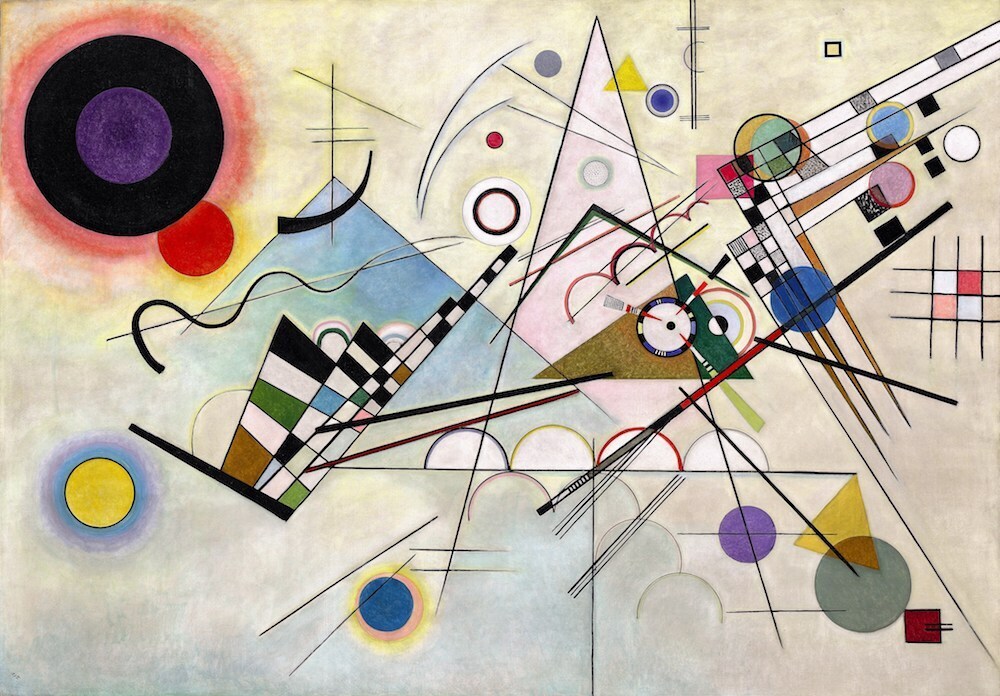
特権を問う:駐留米軍への対応、他国では? 沖縄知事「日本は国際常識と全く逆」
https://mainichi.jp/articles/20240412/k00/00m/040/179000c
#mainichi_rss_etc_mainichiflash #社会 #速報 #日米地位協定 #大場弘行 #特権を問う
環境NGOのFoE Japanが、日本・フィリピン・アメリカ三ヶ国首脳の共同声明に対し、見解を発表しています。
・日米比首脳会合に対するコメント:原発の押しつけと人権の保護なき鉱物資源開発に反対する
https://foejapan.org/issue/20240412/17041/
「声明では、再生可能エネルギー分野における協力に加え、原子力、特に小型原子炉の開発の推進が盛り込まれている。また鉱物資源分野でも3カ国の協力を深めるとしている。
フィリピンでは、国際協力銀行(JBIC)や、IHI日揮ホールディングスなどが出資する米新興企業のニュースケール社が、次世代原発とされる小型モジュール原子炉(SMR)の建設を検討しているが(2)、SMRも通常の原発かそれ以上にコストが高い。SMRという新たな装いをしていようとも、ライフサイクルにわたる放射能汚染、核廃棄物、事故リスクに加え、テロや戦争のターゲットとなるリスクなどの問題を抱えていることは、従来の原発と何ら変わりはない」
「鉱物資源についての協力も強調された。フィリピンは電池材料であるニッケルの生産国である。フィリピンのニッケル開発の現場では、これまで先住民族らが先祖伝来の土地から追いやられたり、伝統的な生活ができなくなるなど、甚大な影響を受けてきた」
日本企業によるフィリピンのニッケル鉱山開発で、今までどのような問題が起こっているか。
FoE JapanとPARCが共催したセミナーのこちらの報告が参考になりました。
・低炭素技術がフィリピンに何をもたらしているか 住友金属鉱山のニッケル精錬をめぐって
https://www.chosyu-journal.jp/shakai/23133
「ニッケル採掘現場と製錬事業地域からの水が流れ込むトグポン川から、世界保健機構(WHO)の基準を大幅にこえる六価クロムが検出された」
「住友金属鉱山がもし日本でこうした対応をすれば、すぐに大きな社会問題になるだろう。だが、残念ながらフィリピンでは政府が事業者に厳しく対応を迫ろうとしない。日本企業のダブルスタンダードであり、また公害輸出だ。その企業倫理を疑わざるをえない」
「フィリピンでは「超法規的殺害」というものが多く起きている。政府が進める国家事業や大企業が進める鉱山開発によって土地が奪われ、住民生活が脅かされるとき、生活を守ろうと思って反対の声をあげると、その声を黙らせ、反対運動を弾圧するために、リーダーが見せしめのように殺されてしまうということが頻繁に起こっている。ニッケルの開発現場で、命をかけて土地を守ろうとしている人々の人生を狂わせてしまう現実がある」
アフガーニーは「帝国主義の時代」における反植民地思想家・運動家としては、例えばインドのガンジー・ネルー、中国の孫文に比較できる存在である、と言えるでしょう。
東南アジアでは、ベトナムのファン=ボイ=チャウ、フィリピンのホセ=リサール、ジャワの女性教育の主導者カルティニなどがアフガーニーと同時代を生きた反帝国主義思想家です。
アフガーニーの特徴は、近代化した「イスラム」を広く定義することで、ペルシアとアラブを包含する運動を構想したこと。
これがペルシアでは「タバコ・バイコット」運動、エジプトではオラービー革命を生み出していった。
オラービー革命を鎮圧した英国はエジプトを完全保護国化。これに対する抵抗が、1952年のナセルをリーダーとする自由将校団の共和国革命へと繋がっていく。
また「タバコ・ボイコット」運動の反帝国主義は、WWII後世俗派ナショナリストのモザデクの石油国有化への流れとなる。
エジプト、アラブ、インド三者とも、英帝国主義への抵抗としてナショナリズムが勃興したが、WWII後英国に代わって覇権国家となった米国が、三カ国に同時に介入していく。これが国際冷戦レジームの中東・南アジアにおける大きな構図である。
非同盟中立のインドは、冷戦時代、米国にかなり揺さぶられた。
集英社の『アジア人物史』、著者の一人、栗田禎子先生からご恵投いただきました。ありがとうございます。
栗田先生の担当は、ジャマールディーン・アフガーニー。アフガーニーは、西洋帝国主義列強、とりわけ英国によるアラブ・イラン・インドへの侵略に対して、立憲主義・法治主義に基づいた、「近代化」したイスラム主義と、アラブ、イラン、インドのイスラムの連帯を説いた思想家。
このアフガーニー、1980年代の私の高校時代は教科書にも掲載されていなかったように思う。
史上初の黒人共和国ハイチの指導者、「黒いナポレオン」トーサン・ウーヴェルチュールとともに、研究が教育に徐々にではあれ、フィードバックしていった例だろう。
それにしてもこの大部な書物、いくら荒木飛呂彦の装画とは言え、4000円台、とは集英社もかなり大胆な賭けに出た、という感じはする。
「孤独感や疲弊を感じているアメリカ国民」に同情する前に、日本で被災したまま放っておかれて孤独を感じたり疲弊したりしている人たちに寄り添ってほしいです、首相。
「人権が抑圧された社会を私は子どもたちに残したくない」?
なぜ日本でそれを実践しないでアメリカ行ってそんな演説してるんですか。
こうしたアメリカへの「従順さ」への「ごほうび」として、首相は大統領の車に乗せて貰ったり、NASAが月に宇宙飛行士を送る計画にいち早く日本から2人が選ばれることが決まったりしています。
増税して軍事費を2倍にして、そのお金でアメリカの軍需産業を潤し、アメリカの軍事作戦に参加し、手を血で汚す。
首相は楽しそうですが、それで、私たち市民は何が得られるのですか?
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240411/k10014419741000.html
「岸田総理大臣は「ほぼ独力で国際秩序を維持し、孤独感や疲弊を感じているアメリカ国民に語りかけたい。アメリカは助けもなくたったひとりで国際秩序を守ることを強いられる理由はない」と述べたあと、「自由、民主主義、法の支配を守るのは日本の国益で、人権が抑圧された社会を私は子どもたちに残したくない。日本はすでにアメリカと肩を組んでともに立ち上がっている。アメリカはひとりではない。日本はアメリカとともにある」と訴えました」
昨日、4月11日はJ.プレヴェール(1900-77)の命日。
プレヴェールは、ブルトン、アラゴン、R.デスノスらシュルレアリスムのグループから出発。
その後、ジャン=ルイ・バローとともに劇団「10月グループ」(1917年10月革命にちなむ)に参加。
その後、ジャン・ルノワールやマルセル・カルネとともに映画の世界へ。カルネの戦中の映画『天井桟敷の人々』では、脚本を担当。
この時の音楽担当のハンガリー系ユダヤ人J.コスマとともに「枯葉」をはじめとする多くのシャンソンを世に送り出した。イブ・モンタン、E.ピアフ、J.グレコなど多くの歌手が、プレヴェール=コスマを歌うことになる。
ちなみにサルトルはグレコのいくつかのシャンソンを作詞している。このこともあって、グレコはWWII直後のサン=ジェルマン・デ・プレの「ミューズ」と称される。
ボリス・ヴィアンの他にマイルス・デイビスもパリに亡命、戦後のパリのジャズ文化は活性化することになる。 サルトルとも親しかったマイルスはグレコと一時同棲する。
プレヴェール=コスマはこの世代のシャンソンの象徴となり、次世代のS.ゲーンズブルは「プレヴェールに捧ぐ」を書く。
東大仏文科出身の高畑勲は、『ジャック・プレヴェール全詩集』を上梓している。 [参照]
Le 11 avril 1977, mort de Jacques #PREVERT (né le 4 février 1900 à Neuilly).
#Poète, surréaliste, scénariste et dialoguiste de talent. https://www.partage-noir.fr/jacques-prevert-reve-evolution-revolution
Marguerite de Navarre, also known as Marguerite of Angoulême was born #OTD in 1492.
She was a significant figure in the cultural and political landscape of 16th-century France. As an author and a patron of humanists and reformers, she was an outstanding figure of the French Renaissance. Marguerite's most famous work is "The Heptameron," a collection of short stories similar in style to Boccaccio's "Decameron."
Books by Marguerite de Navarre at PG:
https://www.gutenberg.org/ebooks/author/32596
バイデン大統領、
「日本も英米豪の軍事同盟AUKUSに”第2の柱”枠で参加する」
「新たにアメリカ・日本・オーストラリアでミサイル防衛ネットワークをつくる」
など、軍事の具体的なことをいろいろはっきり言ってるけど、
日本のメディアが強調するのは
「首相がバイデン大統領の車に乗せてもらった」とか、そんなことばかりですね。
小泉元首相の訪米時に大統領専用機に乗ったことが妙に強調されたことが思い出されます。
日本は米国に「特別扱い」されている、と思いたいのでしょうか。
ちなみに、AUKUSの”第1の柱”は、豪防衛のための原子力潜水艦の提供、”第2の柱”は軍事のための技術供与です。
”第2の柱”での参加ということになれば、当然、経済安保(セキュリティクリアランス)、軍産学共同(デュアルユース)、などの話とつながってくると考えられます。
また、今回アメリカは、岸田首相と同時にフィリピンの大統領マルコスJr.も呼び、「(対中)防衛」の話をしているのですが、
日本のマスコミは、マルコス氏も来ているとは、あまり報道していないような印象です。
それにしても、フィリピンって、せっかく一度はすべての米軍基地を撤退させたのに、ここ数年でまた元に戻りつつあるんですよね・・・。
岸田訪米で「日米軍事一体化強化」。英語誌では当然「軍事同盟」強化と報道。
実際には米軍指揮下の連携の範囲をさらに拡大するだけだが。
それにしてもハワイ太平洋司令部の移転と軍事費倍増を伴うことは大きい。
台湾有事が無理と来れば、今度は南シナ海への中国の海洋進出を阻止、ときた。しかし、筋論としては、そこは日本が責任をもつ海ではないし、実際には米海軍とオーストラリアで十分に対応可能。
どうも日本の政治家は忘れがちだが、中国は建国の成り立ちからして陸軍大国。米国は、英国と同じく元来は陸の常備軍をもたない海洋国家である。中国指導部がわざわざ相手に有利な場所を選ぶ筈もない。
しかし、日本政府、米国への従属度は、もはや政権が清和会であろうと宏池会であろうと、関係ないようだ。
繰り返すが、日本社会は5年度で軍事費倍増に耐えられる状態ではない。いわんや米軍への「思いやり」予算など「バラマキ」をしている時ではないのだ。
岸田は大統領専用車に乗せてもらって喜んでいるようだが、小学生でもあるまい。
バイデンはバイデンで日本とのfrendshipを発信している暇があったら、ガザ地区への人道支援をイスラエルに強制すべきだろう。
エジプトとイラスエルの国交樹立が何故「パレスティナを見捨てた」ことになるのか?
元来エジプトをはじめとするアラブ諸国は1948年にパススティナに建国されたイスラエルを認めていなかった。
しかし1973年までの四度の中東戦争の内、エジプト側が戦略的に勝利した、と言えるのは第二次中東戦争の際のみ。
とりわけ20世紀最後の「電撃戦Blitzkrieg」とされる第三次中東戦争ではナセルのエジプトは米国の支援を受けたイスラエルに大敗。
後を継いだサダトは米国の仲外によってイスラエルと単独和平。シナイ半島返還と引き換えに、パレスティナをイスラエルに「引き渡す」決断をする。
ここから「アラブの大義」の象徴はPLOのアラファトに移る。
エジプトはと言えば、サダトが暗殺された後、やはり軍部代表の米国に従属した状態でムバラクが30年軍事独裁政権を続け、アラブの春で失脚した後は、また軍のクーデタ―でシシが大統領に。
これでは、新自由主義を引き起こす格差と貧困にセイフティ・ネットを提供するムスリム同胞団が勢力を拡大するのは当然である。
ちなみにアラブ民族主義は元来レバノンのキリスト教徒が主導したもので、政教分離を前提としていた。実際エジプト人口の10%はキリスト教徒(コプト教)である。
私たちの暮らしやいとなみ、生は「コスト」だと国が明言。
https://www.47news.jp/10766174.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
この記事の動画、わかりやくてよかったです。
ここに出てくるADSBexchange.com
みてみました。
今現在飛んでいる飛行機がいっぱい表示されます。
記事にでてくる、スーパーハーキュリーズ(ロッキードマーティンの輸送機)も太平洋上を飛行中みたい。
また、よく見ると、KAWASAKI P-1(川崎重工がつくった 哨戒機。1機258億円)、KAWASAKI C-2(川崎重工がつくった輸送機。1機230億円)なども飛んでいます。
同じところを繰り返し移動しているので、おそらく演習なのでしょう。
民家があると思われるところを何度もいったりきたりして飛んでいます。
QT: https://rss-mstdn.studiofreesia.com/@mainichi_rss_etc_mainichiflash/112243505768405195 [参照]
 ニュース速報(総合)
@mainichi_rss_etc_mainichiflash@rss-mstdn.studiofreesia.com
ニュース速報(総合)
@mainichi_rss_etc_mainichiflash@rss-mstdn.studiofreesia.com
1990年代位から欧米で大騒ぎするようになった「イスラム原理主義」、元はと言えば、イラン、イラク、エジプトという大国の近代化を米英が強引に覆したことに拠る。
イランは、WWII中米英とソ連が共同占領。戦後はアングロイラニアン石油(現BP)が利権を独占。これを1951年世俗民族主義者のモザデクが国有化すると、MI6とCIAはお馴染みの連携プレーでこれを1953年に打倒。
王政が78年にフーコーが「一般意志が地上に舞い降りた」と呼んだ革命によって打倒されると、米国はこれを敵視。イラン・イラク戦争ではフセインを支持した。
この戦争体制によって、イラン革命支持層の中の立憲近代派、共産党は一掃された。
中東最大の共産党と言われたイラク共産党はフセインのバース党によってすでに粛清。
また米国の援助で巨大になり過ぎたイラクは2度の湾岸戦争で崩壊。あとにはスンニ派ジハーディストとISILが残された。
エジプトは1979年にイスラエルと国交を結び、パレスティナを「見捨てた」。また79年はエジプトの新自由主義が本格的に起動。
その矛盾が2011年のアラブの春となって表れたが、軍部は選挙で選ばれたムスリム同胞団政権をクーデターで倒し、シシを大統領に。これでは米ーイスラエル枢軸に対抗すべくもない。
東大出版会から刊行された『女性/ジェンダー』、著者の水溜真由美さんからご恵投いただきました。
水溜さんは、日本近現代思想史専攻で森崎和江研究の第一人者。現在北海道大学教授。
他にも石牟礼道子、堀田善衛など数多くの作家・思想家に関する研究・著作があります。
今度の出版会の本は、女性/ジェンダーに関する、近代日本のテクスト、例えば与謝野晶子、平塚雷鳥、高群逸枝、そして山川菊枝。また田村俊子、湯浅芳子、松田解子、さらに田中美津、松井やよりなどのテクストを4つのテーマに分けて収録、それに現代的視点から解説をつけたものです。
また上野千鶴子さんの世代に典型的な「第一波/第二波フェミズム」という進歩・段階史観を脱構築している点でも画期的、と言えるでしょう。
このテーマに関心がおありの方は、是非お読みください。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
