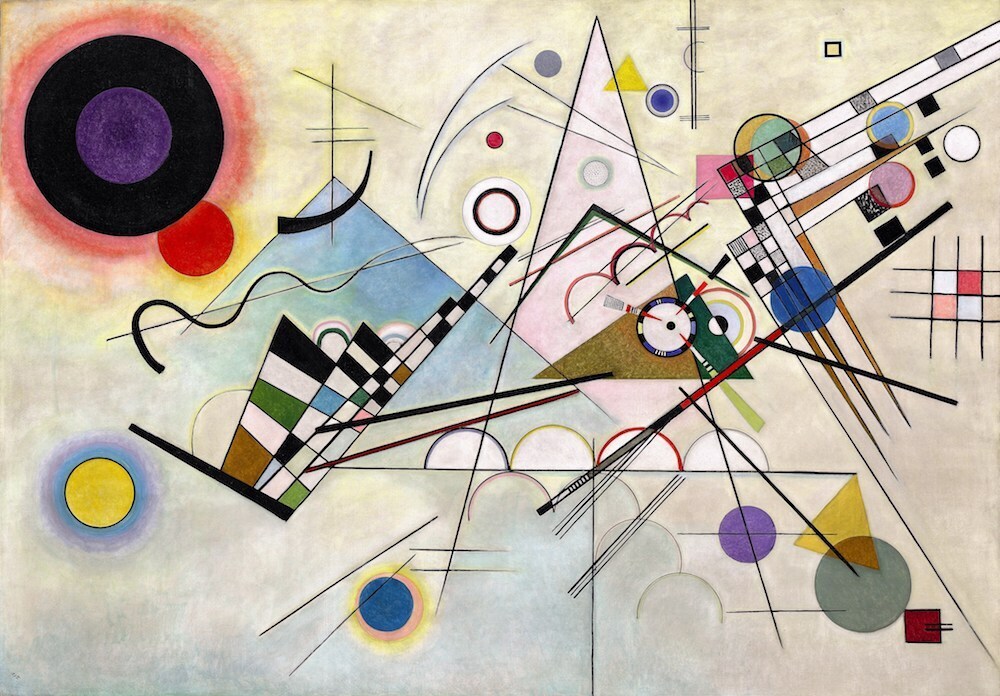
「荒野のリア王」木庭顕さんが、ついに「荒野」からお戻りになり、今週の「朝日」デジタルに16頁に及ぶ批評を寄稿している。
ここで木庭さんは「2013年体制」と呼ぶ「極右=ウルトラ・ネオリベラル」体制の起点を1980年代の土光臨調と国鉄解体に見る。この視点は私たちが1990年代に行った「80年代研究会」とその成果、例えば2000年の『現代思想』「ポストモダンとは何だっのか?」、あるいは2023年4月の『現代思想』三宅・大内対談「新自由主義下と教育とイデオロギー」とほぼ同じ。
また木庭さんは新自由主義的再編までの戦後日本体制を「利益集団多元主義」と呼ぶが、これは大企業及び、農協、日本医師会、特定郵便局長、各種業界団体などと自民党の利益調整政治を指す。
新自由主義的再編はこの「利益集団多元主義」さえも立ち行かなくする。例えば小泉による郵政解体などはその典型。
この再編以降の特徴として、木庭さんは、金融、軍事、デジタルの前景化を強調。勿論、統一教会と「反社」による「闇」の浸透も忘れていない。
最後に「希望」として語るのは「個人」をベースにした「連帯」、「新しい市民社会」である。
これは私が「世界史の中の戦後思想」で提唱した「21世紀の社会主義」と同じではないが、かなり重なる概念である。
フィレンツェの政治的人文主義者マキャヴェリ(1469-1527)は、日本では「権謀術数」のイメージで語られることが多いが、研究の世界ではポーコックの『マキャヴェリアン・モーメント』以来、ローマ的「徳」を重視する「共和政論者」としてまず位置づけられる。
「ディスコルシ(ローマ史論」、「フィレンツェ史」では共和主義が前景化する。有名な『君主論』は失脚した後、フィレンツェの「僭主」となったロレンツォ・ディ・メディチ2世に献じられたもので、そこでは教皇アレクサンドル6世の息、元枢機卿・教皇軍司令官のチェーザレ・ボルジアが「獅子の力と狐の狡知」を兼備した理想の君主として語られる。
ただ、いずれにせよ、マキャヴェッリはローマ共和政の市民軍を理想とし、「運命の女神」に対する「男性的能動性」を強調したことには違いはない。
しかし、宗教改革・トリエントの反宗教改革によって、ヨーロッパ、とりわけドイツ、ネーデルランド、フランスが宗教内乱(聖バルテルミーの虐殺)に陥っていくと、軍事的「能動性」を抑制する必要性が感じられるようになる。
この要請に応えたのが、ネーデルランド後期人文主義のリプシウスの新ストア主義的な国家哲学。リプシウスの新ストア主義は、オランダのみならず仏のアンリ4世にも受け入れられていく。 [参照]
日本社会には極秘で行われた原爆調査団には当時東大医学部副手であった加藤周一さん(血液学博士)も参加している。
ちなみに広島・長崎の原爆被害の情報は米占領中は報道禁止だった。占領終結後、1952年の新藤兼人監督、乙羽信子主演の『原爆の子』ではじめて全国に知られたと言われる。
草野さんは理論物理学者の川崎昭一郎さん(1932生)等とともに、戦後の原水爆禁止運動の中心となる。川崎さんは、ビキニ環礁で被爆した第五福竜丸保存運動の責任者だった。
川崎さんは千葉大理学部物理学科教授でもあり、つい最近まで千葉大の理学部がリベラル左派多数だったのも、それと無縁ではない。
今年のノーベル平和賞は被団協が受賞したが、2017年は市民団体核兵器廃絶国際キャンペーンが受賞。この市民団体の日本事務局長が川崎昭一郎さんの息子、川崎哲さん(ピースボート共同代表、1968生)である。
川崎さんは私立武蔵ー東大法学部ー平和運動家という、今や「絶滅危惧種」のエリートで、私もお名前は知り合いを通じて四半世紀前から存じ上げていたが、直接お会いしたのは、今年の4月の「地平社」立ち上げレセプションが初めてである。
父の昭一郎さんが2年前に亡くなった際、メディアに「父は家では運動のことは語らなかった」と語っていたのは含蓄が深い。
モンテーニュ、ラブレーなどの「超大物」を擁しながらも、ヨーロッパ研究者に「フランスにもルネサンスがあったのですか?」と何度も聞かれて渡辺一夫が慨嘆したことは投稿しました。
ところで、ルネサンス以来の「油彩」の技法を元来発達させたのは、「北方ルネサンス」とも呼ばれる15-16世紀のネーデルランド。
日本では、ヴァン・エイク兄弟、ブリューゲル、ボスなどの名が知られる。
またデューラーは北方とイタリアを繋ぐ巨人。サルトルの『嘔吐』の初版表紙はデューラーの「メランコリア」。
美術史では北方ルネサンスは「古代復興(ヒューマニズム)を欠く」ともされるが、これは正確ではない。エラスムス、フッテンなどの人文主義の巨人がいる。
またライデン大学はリプシウスを代表とする後期人文主義の拠点となる。ボダンの同時代人、リプシウスはキケロを批判し、セネカを擁護する新ストア主義の国家哲学を展開。
この新ストア主義、マウリッツの軍事革命を起点として近世・近代の「規律=権力」の基礎となる。
この後期人文主義、視覚芸術ではレンブラント、フェルメールの時代。
フーコーはリプシウスに言及しないが、『監獄の誕生』は事実上「リプシウスの長い影」を追跡した書物とも言える。
左)メランコリア
右)「死の勝利」(ブリューゲル)
『ディア・ピョンヤン』などで知られる、ヤン・ヨンヒ監督の『スープとイデオロギー』を観る。
前作で登場していた「おもろい」父は既に亡くなり、認知症になりゆく母を見守るドキュメンタリーでもある。
大阪・鶴橋は在日の街と言われるが、とりわけ済州島出身者が多い。中には1948年の4・3事件の際に亡命した来た人も多い。
詩人の金時鐘さんもその一人。また金石範の『火山島』は4・3事件を扱った大著として知られる。日本では映画「月はどっちに出ている」、「血と骨」の原作者として知られる梁石日さんもお二人の仲間である。
ヤン監督の母も4・3事件の際、18歳で蜂起に間接的に関わり、当時の婚約者であった医師はゲリラ闘争に参加して死亡。本人は幼い弟と妹を連れて大阪に密航した。
この済州島の4・3事件は拙著『世界史の中の戦後思想』でも扱ったように、東アジア冷戦の前景化が直接関わっている。GHQ内部のラティモアなどは半島分断政策を批判し、朝鮮人自身のイニシアティヴでの統一を主張。
しかし「マッカーシズム」の嵐がラティモアなど「植民地解放派」を一掃、米軍が直接に介入する。この際、李承晩が送り込んだ反共民間軍事組織によって島民6万人以上が虐殺された。
監督の母や金時鐘はまさに、この大虐殺の「サバイバー」なのである。
「ルネサンス renaissance」とは仏語で「再reー生naissance」という意味。ギリシア・ローマの古典文化の復興というニュアンスをもつ。
元来仏の19世紀の歴史家J.ミシュレが提起し、ブルクハルトの「イタリア・ルネサンスの文化」によって決定的となる。
日本では特に美術史を中心に導入され、14世紀―16世紀のイタリア美術を連想させる。高階さんは主にフィレンツェを中心とした古典期ルネサンス(ボッティチェリ、レオナルド、初期のミケランジェロなど)、若桑さんはカール5世による1527年のローマ劫掠以降のマニエリスムを専門とする。
また思想としては林達夫、高階秀爾ともにフィレンツェを中心としたネオ・プラトニズムに強く焦点を当てる。
これに対し林達夫と同世代の渡辺一夫はラブレーを中心としたフランス・ルネサンスを中心に研究。ただ、渡辺が「フランスにもルネサンスがあったのですか?」とよく聞かれると嘆いたように、やはり視覚芸術を中心とした見方では仏は影を薄くなる。
またフィレンツェを中心とした政治的人文主義=ローマ共和政の理念は、ポーコックの描くように17世紀イングランド、18世紀米国の革命言説に大きな影響を与えた。ここにオランダが占める位置を考えることは今後極めて重要になるだろう。 [参照]
美術史家の高階秀爾さん死去(享年92)。
高階さんは戦後日本の美術史の大立者であり、専門とは別に一般の知的読者に向けても『ルネサンスの光と闇』、『近代絵画』、『名画を見る眼』など明快な見取り図とパノフスキー的なイコノロジーを組み合わせた名著がある。
実は私も高校、大学1,2年生の時は高階さんの書いたものはほぼ全て読み、実はパノフスキーを応用した精神史を組み立てたい、と夢想していた。
日本の戦後のルネサンス研究は林達夫、高階秀爾、若桑みどり(マニエリスム研究)という系譜があり、戦後自身はほとんど書かなかった林達夫が主宰する平凡社の研究会に、高階、若桑氏なども参加していた。
若桑さんは美術史におけるフェミニズム批評の導入者でもあり、とにかく凄いバイタリティの人だった。
ただ、その後美術史研究は、カラヴァッジョやフェルメールなどの個別研究は進んだものの、「ルネサンス」を全体としてどう捉えるか、という点は棚上げされた感がある。
他方、政治思想史の方はある時期から政治的人文主義の研究が流行したが、これは美術史とは仕切られたまま。また人文主義法学はこれとも別。
ここらで12世紀から17世紀までに至る人文主義とルネサンスの関係を政治・法学と美術を横断して再考する試みが待たれる所である。
「ケン・ローチと英国の左派文化」
「麦の穂を揺らす風」、「私はダニエル・ブレイク」で二度パルムドール受賞、英国を代表する左派映画監督のケン・ローチ。
トニー・ブレアの「ニューレイバー」に反発して労働党を離党。J.コービンを支援して復党するも、コービンを追い落としたスターマー(現首相)によって除名。
ケン・ローチはサッチャー政権時の炭鉱労働者潰しや国鉄民営化の際の労働者弾圧を描いた映画も作ってきました。「ナビゲーター」は後者で日本でも見ることができます。
他にもスペイン市民戦争を舞台にした「大地と自由」、ニクラグアのサンディニスタ革命下のニカラグア女性とスコットランド男性の関係を扱った「カルラの歌」があります。
UK内を舞台にする際にも、アイルランド(「ルート・アイリッリュ」、「ジミー、野を駆ける伝説」)、スコットランド(「天使の分け前」)など周辺地域を舞台にすることが多い。
「私はダニエルブレイク」は現在の英国の福祉行政が如何に残酷なものであるかを描いた秀作です。
今日は、東京新聞の発刊140周年記念日だったらしい。
そこで、2面に、ドーンと「祝 東京新聞創刊140周年 お祝い申し上げます」と言葉とともに、地平社の広告が出ている。地平社立ち上げの際に上梓された、私の『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』も久々に新聞広告で見た😀 。
12面では東京新聞の140年を振り返る図表、13面では編集局長と文芸評論家の斎藤美奈子さんの対談。
お二人とも「戦後民主主義」をポジティヴなシンボルとして何度も使っている。これは新聞メディアとしては、1960年以来なかったことではないか?ちょっと驚きである。
ここでの「戦後民主主義」は大日本帝国の植民地主義と侵略戦争への反省を意味している。編集局長が「加害責任を曖昧にすると、再び過ちを繰り返すことになる」と。これは他の新聞メディアで見られない文字列だろう。
他にも脱原発、五輪反対、反差別などの方針が明快に示されている。これもなかなかに頼もしい。
ちなみに現在他の新聞は「読売」含め、劇的に部数を減らしているが、「東京」は維持している。つまりリベラル左派支持が首都圏に数十万世帯ある。野田立憲はこの票のほとんど失うだろう。
『地平』が「東京」と連携するなら、一挙にリベラル左派言説が広がる可能性はある。
「暗殺」(2015) ・「密偵」(2016)
日帝支配下の朝鮮・満州・上海を移動する「独立」運動の闘士たちの映画。
決していわゆる「シネフィル」的な映画ではないが、「密偵」(2016)と並んで、2010年代の「韓国」映画の湧き上がるパワーに溢れている。
日本映画・批評の低迷は、政治・社会と正面から向き合ったよい意味での「大河メロ・ドラマ」をひたすら回避してきたことに一因があると思う。無理につくろうとすると、結局山本薩夫や山崎豊子のリメイクになってしまう。
ここでは詳しくは論じられませんが「この世界の片隅で」(映画)の決定的な弱点は脚本の弱さ、というか悪い意味でのナイーヴさにある。
映画は「総合芸術」なので、いくら視覚的に繊細な絵をつくれても、戦争を扱いながら脚本を決定的にダメであれば、少なくとも私は評価できない。
J.ルノワール『ラ・マルセイエーズ』(1938)。ジャンは有名なA.ルノワールの息子。この映画では、兄ピエールはルイ16世役で出ている。
ルノワールは1930年代、「トニ」(35)、「ランジェ氏の犯罪」(36)「ピクニック」(36)、「大いなる幻影」(37)、ゲームの規則(39)など映画史に残る傑作を立て続けに監督。「トニ」、S.バタイユが主演した「ピクニック」ではビスコンティ、「ラ・マルセイエーズ」ではベッケルが助監督を務めた。
この映画は「人生は我らがもの」と同様、反ファシズム人民戦線への連帯として撮影された。
最初は1789年7月14日、バスティーユ襲撃を知らされたルイ16世が「暴動か?」ー側近「陛下、これは革命です」の有名な場面で始まる。
映画では南仏のプチ・ブルジョアのインテリ、マッソン(石工だが、フリーメーソンの意味も掛ける)、貧農、下層都市民の4人に焦点があてられる。
最後は、共和国の存続をかけてヴァルミーでプロイセン軍に立ち向かう場面で終わり、「ここから、そしてこの日から新たな世界史が始まる」というゲーテの有名な言葉が引用される。
この場面で「自由」=「恋人」の比喩が用いられる。レジスタンス中のエリュアールの有名な「自由よ、僕は君の名を書く」はここから来たのだろう。
1951年と言えば、日本では堀田善衛の「広場の孤独」が発表された年。また、サン・フランシスコ講和条約(日米同盟)に反対して、平和4原則、非同盟中立路線が社会のかなりの部分の同意を得る。
欧州ではサルトル、メルロー=ポンティ、ボーヴォワールの『現代』を中心とした独立左派が朝鮮戦争の勃発のアルジェリア独立問題で、四分五裂へと追い込まれていく。
この中であくまで「中立」と植民地独立を堅持したのがサルトルと『現代』です。メルロー=ポンティとカミュは、朝鮮戦争とアルジェリア問題にある意味「躓き」、冷静な状況判断能力を失って脱落していきます。
そうした意味でユーラシアの東端と西端で「国際冷戦レジーム」への抵抗としての「中立主義」が成立し、ある期間までは有意味な参照関係が成立したのは、こうした世界空間の再編、という背景があったと思います。
ロッセリーニ自身はその後、アッシジのフランチェスコの伝記(?)映画(「神の道化師 フランチェスコ)を撮り、ある意味、キリスト教左派的な社会主義に向かっていきますけれども(「殺人カメラ」)・・・
現在の研究では米国は伊共産党に政権にわたすつもりはなく、万一選挙で保守連合が過半数をとれなかった場合、英とともにイタリアを軍事占領する予定だった、ことが明らかにされている。
結果はキリスト教民主党を中心とする保守の僅差の勝利。スターリンがイタリアに軍事介入する意志がないことを知っていたトリアッティを含めた共産党最高幹部はむしろ、ほっとしたかもしれません。
実際、ギリシアでは優勢だった左派が英軍の介入で排除され、ソ連もそれを見捨てた。(というか、チャーチルとスターリンはそのことについて大戦末期に合意していた)。
この映画「1951」では米国人で、イタリアの資本家の妻となったI.バーグマン演じる主人公(米国人)は、子供の死とともに「社会問題」に目覚め、「イタリア共産党」の文化部長の親族(イタリアでは上流階級出身のコミュニストはかなりいた)としばらくともに行動するが、結局袂をわかち、半ば自分の意志ともとれる流れで精神病院に監禁される、ところで映画は終わる。
日本では1951年、と言えば堀田善衛の「広場の孤独」が発表された年(続く)。
ロベルト・ロッセリーニ「ヨーロッパ 1951」
「無防備都市」、「戦火のかなた」、「ドイツ零年」のネオリアリズモ期のロッセリーニの3作品はよく知られていると思います。
実際、傑作でもあるし、ゴダールの「映画史」でも、もっとも登場回数が多い三作かもしれません。
1944-1945のイタリアは反ファシズムの熾烈な内戦(中部・北部イタリア)を経て、(ロッセリーニの前2作は、イタリア・パルチザンのたたかいが舞台)、戦後国民投票で王制を廃止し、共和国へと移行。
ところが、戦後た直ちに地球規模での国際冷戦レジームの構築が始まり、イタリアは分断されたドイツ、ギリシアなどともに、ヨーロッパにおける最前線地帯となる。
ただし、共産党の存在が認められたように、ドイツ、ギリシア、韓国と比較すると「緩衝地帯」としての要素も入っては来る。
この点、フランスと類似する面もあります。日本は同じく「前進基地」であると同時に「緩衝地帯」とされた点で、近い面もある。ただし、イタリアは長くイタリア共産党(PCI)が野党第一党である点が大きく異なります。とくに内戦地域になった中部イタリアでは圧倒的。
しかし、ロッセリーニは非「共産主義」左派であったため、冷戦の激化とともに、難しい立場に立たされていく(続く)。
A.ゲルマン「わが友イワン・ラプシン」を観る。これで公開されたゲルマンの映画は全て観たことになる。
1938年生のゲルマンは「道中の点検」(1972)が検閲で上映禁止になって以来、ペレストロイカまで映画が創れなくなる。
作家は、まだ「密かに書く」ことができるが、チームと最低限の資金を必要とする映画監督にとっては撮影禁止はつらい。
結局ゲルマンは1998年の「フルスタリョフ、車を」がロッテルダム映画祭が上映されるまで沈黙を強いられることになった。
「神々の黄昏」(2013)の撮影後死去。この映画は死後上映ということになる。
ソ連・ロシアの映画監督としては、タルコフスキー、ソクーロフなどが著名だが、ゲルマンは別格の貫禄がある。「宇宙飛行士の妻」などで知られる映画監督のA.ゲルマンJrは息子。
ゲルマンのキャリアは、やはりポルトガルのサラザール独裁政権時代、沈黙を守り、その後105歳まで映画を撮り続けたオリヴェイラと相通じるものがあるように私は感じている。
オリヴェイラ、晩年は駄作も多かったが、1991年の「神曲」や95年の「メフィストの誘い」はやはり傑作である。
哲学・思想史・批判理論/国際関係史
著書
『世界史の中の戦後思想ー自由主義・民主主義・社会主義』(地平社)2024年
『ファシズムと冷戦のはざまで 戦後思想の胎動と形成 1930-1960』(東京大学出版会)2019年
『知識人と社会 J=P.サルトルの政治と実存』岩波書店(2000年)
編著『近代世界システムと新自由主義グローバリズム 資本主義は持続可能か?』(作品社)2014年
編著『移動と革命 ディアスポラたちの世界史』(論創社)2012年
論文「戦争と奴隷制のサピエンス史」(2022年)『世界』10月号
「戦後思想の胎動と誕生1930-1948」(2022年)『世界』11月号
翻訳F.ジェイムソン『サルトルー回帰する唯物論』(論創社)1999年
