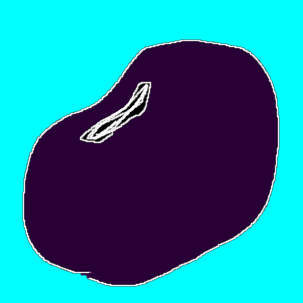
3ピースバンドの可能性を追求するのが五七五の俳句だとしたら、こういうのは自由律俳句だな
それぞれに意味なり必然性なりあるんだろうけど、後者の選択肢など存在しないかのようなポピュラー音楽・ロックシーンにモヤモヤするといえばする
なんでギター2べース1ドラム1とか、2MC+1DJとかから逸脱しないの
本当に独自のスタイルを獲得したいなら、ベーシスト2人+ちくわ笛奏者5人+DJ10人とかでやってみてもいいはずなのに
それじゃモテないからだろうか
モテないとお金にもならないし
(ボアダムスの複数ドラム編成初めて見たときはテンション上がった。数十台になるとまた別物だと思うけど)
アナログでできること、やり残してることがまだ山ほどあるのにこぞってデジタルに行ってしまったな
まあだからこそこのデュオみたいなのが目を引くのだけど
#音楽 #ulmm
だいじな情報
加えて絵文字リアクションの並びが
「本質情報はすべて詐欺です」
となっていて、それはそれで含蓄のある言葉のようにも思える
#ulmm
QT: https://sushi.ski/notes/9i45ayxvjm [参照]
 @tukareta_INU@sushi.ski
@tukareta_INU@sushi.ski
ちあきなおみってすごいな
歌というもの自体にあまり興味がないせいかピンと来てなかったけど、映像見てたまげた
あれを単に「歌」と呼ぶべきなのだろうか
むしろ歌というのは本来ああいう、聴覚的なものに限らない周辺の情報(表情とかしぐさとか)と一体で楽しむものだったのかも
それが表現・創作の多様化や録音技術の確立・普及などで、聴覚的な情報のみが切り離されていったのでは
まあそれは無根拠な妄想だけど、周辺の情報をひっくるめた丸ごとがその人の「歌」なのだという捉え方は自分にとって魅力的だ
歌ってピッチの正確さのように定量的な基準が幅を利かせがちで、それがすごく窮屈だと思うので
(楽器の演奏だって同じことのはずだけど、楽器の場合は不協和音や非楽音の存在が比較的許容されやすい気がする。歌に対して楽器は脇役になりがちなのでお目こぼしされやすいのかも)
もちろん聴覚的な情報に特化するのが悪いわけではないけど
#音楽 #ulmm
https://realsound.jp/movie/2023/08/post-1395720.html
記事の内容と関係ないが、『真夏のシンデレラ』というタイトルが引っかかる
オリジナルの『シンデレラ』が真夏の話じゃないとは限らないと思うのだが
Wikipediaによると『シンデレラ』のオリジナルは判然とせず、各地に同類型の物語があるらしい
(確認されてるうち最古のひとつはエジプトが舞台らしい)
ならばなおのこと「そもそも真夏の話だった」ということはあり得る
もしそうだった場合、『真夏のシンデレラ』はたとえば
『盲目の座頭市』
『大きなゴジラ』
『3分で帰るウルトラマン』
のように(誤りではないが)奇妙なタイトルということになるのではないか
#テレビ #ドラマ #屁理屈 #ulmm
※仮にペローの『サンドリヨン』をオリジナルとみなす場合、舞踏会の準備をするサンドリヨンのきょうだいが「がいとう」を選ぶ記述が作中にあるようなので、真夏ではないかもしれない。当時のフランスの気候や風習などは自分には分からないが https://www.aozora.gr.jp/cards/001134/files/43120_21537.html
CNETの記事の後に読むとなおさら面白かった
●AIの記号接地――ある言葉(例えば「メロン」)とその特徴(色や香りや触感、経験や感覚に基づくものを含む)を紐づけること――はまだ人間のそれに及ばないのではないか
●人間の凄みとは、あまり関連のない分野の知識同士を直感で結びつけてしまうことでは
●AIは一般論を土台に考える。人間は個々の対象に付随する情報(人間であれば過去の行動や性格など)をもとに仮説を立てる傾向
●この飛躍が誤りをおかすこともある一方、想像力によって文化を発展させる鍵でもあったのでは
●AIはオノマトペを作り出せるか?
→ある程度可能だろうが、人間の身体性に根差したものができるかは疑問
#ulmm #ai #言語
QT: https://mastodon-japan.net/@honjp/110829396043795409 [参照]
たとえ同じ結論に行き着いたとしても実践には意味があると思う
どんなに小さなことでも、実践することで流れ込んでくる情報の量と多様さというのはすさまじい
それらを応用できる局面は多々あるだろうし、それら自体が形作るナラティブが価値をもつこともある #ulmm
たまにレコードを引っ張り出して聞くと、めちゃくちゃ贅沢な行為をしてるなあと感じる
ダークサイドミステリー「日ユ同祖論」回/似非科学とか陰謀論とか
見た。前半できっちり瑕疵を指摘、後半で言説の起源から時代ごとの受け止められ方をたどる構成
この番組(幻解!超常ファイル含む)は後者を疎かにしないのがよい
似非科学や陰謀論への批判が「非科学的・非論理的な蛮人をインテリがクールに完全論破」的なスカッと系コンテンツとして消費される様子に辟易することが多々ある
やや日の人が以前に「カルト信者の救済活動をしてる人は信者を被害者ととらえたうえで救済・予防方法を考えるので、相手を絶対に馬鹿にしない」といった趣旨の発言をしてた
似非科学や陰謀論に対してもこの態度で接するべきなんだと思う
なぜ似非科学が生まれるのか、なぜ人は陰謀論にすがってしまうのかという背景に目を向けることなく相手の主張をばっさり切り捨てても、公開処刑になるだけ(仮に当人にその意図がなくても、それを求めてうろついている野次馬が大勢いる)
「救いたい人はそうすればいい。科学的・論理的妥当性に基づく指摘の何が悪いのか」というかもしれない
けど、見も知らぬ大勢の「お前は間違ってる」の大合唱が相手をどれだけ追い込むか。それによって問題は解決に近づくのか、遠ざかりはしないのか
考え抜いたうえで弁舌をふるってるのか疑わしい人はいる
#ulmm
積んでるゲーム・映画・本の消化にかかる時間をざっくり計算したら5,881時間だった
脳や各知覚器官が使い物にならなくなるまでにあと40年=14,600日あるとして、1日あたり24分を費やせば全部消化できることになる
これから出会うものに費やす時間とは別に確保する必要があるし、どんぶり勘定きわまる計算なので実際はこれより相当長くなると思うけど、もっと膨大な時間だと思ってた
→「全部消化するのは土台無理」という諦念→余計消化に億劫に→さらに積み増加→
の悪循環に陥ってた感があるけど、十分に手の届く数字が示されたことでちょっとモチベーションが湧いてきた
やるぞ俺はやるぞ
遠くに霞んで見える目標に適当でもいいから実体を与えるって大事だ
靄が晴れると意外と近くにあることに気づく
近寄ってみたら蜃気楼かもしれないけど、一本道なんだから歩かないより歩いたほうがマシに決まってる
相田みつをカレンダーのようなことを書いてるけど、自分のような人間にとっては積んでは崩す営みこそが人生なのだからそれはそうなる
「野蛮な時代だったんですねえ」と、現代を生きる自分とこの史実を切断し、自らを守ることもできる
でもそれ嫌い
今現在の我々の所業を50年後の人が見て「令和って糞みたいな時代だったんですね」と言われることは普通にあり得るわけで
番組でも、2014年に実施寸前で中止になった、モンスター・スタディに劣らず非人道的なニュージーランドの実験を紹介していた
日本にしたって、構造的な不平等や人権侵害などの指摘・報告は(そのすべてが的を射てるかはさておき)毎月毎週のようになされているのだし
コロナ禍でのあれこれによる一番大きな学びは、自分含め人間ってたぶん100年前と同じぐらいバカだよね、ということだった
1000年前でも同じだし、1000年後も同じなんだろうたぶん
関係ないけど「昭和はこんなにやばかった」的コンテンツへの嫌悪感もこういう意識と同根なんだろうなと思ってる
まあ自分は和暦でいうと昭和期・平成初期あたりの大衆文化が好きだから(どちらかというと欧米寄りだけど)、余計にそう思うのかもしれないけど
#ulmm
昔飛び入りOKのある祭りで山車を引かせてもらった
体感で大型トラックぐらいある山車を全力疾走で引っ張って、どんなライブでも経験したことないぐらい血沸き肉躍ったけど、後で冷静になるとあれ転んだら死んでたかもな…と
でも死を含む非日常的なあれこれと日常が混交してこそ祭りには意味があるような気もするし、何をどこまで対策すべきかは難しい
そもそも危険を織り込んで参加するものだろっていう考え方もあるけど、それで済む問題と済まない問題があるしね…
自分も飛び入り参加でもしケガしてたらどうしたか?といわれると正直分からない
覚悟もないのに参加して軽率だった、もうしないと言って済ませることもできるけど、それは祭りのある側面を保身のために否定するということであり
…我ながら煮え切らない書きぶりだけど、プロレスなどと同じく祭りもその構造(責任の所在など含め)を明確にしてしまうことで消失する何かがあるように思われるので、致し方ないこととも思ったり
趣味方面で見聞きしたものの記録が中心です。ブロック・フォロー・リムーブなど気兼ねなくどうぞ。
キーワード購読などでたどり着いた見ず知らずの方の投稿にリアクションすることがあります。ご容赦ください。望まれないようでしたら、お手数ですがブロックをお願いします。
またキーワード購読を多用している関係上、いわゆる先回りブロックを日常的・半機械的に行っています。TLの煩雑化を避けるためであり、敵対的なものではありません。

