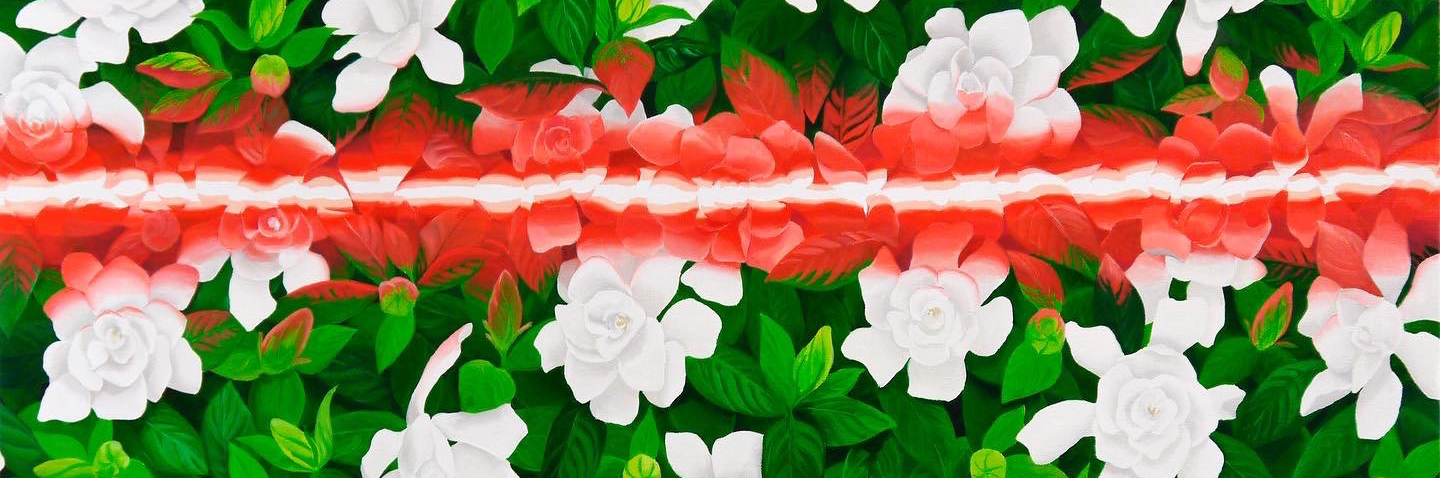
今年も映画をいくつか見たけど、「NOPE」や「LAMB」、一部「RRR」も、人間が支配しきれない人間以外のものたちのパワーをぶつけてくる映画が多くて嬉しかった。
「Pig」みたいな、いわゆる男のプライドを男が壊しにかかる話があったのも良かったけど、やっぱり私は「ガンパウダー・ミルクシェイク」が今年の一番だった。拠点が図書館なところもまじ最高だし、自分を投影しながら見れるエンタメってこんな楽しいんだな!というのを思い知った一本だった。
例えば、シリアスな人間模様や問題を描いたりする映画も必要だけど、たまにこういうただただ爽快感を味わう映画も見たくなるので、元気ない時に何の不安もなくぶち上げてくれる映画は貴重だよね。
Painter | Asexual | 植物を描きながら人間について考えている http://hasegawa-yuki.com/
2022年 12月 に登録
