
北川民次作・カゴメ旧本社壁画「トマト」の原画発見 29日から名古屋で初公開:中日新聞Web https://www.chunichi.co.jp/article/908588
名古屋市美術館で北川民次展(「北川民次 メキシコから日本へ」展)が開催されるんですね。今知った(爆)。2024.6.29〜9.8。
メキシコ革命後にリベラやオロスコ、シケイロスらによって強力に推進された壁画運動にほぼリアルタイムで際会し、戦後愛知県各所で壁画を手がけた北川の回顧展が現時点で開催されるの、なかなかにタイムリーではあり。上手く日程をfixできればいいんですが……
小松原智史「ふたたび巣をたてる」展|2024.6.22〜7.28|the three konohana(大阪市此花区)
──DMが届いてました。the three konohanaの今年初となる企画展は、同ギャラリーで何回か個展を開催している小松原智史(1989〜)氏の新作展。ドローイングを主たる表現手段としつつも、表現やコンセプトが毎回の個展ごとに深化していっているだけに、今回も要注目。
しかしそれにしても、同ギャラリーを運営している山中俊広氏は、学芸員を兼任している大阪芸術大学博物館で現在開催中(〜6.13)の「群衆|不在 アンリ・カルティエ=ブレッソン──揺れ動く世界へのまなざし」展が終了した直後からこの展覧会の準備に忙しくなるわけで、以前から氏の知己を得ている者としては、まぁ健康には気をつけていただきたく 

当事者のうち、日テレと小学館が報告書を出してますが…… まぁ日テレ側が今回に限らずドラマの制作に際して契約書を作ってこなかった(し、今後もそうし続けるらしい)という事実に唖然としますし、それで原作者側に対してたかが原作者がと言いたげな調子に終始してるの、かつて球界再編騒動のときに某ナベツネが「たかが選手が」と言ったことを彷彿とさせ、ナベツネスピリッツがいかにグループ全体に浸透しているかがよく分かるものとなっている。あと脚本家の相沢友子とプロデューサーの三上絵里子が(女性だからか?)なんとなく免罪されてるのは純粋に疑問。こいつらがフェミ臭いクソ仕事&クソムーブをカマし続けたのが諸悪の根源ちゃうんかぃ、というね……

演劇×女子高生×百合マンガで『君のためのカーテンコール』という作品があり、現在でもなぜか(単行本第1巻所収分も含めて)全話無料公開中なのですが、途中からテレビドラマの脚本家兼劇団主宰者のおねいさんが出てきて「プロデューサーの意向を汲んで 事務所の意向を汲んで 流行や視聴者の要望を汲んで」と言っており、これが昨年8月に配信されてるの、先日来再燃しているあの問題(あの問題?)を完全に先取りしていたのでした 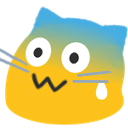

勤務先で見かけたんですが、日本電気協会が8月に配信する第59回電気関係事業安全セミナーのタイトルが
「“ヒューマン”はこれからどこへ向かうのか!? 〜エラーもするがそれだけではない…はずだ!〜」って、またなんとも激アツな

こういう、自我とも主体とも異なるっぽい〈ヒューマン〉を実践レベルで立ち上げるの、本当は哲学や思想の役割のはずですが、昨今の人文どものお脳がスポンジケーキ状態なばっかりに……
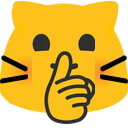
https://store.denki.or.jp/frontend/seminar/detail/135
ハニワや土偶に魅せられた芸術家たち ― 今秋、東京国立近代美術館で「ハニワと土偶の近代」展 | ニュース | アイエム[インターネットミュージアム] https://www.museum.or.jp/news/116694
2024.10.1〜12.22。《展覧会構成は、序章「好古と考古 ― 愛好か、学問か?」に続き、「『日本』を掘りおこす ― 神話と戦争と」「『伝統』を掘りおこす ― 「縄文」か「弥生」か」「ほりだしにもどる ― となりの遺物」の3章》だそうで、ハニワや土偶に「美」を見出す視線を近代的なものとして、〈つくられた伝統〉((C)エリック・ホブズボーム)論の枠組みにおいて再走査していくといった趣でしょうか。同時期に東京国立博物館でも「挂甲の武人 国宝指定50周年記念
特別展「はにわ」」が開催される( https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2660 )というのが吉と出るか凶と出るか 
美術史上初の展示手法を用いた「トリオ」展、全34組からベストトリオ、あえてワーストトリオを選んでみた 東京国立近代美術館「TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション」が開幕 | JBpress autograph https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/81197
東京国立近代美術館で先日始まった「TRIO パリ・東京・大阪 モダンアート・コレクション」展、このあと大阪中之島美術館にも巡回する(2024.9.14〜12.8)けどまぁスルーするかもなぁと思ってたら、お題に沿った作品を各館(東京国立近代美術館、大阪中之島美術館、パリ市立近代美術館)から一点ずつ出して三点セットで見せるという方式を取っているとのこと。上手くいってるのか大スベりしてるのかはともかく、これはちょっと見届けないとアカンのかなぁ…… 
ところで今回の展覧会では、
カルティエ=ブレッソンの写真について語られる際に代名詞となっている「決定的瞬間」という言葉が(既訳からの引用を除いて)キャプションや説明文、彼自身によるアフォリズムから排除されています。1952年に出版された写真集Image à la sauvetteの英語版が出版されたときにThe Dicisive Momentと改題され、さらに日本語訳されたときに英訳を直訳した「決定的瞬間」となって広く知られるようになったのですが、フランス語タイトルでは「逃げ去るイマージュ」とでも訳されるImage à la sauvetteにはどこにも「決定的」「瞬間」というニュアンスはなく((ベルクソンが論じたように)イマージュとは何らかの持続性・不(確)定性をともなったものとしてある以上、それは必然である)、先に述べたように、この展覧会では〈群衆〉をカルティエ=ブレッソンの写真において被写体以上のイマージュとして再定位する──「揺れ動く世界へのまなざし」というサブタイトルは、そのこと以外ではない──ことが目指されている以上、「決定的瞬間」という言葉を無批判に用いることは、単なる誤訳以上の問題を含んでいると言わなければならないわけで。
そう言えば今回は博物館に加えて、大学内の図書館のミニスペースでも彼の写真集の現物が展示されていましたが(手に取ることはできませんでしたが)、見ての通り、その表紙はマティスが担当しており、写真集の表紙に別人の、写真ではない作品を使用するって、現在の日本ではちょっと考えられないだけに、なかなか驚かされたのでした。
「群衆|不在」というタイトルからもうかがえるように、
今回は「群衆」が被写体となっている作品と「不在」=人物が写っていない作品とが選ばれています。よく知られているようにカルティエ=ブレッソンは主に1940〜50年代にフランスのみならず世界各地を報道カメラマンとして取材し、植民地支配からの独立運動や内戦、体制変動を現地から記録し続けてきました。インドではガンディーの葬儀を、中国では国共内戦の帰趨を、フランスでは(アルジェリア独立戦争などによって)急速に行き詰まる第四共和制を──といった具合に。で、それらのムーヴメントはほぼ必然的に〈群衆〉から発生する/〈群衆〉を政治的主体として発生させるから、このテーマを彼の写真に対する新たな切り口として導入するのは、確かに理にかなっています。
そして今回のこの展覧会においては、カルティエ=ブレッソンが写真家を志して間もない時期(1930年代前半)の写真も紹介し、若き日の彼がシュルレアリスムの近傍にいたことにも触れることで、〈群衆〉に単なる被写体以上の意義を与えていたことに注目しなければならないでしょう。カメラとシュルレアリスムを通して見ることで、〈群衆〉はいわば世界に対する無意識──というかここでは下意識とした方が適切でしょうか──の領域として立ち現われてくるし、かかる下意識の領域もしくはイマージュの領域は持続的であるから、その不在もまた〈群衆〉の一局面となるわけです。彼がそのことにどこまで気づいていたかは分かりませんが、少なくとも第二次大戦後1960年代前半までの写真には、そうした下意識の領域としての〈群衆〉を直視する強い持続力があったと言えるでしょう。
写真界隈においては既に古典の地位を確立してひさしいと思われるカルティエ=ブレッソンですが、単なる古典ではなく常に振り返られるべきアクチュアリティを持っていることを、これ以上ないくらい雄弁に作品によって語らせており、その点もまたポイント高。6月13日まで。
大阪芸術大学博物館で開催中の「群衆|不在 アンリ・カルティエ=ブレッソン──揺れ動く世界へのまなざし」展。20世紀フランスを代表する写真家としてつとに知られるアンリ・カルティエ=ブレッソン(1908〜2004)の自選ベスト集──日本では大阪芸術大学だけが所蔵しているという──全411点の中からチョイスされた100点からなる展覧会。写真の選定は、the three konohana(大阪市此花区)を運営する傍ら、昨年から同博物館の学芸員も兼任している山中俊広氏。

「AIと共存すべき」人気声優・梶裕貴 自身の声で自由にしゃべれるAIソフト発売へ 「たくさん悩んで」決断 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2405/28/news094.html#utm_term=share_sp
《ソフトで合成した音声は「個人または同人サークル」に限り、商用・非商用問わない幅広い用途での利用を許諾する方針という。二次創作ガイドラインも整備中だ》そうで、これはまた思い切りましたな。まぁ当方が利用することはないですが(←反AIとか、そういう政治的な話ではなく、単純に使用するシーンが生活の中にないだけです  )、例えばしゃべりがヘタクソな大学教員がこれ使って梶氏の声でパワポとかの内容を読み上げるとか、そういう用途に使えそう? あと奥さんのケケ達もとい竹達彩奈嬢を巻き込んで、女性版もリリースあくs(ry
)、例えばしゃべりがヘタクソな大学教員がこれ使って梶氏の声でパワポとかの内容を読み上げるとか、そういう用途に使えそう? あと奥さんのケケ達もとい竹達彩奈嬢を巻き込んで、女性版もリリースあくs(ry 
奈良博「超 国宝」、京博「日本、美のるつぼ」 ― 2025年春に関西の国立博物館2館で注目の特別展が開催 | ニュース | アイエム[インターネットミュージアム] https://www.museum.or.jp/news/116584
両方とも2025.4.19〜6.15。奈良国立博物館の「超 国宝─祈りのかがやき」展は《(奈良の)仏教・神道美術100%の展覧会とな》り、京都国立博物館の「日本、美のるつぼ─異文化交流の軌跡」展は《1900年パリ万博への参加を契機に明治政府が編纂した書籍で、官製の日本美術史といえる『Histoire de l'art du Japon』を軸に、「世界に見せたかった日本美術」を展示》するそうで、話題性というか見た後誰かに語りたくなる度は後者の方がありそう? しかしそれにしてもなぜ会期を揃えたんでしょうか……
「芸術新潮」6月号 特集「安彦良和 アニメの快楽、マンガの叡智」 美術展ナビ限定のスペシャルインタビューも https://artexhibition.jp/topics/news/20240523-AEJ2075098/
なんだかんだで来週末6月8日から兵庫県立美術館で始まる「描く人、安彦良和」展ですが、今月号の芸術新潮誌で特集が組まれてるんですね(←そこからかぃ)。あとで読む。
「描く人、安彦良和」展は早めに見に行かないと混雑がシャレならんことになりそうですが、個人的には『機動戦士ガンダムTHE ORIGIN』のかと思いきや『トニーたけざきのガンダム漫画』のナマ原画だったとか、そういう珍事件が発生してほしくないと言えば嘘になる  あと島本和彦氏が「カズヒコ・ヨシカズ」名義で描いた「あしたのG」もうっかり展示されてゲフンゲフン←←
あと島本和彦氏が「カズヒコ・ヨシカズ」名義で描いた「あしたのG」もうっかり展示されてゲフンゲフン←←
好事家、インディペンデント鑑賞者。オプリもあるよ♪

