
現在利用してるSNSのアカウントをこちらにまとめておきました。
またちょっと(ネガティブな)話題になってるあの大阪万博の木造のあれ、無邪気にはしゃぐ建築家氏の様子が流れてきたけど、なんかプラレールで線路を丸くつなげてはしゃいでる子みたいで、それに350億円(税)か~と溜息が出てしまった
1000円でも10000円でもあったら助かる人が山ほどいるのに、あれに350億かぁ
今話題のmixi2を始めてみました。
mixi2を色々と触ってる所だけど、BlueskyとMastodonのいい所取りという感じ?
興味のある方は、うちをきっかけにどうぞ〜!
nmmrm13からの #mixi2 招待🎟️
一緒にはじめよう!🚀
https://mixi.social/invitations/@nmmrm13/D1JsMCXfm4fHGD9CpdjoNv
立花孝志がまたも落選したのは良かったですが、当選した現職も反ワクチン論者というのは、もはや地獄ですね…。とりあえず、警察には立花が次の選挙に出馬する前に、一日も早く逮捕してほしいと思います。
※立花孝志のような政治ゴロを地方選挙から排除するために、知事・市町村長選挙でも、地方議会選挙と同様に「3か月以上の居住実態」を立候補の要件とすることを提案します。これが実現して困る人は、立花以外にはいないでしょう。
https://www.sankei.com/article/20241215-S6EGQWD4VRJ2HCJPQB66FYTXFI/
まるごと生ポテト(注文受けてから生じゃがいも丸ごと1個剥いて揚げる)とかスーちゃんシェークとか良いなぁ…… 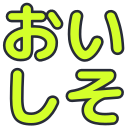
【予告】名古屋市星が丘に新しいスガキヤ『スーちゃんハウス』がOPEN!
https://www.sugakico.co.jp/news/hoshigaoka/
靴下を干す時は履き口が上?下? 正解に「メリット多いな」「次からそうする」 – grape [グレイプ] https://grapee.jp/1789083
ほー。
レジでの支払い方法云々の内容を昨日買いた所だけど、ふとそんなゲームがあったのを思い出した!
「支払い技術検定」ってゲームで、
なるべく手持ちのお金をいかに少なく、どこまで支払えるか?という奴。
ちなみに、以前母にもやってもらった事があるのですが、「いつまでも終われない〜💦」と最強でした。
「保険証を捨てないで」医師たち緊急呼びかけ もう再発行不可で二度と入手できない「保険証」使えなくなると誤解広まる(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/20808c3c3af0612f585015645c9f1c5555fb0489?page=1
12月からは、新規発行だけでなく再発行もできなくなるので、なくしたら大変です。二度と入手できません。
現行の健康保険証は、12月2日以降も使えます。有効期限まで最長で約1年使用できますので、間違って捨てないよう気を付けて下さい。
従来の保険証の発行停止がすぐそこまで来ているのに、マイナ保険証のトラブルは、減るどころか一年前の前回調査より10パーセントも増えています。
老若男女、すべての人が安心して保険診療を受けられるためにも、健康保険証の併存、存続を望みます。
■猫と本と映画と家族を愛する、インドア派。
■美味しい本情報と、ステキな猫情報には、まさに「猫まっしぐら」状態なキラキラお目々で飛びつきます。(笑)
■ちなみに、「あんな」と読みます。 そして、インテでもあります。
