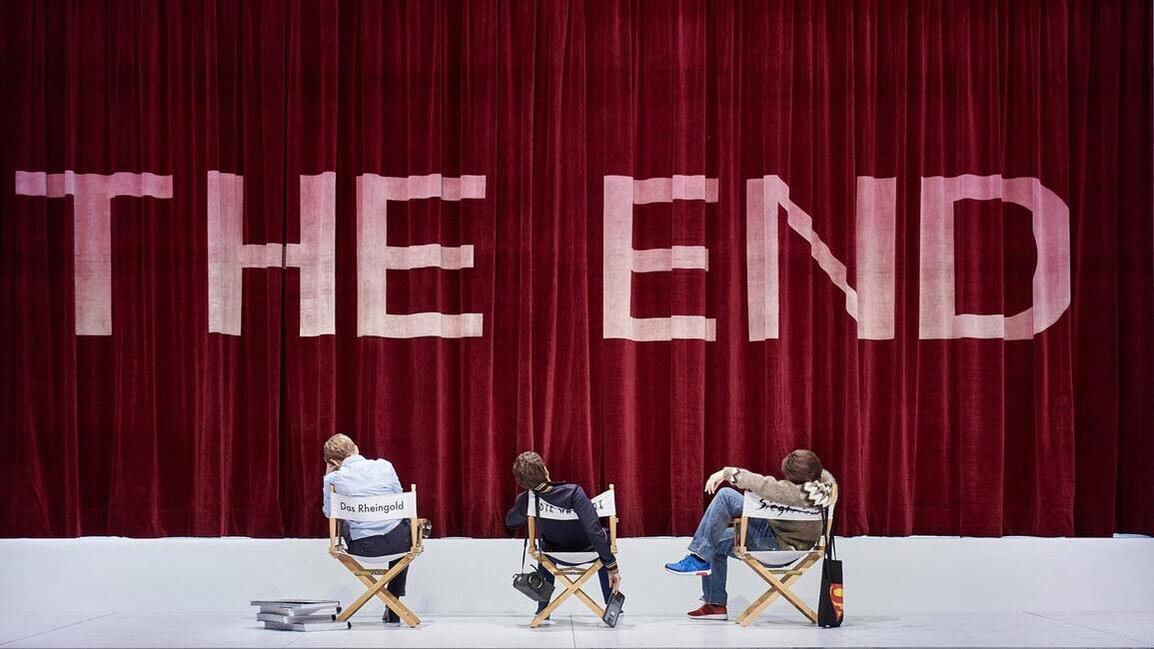
でもほんと、批評って何してるんだろうな。何かについて書いているんだけど、なんでそんなことしてるんだろうっていう。少なくとも私は、これでメシ食ってるわけでもないしね。私が見たこと、見えたことを書き留めてるんだろう。しかしこの「私」というの固有の「この私」だけのことではなくて、どの「私」であってもこういうふうに見えるってことは納得してもらえますよね、なぜならこの表面にはこれとこれがあるから、って「あなた」に説明をしているのがテマティスム批評なので、「この私」に収斂するものではないと思っている。もちろん、それをちゃんと書き留めたのは「この私」ですけどね、っていうのは当然ある。私にとっての写真もそういうものだな。撮ってるのはカメラだし。では、どうして私は小説を書かないんだろう。
そのなかで、言葉だけを使った表現という意味では同じかもしれないけど、やはり批評と小説というのは違うものだなと思った。本当に書くことができてよかった。
「映画化」することで、活劇を室内劇にしちゃったような気もするんだが、私の映画化した『黄金列車』はこうしかならなかったということで(最後は室内から飛び出す感じにしたかったのは、「死の行進」との関係について書いてるうちから決めてた)。あと、うろ覚えだけど蓮實重彦が昔「『表層批評宣言』は70分ぐらいのバッド・ベティカーの感じで書いてて」みたいなこと言ってて、何のこっちゃ判らんがかっこいいなと思っていたけれど、今回、何となく判った。私の『黄金列車』論も90分ぐらいでばしっと終わらせたかったけれど、110分はある感じになった。130分とかになっていなければいいなと思っている。
『黄金列車』について書いてみようと思ってから、いろんな人の評価や対談なんかを読んだり、ウェブの合評会とかも潜って聴いたりしたけど、あれ、俺が見つけたこれって『黄金列車』のすごくおいしいところのはずなのに、誰も書かないなと思ったので、慌てて書いた。
慌てて、と言っても、何回も読み返さなきゃ色とか日付は確認できないし(キンドルとかなら検索一発だったんだろうか。電子書籍やっぱり入れるべきなのか)いわゆる文芸批評でも、僕の書き方は映画のそれと同じテマティスムなので、どうしたって時間はかかる。
でも、読みながらちゃんと資料とつき当てていけば、あえて書かれていない街中の橋の名前が判ったり、登場人物の凡その住んでる場所も判ったり、とにかく楽しかった。ホロコーストがらみの本ばっかり一年ぐらい読んだので、学生の時から比べて、ナチの知識がアップテートされたのもよかった。
