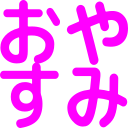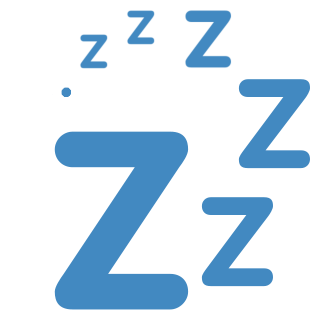京都市立芸術大学、新学長に小山田徹教授を選出 | 京都新聞 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1374277
ダムタイプ設立以来のメンバーとして知られる小山田徹氏が京都市立芸術大学の時期学長になるそうで。とかくダムタイプがクローズアップされがちですが、氏自身の活動としては小さな焚き火が点在する場を作るイベントを関西各地で行ない続けてます。当方もコロナ禍前に大阪市内で遭遇したことがあり。
でも、京都市芸、せっかく新キャンパスに移転したのに、失火で全焼してまう?

「日韓朝美術」展|2024.12.13〜22|KUNST ARZT(京都市東山区)
※出展作家:井上裕加里、岡本光博(兼キュレーター)、肥後亮祐、李晶玉(リ・ジョンオク)
DMが届いてました。KUNST ARZTが時折開催するグループ展「○○美術」シリーズ(シリーズ?)ですが、「日韓朝美術」って、またなかなかエグいところを攻めてるなぁと思うことしきり。出展作家のラインナップを見るに、日本/韓国/北朝鮮それぞれが相互に嵌入している現状を改めて問い直すことが行なわれようとしていると言うべきでしょうか。以前から日韓関係を主題にしている井上女史と、朝鮮大学校で美術を学んだ経歴のある李女史が出展作家の中にいるので、かなりクリティカルなことになりそう。さて……
ソニー、KADOKAWA買収へ協議=関係筋 https://jp.reuters.com/economy/industry/LUASZPBASNMXNOGVBCM2QDCW6Q-2024-11-19/
確かにソニーはコンテンツ系の子会社もいくつかありますが…… まぁKADOKAWAのシン・本業な『角川 俳句』誌や歳時記の編集が滞らなければ、割とどうでもいいんじゃないでしょうか 
詩人の谷川俊太郎さん死去、92歳…「二十億光年の孤独」や「鉄腕アトム」主題歌など親しみやすい詩 : 読売新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20241119-OYT1T50011/
谷川俊太郎(1931〜2024)。当方、詩や詩人については基本的に無知ですが、そんな者でも名前と作品(詩以外であったとしても)に接したことがあるくらいのポピュラリティを、もともと詩や詩人が軽んじられがちな日本文学の中において獲得したのって、ほとんど奇跡に近い──彼に匹敵しえたのって、あとはやなせたかしくらいではないだろうか──だけに、巨星墜つとしか言いようがなく。
「岡﨑乾二郎」展が東京都現代美術館で2025年4月開幕。造形作家であり文化全般にわたる批評家としても活躍する作家の新作を中心に紹介 https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/kenjiro-okazaki-news-202411
2025.4.29〜7.21。東京都現代美術館、昔常設展内の特集企画で岡﨑氏を特集してたことがありますが、これはそれ以来でしょうか。豊田市美術館で「視覚のカイソウ」展をやって、これで氏のキャリアの棚卸しは終わったかなぁと思われた矢先に倒れはって、そこから近作ではさらなる超展開を見せている──関西にいてると断片的にしか伝わってこないものですが……  ──だけに、その超展開を一望できる良い機会にはなるんでしょうけど……
──だけに、その超展開を一望できる良い機会にはなるんでしょうけど……

沖縄北部豪雨 住宅修理費、県が単独支給へ 「災害救助法」適用と同規模を検討(琉球新報) https://news.yahoo.co.jp/articles/011f19b6c18f353044bae6a122b3b3dc1579b5a5?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20241116&ctg=loc&bt=tw_up
《今回の豪雨被害では、県の対応の遅れにより被災者の支援などに国費を活用できる災害救助法の適用が難しい見通しとなっているが、》──琉球新報だけにここからどうエクストリーム政府批判&知事擁護の論陣を張るんかと思いましたが、案外あっさりと「県の対応の遅れ」を認めましたね。今回の豪雨による災害、明らかに 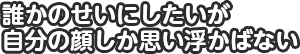 案件やろこれと思うことしきりでしたから
案件やろこれと思うことしきりでしたから 
当方の勤務先でも、(すぐ北の鹿児島県)与論島は災害地域に指定されたから荷物の配送なども忖度できるんですが、沖縄本島がいつまでも指定されないから配送側も忖度できずに大変なことになるよなぁと、別部署の上司とかが頭抱えてましたから 
ワコールHDが東京・南青山に所有する「スパイラルビル」の売却を検討していることが明らかに https://article.yahoo.co.jp/detail/44bf0a1a138f4ad7cddb2ee5cac3e5a1b66abdc7
ぇあれってワコールの持ち物件やったん!?(←そこからかぃ) 表参道のスパイラル、当方は池内務氏が一時期手がけてた「巧術」を見に行ったりした程度ですが、前時代における最先端──その掉尾を飾るのが六本木ヒルズ&森美術館なのかもしれない──の生き証人がまたひとつ……? 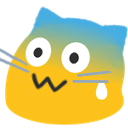
好事家、インディペンデント鑑賞者。オプリもあるよ♪