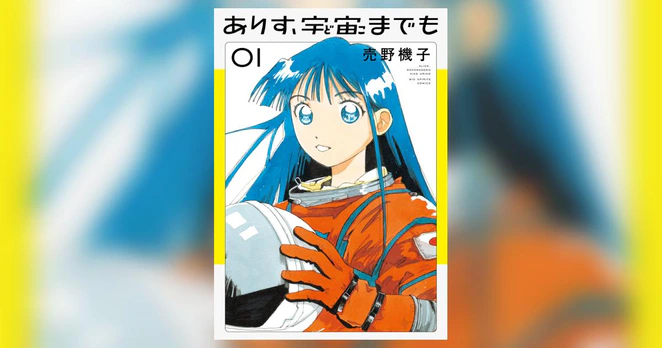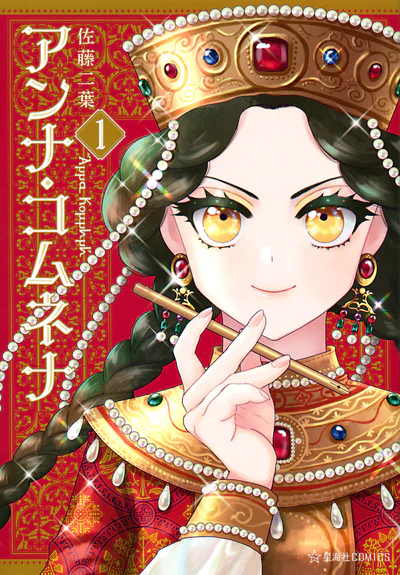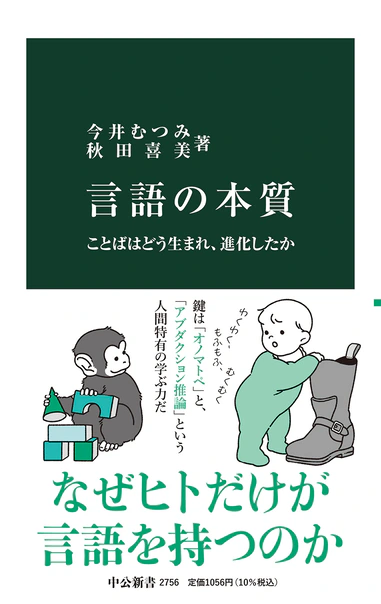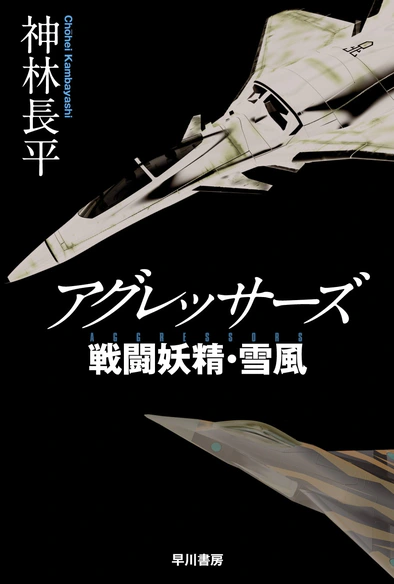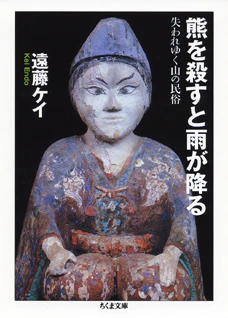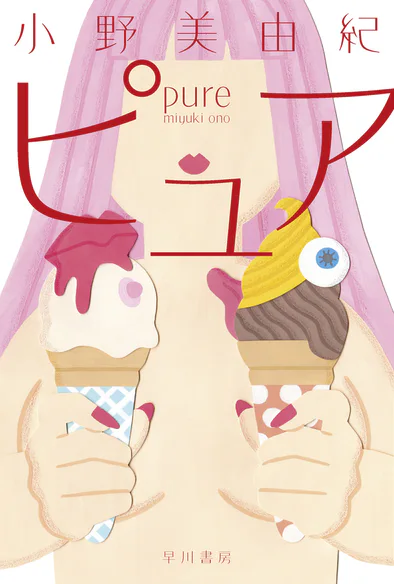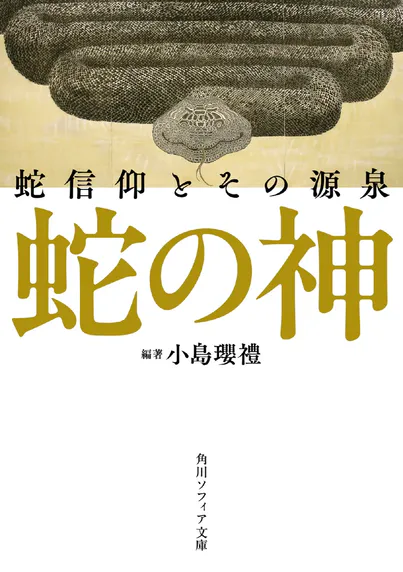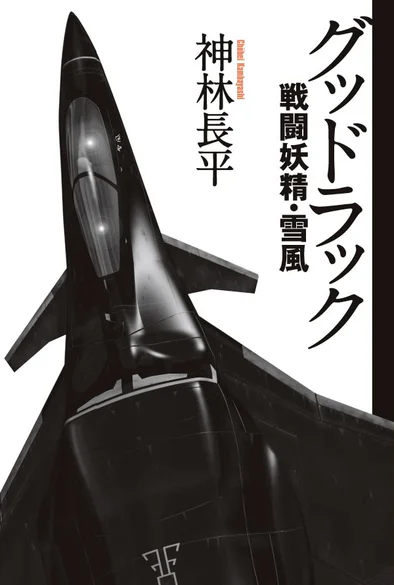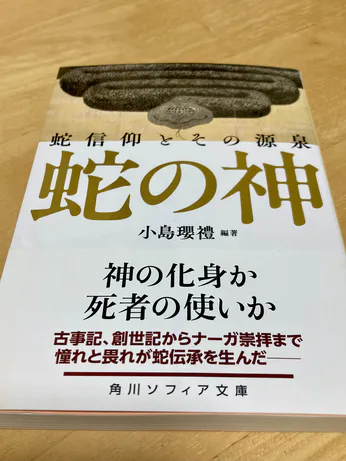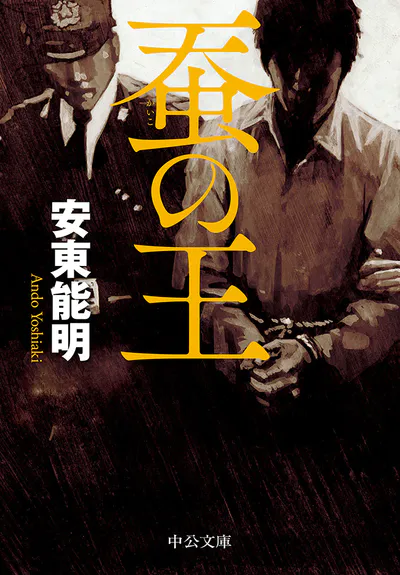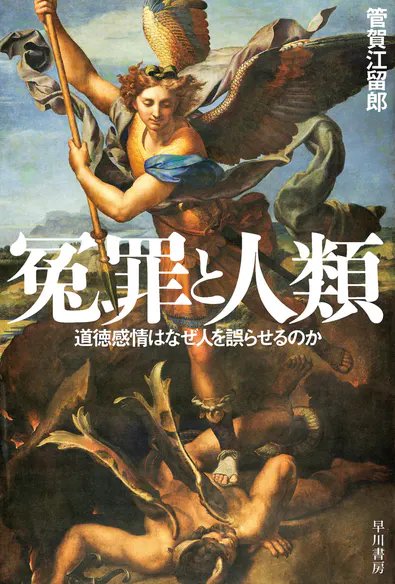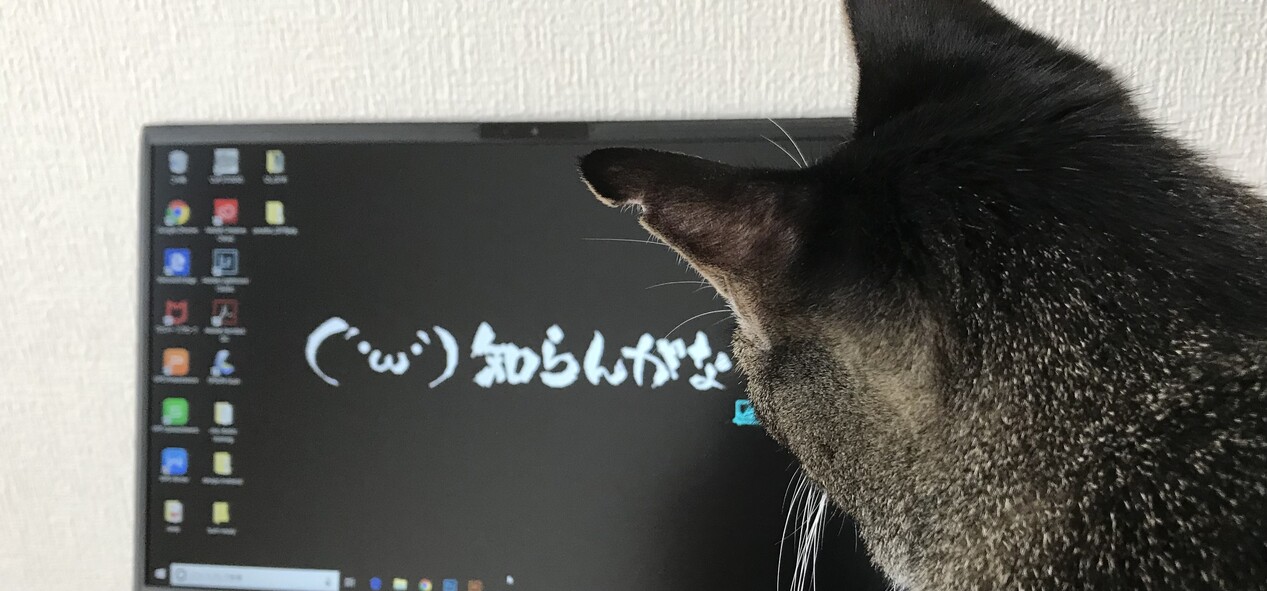
氷 /アンナ・カヴァン
破船 /吉村昭
枯木灘 /中上健次
死の泉 /皆川博子
海と毒薬 /遠藤周作
虐殺器官 /伊藤計劃
天体議会 /長野まゆみ
華氏451度 /レイ・ブラッドベリ
からくりからくさ /梨木香歩
桜の森の満開の下 /坂口安吾
NASAの存続が怪しくなってきて、アルテミス計画を目指す中学生の話『ありす、宇宙までも』がこの先どうなるのかという
橘省吾『はやぶさ2 は何を持ち帰ったのか』
https://www.iwanami.co.jp/book/b639909.html
にわかに小惑星が話題になっているタイミングで読んだのはただの偶然。
数多の困難を乗り越えて帰還したために(そしてその最期があまりにも美しかったために)、擬人化され感動物語の主人公になるなどしていた初代に比べ、抜かりなくミッションをこなした二代目は当時さほど話題になっていなかったように思うが、学術的には「2」の功績はかなり大きいらしい。タイトルの「何」かとは要するに小惑星リュウグウから採取した鉱物で、それを分析することで太陽系や地球、生命の成り立ちを探る手がかりとなるそうだ。それにしても、わずか数十グラムという微量な粒子から、実に多彩な情報が読み取れることに驚く。
ある意味、はやぶさ初代の失敗があったからこそ、確実に試料を採取できる装置を開発することができたわけで、本当に宇宙開発では失敗は失敗ではないのだな、と思う。
専門的な内容だがとても分かりやすく読みやすかった。しばしば文中で宮沢賢治が引用されていたが、賢治の知識の深さと物語化の巧みさに改めて舌を巻くことにもなった。そのうち読み直そ…
佐藤二葉『アンナ・コムネナ』全6巻
https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000360352
完結!
4コマ漫画という形式ゆえに端折られている部分も多かろうし、補足情報があっても分かりにくいところもあったが(何しろ親族の名前を子供につけるという命名の慣習から同じ名前だらけなので…)、どの登場人物も愛すべきキャラクターで、とても楽しく読んだ。特に主人公、当時の女性としては最高位と言える高貴な立場(皇女)であり、威圧的だったり強引だったりするところはあるものの、とにかくチャーミングでぜんぜん高慢には見えないのが面白いと思う。
当時のジェンダーバイアスがいろいろ出てくるが、自ら考え実践すること(つまり学問)によってそれを克服できる可能性が高まる、と何度か示唆されている。物語全体に「学問が生み出す希望」が通底しているのが良い。
今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』
https://www.chuko.co.jp/shinsho/2023/05/102756.html
オノマトペの発達心理学的および言語学的研究から、人間が言語を獲得する仕組みや、言語というシステムそのものが発達・進化する仕組みをまとめたもの。自分たちが何気なく使っている言葉について深く考えることはまずないが、たった一語を発するのにどれだけ複雑な処理を行なっているのか、改めて考えてみると途方もないことをしているのかもしれない、と思える。また、AIや動物との比較から、言語の身体性、思考の拡張性(本書でいう「アブダクション推論」)など、人間の人間たる由縁のようなものも見えてくる。
オノマトペはだいたいが音声を写し取ったもので、身体的(感覚的)に理解しやすい。実体のない抽象的概念は表現できないが、言語そのものの進化の段階で、オノマトペが副詞的に使われるようになり、さらに名詞化・動詞化して語彙が増えていったというのが面白かった。
神林長平『アグレッサーズ 戦闘妖精・雪風』
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000021586/
シリーズ第4作。
巻が進むにつれ、主人公の戦いが戦闘機による戦闘そのものより哲学的・思索的になっていくのを面白く読みつつも、アクションが物足りないという気持ちはなくもなかった。この巻にして新たなキーパーソン(攻撃性マシマシ)が出てきて、ド派手なドッグファイトに突入したのでテンション爆上げですわ。やっぱり空戦のスピード感たまんねぇなァ!
(そんなアクションシーンを堪能していてふと思った。「身体性が実存を保証する」というテーマが第1巻から繰り返し出てくるが、機体操作アクション(パイロットが五官で確認する事項)がしつこいくらい詳細に描かれることすら、「実存」の保証であったのでは…?)
このシリーズでは、ちょっとどろっとした闇を描いたあと、突如パラダイムシフトが起こって世界の見え方がガラッと変わる瞬間がしばしばある。その反転の鮮やかさがつくづく気持ち良い(悪い方向にガラッと変わる時もあり、それが物凄くホラーで泣きそうになるが…)。
遠藤ケイ『熊を殺すと雨が降る 失われゆく山の民俗』
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480422880/
内容は面白く、別に読みにくい文体でもないのに、何故かなかなか読み進められず数年かけてチマチマ読んでいた本。
杣、猟師、炭焼きなど、山での生業が丁寧に紹介されている。淡々としているが取材対象への敬意や情を感じる文で、差し挟まれるスケッチのリアルさには度肝を抜かれる。
圧巻は熊猟についての部分で、仕留めるのに骨は折れるが、捨てるところがないとか、現金収入になりやすく集落全体で恩恵に与ることができるとか、漁村における鯨と同じような存在らしい。あとはやはり、終章の「山の禁忌」(口伝、言い伝え)が面白い。
副題にあるように、初出の1992年時点で既に「失われゆく」ものであったということは、そこから30年経過した今では残るものも更に少ないのでは。自分の命を賭けての生業だからこそ、相手となる自然にきちんと礼節を保って真剣勝負をする、それが過分を防ぎバランスを保っていたのだろうが、時代の変化は止めようもない。せめて敬意を払うことを忘れないようにしたい。
小野美由紀『ピュア』
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000614429/
性暴力の被害者はずっと軽んじられていて、未来においてもそうかもしれないと示されるのはつらい。しかし、そうならないようにという希望の形として、怒りを表明せざるを得ないのだと思う。
ゴア表現や性表現がかなり露骨(痛覚に訴えてくる系)なのと、テーマ上仕方ないがミサンドリーに感じる部分も多く、読むのがきつかった。テーマは明快で、性差からくる理不尽や不均衡などへのかなりストレートな批判。ギャルっぽい語り口の軽さで物語世界の歪さ、グロテスクさが際立つのは面白いが、一方で、ギャル語に若干「古さ」を感じもしたので、時代性が出る表現は諸刃の剣だなぁ。
テーマ性よりも設定のユニークさを楽しむタイプの SFだと思う。性自体を否定しているわけではないし、性を超えた結びつきを書きたいのは分かるが、人物造形がわりとステレオタイプだったり、思春期少女同士の独特な執着を同性愛に単純化しすぎていたりするようには感じた。潔癖さが見え隠れするので、ティーン小説を読んでいる気分になった。
キム・チョヨプ『わたしたちが光の速さで進めないなら』
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000614654/
SF短編集。どの話にも、どこかしらで「ままならない」という感想を抱いた。失って戻らないものが頻繁に出てくる。物語世界では人間は時間的にも空間的にも大きな距離を移動できるようになっているが、そのように遠くまで行けるようになった世界では、喪失はより大きいのかもしれない。
デビュー作の『館内喪失』が叙情的かつ繊細で良かったが、印象に残ったのは『感情の物性』。感情を物体化し、手で触れたり身に着けたり部屋に飾ったりできる雑貨にしたものが発売されて話題になるというストーリーで、近未来どころか技術的には現代に有り得なくもなく、SFとくくるのすら迷う。どちらかというと純文学っぽく、小説として面白いかというとそれも微妙だが、感情を「身体性」で捉えようとする試みは興味深く感じた。
小島瓔禮『蛇の神 蛇信仰とその源泉』
https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000063/
日本を中心に世界各地の蛇にまつわる民話・神話・伝承・風習などを集めたもの。ボリュームは軽めで読みやすいが、八岐大蛇やレヴィヤタンなど英雄譚で有名なものはあまり出てこなかったり、島嶼地域の話には出てきそうなウミヘビについては言及がなかったり、ちょっと物足りなさはある。神聖視するにせよ敵対するにせよ、蛇は基本的に人間の理解の及ばない(与しない)「他者」として存在する、というのが主題のようだが、そこに収斂するような論考ではなく、さまざまな事例の紹介という感じ。
とはいえ、雑学好きとしてはかいつまんで色々な話を知れて良い。特に、蛇遣い(いわゆる「憑き物」としての蛇)の話や蛇除けの呪文など、人間の生活に密着した話は興味深く読んだ。
神林長平『グッドラック』『アンブロークン アロー』
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000610540/
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000610541/
『戦闘妖精・雪風』の続編2冊。内容的に一気読みせざるを得なかったが、一気読みして内容の濃さと分量にちょっと死にそうになってるゼェハァ
得体の知れないエイリアンとの戦いを通して、第1作から一貫して「人間とは何か」「自分とは何か」というテーマを描いている。自分以外はどうでもいいと嘯いていた主人公が、他者との繋がりを認識するなかで自分を再発見していく。その過程は難解かつ劇的で、脳を激しく揺さぶられるような展開と表現に翻弄される。特に第3作で主人公たちが翻弄される時空間の歪みの描写は圧巻。
詳細すぎる戦闘機の起動や操縦アクションの描写、超スピード&ド迫力のドッグファイトなど映像的に楽しめる部分も多いが、やはり、コミュニケーションが重要なテーマなのもあって、長大な思考実験的会話が、かなり難解だが面白い。
第1作のラストでは他者とは分かり合えないという絶望を感じたが、第3作のラストでは他者との関係性に強い希望を抱いている。まだ物語は続いているが、この先どう着地するのか楽しみ。
この本をテーマにした読書会に参加した。
自分は単純にパーソナルな観点で、モノのように扱われてきた主人公が、その苦しみから逃れようと自らモノになるのを望み、その手段として拒食を選んだのではと見たが、会全体では、「肉」を「暴力」特に家父長制に基づく暴力と捉え、それへの抵抗としての拒食。或いは文字通りの「生命」と捉え、自分や家族(特に戦争で人を殺した父親)、人類普遍の罪を贖うための拒食、という見立てだった。
これはたぶん、作品の主題が第1章にあると見るか、第3章にあると見るかの違いで、自分は後者と見たからだろう。
第3章は、主人公の姉が語り手になる。この姉は主人公が上手く社会に適応した場合のモデルケースだ。適応できなかった主人公は、世間的には「狂った」ので社会から離脱できてしまうが、姉は、子供と妹の保護者として正気を保つよう努めなければならず、狂うことも逃げることもできない。大半の女性はこの「姉」だと思う。実は、姉も肉体を損いながら「肉」に対抗して戦っているのは同じで、妹とは戦い方が違うだけとも言える。
戦いに疲れ切った姉の姿は痛々しいが、ラストで彼女からあふれた漠然とした怒りは、妹(暴力への諦観)を救う希望であると思う。
ハン・ガン『菜食主義者』
https://chekccori-bookhouse.com/product/菜食主義者/8972/
読んでいて文字通り心身に痛みを感じて涙が出た。肉食をやめ、食べることそのものも拒否して「植物」になろうとする主人公の女性は、いろんな痛みを感じなくなりたかったのかもしれない。
短編集として読めるが、3章構成の長編として読むとだいぶ印象が変わる。表題作(第1章)単体では、肉食を拒むことで息苦しい社会を脱しようとする主人公の孤独。通して読むと、模範的な女性像でありながら主人公と同じ闇を抱える姉の内面の吐露から、女性が女性として生きることの困難を思う。
一方で、女性を抑圧する側の男性のコンプレックスも見える。「自分にとって脅威にならないから」主人公と結婚した夫。妻に依存しつつ凡庸な芸術家もどきとして燻っている姉の夫。しかし、この小説の男たちは結局暴力で女性を押さえつける。それでしか女性に「勝てない」のだろう(家父長制の象徴のような父が殴ったり怒鳴ったりするのも、それしか子供と接する方法が分からないせいでないか)。
物語としては第1章と第3章だけでも十分だが(第2章は生理的に抵抗感のある内容でもある)、第2章で男性側の弱さと狡さが描かれることで、主人公が希求するものがより純粋になっている気がする。
安東能明『蚕の王』
https://www.chuko.co.jp/bunko/2024/11/207575.html
『冤罪と人類』の記憶が薄れないうちに。作者自身が二俣事件のあった地域の出身で、実在の関係者に取材しているので限りなくノンフィクションに近いが、あくまで小説であることに注意しなければいけない。この作品がそうと言いたいわけではないが、「たとえ作り事でも尤もらしいストーリーであれば人は信じてしまう」のが、この冤罪事件の肝なので。
ただ、そうは言っても血が上るのがわかる程度に、作中の警察官や裁判官の言動には腹が立った(ニュアンスは付け加えているにせよ、セリフ等はほとんど資料の引き写しのようだから、ほぼ実際の通りだろう)
臨場感ある表現で書かれた文章によって、「拷問王」のカリスマと歪さが際立つ。人倫に悖る方法で手柄を挙げる一方で、面倒見が良く快活な人柄で部下に慕われていたという二面性には、世間で評判のよくない有力者が、実際に顔を合わせると会った人を魅了してしまうという話を思い出した。
自分は土地勘や事件の経緯などの予備知識がわりとある状態で読んだのと、人物造形等はほぼ資料通りという点で、小説としての是非は判断しづらいが、冤罪が少数者の思い込みで簡単に生み出される恐ろしさを知るには良い作品だと思う。
#読了 # 読書
菅賀江留郎『冤罪と人類 道徳感情はなぜ人を誤らせるのか』
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000613688/
有名な「二俣事件」と、その捜査に大きな影響を及ぼした「浜松事件」を中心に、戦中から戦後に静岡県で続発した冤罪事件についての論考。膨大な資料による力作で、犯罪プロファイリングの先駆者・吉川澄一の話などは面白く読んだが、余談に逸れやすく、衒学的でかったるいところも多かった。
一連の冤罪事件は「拷問王」と呼ばれた某刑事たちによる現場の暴走とかいう単純な話ではなく、当時の社会情勢、組織間の関係性(権力勾配や面子)、政治的野心や虚栄心など、さまざまな歴史の糸が絡まり合って起こったものらしい。
ただ、警察や検察にしろ、弁護士や裁判官にしろ、事件地域の住民にしろ、犯人を憎む心は同じで、その根底には「被害者への共感」や「正義感」という真っ当な感情(著者のいう「道徳感情」)がある。しかし、偏った考えに固執し、それにそぐわない情報を無視したり捻じ曲げたりしたとしたら、それはもはや真っ当ではない。無罪確定後も、犯人とされた人やその家族の多くは「悪人」として村八分にされ続けたそうだ。犯人逮捕までの不安や恐怖ゆえだから同情はするが、こういう行き場のない報復感情ほど怖いものもない…