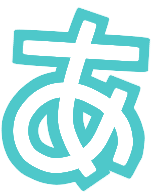#ノート小説部3日執筆 書きました〜。期末テスト最終日の男子学生二人が、不思議なパン屋さんに入る話です。お題→真夏日
【陽炎のパン屋さん】
その日は期末テストの最終日で、昼のうちに学校から出ることができた。
「なー、何処行く? ファミレス? 鯛焼き屋?」
「うーん……」
いつも一緒にいるクラスメートの言葉に、僕は唸った。テストで頭を使ったし、お腹も空いた。何か食べたいけど、僕は何を食べたいんだろう。
「ん? ……何だろう、あれ?」
いつもの駅への道すがら、彼が路地の向こうのその店を見つけたのは、そんな時だった。その店は、開店したばかりのようで、お祝いの花がいくつも置かれていた。
変わっていたのは、その花を差出人の名前。「せせらぎ川のカワウソ村長」とか、「梅林のメジロおばあさん」とか……。ついでに言えば、お花も、川べりに咲きそうな野の花だったり、この時期には咲かない梅みたいな花とか。
「なんか、かわいいな。ファンシーなお店だ」
「何のお店だろうね?」
辺りを見回しても、看板らしいものはない。何屋さんか、わからない。
「……でも、なんか、美味しそうな匂いしねぇ?」
「ほんとだ。パン屋さんかな……?」
何やら、こんがりと焼き上がるような匂いが漂ってきた。その匂いにつられて、僕達はドアを開き、店内へと入った。
「……おお! すげー!」
そこは、本当にパン屋さんだった。美味しそうなパンが、いくつも並んでいる。でも……。
「……此処、良い匂いはするのに、人の気配がねーな?」
確かに。パンはいっぱいあるし、値札もあるのに、肝心の店員はいない。……もしかして、無人販売ってやつなのかな。個人経営のパン屋さんなら、あり得なくはない。お店自体も小さいし。
「ああ、なるほど。……お、ほんとだ。レジのところに、自分で計算してお金をピッタリ入れてってくれ、ってある」
ふむふむと彼が納得する様を見つつ、僕は財布を取り出した。うん、小銭もお札もいくらかある。
「あ、そっか。お釣りは出てこないから、全部ぴったりに出さなきゃならないんだよな」
彼もいそいそと財布を取り出した。さて……僕はどれにしようかな? 美味しそうなパンを前にしてると、いくらでも食べられそうな気がする……。
「お前、随分買ったな―! って、俺もだけど」
「うん」
手持ちのエコバッグに入れたパンを、僕は嬉しげに見つめた。だって、どれも美味しそうだったし。
というか、僕が食べたかったのは、こういう、パン屋さんのパンだったのかもしれない。現に、お腹が空いてたからとはいえ、こんなにたくさんのパンを買ってしまった。
「それにしても、不思議なお店だったな。人の気配は全然なかったけど、良いのかなあ。不心得者に盗まれたりしないのかな――」
彼が来た道を振り返り、固まった。僕も振り返った。
目を、丸くした。
「……ない。さっきのパン屋さんがない!」
路地の向こうにあったはずのパン屋さんは、ただの空き地となっていた。あそこには確かに、パン屋さんがあったのに。
手元には、パンがある。焼き立てのパンだ。さっきにあのパン屋さんで買ったパンが。
……パンはあるのに、パン屋さん自体がなくなってしまった。
真夏日の炎天下で、僕達は、呆然としてしまった。
――夏にしか見かけない、不思議なパン屋がある。
路地の向こう、家と家の間の空き地、空き家と化した家……そこに、いつの間にか開かれるパン屋だという。
パン屋を開くのは、パンを焼くことが大好きな魔法使い。たくさんのパンを焼き、お客を待っている。
人の気配がないのは、姿を現したらきっと、お客をびっくりさせてしまうから。
店が消えてしまうのは、定期的に場所を移動する魔法を、店自体にかけているから。
開店祝いの花が変わってるのは、魔法使いと付き合いのある動物達からのものだから。
そのパン屋は、真夏の陽炎のように移ろい、消えていく。人々の記憶の中にだけ、その存在を残す。そんな店なのだと、言われている。
#ノート小説部3日執筆 #一次創作 $[font.serif 昨夜の梅雨に貴方を抱いて]
僕たちの今日は雲の形状で、積みあがった入道雲ではなく、東へ向かっていくつもの塊が走っていく速さだ。それは梅雨の晴れ間の真夏日に担任教師から押し付けられたプール掃除、僕たちの人生に選択肢はない。そのくせ自分で手を動かさないと明るい未来も無いので、こうして水の抜かれたプールの底をブラシでこすり続けることになる。
炎天下にホースの先を指で潰して水を好き放題まき散らせるのは若さの特権なのだろう、一瞬の微かな虹を自分で作れると信じてひたすら虚空に散水すると、太陽光にきらきら、白い体操着にパタパタと水滴が舞ってそこだけグレーが濃くなる。
「お前、着替えないんだからやめーや!」
水をかけられたハシダがケラケラ笑って、ホースを持ったプールサイドのソエジマをブラシの先で擦ろうとする。
「無理無理無理! マジでやるよ、ずぶ濡れよ!?」
ソエジマが嫌がってハシダの足元にピシャリと水の鞭を打つと、ハシダは慌ててプールサイドから離れる。いっこうにプールの底は掃除されない。
「なあ、水こっちにかけてくんねーかな? 葉っぱこびりついてんだけど」
呆れた表情で汗を拭くサカキがブラシでプールの底にべったりくっついた茶色い枯葉を小突く。するとソエジマはホースの角度を高々と掲げて、枯葉に向かって大きな放物線を描く。慌てたサカキが身をよじってそれを避けると、ソエジマは放物線の狙いをサカキに向かって動かす。
「はいサカキさんお届け物でーす!」
「お前ふざけんな止めろ!」
ソエジマはニヤニヤ水をかけ続けて、それを怒るサカキを見てハシダがゲラゲラ笑って、水しぶきはプール全体に広がって、水滴のプリズムが虹色のカーテンを引く。太陽が照り付けるプールに水蒸気の湿度ばかりが濃くなっていくけれど、ときに風が僕たちに忖度するみたいにさわやかな風を送ったりするのだった。
僕はソエジマの背後の休憩スペースでブラシを持ったまま、プール掃除が本格的に始まりそうになるまで待っている。休憩スペースのトタン屋根はほぼ真下に影を作って、ベンチに座る僕の素足のつま先にくっきりと明暗を描く。火傷しそうな日なたのプールサイドに出るのが億劫だな、と日陰に引きこもっていると、担任のタカギ先生がサンダル姿で僕らの見回りにやって来た。
「あれ、タカギ先生スカートで掃除すんの?」
ソエジマが言うと、タカギ先生はしかめっ面で返事する。
「わたしがするわけないでしょ、はよやれ」
そう言って、タカギ先生はパタパタとサンダルを引きずりながら休憩スペースにやってきて、僕の隣に座った。
「体調悪いのか、スガノ」
その問いに、僕は首を振ったあと答える。
「暑いんすよ」
「そんなのみんな一緒だろ、やんな、単位の代わりなんだから」
そう言って僕のブラシをサンダルで蹴り小突くタカギ先生に、僕は上目づかいで笑ってみせる。
「立場を利用したハラスメントですよ、先生」
「そういうのは真面目に勉強してから言え」
腕組みするタカギ先生の、半袖のブラウスから除く白い腕を、僕は指で軽く撫ぜる。その指をタカギ先生は羽虫を払うように手の甲で打ってみせる。
「やめろ」
「なんで? 昨日の夜はあんなに喜んでくれたのに」
昨晩はタカギ先生に包まれて、タカギ先生をたくさん抱きしめた。タカギ先生の部屋の匂いはいつも学校で通り過ぎるときに香る臭いよりも濃厚で、鼻腔から入って体の奥にこもった熱の蓋をこじ開けられるような、とても魅力的な蒸気だった。静かに街を満たすような梅雨の雨は僕たちを世界に二人きりにして、ただひたすら互いの躰を求めあった。永遠のような夜を、眠ってしまうことで朝にしたくなかった。
「人前だろ、ばか」
朝になり昼になっても、日差しの下でタカギ先生の耳元が紅くなっていたのがはっきりと見てとれたけれど、それは真夏の気温のせいかもしれない。僕たちに目もくれず、ハシダもサカキもソエジマも、空っぽのプールではしゃいでいる。
「ほら、見てないよ、あいつら」
僕が微笑んでみせると、タカギ先生は眉根を寄せて僕を睨みつけてきた。それはなんと言えばいいのか、僕を責めるような、それでいて寂しそうな表情だった。
「私に犯罪者になってもらいたいのか」
タカギ先生の言葉に、僕はゆっくり微笑んで見せた。
「それは嫌だな、確かに」
僕の言葉にタカギ先生は、はしゃぎまわるハシダ達に向きなおって、ゆっくりとため息をつく。抱きしめてあげたいと思うほどにいじらしいタカギ先生だったけれど、いま僕がそれをすれば今度は僕が学校に居られなくなる。
「もうすこしだよ、待ってて、僕の青春が終わるまで」
僕が言うと、タカギ先生は俯いて、目元をこすって深呼吸した。
「わたしの青春もこんな風だったらよかったのに。スガノと同い年の青春が良かった」
そう言ってタカギ先生は立ち上がると、僕の襟元をつかんで無理やり立たせてみせた。
「わかったよ、やるよ、掃除するよ」
僕が言うと、僕より少し背の低いタカギ先生はこちらを上目遣いに見つめる。
「待ってるからね。焦らず、急がず、でも、最短距離で迎えに来てね」
そう言ってタカギ先生は振り向いて、ハシダたちに向かって大声を張り上げた。
「てめえらいいかげんにしろ! ガキじゃねえんだからさっさとやれ!」
真夏日の炎天下で僕たちはありったけ水を撒いて綺麗な虹を作る。虹を若い日々に作りそびれた大人たちは永遠に憧れ続けるのかもしれない。僕はこの夏を悔いなく虹で染めて、この後の人生を背筋をまっすぐにして生きれるようにしないといけないと思った。
#ノート小説部3日執筆 にゃんぷっぷーとラノベ編集者の飼い主の話です(一次創作『子々孫々まで祟りたい』のキャラ奥武蔵がでできますが、知らなくてもまあ読めると思います)
にゃぷはかわいがられるのと、オタくんをほめたり応援したりするのがお仕事のにゃんぷっぷーにゃ。オタくんはにゃぷのために家のクーラーを効かせてお仕事に行ってくれるけど、今日の日差しはギラギラにゃ。オタくん、大丈夫かにゃあ?
案の定、オタくんはぐったりした顔で帰ってきたにゃ。
「外回りが……多くて……死ぬかと思った……」
「大丈夫にゃ?」
「イオンウォーター飲むから……」
オタくんの手には、近くのスーパーの袋があったにゃ。オタくんは袋から出したでっかいペットボトルをぐびぐび飲んで、ひといきで8割くらい飲みきって息を吐いたにゃ。
「いや、暑いの本当に体力消耗する、今日筋トレできるかなあ」
「無理しないでほしいにゃ!」
「とりあえず、ご飯にしてから考えるね……」
オタくんはいつものナッシュっていうお弁当をレンチンしてくれて、2人でご飯にしたにゃ。
オタくんは暑いだけじゃなくてお仕事が大変だったらしくて、疲れた顔だったにゃ。
「担当してる作家さん、暑さとか気温変化でやられてる人多くてさ。大体がダブルワークだし、そういう人は寝る時間削ったり栄養のための時間削ったりが多いから、心配で」
「ぷにゃあ、みんな大変なのにゃ」
「作家さんって、書くほうが好きだから健康管理に使う時間がもったいない! みたいな人が多くて、でもそういう人長い目で見ると必ず体壊すからさあ……打ち合わせの度にnosh勧めたり水分摂取勧めたりスクワット勧めたりして、最低限の健康管理してくださいって言ってるんだけど……」
「編集者ってそんなこともするのにゃ?」
「前、サブ担当してたベテラン作家さんが不摂生の果てに突然亡くなったことがあって、それから気をつけてって言いまくってるねえ」
「ぷにゃ!?」
そんなことあったのにゃ!?
オタくんはため息をついたにゃ。
「その作家さん、食べるの大好き、アルコールも大好き、って人だったから夏の暑さとは関係ないんだけどさあ。生きるだけで厳しい季節が夏だし、作家やるような人は不摂生になりがちだし、体壊したら書きたいものあっても書けなくなっちゃうし、本当に気をつけてほしい」
「ぷにゃあ……」
にゃぷは口ごもったにゃ。そういう人を元気づけてあげたいけど、にゃぷには何もできないにゃ。
「だからさ、せめて俺が担当してる作家さんには、健康管理、口酸っぱく言っとこうと思って。にゃんぷっぷー、今日もひとつ応援と褒めを頼めない?」
あ、そっか! にゃぷは他の人には特に何もできないけど、他の人を応援するオタくんのことは応援できるのにゃ!
「オタくん、フレーフレーにゃ! オタくんは作家さんのことを考えててとっても偉いのにゃ! オタくんならきっと作家さんをとっても応援できるにゃ!!」
にゃぷはペンライトを両手で振ったにゃ。
にゃぷは、かわいがられるのと、オタくんを褒めたり応援したりするのがお仕事のにゃんぷっぷーにゃ。なかなか、やりがいのあるお仕事にゃ。
#ノート小説部3日執筆 「アイスを買いに」お題:真夏日
8月某日、理性は限界を迎えた。現在時刻12時、外気温33℃の真夏日、人間が外出するなんて到底考えられないような日だからこそなのだろうか、アイスが食べたくて仕方がない。もう二度と外出はするまいと、両手いっぱいに買い込んだストックは5日前に底をつき、なけなしの氷をかじることで何とか耐えていたが、もう限界だ。今すぐアイスを食べないと死ぬ。幸いにも、最寄りのコンビニまでは歩いて10分ほどなので、仕方なく準備をして出かけることにした。
「暑い、死ぬ……」
歩き始めてまだ30秒も経っていないが、早くも家から出たことを後悔した。前から感じていたのだが、気温があまりにも高いと、汗が蒸発して体を冷やすという機能が意味をなさなくなる。そして日差しが痛い、暑いとかではなくて痛い。テレビで流れている日焼け止めのCMには縁がないと割り切っていたが、どうやら考え直す必要がありそうだ。
そんな感じで、歩く死体のように歩を進め公園の前を通りかかったとき、公園のブランコに座っている一人の男の子が目につく。夏休み真っ盛りの時期であるはずなのに、彼はランドセルを背負いブランコを漕ぐでもなく、ただ俯いていた。このままではアイスどころではないので、自販機で飲み物を買うついでだ、と言い訳をしながら少年のもとに向かった。
「ねえ、君。どうしたの?」という問いに、少年は「なんでもない……です」と下を向いたまま答える。彼はこちらのことを見ようともしないが、話しかけてしまった手前、このままでは引き下がれない。彼が熱中症になるのだけは避けねばならない。
「兄ちゃん暑いの苦手でさあ、アイス買いに家から出てきたんだけどさ、少し歩いただけで汗ビッショリで大変でさ」
「で?」
「えーと……だから飲み物でも買おうと思ってさ、君も何か飲みたいものある? 暑いし熱中症になったら大変でしょ?」
「悪い人?」
「違う! 違う! 別に君をどうこうするつもりは一切無い! ただ君が暑さで倒れたりしないか心配なだけだよ! 」
「……何でも選んでいいの?」
「良いよ! そこの自販機にあるやつなら何でも買ってあげる」
少年にこちらの敵意が無いことが伝わったのか、彼は「それなら」と自販機へと歩き出した。そして、180円のスポーツドリンクを指差し、僕の前でピースをした。「2本ってことね」と小銭を投入する。結局、自分のと合わせて計3本のスポーツドリンクが受け取り口に落ちた。注文された2本を手渡すと「ありがとう、ございます」と少年が少し微笑みながら礼を言った。
少し歩いたところにあった木陰で、飲みながら休憩をとる。彼も警戒をある程度は解いてくれたようで「さっきの質問さ」と話し始めた。
「俺、学校行かなきゃならないんだ。今日」
「やっぱりそうか、そうなると夏休みの宿題とか?」
「まあそんなとこ」
「じゃあ急がなきゃいけないんじゃないか? 先生とか心配してるだろうし」
「そうかもね、まあいいでしょ。まだ時間はあるし」
そう話す彼は、余裕たっぷりといった感じで、良い意味で小学生らしくなかった。その後、蝉の声がうるさいとか、大学生の夏休みは2ヶ月あるんだぜとか自慢をしていると「そういや」と言いながら少年は空になったペットボトルでこちらを指し「買いに行くんでしょ! アイス!」と彼は今日一番の元気で、こちらの用事を思い出させてくれた。なんとなく嫌な予感がしながらも聞き返す。
「……食べたいのか?」
「うん! あの、2本になるやつ」
キラキラとした目でこちらを見つめてくる若さが、断るという選択肢を無くしてしまった。もうなんとでもなってしまえ、と思いながら、彼を連れて本来の目的であったコンビニへと歩き出した。
結局、彼を連れて買い物をした。彼はあれだけ元気に宣言していた割に、買いたいものも欲張ることなくすんなりと決め、こちらもそれを受け取り自分のものと合わせて会計を済ます。コンビニ内で声をかけられなかったのは不幸中の幸いだった。そして、コンビニの外で、彼のアイスを渡し「バレないように食べるんだぞ」と念を押して別れようとしたとき「待って!」と少年が、こちらを呼び止めた。
「これ!」
そう言って彼は、2本に分けたアイスの1本をこちらに差し出した。
「いいのか? 2本を一人で食べたほうが美味いぞ?」
「いい! 兄ちゃんが買ってくれたやつだし、それに、俺のこと見つけてくれたし」
「あんだけ目立ってれば誰でも分かるよ。それより、気をつけてちゃんと学校行くんだぞ! 水分補給もしろよ、あと」
「分かってるよ! もう行くね、ありがとう! ばいばい!」
そう言って少年は道を駆け出していった。台風みたいなやつだったなと思いつつ、こちらもアイスが溶ける前に帰らなければと走り出した。
帰り道、彼と出会った公園の前に、一人の女性が立っていた。もう走るのも限界だったので、歩いて挨拶をしようとしたとき、彼女が話しかけてきた。
「あの、今日、すごく暑いですね」
「そう、ですね」
「アイス、買われたんですね」
分かってるなら引き止めるなよ、という叫びをグッとこらえて「ええ」と答える。
「その、左手に持ってるやつ。息子が好きだったんです。それで、それを思い出して話しかけてしまって。すいません」
嫌な予感がする。そして、今日はそれが当たる日だ。
「失礼ですが、その息子さんは……?」
「事故にあったんです……今日みたいな暑い日に。それで……」
「そう……ですか。すみません、辛いことを聞いてしまって」
「謝らないでください、私が勝手に話し始めたことですから」
その後、互いに気まずい沈黙が流れるが「そうだ」と彼女がまた話し始めた。
「約束してたんですよ。あの子と」
「それは、どんな」
「そのアイス食べようねって、帰ってきたら二人で」
そう言って僕の左手にある、彼とさっき分けたアイスを指差した。
「今から買いに行かれるんですか?」
「ええ、あの子もきっと喜ぶでしょうから」
そして、彼女は「聞いてくれてありがとうございました」と言い残して去っていった。
家についた頃、買ってきたアイスはほとんど溶けてしまっていた。まあ仕方がないか、と自分を慰めて冷凍庫に戦利品を詰め込む。そうやって整理していく中で不思議なことに気がついた。彼と分けたアイスは、何故か溶けることなく残っていたのだ。きっと彼からのお礼だろう。
アイスの蓋を千切って食べ始める。まだちゃんと凍っているみたいで、吸い出すのに少し苦労した。食べながら少し天井見上げ呟く。
「良かったな。今日は2本も食べれるらしいぜ」
一人で食べるそれは、いつもの2倍美味しかった。
(ミスあったので再投稿)【お題 真夏日】『暑いですね』#ノート小説部3日執筆
夏は暑いから大嫌いだ。とくに、35℃を超えるような真夏日は外に出ることすら億劫である。
しかし、幸か不幸か真夏日が連日続くような時期には夏休みがある。私はその夏休みを有意義に過ごすことも無く、ただ冷房の効いた涼しい自室でダラダラ過ごしていた。友達も多くない。それ故、LINEが届くこともない。虚しい時もあるが、そんな虚しい気持ちになった時は寝ることで誤魔化している。
そんなある日だった。たしかそれは夏休みも中頃に入った頃。1人の数少ない友人からLINEが来た。一緒に遊ばないか?というメッセージにいいよ、と返信する。すると彼は『日程も時間も言ってないのにいいのか?』とメッセージ上でも分かる。呆れている。私は『どうせ暇だし』とだけ返せば、日程と時間、そして概要が送られてくる。どうやら彼とその友人を集めて百物語をするそうだ。怪談話か。面白そうだ。どうせ暇な毎日。参加しないという考えはなかった。私はそう彼に伝えると、彼はありがとう!また連絡するよ!と私に送った。
百物語が行われる当日。どうやら彼の友人の両親が経営している旅館の一室を借りて百物語をするらしく、かなり雰囲気だけはそれっぽくなっていた。夜中の20時から始まった百物語。10人の参加者が10個怪談話をする……というコンセプトだ。私も10個の怪談話を持ってきた。……上手く話せるかは別だが。
様々な話を聞いて、喋って。そろそろ100も近くなってきた頃。怪談話で冷えた肝は、体温も低くしていた……はずだったのだが。妙に暑いのだ。主催の友人に暑いと伝えたが、皆はそこまででは無いようだ。98個目の話が終わった時、私は冷や汗ではなく暑さによる汗をかいていた。皆があの話は怖かったと話す度に私は暑くて気が狂いそうになったのだ。そして99個目の話は私が担当だった。本来は持ってきていた話を話す予定だったのだが、当時の私は本当に暑さで気が狂っており、即興で話始めたらしい。今から話すのはその時の話を友人から聞いたものだ。
「真夏の夜って酷く暑いですよね。今、怪談をしているというのに私はとてもとても暑い。肝は冷えるのに身体は熱い。例えるなら湿度の高い所に長袖で放り込まれたかのようで、気持ちいいとは到底言えないのです。今から話すのはなんてことない話です。ただ、暑いだけ。暑くて暑くて仕方ない私の話です。冷えた肝に少しでも暑さを届けられたら幸いでございます。そう、これは2週間ほど前の話でしょうか。その日の夜も、今日のようにとても暑かったのを覚えています。暑さに耐えきれなくなった私はコンビニに行きました。あまり人のいないコンビニは涼しく、とても快適だった。そのコンビニで何かを買おうと商品棚を見つめていたら、とある女性に話しかけられたのです。その女性はこんな暑い時期に何故か長袖で、その真っ黒な服はまるで喪服のようでした。そんな中、女性は私にこういうのです。『暑いですね』って。そりゃあ、貴方のような長袖を着ていたら暑いでしょう?当然です。私は『はぁ』とだけ言って女性との会話を強制的に終わらせました。女性はピクリとも顔を変えません。私はなんだか嫌な気分になって適当におにぎりを買ってコンビニを出ました。しかし、途端に寒くなってきたのです。先程まで暑かったはずの外が、寒くて寒くて仕方ありません。私は急いで家に帰りました。家も寒いです。なんでこんなに、なんでこんなにと。真夏日のはずだと。冷房を切り、暖房に付け直す。それでもまだ寒い。寒いのです。私は長袖を着ました。買った覚えのない長袖でしたが、とても暖かい長袖が丁度あったのです。それは真っ黒な服でした。その服を着ると寒さが無くなるのです。むしろ、暑くて暑くて仕方がない。その服はまるで、喪服のような服でした。ああ、そうです。私が今着ているような。ねぇ皆さん、『暑いですね』」
#ノート小説部3日執筆 【真夏日の余命】お題:真夏日
日本列島に居座っていた梅雨前線が失せた頃、友人はやってきた。ごめんください、と玄関の戸をガラガラと引いて現れた友人はカンと冴え渡る青空と、いっそ死を賜ろうかと言いたげな直射日光を後光として背負っている。
「相変わらず夏を連れてくる御仁だね、君は」
早朝にも関わらず茹だるような暑さを寄せ付けまいとする私の右手には団扇。ぱたぱたとそれで己を煽りながら、私は友人を迎えた。
「ここに来る途中で出会いまして。道に迷っていたようですから」
「まぁだ真夏日には早いんじゃないの」
「昨年よりかは夏らしい時に来たと思ってくだすれば」
失礼、と敷居を跨ぎ、友人が家にのそのそと入ってくる。その右手にはどこで誂えてきたのだろう、向日葵の花束が抱えられていた。
友人を土間から上がらせ、くつろいでいた居間へと通す。恐縮しながらソファに腰掛けた友人に麦茶を出しながら、私は扇風機のスイッチを親指で押した。ぶぅんと唸りながら水色の羽が勢いづく。
「しかし真夏日もあまり出しゃばれない様子で」
「へえ。なんで。ここ数年、夏と言えば恐ろしく暑いじゃないか。冷夏なんてくたばっちまってるよ」
「それです。暑すぎるんですよ」
出された麦茶入りのグラスを持ち、友人がグッと呷る。ここに来るまでに連れ立った夏の暑さのせいか、グラスはすぐに空になった。こつと音をさせ、グラスを置いた友人は生気をやや取り戻したらしく、改まった顔を私に向ける。
「真夏日とは」
「うん?」
「真夏日とは、最高気温が三十度以上のことを指します」
「そうだね」
「ただし三十五度以上は、猛暑日となります」
「……つまり、三十度以上三十四度以下が、真夏日の定義だと。なるほど」
私の返答に友人は重々しく頷いた。
「つまり、夏が盛りになるにつれて勢いづくのは猛暑日でしょう」
「ははあ、だからあまり出しゃばれない、か。私らにしてみたらどっちにしろ、いい加減にしろとしか言えないんだけども」
私は麦茶の入ったピッチャーを傾け、友人のグラスに注ぐ。網戸が外の熱気をある程度は防いでくれるが、土から出たばかりの蝉の叫びは元気に耳に飛び込んでくる。
「なので私どもは考えました」
「…………」
友人が己のことを〝私ども〟と自称する時。だいたいロクでもない事がやってくる。友人の言う〝私ども〟は己であり、そしてその背後に蠢く、何か――私のような一市民には到底触れることの出来ぬ何か、だ。それらが、この暑さに音を上げている。これ以上先は聞きたくないのが本音だが、私はあの忌ま忌ましい奴らが、夏の暑さにやられてドロドロに溶けかけていることを想像して思わずニヤついてしまった。
「いちど海を凍らせてみようかと」
「やめなさい海の家が泣くぞ」
私の制止に友人がふむ……と神妙に俯く。彼の背後では〝私ども〟の〝ども〟の部分が新しい解決策を模索しているに違いない。
からん、とグラスの中の氷が鳴る。
ぎこちなく首を振る扇風機はぶぅん、と唸り続けている。
蝉は叫んでいる。土から出てしまった事を後悔しているようだった。
先ほどまで夏の日差しの陽光を背負っていた友人は、今やこの古家、うす暗く蒸し暑い陰惨とした居間で、項垂れ、考え込み、そして、言い聞かせるような声を発した。
「私どもは、真夏日を死なせたくないのです」
私はこの友人が持ってきた向日葵の花束から一輪、一際大きく明るく笑うそれを引き抜いた。古くさい家の中でそれはさんさんと輝いている。今は無邪気に笑う、真夏日の申し子たるこの花も、猛暑日が続けば萎れて死ぬのだろうな、とふと思った。 #ノート小説部3日執筆
大遅刻申し訳ありません! 少しだけNSFW表現あります【#ノート小説部3日執筆 】『煙と歴史と吸血鬼』(お題:近代日本)
「煙草だよ!」
目の前の老人は、開口一番そう叫んだ。こりゃアカン。瞬時に悟り、わたしは営業スマイルを顔面にはりつける。さて、どこから切り込んだものか。
「あの……ナガノさんは、吸血鬼でいらっしゃるんですよね」
老人はグビグビと生ビールを飲み干し、ダンッっとビールジョッキをテーブルに叩きつけた。
「そうだよ! 永遠の『永』に乃木坂46の『乃』! いかにも吸血鬼だろ」
どこが「いかにも」なのかがわからない。ペンを握る手が震えてきた。が、ここで退いたら4歳の子役から102歳の老人まで話を聞いてきたインタビューライターの名が廃る。
「永乃さんは不老不死……みたいなことをですね、聞きまして」
「不老じゃねえよ! 普通にふけるのが遅いだけ!」
永乃老人は勝手に生ビール追加すると、マッチと煙草を取り出し、火をつけてスパーッっと一服した。
「吸血鬼が不老不死なんて誰が言いはじめたんだろうな。俺が言いたいのは煙草! 煙草の話なんだよ!」
しかし、こちらが聞きたいのは、「まさか日本に不老不死の吸血鬼が!? その奇妙な半生を語る」的な話なのだ。
「永乃さん、生年は?」
「黒船より前だな! そっからいろいろあってよう、今でいう蛤御門の変? で腕を斬られたんだよなァ。自分の血はまずいって知ったのはあのときだ」
何も入ってないセーターの左袖に目をやりつつ、吸血鬼らしいひと言がとれたことに安心する。
「あの頃はキセルをふかし合って、国の行く末がどうのって話し合ったもんさ。火をかしたりかされたり……」
そこで永乃老人が言葉を切った。
「この辺の話は辛気臭くなるからやめよう」
「むしろそこが聞きたいのですが……吸血鬼が見た幕末! なんて」
「あんた、本当にそんなことが聞きたいのか」
永乃老人の視線は、なかばあわれむようだった。その目に呑まれて、わたしは思わず考えてしまう。今、セブンスターのメンソールを持っている永乃老人の手。本当にこの手がかつてキセルを持ち、幕末の志士たちと語らっていたのだろうか。
「今のこれ」
永乃老人がひとさし指と中指で挟んで、煙をくゆらせる煙草を持ちあげる。そういえば、老人が出した唯一の取材条件は、「煙草を吸いながら酒が飲める取材場所」だった。
「紙巻の『シガレット』が入ってきたのは、明治に入ってからだな。舶来の包みがそりゃあしゃれていてよ、俺は夢中になった。文明開化の味がしたねえ」
老人によると、それまでキセルに詰めていたのは細く刻まれた煙草であり、柔らかな味わい。対して紙巻煙草は骨太な味がしたのだという。
「国内でも煙草がじゃんじゃん作られるようになった。俺はその配達員をやっていたんだな。俺ぁだんぜん、村井派だった。知ってるか?」
わたしは首を横に振る。
「明治にゃふたりの煙草王がいてよ。『国産、国益』を謳った天狗煙草の岩谷と、輸入もんを扱う村井兄弟商会の村井。このふたりが宣伝合戦を繰り広げたんだ。俺はしゃれたもんが好きだから、もちろん村井のもとで働いた。配達のための荷車を引くんだが……そこにドーンと」
永乃老人は、煙草を持ったままの右手で、大きく空に半円を描いた。煙とともに灰がパラパラと散るが、老人の表情は晴れやかだ。
「『ヒーロー』』やら『オールド』やら煙草の名前や包みが描いてあって、それを引くのが何より誇らしかった」
何か他のことを聞かねばならない気がする。が、わたしは文字通り煙に巻かれている。
「そりゃあもう、F1だよなあ」
「ん゛っ!?」
突然のことに、わたしは思わずウーロン茶を噴き出しそうになった。
「だってF1マシンって走る広告だろ。まあ村井の荷車はレースをしていたわけじゃないが……。俺はF1にも夢中になったね。マクラーレンの真っ赤な車体にマールボロのロゴ」
「その間にはいろいろありますよね、大正とか戦争とか」
ふたたび、老人があの目をして言った。「本当にそんなことが聞きたいのか」。
「聞きたいですよ。モボ・モガの時代とか、戦時中の話とか!」
さすがにここは食い下がらざるを得ない。
「明治の終わりごろ、煙草は専売制になっちまったからなァ。戦争って最近のほうか? 俺はこの腕だから戦地には行けなかったけどよ、あの最中は煙草どころじゃなかった。箱はインキの節約で一色になっちまったし、シケモクにありつければ御の字」
本気でこの時代のことは語らないつもりらしい。
「俺にとっちゃ、紙巻き煙草はしゃれていて憧れで、ド派手なもんなんだ。あんたわかるか、シューマッハとミカ・ハッキネンが……」
「はあ……」
とんでもないところに話が飛んだ。4本目か5本目かの紫煙の向こうから永乃老人はわたしをちらりと見やり、話の先を変えた。
「それでな、とにかく煙草なんだよ。いつの間にか『健康増進』っつってよ、F1では煙草の広告は全面禁止。マールボロのあのロゴがバーコードになって、そのうちなくなっちまった。信じられるか?」
「でも、仕方ないんじゃないですか。F1、今、アメリカですごい人気ですし」
煙草のロゴがド派手な広告だったと言われても、その時代を知らないわたしには、ちぐはぐな答えしか返せない。
「俺ぁいまでも信じられんよ。昔はいろんな俳優がCMでスパスパうまそうに煙草を吸っていたのに、いつの間にかテレビのCMは全面自主規制。いまじゃ煙草を吸いながら酒も飲めねぇ。この店だって、あんた、ずいぶん探してくれたんだろ。煙草は、もうハイカラでもなんでもねぇんだよなあ……」
わたしはしびれを切らした。
「で。永乃さんはどうやって生きてきたんですか? 吸血鬼として。血、吸わなきゃいけないんでしょ」
今度は永乃老人が、本気であきれた目つきをした。
「そんなこと、人に聞くか? あんた、どこでどうやってヤってるかなんて人に言わねぇだろ。『吸う』つって話せるのは煙草のことぐらいよ」
だったらなんでこのインタビューを受けた!? 吸血って食欲より性欲なの? という疑問を飲み込みながら、わたしは悟った。このジイさんは吸血鬼だなんて、人をかついでいるだけなのだろう。
知り合いの編集者が転職したオカルト誌からの依頼だったが、こんなインタビューを載せるわけにはいかないはずだ。言い訳を考えながら、わたしは勘定を済ませ、老人に礼を言って、店を出た。
もっとさんざんだったのはその後だ。インタビューからそのまま向かった編集部で、「ぜんぜんダメでしたよ」とICレコーダーを回してみれば、永乃老人の声だけが入っていなかった。ひたすらわたしの声と、店の喧騒だけ。
「吸血鬼って、声、録音されないんですかね……」
結局、巻末の小ネタを載せるコーナーに、「吸血鬼、声が録音されず!?」と小さな記事が載った。
***
煙に巻かれた気分も薄れてきたある日。わたしは通りすがった博物館の企画展に立ち寄った。「日本の喫煙史」の文字があったからだ。展示は時代を追っている。江戸時代、そして明治……。「明治の煙草広告合戦」のパネルには、荷車を引く人物が映っていた。ずいぶん粗い写真だが、法被姿のその人物は弾けるような笑顔を見せており――左腕がないように、見えた。
#ノート小説部3日執筆 でノート小説を書くにあたっての相談や質問ができる「Misskey.ioノート小説部」のDiscordサーバーも以下のリンクにご用意してあります。作品の批評や雑談のできるテキストチャットや、お題を自薦いただける会議部屋などもございます。わたくし小林素顔がサーバー管理者なのでお聞きになりたいことがございましたらお気軽にご参加くださいね!
https://discord.com/invite/ReZJvrqG92 [参照]
#ノート小説部3日執筆 第11回のお題は「真夏日」に決まりました! 今回は6月30日(日)の24時間の間での公開を目標としましょう。作品はノートの3000文字に収まるように、ハッシュタグの#ノート小説部3日執筆 のタグを忘れずに! [参照]
#fedibird の皆さまもご協力よろしくお願いします~!
QT: https://misskey.io/notes/9v0s0ca8q0g708y7 [参照]
#ノート小説部3日執筆 の第11回を6月28日(金)~6月30日(日)の間で開催します!お題を決める投票をこのノートの投票機能で行います。Misskey.ioノート小説部のDiscordサーバーの参加者に募ったお題と前回から繰り越されたお題あわせて10個のなかから一番人気のものを第11回のお題とします。今回は6月30日(日)の24時間の間に公開する運びにしましょう。順位はつけません。一次創作・二次創作問いません。R18作品は冒頭に注記をお願いします。よその子を出したい場合の先方への意思確認とトラブル解決はご自身でお願いします。皆さんの既に作っているシリーズの作品として書いても構いません。ノートに書き込むことを原則としつつ、テキスト画像付きも挿絵つきも可です。.ioサーバーに限らず他鯖からの参加者さまも歓迎いたします。それでは投票よろしくお願いします!
#ノート小説部3日執筆 お題【近代日本】
「それはアテにならない」
いわゆる、『前世の記憶』というものを持って今を生活している。
前世の自分は江戸から明治への激動を生き抜いてきたわけだし、今の自分は平成から令和への節目を経験した。どうも、前世の生き方と似たような生き方もしているようだ。理由は違えど、身体に残る傷跡はほぼ同じ、遭遇する出来事をよくよく考えてみたら前世でも似たような事が起こっていた、と後から判明する。何かそういう因果があるのかもしれない。
そして同じ境遇の人間とも出会う。つまりこれは再会、ということになるのだろうか。
(……だが、この先の出来事は予想がつかない……)
事が起きてからでないと過去に起きた出来事かどうかの答え合わせはできないので、事前に回避する、ということは不可能だった。
(……それに全部が全部、思い出せているわけでもないからな)
内容によっては断片的にしか思い出せない。その最たる例が、再会相手を殺そうとしていたことだ。出会ったのは明治になってから、彼が東京に出てきたからである。もともと地方で寺子屋と剣術道場をしていたが、道場破りという名の襲撃を受けて全てを焼き払われ、一家で東京まで逃れてきたのだ。
(……でも、出会ったきっかけはなんだった……?)
明治初期の東京という場で何故か出会い、命を狙い、奪うことは叶わず、共に行動する機会が増え、そこから先はわからない。
「……」
「……眉間のしわ増えてるぞ」
「!」
いつの間にか買い出しから帰ってきた同居人が荷物を持ったままこちらを見ていた。考え込んでいて帰宅に気が付けなかったようだ。
そう、過去の自分はこの男を殺そうと躍起になっていた。
だが、今は。
そんな気持ちは全く湧いていないが、またそう思う日が来てしまうのだろうか。
「……なぁ、明治の俺は何でお前を殺そうとしたんだろうな」
「……突然どうした……っていうかそれはおれの疑問では」
「だよなぁ……」
「……何を気にしてるのかは知らないけど、過去と似たような境遇ではあるが全く一緒ってわけでもないし」
そう言いながら彼は買ってきた品々を片付けている。一通り片付けが済むと、お茶と共にリビングへ戻って来た。差し出されたお茶を受け取り、揺れる水面を見つめる。
「……ある意味、変えられない事を恐れている……とか」
詳細については言及しなかったが、自分の気掛かりな事を口にした。
「それに事が起こるまでそれがかつて遭遇したものなのか、全く関係ないのかもわからない。ましてや、これから先の俺達がどう…なるのかも」
「……確かにそれはそうだけど、全く一緒じゃないんだから事が起きたらその時はその時なりに対処すればいいんだよ」
彼はあっさりそう言うと、人当たりのいいいつもの笑顔を向けてくる。
「……まぁ、おれも気がかりなことがあるとすれば、まだ『オンボロ長屋の妖怪ババァ』に遭遇してないことかな」
「……いたな、そんなのが」
お互いに殺す殺さないとモメている時に出会った老女のことだ。彼女は二人を見るなりこう言い放った。
『……やだねぇ、死の香りを纏って来る奴はねぇ』
「あれはどちらか片方に向けて言ったものだ、というのは確かだったな。……てっきり、俺に言ったものかと思ったが……」
それよりも彼に向けて言ったのではないか、と今になって思う。思い出せる限り、事ある毎に命の危機に瀕していたのは彼の方ではなかったか。
「……あのババァに会ったら、また同じ事を言うと思うか?」
「そもそも会うかどうかもわからないけど……今の時代でも元気だといいな」
「……そう言ってやれるお前はすごいよ……」
#ノート小説部3日執筆 『とある神さまの回顧録』
黒船の来航から始まったこの国の動乱が収まって明治の世が訪れた。
人々は西洋の文化をこぞって取り入れようとし、この国に古くから根付く文化が蔑ろにされる事もあった。
それはそんな時代から始まる小話…。
●
ある時、西洋の船に乗ってこの国に上陸した男が居た。男は新たに開かれた東洋の神秘を知ろうとやってきた…と、表向きはそう言っていた。実際のところ、男は美術品や発掘品を盗んでは売り飛ばす悪党だった。母国では碌に稼げなくなり、新しい狩場を求めてこの国へやって来たのだ。
男は船を降りると早速情報を集める。この時代、外国人は持て囃されていたので人々は喜んで情報を提供してくれた。男はすぐに稼ぎになりそうな古い神社に目を付けた。神社の奉納品や催事道具は西洋に持ち出せば金になりそうだと息巻いていた。
数日間の下準備を経て、男は神社に忍び込んだ。首尾よく金目の物を盗み出し、後は立ち去るだけとなる。そして境内へ向かうと、そこには予定外の人影があった。
「こんな時間に参拝かね?」
そう言いながら男に近づいてきたのはもはや古き時代の人物とされる侍の姿をした若い男だった。侍の出現に男は困惑したが、口を封じてしまえば問題ないと判断してナイフを持って突進してきた。侍は一切動じず男が侍に接触したと思った途端、男の身体はそのまま侍を突き抜けてしまう。男は何が起こったのか分からず振り返るが、そこには傷ひとつない侍の姿があった。
「それが南蛮の武器かね? 何ともみすぼらしい」
男は再度突進するが、やはり侍の身体を突き抜ける。まるで実体が無いようだった。男はようやく相手が人間じゃないと理解して逃げようとする。しかし走り出そうとした直後、足に激痛が走って転んでしまった。転んだままで男が足を見ると、いつの間にか深く斬られていた。
「まったく、どこの国にも盗人はいるものだな」
そう言いながら侍はいつの間にか抜いていた刀を鞘に納める。そして男に近づくとその顔をまじまじと見つめた。
「お主にも苦労はあるのだろう。だがここの物を持ち出すのは許せぬ行為。その償いはしてもらおう」
侍がそう言った直後、男は意識を失った。
翌朝、神社の外で首のない西洋人の死体が見つかり大きな騒ぎになったが、犯人は分からぬまま迷宮入りとなってしまった。
●
時は流れ、時代は大正と呼ばれるようになった。人々の間には大衆文化が広まり、ラジオで情報を手軽に取得できるようになった。政治的混乱が続く中で、人々も政治への関心を高めていった。
そんな時代にとある男が居た。男は内閣の議員で民衆への政治参加を推進する派閥に属していた。しかし中々実現することができず悩んでいた。休暇を利用して良い案を出そうと男は当てもなく歩き回っていた。そんな時、道を間違えたのか古い神社に迷い込んでいた。
「こんな場所に神社とは…これも何かの縁、参拝でもしていくか」
男はそう言って古びた本殿に向かう。そして賽銭を投げ入れて綺麗な作法で参拝をして悲願の達成を願う。参拝を終えて男が帰ろうとすると、鳥居の下に誰かが立っていた。
「今どき参拝される方は珍しいですな」
そう言って鳥居の下に居た中年風の男は議員に話しかける。
「ここの人ですか? 最近の人々は信仰を忘れてしまったようですね」
「その通り、故にここも管理がままならぬ状態でしてな。差し支えなければ何をお願いしたのか聞いてもよろしいですかな?」
男は議員に何を願ったのか尋ねる。別に隠す理由もないので議員は内容を明かした。それを聞いて男は少し考え込むような仕草をする。
「それは難しい願いですな。今は時が移ろうのが早すぎて人々は付いてこれない状況。今すぐに実現するのは難しいですな」
「それは承知の上。まるであなたが願いを叶えてくれるかのような物言いですが、あなたに何ができるんですか?」
男の願いを吟味するような言い方に議員は少しムッとする。
「私に力があれば解決策を提示することもできたでしょう。ですが私はこの通りあなたと話すことしかできない。でもこれだけは言いましょう。今の人々が新しい文化を作っているように、政治にもいずれ新しい風が吹きます。それがいつかまでは断言できませんが、あなたの願いはいつか叶うはずです」
「気休めを言う。そんな言葉なら何度も聞きましたよ。話すだけ無駄だったようですな」
議員は男の言葉に嫌悪感を覚えて足早に去って行ってしまった。
「時代は変わる…ただそれが良いものかどうかは、そうなった時にしか分からんものだよ」
男がそう言いい終えた瞬間、その姿は誰にも見られることなく消え去った。
●
更に時代は進み昭和と呼ばれるようになった。国は世界を相手に大戦争を仕掛け、そして今敗北しようとしていた。連日のように敵の爆撃機が空襲に飛来し、人々はただ逃げ惑う事しかできなかった。
この日も空襲が起き、とある女性が必死の思いで古い神社へと逃げてきた。夫は戦地に駆り出され、ひとり身だった彼女はたった一人で神社まで逃げ込んでいた。
「ああ…街が…」
階段を上がって高台から街を眺める彼女の目に、焼き尽くされる街の姿が写る。あの炎では自分の家も無事ではないだろうと、彼女は絶望のあまり膝をつく。
「大丈夫ですか?」
誰かに声を掛けられる。膝をついたまま振り返ると、そこには優しそうな初老の男性の姿があった。
「ここまで空襲は来ないでしょう。さあ、本殿へ入りなさい」
そう言って男は女性を立たせようとする。
「ありがとうございます。でも…この先どうすれば良いでしょう」
女性は不安を口にする。明日の希望が見いだせない状態だった。
「どんな状況でも生きていればそれだけで希望になります。私にまだ力があれば、もう少し多くの人を助けれたのかもしれないのに…」
「それはどういう意味ですか…?」
男が良く分からない事を言うので、女性が聞き返すが、直後に頭上に爆弾が落下してきた。
「危ない!」
男は女性を本殿へ突き飛ばす。直後に境内で爆発が起きた。
吹き飛ばされた女性ははっと振り返るが、そこに男の姿は無かった。
それから数日後に戦争は終わった。神社で一夜を過ごした女性は奇跡的に生還した夫と再会し、二人で戦後を懸命に生き延びた。
●
時代は進み平成となった。人々は豊かな生活を謳歌していたが、優れた技術は人々の心を貧しくしていった。そしてインターネットの台頭で人々は手軽に世界と繋がった。同時に新たな問題も多く発生し、この国は迷走するようになった。
「これが時代というものか…」
もはや存在すら忘れられた朽ちた神社に老いぼれた老人が居た。老人は倒壊した鳥居の向こうから見える都市を見ながら昔を懐かしむような目をする。もはや人々が神に頼る時代は終わり、神社は観光地という新たな役割を求められていた。
「もう私の役目は終わったか…」
老人がそう呟くとその姿はすっと消え失せて、同時に本殿が崩れ落ちた。
それから、再開発の名目で神社だった場所は跡形もなく消えてしまい、そこに神様が居た事は誰の記憶からも消えてしまったのだった。
了
#ノート小説部3日執筆 「甘き夢見し」 お題:近代日本 ※歴史上人物夢要素あり
私はあの坂本龍馬と今寝食を共にしている。
本来なら同じ時間を過ごすはずのない人。
だって私は平成の世に生きる、歴史モノの乙女ゲーが好きなだけの一介の女子大生だ。
それに対して彼は幕末を生きた偉人──そして私の最推し──時代がそもそもかけ離れている。
けれど気がついたら私は幕末、慶応3年の京都にいた。
そしてなんやかやで龍馬に拾われて、今はこの近江屋に彼と寝泊まりしているというわけ。
夢みたいだけど、試しに頰をつねってみたらちゃんと痛かったので現実なんだと思う。多分。
近江屋といえば、歴史好き、特に坂本龍馬好きなら看過できない事件があった場所だ。
慶応3年の霜月某日、彼はここで死ぬ──そう、近江屋事件。
私はその近江屋事件を間近に控えた坂本龍馬と一緒に暮らしているのだった。
これは千載一遇の好機なのかもしれない。
だって私は彼には生きて明治の世を見てほしかったのだから。
文明開化、新しもの好きの彼なら絶対に気に入るだろうその新時代を。
そう思っていたから、きっと神様が願いを叶えてくれたのだ。
私は近江屋事件の一部始終を知っている。だからきっと、寺田屋事件の時のおりょうさんのように彼を助けられるはず。
中岡慎太郎と彼が密会する夜に、十津川郷士を名乗る男たちがやってくる。それが合図だ。
そうしたら私は龍馬に暗殺者たちが来たことを知らせて一緒に逃げる。うん、我ながら完璧。
好感度もきっとうなぎ登り間違いなし。
もし彼がすぐに動いてくれないようなら、どてらを着ていてすぐには懐刀を抜けない彼に代わって、彼の背後の刀掛けにある愛刀陸奥守吉行で私が応戦すればいい。
剣道は高校の授業でちょっと習っただけだけど、とりあえず最初の一太刀を防げればきっとどうにかなる。
私はすっかりヒロイン気分でその日が来るのを待つことになったのだった。
かくして、その夜は来た。
私は中岡慎太郎と密談するのに邪魔だからと隣の部屋にいるよう命じられたが、離れや階下の近江屋さんたちのところにいるよう言われなくて本当に良かったと思う。
ここなら階下で騒ぎがあればすぐに気づけるし、龍馬にすぐに急を知らせることもできる。
そんなわけで、十津川郷士たちがやってきて応対に出た藤吉さんが斬殺されて断末魔を上げたのを契機に、私は龍馬と中岡慎太郎が密談している部屋に飛び込んで刺客の来襲を告げたのだった。
もちろん刺客たちも速攻で私たちのいる部屋目がけて殺到してくるわけで、ひとりの男が龍馬に向かって小太刀を振り下ろしてくる──
私はそれを返り討ちにするつもりで刀掛けの陸奥守吉行を手に取り、その重みに思わずたたらを踏んだ。
(真剣ってこんな重いの?!)
これでは到底鞘を払って返り討ちにするなどできそうもない。刀を抜きかけた鞘で一撃を食い止めるのがせいぜいだった。
それでも、龍馬が致命傷を負う展開だけは回避できたみたい。
異常を察した龍馬はいち早く窓を開け放つと、まだ陸奥守吉行を手にしたままの私を連れて、窓から外に脱出したのだった。
「まっこと、おまさんは命の恩人じゃ」
材木屋の倉庫に身を潜めて一夜を明かし、追っ手が諦めて引き上げていくのを確認すると、龍馬は安堵したように笑んで私の両手を握ってくれた。
やった、私は龍馬の運命を変えることができた。これで彼に文明開化の時代を見せてあげることができる。
……そう喜んだのも束の間。
「で、おまんこれからどうするがじゃ」
ついでに命を救われる形になった中岡慎太郎が龍馬に問うて、それに対して彼は意外な答えを返したのだった。
「わしゃこのまま死んだことにして、蝦夷に渡るつもりじゃ。ちっくとばあ敵を作りすぎたようやきの、ここいらが潮じゃろう」
え、蝦夷?!
確かに龍馬は北海道で事業を立ち上げたがっていたとは聞いてるけど……今?!
新時代の幕開けも見ずに北海道に行くって言ってる?!
でも狼狽えたのは私だけで、中岡慎太郎は諦めの境地といった表情を見せて龍馬の判断を容れたのだった。
「おまんは言い出したら聞かんきの……大政奉還後の新体制にはおまんの力が必要じゃちゅうても無駄じゃろう」
「さっすがは慎太、ようわかっちゅうの」
わかってないのは私ひとりだった。
「おまさんはもちろん着いてきてくれるろう?」
挙げ句、人懐こい笑みでそんなことを言われてはノーとは言えず、私は文明開化の街並みを見ることもなく龍馬と共に北海道へ渡ることになったのだった。
そして私たちが北海道に移住して程なくして江戸の世は終わり、明治時代となった。
旧幕軍は甲府、会津、そして箱館へと転戦して遂には討伐され、帝は東京に遷都したという。
私はといえば、この文明もクソもない未開の土地を耕して糊口をしのぎつつ、龍馬が興した商会とは名ばかりの何でも屋の手伝いをしている。
現役女子大生の端くれとして一応多少の英会話はできたので重宝されてはいるようだけど、マックはともかく牛鍋屋もカフェーもない寒村暮らし。しかも龍馬ときたら商会の留守を私に任せて方々に飛び回って滅多に帰り着きゃしない。
「私は! スローライフがしたくて龍馬を助けたわけじゃないんだけど!!」
電気もない。ガスもない。あるのはだだっ広い野っぱらだけ。
龍馬や他の移住者たちの努力もあって、少しずつ街並みは整いつつあったとはいえ、それでも私が期待していた「明治の街」にはまだ程遠い。
いっそ「メリケンの視察に行くぜよ!」とか言ってほしくもあったが、龍馬は私が思っていたより遥かに保守的で、私を商談の場にすらろくに連れて行ってくれなかったから、多分アメリカ視察の話が来たら私を置いて単独渡米してしまうに違いない。それはここ数年共に暮らしてみてひしひしと感じた。
先進的だと評価されがちな彼だけど、あくまでそれは中近世レベルの人の中ではの話で、平成の男女平等レベルが当たり前だと思っていた私からすれば断然前時代的な人でしかなかったのだ。
稗や粟ばかりのご飯はもう飽き飽きだ。魚の干物ももううんざり。
白いご飯が恋しい。醤油と砂糖で甘辛く煮た牛肉があるとなお良い。
文明開化で洋風化が進む東京で、オシャレに彼と和洋折衷なデートがしたかった。
「どうしてこうなった!!!」
そう叫んだところで目が覚めた。
「……っていう夢をみたわけよ」
私は三条大橋のスタバで友人に夢の顛末を話した。
「あはは、夢ならもっとちゃんと夢らしくあれよってヤツ〜〜」
「ほんとそれ!」
秋が深まり寒さが忍び寄る中、暖房の効いた店内でフラペチーノを啜れる喜び。
「まーアレじゃん? あんた今日の展示見に行くの楽しみにし過ぎてアレコレ調べてたから、夢にみちゃったんじゃん?」
「それにしてもさ〜、もうちょっとさ〜」
「そこはほら、龍馬救えただけでも良しとしないと」
「んー、そういうことにしとくかー」
平成の世の終わりが迫る中開催される刀剣展。
そこには私が夢の中で握った陸奥守吉行も展示されている。
私と友人はこれからその龍馬の遺品を見に行くのだった。
#ノート小説部3日執筆 、楽しいですか?
#七神剣の森 スピンオフ『殉じる者たち』#ノート小説部3日執筆 お題「近代日本縛り」(※戦時中・戦後 時代背景に即した表記あり。スピンオフのため単独では??かも)
「お家存続の危機なのだ。雷神よ、どうか力を貸してくれんか」
二十年ぶりにその地を訪れると、すっかり頭の白くなった馴染みの男が、大きなニレの木陰で顔をシワだらけにして頭を下げてきた。もっとも頭の白さでは、私も負けていないが。
「この世界に介入するつもりは無い」
「しかし子孫が絶えれば剣を継ぐ者も絶える。それではそちらも障りが出よう」
「血族さえ残っていれば良い。この社を保つ必要は、私には無い」
「それはそうだ、この社はそなたを祀るものではないからな。だがその血族ですら危うい。男児はみな、戦争に取られてしまった。今はまだ俺が生きているが、後継となりうる子は、十八になった一番下の娘、照代しかいない」
戦争。この世界は、まだそんなことをしているのか。人の命が量的資源としてしか見做されていない時代を、彼らは生きている。大勢居て、大勢死ぬのだ。嫌悪感が顔に出ないよう気をつけながら、私は渋面を作った。
「……それで、力を貸すとは」
「照代を神隠ししてほしい。この戦争が終わるまで」
「私は構わないが、……そもそも、終わるのか?」
「戦争自体は、間もなく終わるだろうなぁ。もう疎開してくる奴らの顔を見れば分かる。こっちは長くは持たない。願わくば敵国の方が消耗していて先に潰れてくれれば、というだけだ」
「そんな解決の仕方では、国力を取り戻し次第再戦となろう?」
「そうだな。その時は俺も、きっと子を産んだ照代も戦うとも。使命を次代に繋げた後なら、俺はお国のために死んでも良い。国民皆兵と云うのだ」
「……」
狂っている。私はその言葉を辛うじて飲み込んだ。
「……光の剣を、使うのか」
「いや……あれを今表に出すと確実に、私の管理下から徴発される。あれはむしろ、森の中に隠し、封印してしまった方が良い。ただしく継承し、いずれ本来の使命を果たすこともまた、お国のためになる」
「……つまり」
私が旧友の言葉から思想を取り除いて理解を示すと、彼は再び頭を下げた。
「光の剣と共に照代を五年、いや三年、お前の手元に置き、戦争が終わったこの世界に無事に返してくれ。そして、ほぼ全ての権能を封印した状態で、この鎮護の森に安置してほしい」
「……安置まで、私に任せるのか。では、お前は……」
「……この地の長として、俺はこの地の人民に責任がある。だから、頼む」
その覚悟は理解できた。私も自分が預かる民の幸福は、何に変えても守りたいものだからだ。
幸福。
今のこの世界の人間にとっては、戦争に貢献して死ぬことこそが幸福だということなのだろう。
私の世界において実現させようとしているそれとは余りにも、断絶していた。
「……私の手元で三年も暮らすと、この世界に戻りたくないと言われるかもしれんぞ」
「そうだな。そちらは真に常世か蓬莱か、はたまた極楽かと思うような処だ。だが、俺達には使命がある。照代にも理解してもらえよう」
さて、それが本心からの言葉だったかどうか。
ヒトでない私の目には、ただ覚悟を決めて穏やかに微笑む男の姿が映るだけだった。
三年後、私は約束の通り照代をこの世界に返し、光の剣を封印した。照代は涙を流していた。迎えは、来なかった。
「問題無い。二十年に一度はこうしてまた会いに来る。それまで、息災に暮らせ」
「はい。私は私の使命を果たします。どうか……ご加護をくださいませ、雷様……」
「……無事に生き延びよ。あと十七年、生きていさえすれば、私がどんな傷病も治してみせよう。其方はもう、私の民でもあるのだから」
「お世話に、なりました……」
父のように深々と頭を下げる彼女に頷き、私は空高く舞い上がった。
歩いて去っては、追いかけられるかもしれないと思ったからだ。
あるいは、自分が引き返してしまうことを恐れたのかもしれない。
私の中にある心は、私が一番良く分かっていない。
十七年の時が過ぎた。
私が再び社を訪れると、そこに居たのは知らない男だった。
「失礼、ミツルギ・テルヨをご存じないか」
声を掛けた瞬間、男の顔が怪訝そうに歪む。
「ミツルギ……前宮司のお子さんかどなたかでしょうか?
申し訳ありませんが、ここの本来の宮司はもう二十年程前に亡くなったそうで、私は縁もゆかりも無い雇われ神主なんです。ミツルギさんならこの近所に何軒かありますから、訪ねていただければ手掛かりが見つかるかもしれません。ただうちの氏子に、テルヨさんという方はいらっしゃいませんね」
それは、つまり、もしや。
私は嫌な予感を抱えながら、彼に礼を言ってミツルギ一族を当たることにした。
手掛かりは間もなく見つかった。本家宅に今、彼女の息子が滞在しているというのだ。私はその場所を聞いて戸を叩いた。
「……お待ちしておりました、雷様」
出迎えたのは、この国では珍しい、狐色の髪の少年だった。
緑豊かな庭がよく見える木造のテラスのような場所に通される。確か、縁側と言ったか。私が来るから本家に行きなさいと母に言われ待っていたのだと彼は語った。私は照代が生きていたことに内心胸を撫で下ろした。
「彼女は元気なのだな」
「……母は強くて、元気で、自由な人です。神隠しから帰ってきて以来、世間に馴染めず……アメリカ兵との間に子を作り、この町に居られなくなり……いえ、あの人が自分から出ていったのだと思います。
僕は、小さい頃からあなたの話を聞かされ続けてきました。だからあなたが本当の父親かもしれないと、思っていたのですが……どうやら、違うようですね」
少年は複雑そうに、顔にシワを寄せながら笑った。顔立ちも髪の色も、私とは似つかない。照代ともあまり似ておらず、その兵士とやらの血を想起させた。
「私には愛する妻子がいるのでな。テルヨとは何も無かった」
「……ありがとうございます。ようやくひとつ、母を信じることができました」
「……」
子供の言う台詞ではない、と思った。しかし、彼女の子供らしいとも思った。じっと耐えることが異常に得意な一族だ。彼女自身も、恐らく遠い地で、私にもう一度会うことを我慢しているのだろう。
「……僕の名は、慈恩と言います。英語では、天国の意味になるそうです。母はずっと、あなたの世界に帰りたかったのだと思います」
「……だが、ここには来ていない……」
「待望の男孫だった僕と違って、あの人の居場所はこの家にはありませんから。それに、夢はそう何度も見るもんじゃないとも言っていました」
少年の長い睫毛が暫く固く綴じ合わされ、それから私の方へ向けて開かれ、その奥から強い意思を持つ双眸が現れた。
「雷様。異界の神。あなたにはこの世界はどう見えていますか。戦争は終わりました。もうすぐ平和の祭典オリンピックが開かれます。人だけが、人の心だけが、まだ戦争に取り残されている……」
「……他者からの評価に意味はない。私はここに二十年ごとに、七界を旅するこの世界の代表を呼びに来ている。次は其方自身が見て、判断する番だ。この世界を守りたいか、否か」
「……分かりました。覚悟はもとより出来ています。連れて行ってください、今度は、僕を」
一年ののち、神隠しから戻ったアメラジアンの少年は、種々の困難を跳ね除け無事に本家の跡を継いだという。
#ノート小説部3日執筆 お題:近代日本縛り(大正)綿あめって明治後期から大正にかけて普及したんですって(雑学)
公園の中の茶店の片隅。梅雨時期の日差しを遮るひさしの下に彼女と青年は座って、公園を散歩する老若男女を眺めていた。居るのか居ないのかの影の薄さ。席を借りるのだからと、そういう時だけは欠片ほどの存在を表して、茶代を彼女は払う。
「なんだかねえ、俺にはなにが変わったのか大してわかんないけどねえ」
茶をすすりながら、青年は苦笑する。
席に赤い敷布の茶屋の番茶。古い桜並木の公園。蓮の池。どれだけ前に見たか忘れた景色と青年には変わりない気がする。
「でも、何年もかけて少しずつ変わっているのよ。だってこの茶屋は前にお茶を飲んだ茶屋とは違うわ」
「そうだけどさあ」
「ほら、みて。女の人が男の人に連れられないで散歩している。ちょっと前ならお姫さまだったような人が隠れもしないで自由によ」
彼女は散策路を楽し気に歩いていく女性の一行を見て呟く。言われてみれば、都──と呼ばれていた多くの場所──では、一人歩きの女はたいてい下働きの奉公人だった。農村、漁村の方が割合は多いとはいえど、栄えている場所では女はとかく隠れて自由がない。家の中、あるいは遊郭の中。自由である女には、持ち物が少ない。昔から女に与えられた自由は僅かだ。
「──お嬢は……」
言いかけて、青年は続く言葉を飲み込んだ。
何を言うというのだ。何年、何十年、何百年隣にいるのに、今更。
「なに」
珍しく彼女が青年の言葉に耳を傾けようと彼を見詰めたけれど、青年はその視線から逃れるように顔を逸らした。彼女の視線は真っ直ぐで、青年には嘘を吐ける気がしない。
「いや、なんでもない」
ただ、なんとか言葉を濁して茶をすする。
「あなたには羨ましそうに見える?」
青年を見詰めたままの彼女は静かに問いかけてきた。
文明開化──らしい。そうして、それぞれに構えていた国が一つになったのだと聞く。外国との交易を再開したのが、ひとつ前の時代。それから、また時代がひとつ新しくなった。結局、この国は古い家系を頭に据えていないと落ち着かない。
「羨ましそうではないかな」
青年は少し笑う。
彼女はきっと何にも囚われたくなくて、ひとりで居たのだろう。出会い頭に衝突するような偶然で青年と出会わなければ、きっとまだ彼女はひとりで居るのだろう。
「お嬢はさあ……俺なんか振り払おうと思えばいくらでもできるのに、どうしてしないの」
唐突に青年は問いかける。彼女は青年を見詰めた視線をふいと離してしまって、温くなった茶を飲んでいる。
彼女は普段は寡黙で、青年との間に会話が成立することの方が珍しい。青年の問いかけなど、答えたくないと思えば答える必要もない。視線を逸らした彼女に青年は、矢張り答えてくれないかと溜息を吐きかけた。
「……また、ひとりにしてしまってもいいの?」
不意打ちで彼女が独り言のように呟いて、青年は驚いた顔を上げた。
「え。嫌だよ」
思わず真面目な声で返事をする。
「大丈夫。今更、ひとりにしないわ」
余程、青年は情けない顔をしていたのか、茶碗を置いた彼女は茶席に放られた青年の手に手を重ねた。温度はないけれど、感触はある。青年よりも華奢で小さな手に、彼はなぜかほっとする。
「ねえ。人の歩いている姿も、着ているものも、建物や町並みだって凄く変わったように見えても、中身はあまり変わっていないのよ。きっと、男の人なしに歩いている女の人だって、少し怖いんだわ。そういう風に変わってきて、そういう風に慣れようとしていても急な変化には追い付かないのよ。……だから、あなただって、明日私が居なくなってしまったらきっと怖くなってしまうわ」
「子ども扱い」
「……きっと、私も、寂しい……」
青年がぶっきらぼうに呟くと、彼女はぽつりと零した。
時代がいくつ変わっても隣にいたから。
青年が推し量れない彼女の気持ちの中にも、そんな感情があるのかと驚いた。彼は彼女ならば、青年を放逐してしまっても変わらない無表情で次の日には知らないどこかへ行っているのだろうとばかり思っていた。
涙も流したことがない癖に泣きそう、などと思った青年はすん、と息を吸って彼女の手を握り返した。
「お嬢の方が寂しいんだ」
負け惜しみのように呟いて、青年は勢いよく立ち上がった。自然、彼女も青年の手に引っ張られる。
「あのさ、あれ買いに行こうよ。なんかふわふわした雲みたいな菓子」
「え……?」
「俺はいいけど、お嬢さっきから気になってるみたいだし」
「そう?」
「女の人も見てたけど、あの菓子持ってる子どもも同じくらい見てた」
青年に言われると彼女は黙ってしまった。彼女はよく目の前の人間を見ている。青年は人間を見ている彼女を見ている。間違っているとは思わなかった。そうやって、長い間隣に居たのだから。
「行こう?」
念を押して彼女を覗き込むと、また視線を逸らされたけれど小さく頷く返事が返ってきた。
彼女の好きなものは少なくて、青年が知っているものはもっと少ないけれど、普通の少女のように甘いものは好きだ。女や子どもが喜んで手にしている菓子なのだから、彼女も好きかもしれない。
「舶来の菓子かな。最近になって見かけるやつだ」
手を繋いだまま青年が菓子を持っている女や子どもが多い方へと足を向けながら言う。ほんのりと香ばしい甘い香りがしてくる。
目的の屋台のそばには女や子どもが賑やかしく店を囲んでいた。青年と彼女がその間から覗くと、ざらめを入れた機械から雲のような薄物のような白い菓子が湧き出て店主が器用に棒にからめとっては売っていた。
「へえ、どんな仕組みなんだろうな」
青年が感心したように零すと、彼女の手を握る力がほんの少し強くなった。
「親父、うちのお嬢にもいっこ頼むよ」
くすりと笑って青年は屋台の店主に声をかけて、銅貨を渡した。「はいよ」と威勢のいい声が返ってきて、少し後には今さっきからめとったばかりのふわふわの白い雲のような菓子が手渡された。
「はい、お嬢」
青年が菓子を彼女に手渡すと、珍しく彼女はきらきらとした目で受け取った菓子を見詰めていた。
「俺にはさ、大して変わってないようにも見えるし、変わったかもしれないし変わってないかもしれないけど、目新しいもんも悪くないんじゃない?」
屋台の人だかりを離れながら青年は独り言のように言う。
彼女はしばらく雲のような菓子を眺めていたけれど、食べ方に迷った末か舌を伸ばして舐めるように口にするとほろりと「甘い」と呟いた。
「気に入った?」
珍しいこともあるものだと青年が嬉しそうに訊くと、彼女は静かに頷いた。いつも、達観しているように何かを見ている彼女が、その時だけは見た目と変わらない少女のように見えて、青年には少しおかしかった。
#ノート小説部3日執筆 「昭和と平成」
私は、独特のタバコの匂いが部屋に染み付いている祖父の部屋が大好きだった。祖父の見ていたテレビはちっちゃくて興味がなかったが、それを見ている祖父の隣は、心地よく、ぬいぐるみを抱えて階段を降りたら、転がって落ちるほどだった。それほど小さかった。祖父は私に対して甘かった。おもちゃの電池が切れたと言えば、原付で近くのスーパーまで買いに行ってくれたし、タバコをやめてと言えば、一瞬だけでもやめてくれた。それほど甘かった。でも、祖父から、私の生まれる以前の話は聞いたことはない。するのはいつも母の言葉で、「父と祖父が喧嘩した」とか信じられないものもあった。
戦争の話をするのはいつも祖母だった。私は幼くてよくわからなかったが、窓を真っ黒にして電気もそんなに使わなかった、焼夷弾が降ってきた、窓が割れただったか。とにかく見つからないように暗くしていたことを聞いていたのは確かだった。
誕生日が大空襲の日だと知ったのは、小学校の給食の時間。今日はこんなことがあった日なんですよ、と燃え盛る絵と共に、自分の誕生日と地名、そして大空襲の文字が並んでいる。ゾッとした。広島や長崎で起きたことは知っていた。でも、ここでもあったんだ。それも、私の誕生日に。祖母が言っていた、戦争の話が急に現実味を帯びた気がした。私が生まれたのは戦争が終わって何年も経った同日というだけで、何も関係ない。それでも同日というだけで、あの焼夷弾で町が焼ける赤い炎の絵が思い起こされる。母は私を産むのに必死だったとしても、祖父は、祖母は、この日を覚えていたんじゃないだろうか。
それから、祖父が亡くなった。大好きだったのに、血の気を失った祖父を見て、死んだ物としか思えなくなった。
祖母は歳を重ねるごとに、少しずつボケていった。
今では、家で誰も戦争の話をしない。ウクライナとロシアやガザ地区のことも対岸の火事としか見てない。
大空襲の日は私の誕生日に塗り替えられ、思い出そうとする気配もない。
このまま、戦争を知る者が減っていくのか。
私は語り部になるつもりはない。
子供を残すつもりもない。
だが、先の戦争で何があったのか、あの大空襲の日どうなったのか知る権利が私にはある。
駅近で大空襲の展示があった。誰もが素通りする中、私はしっかりその目で見た。文章も絵も見た。でも忘れていく。
だから何度でも、この目で見て、戦争が持つ暴力性を否定し続ける。それが、同日に生まれた私の役目だと思うから。
#ノート小説部3日執筆 第10回記念お題「近代日本縛り」
『携帯電話(昭和)』
「今の携帯は随分と薄くて小さくなったもんだなぁ」
「え?」
休みを利用して祖父の家に遊びに来ていたヨシキは感心したような声に顔を上げ、スマートフォンから祖父の方へ視線を移す。
そこにいた祖父は目を細め、どこか懐かしそうな表情で笑っていた。
「……昔の携帯って、ガラケー? あれって逆に今より小さくなかったっけ」
子どもの頃に見た携帯を思い出しながら疑問を口にすれば、祖父は首を横に振る。
「いや、それよりもっと前。出始めはこう、肩掛けのバッグみたいなどでかいやつでなぁ……随分と重くて大変なやつだわ」
「……バッグ……?」
祖父の言葉にいまいちピンと来ず、ヨシキは再びスマートフォンに視線を落として検索サイトを開いて「携帯電話 初期」の文字を入れて検索すると……なるほど、バカでかいボックス型の携帯電話が検索結果で出てきた。
「へー、携帯って昔はこんなだったんだ……うわ、連続通話最大四十分!? 短か!」
出てきた情報に目を通していたヨシキがギョッとして声を上げる。それを祖父は楽しそうな表情で眺めている。
「昔はなぁ、それだけじゃなくて車に付ける電話もあったんだよ。ただ、使用料とか高額でねぇ……そのうちにガラケーやPHSが発売されて、一気になくなったんだ。それでも当時は画期的で、持っていると羨望の眼差しで見られたものだよ」
「へえー」
祖父の説明を聞きながら一通り情報を読み終わったヨシキはようやく顔を上げた。
「これ、じいちゃんも持ってたの?」
目を輝かせながら期待の眼差しを向けてくる孫に対し、祖父は申し訳なさそうに眉を少しだけ下げる。
「いや、じいちゃんは持ってなかったなぁ。勤め先の社長さんが持っていてね。触った事はあるけども、な」
「なぁんだ、そっか」
ヨシキがもらした少し残念そうな声を聞いた祖父は「ごめんなぁ」と言って笑いながらも言葉を続けた。
「わしからするとほんの昔の事だけれど、その間に随分と技術の発展があるものだと思ってなぁ。……今は携帯電話だけじゃなく、何もかも小型化して便利な機能がたくさん付いているからなぁ。年寄りはついていけんわ」
その言葉にヨシキは「あー」と納得するような声をもらした。
「機能たくさんで判らないは判るなー。俺でもついていけてないもん。正直、ちゃんと使えてる機能は半分もないんじゃないかな」
「何だ、ヨシキもついていけてないのか。じゃあわしが使える訳ないなぁ」
からからと笑う祖父に対し、ヨシキもけらけらと笑う。
「案外勉強したらじいちゃんは俺より使いこなすかもよ? 色んな事を知ってるし」
「ないない。長く生きてるから知識があるだけだわ」
首を横に振った後、祖父は膝に手を当てながら立ち上がる。
「そろそろ晩飯の用意せんとな。今日は何が良いかねぇ」
「最近暑いし、そうめんにしようよ。昨日買ったなすとしいたけを天ぷらにしてさぁ」
「天ぷらなぁ……最近、揚げ物を食べると胃もたれが……ヨシキの分だけ用意しよう」
「大根おろしをつゆにたっぷり入れると胃もたれしにくいらしいけど」
「残念、大根がないわ」
ヨシキも立ち上がり、居間を出ていく祖父の横を歩いてついて行く。
ぱたん、と襖が閉じられた居間は静かになり、ゆるゆると落ちていく陽に合わせて暗くなっていった。
Misskeyノート小説部のアカウントをFedibirdをお借りして運営することになりました。#ノート小説部3日執筆 などのハッシュタグ企画や、そこで投稿された作品のリポスト(リトゥート?)をこちらで行い、Fediverseにおけるノート小説の振興を図っていきたい所存です。
主宰:小林素顔 https://misskey.io/@sugakobaxxoo

 がくじゅつてきあかげ
がくじゅつてきあかげ