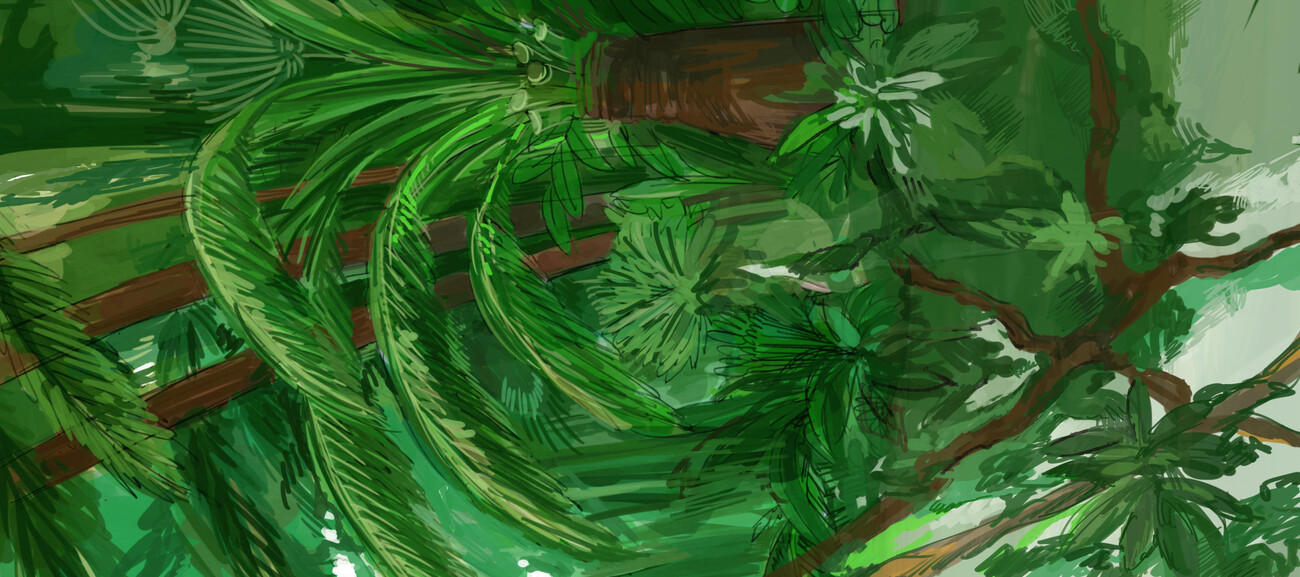
『日本語の勝利/アイデンティティーズ』収録作「万葉青年の告白」
リービ英雄が『万葉集』の小論文を発表しようとした時に「海外の人間には、歌は無理だろう」と言われたことが忘れられず、『万葉集』で全米図書賞をとったリービがその頃のあまり上品ではなかった賞授賞式に呼ばれた時にスピーチは短くしろと言われ、またリービ自身も今のアメリカは難しい話を聞きたがらないのだ、と積極的に諦めた時、ふと「歌は無理だろう」というあの言葉を思い出し、7分間スピーチをした挙句に、英訳された和歌を品のない観衆の前で長々と朗読した話。あまりに良い。
またこの作家は/この読者は(女は、男は、若い子は、アメリカ人は、日本人は…)的「侮り」に引っ張られる人間なので、自戒となって身に迫る話でもある。
『蒼穹のローレライ』(少々うろ覚えなのですが所感)
主人公の瞳が理由不明のまま青く 母親の不貞を疑られて幽閉され、父親にも邪見に扱われて、運よく外に出たとしても近所の人間は不気味がるし帰ったら母親が刃物をもって狂ったように探し回っている、そんなイエとムラで育っている彼が
上手く逃れた先が日本海軍という今から見れば理不尽な組織社会にしか思えない、が一種のテクノロジーの先端集団に行くことで相変わらず孤独でありつつも一種の救いがそこにあり
青い瞳は生物学的にいう先祖返りかもしれぬ、という同輩の明晰な回答は当時では日本海軍などでしか賜れない言葉だったろう
という、ボーイズラブ小説
『国家を超えられなかった教会』当時の日本基督教団の統理と教学局長が1945年に文部省に天皇を神とキリストとの下に置くことは不敬となる、キリストの復活信仰は幼稚で奇怪な迷信であるからこれを信仰問答から除外せよ、というとうとう最終的な絶対防衛ラインともいえる線を越えた宣告をされるんだけど
「私どもは今日まで日本国民として、心から日本を愛し、日本の非常時体制に即応し協力してきたのだが、信仰の最後の線から退くわけにはいかない。ですから、そこまで仰言るのでしたら、私どもにも最後の覚悟があります」と反論して、その後二人で「いよいよ殉教かも知れないね」と話したことが載っている
『国家を超えられなかった教会』 教会堂は徴用され信徒たちも応召し、また九州や台湾に疎開し、牧師も疎開の引率者、徴用、戦火を避けて、軍に睨まれていることを知って犬死したくないと沖縄を去った、ある者は戦場に消え、ある者は土竜のような生活で生きのび、ある者はスパイ容疑で殺され、少なくない者が栄養失調やマラリアで死んだ
戦争が終わった時には教会は跡形もなく、会堂は戦火で破壊され尽くされていたし、生きのびた信徒は他の生きのびた信徒の行方も知らなかった、強制疎開、徴用もあったから逃げることは悪ではなかった、にも関わらず、教会が下した「判断」とそこから起こった状況への対応に問題を感じる、というのは、
沖縄の教会の問題は他府県出身の牧師たちが引きあげたからだと考えていたが、その中には沖縄県出身の牧師もいた、また戦火で信徒が全滅したわけでもなかった、沖縄の教会は、迫りくる戦争と疎開政策の中で為された教職と信徒の「決意と行為」によって、自然消滅したのである。…
ということが淡々と書かれており、私はここまで冷静に鈍い挫折と悔恨を滲ませている文章を他に見たことがない。
『影の獄にて』セリエが弟へストンピーへ多くの者へ行った「罪の傍観」と「裏切り行為」のツケを払ったのは、実は弟への告解という行為によってではなくて、日本軍将校のヨノイへの抱擁とそこから発した処刑死によってだったのだろう #感想
2023年に読んだ面白本
からゆきさん 異国に売られた少女たち
宝ヶ池の沈まぬ亀 ある映画作家の日記2016‒2020
「ブレードランナー」論序説
叛逆航路
坂倉準三 パリ万国博覧会 日本館
森崎和江コレクション 1 産土
新興俳句アンソロジー
「どんぐりの家」のデッサン―漫画で障害者を描く
精神史の旅 3 海峡
HHhH プラハ、1942年
興亡の世界史 東インド会社とアジアの海
黒衣の短歌史 中井英夫全集 第10巻
影の獄にて
三池炭鉱「月の記憶」 そして与論を出た人びと
由煕 ナビ・タリョン
地球追放
占領下の女性たち 日本と満洲の性暴力・性売買・「親密な交際」
越境する民 近代大阪の朝鮮人史
母を失うこと 大西洋奴隷航路をたどる旅
感想『森崎和江コレクション 精神史への旅 1産土』 https://lucette.hateblo.jp/entry/2023/12/25/185249
>森崎の文章のいいところは、逆撫でるように言葉を繰り上げつつ、展翅のピンを打つように言葉を留めながら、ふと文脈を緩めて、主点が軸を見失ってしまうような、そんな言語的快感にあると思う。真綿で締められる知的な興奮というか。「こころのケア」(ひらがなに開かれた心情的な「こころ」という単語と、ケアという西洋医学用語の合わせ技)という単語に似たおかしさと親しみやすさにも似ている。
この言葉合わせの唐突さの謎は、もしかしたら常々森崎が説いている「植民地主義と米」にあるのかもしれない。帝国が軍事行為と政治理念で行った侵略にくべられた炎と、民衆のかまどの火は表裏一体である、と彼女は見抜いていたのだ。無関係ようで、共犯関係にある二つの火。
「⻤太郎誕生 ゲゲゲの謎」 ネタバレメモ
★ゲ謎 過去あるいはあの一つの時代からの離別と決別と考えると割とスムーズに行くんだけど そういう視点から感想も聞きたい
★森崎和江 近代特有の人工的空間、2世代家族ばかりだった植民地朝鮮の出身なので(雑な言い方だけど)日本の閉鎖的なムラ社会が嫌いで、そこは個人の性格や人格が関係なく「おくに」がどこかですべてを計られる空間だった、という事を言っているんだけれど
★森崎が長崎の列島の先のほうにあるとある島を訪れ、その島の人びとは島原の人から差別を受けていたので遠方との結婚が出来ず血族同士の結婚をしている、その現状を彼女が形容して曰く「”おくに”はここで極まっていた」だったことを思い出した、し彼女は「おくに」に一貫して否定的だったこと、を
- litlink
- https://lit.link/samishira
おふね 短歌 SF(MBD) 引揚げ文学
お絵描きとかをする人間。一次創作、艦船と企業・組織擬人化、MBDのFAなど。
★@samishira(misskey・みすでざ)は擬人化と一次創作の告知や作品を上げるために使うことが多いです。
→フォローはMastodon・misskeyの両方で行ったり片方で行ったりしています。私は自由にやるので、お好きなようにフォローしていただければ嬉しいです。
★メモ帳も兼ねているので、投稿内容が別SNS(Twitter(X)等)と重複する場合があります。
