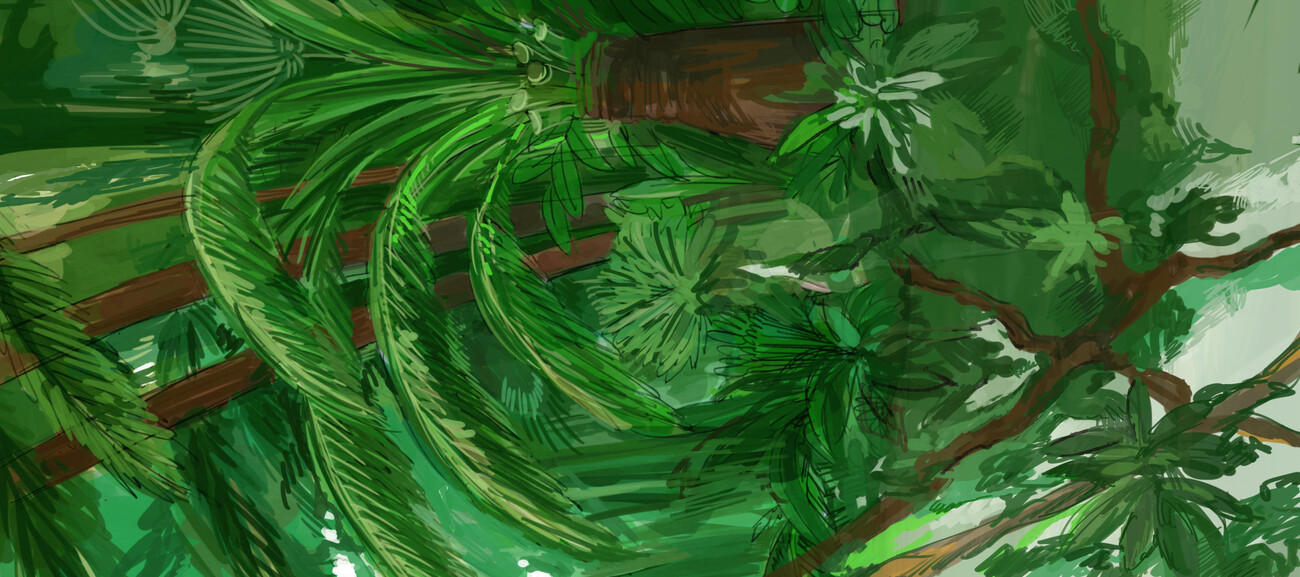
『慰霊と顕彰の間』にある、靖国神社に祀られている人に関わりのあった第一人者がいなくなってきたことで、靖国議論が抽象的で政治的なレベルになっている、観念化しはじめている…という指摘は興味深さをもって私への警句となる #つざメモ
斎藤茂吉の翼賛歌は三好達治の翼賛詩とは別の意味のやるせなさを感じる、茂吉の短歌は歌それ自体は質を保っているように思える、戦争詩歌でも短歌俳句は形式には大きな違いはない、昭和初期の実験精神から止められてしまったけれど、帰る元があったから戦後の影響としては文学者の姿勢に収束でき処理できたのに対し、近代詩は形式そのものが翼賛詩というスタイルができてしまった、それは近代詩発生初期への先祖返りであり、質的にも語彙がバラバラになって墜落していっているように思える、という『月に吠えらんねえ』著者である清家雪子先生の言葉 わからねぇ……翼賛歌は読んでも翼賛詩はあまり読まないからかな……
歴史化とは確かに死者を忘却による沈黙から救い彼らに第二の生を与える作業には違いないが、その作業は歴史家の主観性を伴うため、死者たちは利用される立場に置かれ、彼らは歴史のページの一部として固定され、自らはその位置を拒否することができない。
「アンダーグラウンド」はこの固定化へのささやかな抵抗と、忘却への抵抗の一様式としても存在する。死者はプロットに回収され切らずに常に余剰を残し、残余の中にこそ死者=他者の理解のための可能性が立ち現れるに違いない。その可能性とは、忘却と歴史化された記憶との境界に存在する可能性そのものとしての可能性である。……
という趣旨が書かれた「空白からの視線――クストリッツァ映画における他者の表象」という論文、興味深い
★『艤装の美』解説 設計家村野藤吾は船の持つ暗喩に興味を示したのではないか/近代人は「如何なるが創造的進化の落処かを知るに苦しむもの」である故に明確な到達点の未来を見出せず、また美しき回想の中の過去も喪失した、近代人はこの現在から逃げ出せない、と彼曰く/過去の建築様式にも将来工業化されるはずの未来」の建築様式の実現にも一切期待することもない設計家と成る…
★海上を旅する旅客船は出発港を過去として、向かう港を未来として予定しながら現在の洋上を《点》として航海している/現在を共に生きる者の疑似的な共同体とも考えることができる/その意味で一隻の船舶は村野にとって近代社会のモデルであり、現在を共に生きる者たちを具象化するものに映ったのかもしれない(長谷川尭「船――現在を生きる者たちの世界」)
★また、/客船「橿原丸」はいずれ軍艦になることを艤装担当者はわかっていたはずであるから装飾問題は生じなかったであろう/が、艤装担当者達はまだ見ぬ娘に対して想いを込めその意気の高さを競い合ったのではないか/己の内の散華の美学が橿原丸という娘の旅装に託されていたのだと思えてならない、という指摘が興味深い(竹内次男「橿原丸」)。村野藤吾は橿原丸設計に携わった人。
- litlink
- https://lit.link/samishira
おふね 短歌 SF(MBD) 引揚げ文学
お絵描きとかをする人間。一次創作、艦船と企業・組織擬人化、MBDのFAなど。
★@samishira(misskey・みすでざ)は擬人化と一次創作の告知や作品を上げるために使うことが多いです。
→フォローはMastodon・misskeyの両方で行ったり片方で行ったりしています。私は自由にやるので、お好きなようにフォローしていただければ嬉しいです。
★メモ帳も兼ねているので、投稿内容が別SNS(Twitter(X)等)と重複する場合があります。
