
#ノート小説部3日執筆 月見
最後の「月見」
「もう『月見』の季節か……」
「ああ、今年も派手にいこうぜ」
彼らは笑って頷き合い、彼らの『武器』を取った。
手触りを感じながら弾薬をこめ、スムーズな動作を確認する。
「準備はいいな。いくぞ」
さあ、年に一度のお祭りだ。
夜中、紺色の天には金色の月が静かにのぼる。
まんまるの月、今日は月の可視面積が一年で一番大きくなる日だった。
光学迷彩が施され、肉眼では見えないが月には月人の都がある。
彼らは目を凝らして月を睨む。凹凸の影もはっきりと見えた。
「いた」
まばゆい月と暗い空の境に、何かが見えた気がした。
その点は近づいてきている。
来る。そう思った瞬間、ひゅうと月光を横切ったのはU-sagi型支援機だ。
月人の兵器。宇宙空間をあっという間に飛来したそれは、白いもやをまき始めた。
通称をMoCHiという迷彩雲は、機体どころか月まで覆い隠して見えなくしてしまう。
このもやに紛れて攻撃するのが、いつもの月のやり方だった。
しかしこちらも一歩的にやられるわけではない。
「撃て!」
合図にしたがい、彼らは砲に張り付いて弾を放つ。
このSuSuki弾は金色の尻尾をひいて放物線を描き、もやに当たって散らす。
迷彩雲が吹き飛び、隙間からまた月が姿を現した。
「く……近づかれたな」
頭上をHikiGa-L型攻撃機が飛んでいくのが見えた。
攻撃機は小さな球形のgun-Yaku爆弾をばら撒いていく。
「あち!」
当たるとなんだか臭い。苦くて渋いような、変な匂いだ。
「何やってんだ、すぐO-Dango撃て!」
「おー!!」
こちらも小さな球形の弾をポンポンと撃ち出す。
ちょうどよく当たれば、それは攻撃機を大きく揺らした。
「SaToimo用意!」
「完了!」
「撃て!」
ドンと打ち出された歪な形の弾。
レーダーの探知を逸らすためこんな形になっているらしい。
それはまっすぐ月に届き、そして。
8つの小さい光に別れ、キラキラとして消えて行った。
それは古い母星でいう、花火のようだと彼らは思ったかもしれない。
「……終わりだな」
「ああ、今年も無事に『月見』が終わった」
ここは第182恒星系の第6惑星テン・テー。
対する月は衛星ジョウガ。
植民されたのは400年前、この2者間で戦争が起こったのはその36年後のことだ。
しかし、初めは殺し合っていたものが、惰性に変わるのにそう時間はかからなかった。
人死にが出なくなり、交易も普通になされるようになってから早200年。
年に一度、互いに威嚇を行うだけが『戦争』の名目を保っていた。
この行事は15演練、通称『月見』とテン・テー方では呼称されている。
しかし、その翌年の『月見』は様子が違った。
殺傷力の高い光弾の飛び交う中、彼らは右往左往するばかりだ。
「なんで攻撃してくるんだよ!?」
「知らねえ! なんだあいつら!?」
惑星テン・テーは衛星ジョウガの総攻撃を受けていた。
まわりで人が倒れていく。動かなくなる。
臭いどころではない。血しぶきが飛んだのを見るのは初めてだ。
迷彩雲に紛れて数百のミサイルが飛んできた。
それを知覚した時は、撃墜、防御するにはもう遅すぎた。
「まさか油断させて……! いったい、いつから……!」
爆発は一瞬。パッと光り、すぐにそこに何があったのかわからなくなった。
こうして惑星テン・テーは衛星ジョウガの勢力下に入った。
俗に月見奇襲としてよく知られている事件である。
#ノート小説部3日執筆 お題:【栄養ドリンク】
※自創作の掌編です。初見バイバイ感があります。雰囲気でお楽しみください。酒は栄養ドリンクです(迫真)
------
『One shot bittersweet』
『白夜』に所属する審問官は、皆さんもご存じの通り、大変過酷な使命を背負っています。
神に祈りを捧げ、人々の安寧を守り、夜鬼を排除する。崇高なるその理念のもと、彼らは日夜、人々を脅かす化け物や異教徒と戦い続けています。
調査や戦闘があるたび、一晩中外を駆け回る、なんてこともしばしば……。これじゃあ当然、規則正しく健康な生活なんて送れませんよね? くたくたで帰ってきて、食事の用意をするなんてもってのほか! 適当に済ませて、寝不足のまま次の仕事へ……なんてことも。疲れていても、夜鬼の脅威は待ってはくれません。
「――そこで、開発されたのがこちらになります!」
「はあ」
シスターたちはそう言って、何らかの液体が満たされた濃緑色の瓶を、仰々しく示して見せた。それは一見すると、教会で作られているお馴染みの薬草酒のように見えたが、それとは異なるラベルが貼られている。どうやら違うものらしいな、とさほど熱心な興味もなく眺めていると、シスターたちが口々に文句を言い始めた。
「ノリが悪いですよカウフマンさん」
「せっかく考えて練習してきたのに……」
「そういうところよねー、そういうところ」
こうなれば、彼女らに口で勝つのは不可能である。気を取り直して、精一杯興味がある体の言葉を返す。
「へえ、いつもの薬草酒とどこが違うんだ?」
取って付けた感甚だしいが、満足気にシスターたちは胸を張り、意気揚々と説明してくれた。
「よくぞ聞いてくれました!」
「従来品よりも使用する薬草の種類を大幅に増やし!」
「極東から取り寄せた稀少な生薬も配合!」
「二十四時間戦う人のための滋養強壮、栄養補給薬草酒となっております!」
さすがに二十四時間は戦わせないでくれ――という言葉を飲み込んで、拍手を送る。やり切った感のある表情の彼女らは、にこにこと笑顔を浮かべながら近づいてきて、その瓶を差し出した。
「そういうわけなので、試作品の試飲をしてもらいたいの」
ようやく合点がいった。なるほど、そういう理由で呼び出されたのであれば納得だ。瓶を受け取り軽く回してみると、中の液体が揺れる。ややとろみのありそうなそれは、確かに従来のものより、いろんな成分が濃縮されていそうだ。薬草酒が格別に好きというわけでもないが、彼女らの熱意を無駄にするわけにもいかないだろう。
「分かった。飲み切ったら、感想を伝えるよ」
そうしてこの薬草酒を持ち帰ると、吸血鬼はすぐさまこれを見咎めた。彼は飲酒に厳しい。曰く、血の味が不味く――彼の好みではない味に――なるからだ。事の経緯を説明し、無下に突き返すわけにもいかなかった事情を話すと、吸血鬼は渋々了承し、酒瓶を破壊しようという考えを改めてくれた。ロクスブルギーは、面白くなさそうに腕を組んで言う。
「もっとも、君ではその酒の滋養強壮効果を十分に感じることはできないだろう。既に完璧な食事を、僕が提供しているのだからね」
それはその通りである。仕事による就寝時間の不規則さを除けば、それほど不健康な生活をしている感じはない。大抵の場合、必要な時には既に食事が用意されている。シスターたちが、独身者の審問官はきっと生活が乱れがちだろうということを理由に、試飲を頼んできたことは理解できる。しかしそれは仕方がないことだ。彼女らはこの家に、世話焼きな吸血鬼が住んでいることなど知らないのだから。
血の味が変わらないよう、くれぐれも一度に大量に飲まないように。ロクスブルギーからはそう念を押された。薬草酒の瓶を傾けると、とろりとした琥珀色の液体が小さなグラスの中に満ちていく。まるで深い森の中にいるような香り。舌に乗せれば、強烈な渋みの中にほのかな甘みを感じた。それを二口ほどで飲んでしまうと、身体がじわりと温かくなってくる。寝酒には適当そうだと思いながら、そのまま眠りについた。
こうしてしばらく、グラス一杯の酒を飲む日が続いた。さすがに、様々な薬草を使っているという謳い文句に偽りはないようで、心なしか寝付きも寝起きもよく、身体に活力が漲っているような――気がする。些細だが、自覚できる程度には効能があるようだ。
今日はロクスブルギーに血を与える日であった。日頃完璧な食事を提供してくれる彼にもまた、定期的に完璧な『食事』を提供する必要がある。これは両者の間で了解の取られた、一種の契約だ。
吸血鬼は待ちかねたように首筋に牙を突き立て、いつも通り血を吸い上げたのだが――不意に口を離して呟いた。
「苦」
「酒のせいか? そんなに量は飲んでないけど」
「苦味が強すぎたのだろう。薬を咀嚼して食べているかのようだ」
「……でもアンタ、いつも苦い苦い文句言いながら俺の血を飲んでるよな……」
「それは別に良い。記憶と感情から醸造された苦みには、味わう価値がある。が、添加された苦みにその価値は無い」
口の端から血を垂らしながら――こうしているとかなり吸血鬼に見える――ロクスブルギーは悲しそうな顔をした。彼は仕方なしにもう一口ばかり血を吸ったが、『食事』をあまり楽しむことはできなかったようだ。消沈した姿にさすがに申し訳なくなった。酒はまだ半分ほど余っているが、これ以上は飲まないほうが、友人のために良いかもしれない。感想を伝えるくらいのことは十分にできるだろう。
翌日、そのようなことを考えながら仕事から帰ると、食事の前に一杯のドリンクが供された。それはどうみても柑橘類の果汁のようだったが、鼻を近づけるとかすかに、薬草酒の香りがした。
「これ、どうしたんだ?」
訊ねると、ロクスブルギーはキッチンから大皿に乗った焼き魚を持ってきながら、言った。
「――要は、成分の有効性を試すことができれば良いのだろう。なら、その酒が薬草酒のままである必要は無い」
珍しく、邪悪そうな笑みを浮かべて、彼はこう付け足す。
「ほとんど果汁で割ってやった。これならば酔いようもないし、血の味への影響も抑えられるだろう」
「……なるほど」
どうやらこの世話焼きな吸血鬼は、全員に利益のある方法を探したらしい。つまり、この薬草酒を飲み切って評価を行うことができ、シスターがその結果を受け取ることができ――自分が血を美味しく飲める方法をだ。
「その酒の評価を、請け負ったのは君だ。きちんとやり遂げるように」
「ああ。……ありがとう」
感謝すると吸血鬼は、君を料理するのは手間がかかる、と言って、再びキッチンへと戻っていった。
それからまたしばらくののち無事――この薬草酒は飲み切ることができ、その有効性について正当な評価を行うことができた。
もう少し味を甘く美味しくできないかどうかについては、別件として彼女らに伝えておいた。
#ノート小説部3日執筆 「プロジェクトM~奇跡のドリンク~」 お題:栄養ドリンク
──赤い荒野が果てしなく広がる星、火星。
その開拓初期は苦難の連続であった。
進まないテラフォーミング、不足する食糧。
そんな中、いち早く根付いた作物を利用して、とある飲料の開発が急ピッチで進められた──
プロジェクトM~奇跡のドリンク~
ドーム内一面に広がるネギ畑。
『火星ネギ』として知られるこの品種が、火星で最初に根付いた作物だと言われている。
少ない水、荒れた土地でも瑞々しく立派に育つのが魅力だが、難点があるとすればそれは『主食にも主菜にもなり得ないこと』だろう。
ネギはうどんや蕎麦、焼き鳥などの添え物として非常に重宝されるが、それ単独で食されることはほとんどない。
しかし火星の開拓者たちは食糧不足に喘いでおり、何としてもこのネギから効率よく栄養を摂取する必要があった。
そこで火星ネギを原料とした栄養ドリンク開発チームが立ち上がったのである。
当時開発主任だったH氏はこう語る。
「ネギは風邪に効くと昔から言われていますし、ビタミン類も多く含んでいます。私も最初は『ネギで栄養ドリンクは無謀ではないか』と思いましたが、火星ネギの成分を調べれば調べるほど、栄養ドリンクの素材として相応しいと思うようになりました」
そう言って火星ネギの成分表を見せてくれた。
β-カロテン、ナイアシン、パントテン酸……確かに、栄養ドリンクの成分表示欄でよく見かける文字列が並んでいる。H氏によれば、火星ネギの成分は地球産のネギより濃いそうだ。
もちろんその分辛味と匂いも強いのだが、その主成分である硫化アリルを分解してアリシンに変化させることで疲労回復の効果が期待できるのだという。
まさに栄養ドリンクにはうってつけの素材だ。
だが商品化までの道のりは長かった。
まず糖が足りない。甘味自体は合成物で付加できるが、カロリーとしての糖が他から調達できないため、ネギから抽出しなければならなかった。
火星ネギは発育が良く豊作続きだったとはいえ、ある程度は食糧として流通させる必要があったため、開発チームは少ないネギから効率よく各種栄養素を分離抽出する必要に迫られたのだ。
次に、味と匂いの問題。硫化アリルを分解することで辛味を抑えることはできたものの、アリシンは不安定な物質で、熱を加えると二硫化アリルに変化して臭みの元になってしまう。
「この匂いを何とかしないと商品として売れませんよ!」
「いや、このネギらしい匂いこそがこの商品の個性であるべきだ!」
研究員たちは喧々諤々と議論し、工夫に工夫を重ねてようやく『栄養ドリンク』として相応しい成分を持つ商品を世に出すこととなった。
『MARS-Welsh DX』、火星最初の栄養ドリンク誕生の瞬間であった──
「MARS-Welsh(火星ネギ)とか、まんまなんだよなあ」
音希は作業BGM代わりにつけていたテレビに思わずツッコミを入れた。
『火星ネギの効能をギュッと圧縮』とかいうキャッチコピーと『まずい! もう1本!』『目が覚める強烈な味がクセになる!』といった自虐的なCMが受けて、MARS-Welsh DXの売上は出だしはまあまあ好調だった。そして一部には熱烈なファンも生み出した。
しかし今では取り扱う店舗は少ない。その理由は──
「ほんっっっとーーーーにマズいんだよね、アレ」
多少辛いのはいい。何か効く気がするから。
けれど香料をもってしても覆い隠せないネギともニンニクともつかない匂いが飲んだ後も口の中に延々と残り続けるのはいただけなかった。
そういうわけで火星最初の栄養ドリンク『MARS-Welsh DX』は今でも細々と生産されてはいるものの、その成果は後継のエナジードリンク『MARS ENERGY』に引き継がれることとなった。
こちらのエナジードリンクも『MARS-Welsh DX』を炭酸水で薄めたらだいたい同じと言われている程度には火星ネギフレーバーなのだが、飲みやすいよう匂いや味に様々な改良が加えられて目覚まし代わりにはちょうどいい風味に調整されていたし、また『火星といえばネギ!』と広く知られるようになった今では火星っぽいおみやげとしてもそこそこ人気を博しているのだった。
音希は手元の緑色の缶を一気に飲み干す。
「あーーー、マズくはないけど目の覚める味ーーー! ……じゃあもうひとふんばりしますか」
空になった缶を机の隅に置くと、音希はアクセサリー製作の作業を再開する。
緑色の缶には、火星のイラストと『MARS ENERGY Kasei-Negi Flavor』のロゴが描かれていた。
おわり
#ノート小説部3日執筆 お題「栄養ドリンク」タイトル「用法容量をお守りください」※同性愛表現/BL要素あり
寝不足の頭を振り、買い足した栄養ドリンクの蓋を開けると一気に呷る。
そしてポイッと床の上へと放り投げた。その瓶はカツンッと床に当たった後コロコロと転がり、数時間前に目を覚ます為に飲んだカフェイン飲料の小さな瓶に当たってカチンッと涼やかな音を立てる。
その瓶に一瞬だけ視線を走らせた後、またパソコンへと僕は向かう。
カタカタとキーボードのキーを打つ音が静かに誰もいなくなったオフィスへと響く。
後輩がしでかしたミスのカバーをするのは何も今日が初めてでは無い。それでも、なにもこんな日にこんな大きなミスをしなくても……と多少恨めしい気持ちになるのは致し方ないことだろう。
僕にとって今日、いやもう昨日になっているが、とても大切な日だった。
しかも、しかも、だ。
当の本人は僕に謝り倒しながらも用事があるとかでとっとと帰宅し、こんな真夜中まで明日の書類を作成し直している自分がバカみたいだった。
そしてオフィスデスクの上には何度もかかってきた着信で充電が切れてしまいすっかり静かになってしまったスマホ。その事も更に僕を憂鬱な気持ちにさせた。
きっと今頃家で彼は鬼のように怒っているだろう。それとも呆れ返っているだろうか。
折角、彼がこの日の為にと準備してくれた食事も、飾り付けも全部台無しにしてしまった。
残業が決まった時点でかけた電話では呆れたような声で「相変わらずお人好しだな」なんて言っていたけど、書類制作が難航し途中から少しでも早く帰る為にと、電話にも出なかったせいで聞こえてきた留守電に残された声には段々と苛立ちが含まれていくのが分かった。
それでも仕事を朝一番に間に合わせたくて、そして少しでも早く作業を終え彼が待つ家に戻りたくて彼からの電話にも出ずひたすら栄養ドリンクとカフェインを仕事の共にしてカタカタと資料片手に書類の作成に勤しむ。
……そういえば、彼からの着信が途絶えてからどれくらい時間が経ったのだろうか。
確か最後に時計を見た時は日付を軽く超えていた時間を指していたっけ。
そう思い、その後時計さえも見ずに仕事へ打ち込んでいた自分に呆れながら、視線を左腕に巻いている時計へと向ける。
彼が誕生日プレゼントに、と贈ってくれた大切な時計だ。
だけどその時計の短針は動いておらず、まだ貰って数か月しかしていない新しい時計なのに、と眉根を寄せる。
仕方なく視線を上げ、オフィスの柱に取り付けられている時計へと目を向けるとその時計もまた短針が止まっていた。
その事に益々眉根を寄せ、今度はパソコンに表示されている時計を見た。
「……止まってる?」
小さな窓に表示されている時計も待てど暮らせど1分が経過しない。
流石に何かがおかしいと気が付き僕は辺りを見渡す。
すると先程床に投げ捨てた栄養ドリンクの瓶が消えていることに気が付き、椅子から立ち上がる。どこかデスクの下にでも転がっていったのかと、部署に並べられているデスクの下を覗き込む。整然と並べられているデスクの下は、僕の予想に反して何もなかった。
体を起こし、僕は首を傾げて無意識のうちに栄養ドリンクの瓶をゴミ箱に捨てたのだろうかと記憶を辿る。
そんな僕の耳にカツンッと何か硬い物が床に当たった音が届き、その音の方へと顔を向けるとコロコロと足元までその音を立てた物が転がってきた。
そして足元に転がっているカフェイン飲料の瓶にぶつかる涼やかな音が静かなオフィスの中へと響く。
――それは、先程僕が飲み干して床へと投げ捨てた栄養ドリンクの瓶だった。
ぐわんっ、突然頭が大きく揺れる。
ふらふらとする視界に『僕』がまた栄養ドリンクを開け、勢い良くその中身を喉に流し込んでいるのが見えた。
そして空になったその瓶を床へと腹いせのように投げ捨てる。
カツンッ。コロコロ。カチンッ。
カツンッ。コロコロ。カチンッ。
カツンッ。コロコロ。カチンッ。
…………カツンッ。
何度も、何度も僕の耳に先程僕が投げ捨てた栄養ドリンクの瓶が床にぶつかり、そこから転がり、カフェイン飲料の瓶にぶつかって響かせた涼やかな音が繰り返される。
その音が響く度に僕の視界はぐわんっ、ぐわんっ、と大きく揺れ、煌々と灯っている筈のオフィスの電灯がチカチカと点滅し、ゆっくりと暗くなっていく。
ふらり、と体が揺れ、ドサッと言うなにか重い物が床へと落ちた音が鈍く耳へと届き、目の前にコロコロと栄養ドリンクの瓶がまた転がってきた。
「……え」
辛うじて出た声はそんな間抜けな物だった。
霞む視界の中で何度も、何度も目の前に栄養ドリンクが転がってきてカフェイン飲料の瓶へとぶつかる。
これは一体どういう事なんだろうか。僕は夢でも見ているのだろうか。
相変わらず頭はぐわんっ、ぐわんっ、と大きく揺れている。
寝不足の時に起こる頭痛と良く似た、でも似てない鈍い痛みに僕は転がってくる栄養ドリンクの瓶を見つめながら眉間に深くシワを刻んだ。
こんな無様に寝転がっている場合じゃないのに……そんな事を意識の底で思う。早く仕事を終えて、彼の元へと帰りたい。今日は僕たちがパートナーとなって一周年の記念日なんだ。
彼の好きな花だって花屋に注文してあった。取りには行けなかったけど……。彼が欲しいと言っていたブランドの革財布だってプレゼント用に包装して大事に鞄の中に入っている。
それをまだ渡していない。
僕は未練そのもので腕を伸ばす。
そしてコロコロと転がってきた栄養ドリンクの空瓶を掴んだ。
その瞬間、視界がぐるりと回る。天井にある電灯の点滅は早くなり、どんどんと視界が闇へと塗り潰されていく。
あぁ、僕は死ぬのか。こんな所で無様に。誰にも看取られずに。
彼にはまだまだ伝えたい言葉がたくさんあった。一緒にしたい事だってたくさんあった。
上司に連れられて行ったバーで、堅物で通っていた僕を「面白ぇヤツ」と言って笑った時の彼の顔が脳裏に浮かぶ。
その顔に僕は人生において初めて『ときめき』という物を覚え、彼が働いているバーに足しげく通い、自分とは何もかもが違う彼を必死に、不器用なりに口説いて、口説いてそしてようやくその心を射止めたのだ。
「まだ……まだ、死ねない……」
酷く重い口を動かしてそう掠れた声で呟く。
動かない体を必死になって動かそうともがき、闇の中で抗う。
だけどその努力も空しく、僕の意識はどろりとした闇に飲み込まれ、霧散していった。
ハッと気が付くと、僕はデスクの上に突っ伏していた。その僕の肩を誰かが強く揺すっている。
「……い、……んぱい……っ!」
焦ったような声に聞き覚えがあり、僕はのろのろと顔をその声の方へと向ければ、僕に残業を押し付けて帰った筈の後輩が泣きそうな顔をして僕の体を揺さぶっていた。
あぁ、良かった。すべては夢だったのか。
そう思い、ホッと息を吐いた。
――その耳にカツンッ、コロコロ……と、音が聞こえ、瓶と瓶がぶつかるカチンッと涼やかなぶつかる涼やかな音が木霊した。
#ノート小説部3日執筆 「栄養ドリンク」栄養ドリンクでも救えない
昼休みの時間の休憩室。私と2年上の先輩の視線は上の一点に集中していた。
テレビ。昼休憩の時だけつけていいので番組の内容が会話のタネになる。
今日の番組は、通販番組だ。というか私と先輩の入っている土日のシフトだと、大体が通販番組が多く、ドラマの再放送と運が良ければのど自慢ぐらいしか映らない。なぜかといえば、ここが都会から遠く離れているから、都会の番組が流れないという簡単なことで、チャンネルを変えて良さそうなものを選ぶ。
のど自慢は私と先輩が運よく早めに午前を終わらせたときにじっくり見れるが、大体お昼前はお客が駆け込んでくるので、見れるのは滅多にない。見れたときは午後も頑張れる気がして良いし、先輩と楽しく昼食を取れて最高なのだが、流石にのど自慢が見たいという理由だけでお客を無碍にすることはできない。
見てる通販番組は、大手の通販番組だ。社員自らが出演してモノの良さを語るところではなく、商品の説明と良い点、値段などがナレーターに読み上げられ、買った客の声を直にお届けするところだった。
「この、掃除機どう思う?」
そう言った後におにぎりを食べている先輩の姿をチラリと見て、そしてまたテレビに視線を戻す。口内に残っていたパンを飲み込んで、自分なりの答えを言う。
「このノリ、何ヶ月か前にやってた掃除機の上位互換、と言うか下位互換な気がしますね」
「だよね、いくら軽いからって言ってもすぐゴミ入れるところがパンパンになりそうって前は言ってたのに、更に小さくなってるでしょあれ」
「この外国人のワオ!って驚く顔も何回も見た気がして嫌になっちゃうな」
「チャンネル変えます?」
「他もどっこいどっこいだから変えないでいいよ」
「そうですか」
長い商品説明や良い点が終わり値段の発表がされた。それは性能の良いと高評価の掃除機より安いが、さっきまで映されていた掃除機を見ると高く感じる。アタッチメントを複数つけてさらに安くしてもいらないと感じる。この番組前にはミキサーにフードプロセッサーの下位互換をつけていた。フードプロセッサーは300均一の方が良い品質のものが手に入る。しかも安い。ミキサーを通常価格で買ったとしても通販番組の値段にはならないだろう。
呆れながら、パンを再び口に入れる。昨日スーパーで値下げされていたパンだ。賞味期限が近いと言う理由で値下げされてただけなので、別に味に問題はない。ただ一つ言えば私の食生活が異常なだけだ。朝もパン、昼もパン、夜も米が食べたいとき以外はパンだ。大体一個ぐらいで満足するのも良くないとわかっているが、私はダブルワークで平日も仕事、土日も仕事してると料理をすることすら億劫になってしまい、パンを食べることが一番いいと思ってきている。
米を食べるときは米を買ってきて研ぐのではなく、お弁当屋さんで一番安いのり弁を頼む。たま〜に外食はするが、安い定食でも品数が多くて腹がいっぱいすぎて気持ち悪くなることがある。だから、私の食事はパンだ。
「次は青汁だね」
「青汁っすか」
青汁、苦いが体には良いときく。飲めば疲労もマシになるかなと期待して見たが、青汁が粉に水や湯を入れたものだと知ると一気に飲む気がなくなった。ここは都会ではないが、賃貸の水道関係で、水が飲めたものではない。お湯にすれば確かにマシだが、わざわざ棚の奥にしまっているケトルを取り出して、洗って、丁度の水を入れて沸かして、コップに注いで、洗って、片付ける、工程を考えただけで面倒だ。ウォーターサーバーなら、おいしい水とお湯が飲めると聞いたが、設置する料金、毎月のボトル交換の値段を提示されて即座に断った。
「青汁もいいけど、一番はサラダ食べることだよね。サラダ食べる?」
「サラダはあんまり買いませんね」
「じゃあ青汁」
「青汁も買いません」
「今日も、それだけでしょ。流石に栄養とった方がいいと思うなぁ」
「サプリとかですか」
先輩は首を振る。
「サプリも多量だとよく無いし、ちゃんとした食事があって、不足分を補う形だからなぁ」
「じゃあ、私は無理ですね」
「うん、そうみたいだね」
「あっそういえば」
テレビのCMで思い出した。エナジードリンクなるものを。会社の同僚は「よく飲む」と言ってたがどうなのだろうか。
「エナジードリンクは……?」
「サプリよりももっとダメ」
「なんでですかCMにも出てますし」
「ちゃんと効能が書いてないでしょ。それにあれはコーヒーよりカフェインが多いの。体壊すよ」
「そうですか……」
「それの代わりに栄養ドリンクを飲むのはどう? エナジードリンクより安いものもあるけど、私はこれがおすすめかな」
上に向けられていた視線を下げて先輩のスマホを見る。商品紹介のページでおすすめされている栄養ドリンクが表示されている。
「ちょっと高いけど、疲れによく効いて、朝すごいスッキリ起きれるんだよね。画像ラインで送っておくから、買ってみたら?」
「そうですか」
送られてきた画像を見るが、値段がちょっと高いと先輩はいったが、私にとっては高いものだ。
「買ってみますね」
と言って、会話を終わらせてパンを食べた。このパンを食べるのも何回目だろうか。毎日とは言わないが三日に一回は食べてる気がする。それほどまでに金に困っているかと言われればそれはそれは困っている。一人暮らしなら、平日の事務の派遣だけで充分だが、親がこっちに来て脅しに来ないように、母と父両方にそれなりのお金を振り込み、また実家から出れない妹が無事高校を卒業して、大学に入れるだけの資金を貯めている。妹は私を思って高卒で働くと言っているが、実家にいて稼ぐようになると、より逃げられなくなる。しかも親は気まぐれなので妹が何か機に食わないことをするだけで、支払いを止めることがある。一緒に実家に住んでいたときは、バイトを掛け持ちしていたので代わりに支払ってた。バイトを掛け持ちしてたのは、親の癇癪をお金で解決するためと一人暮らしをするための資金集めのためだった。
お店を閉めて、先輩と別れる。真反対なことが良かった。
私は疲れ切った体のままスーパーに入り、同じように値下げされているパンと他の飲料より値下げされている麦茶を大きいペットボトルで買う。水も大きいペットボトルであったが、最近の防災意識の高まりでほとんどが消えている。スーパー独自のブランドの水が一本残っているだけだ。そこまで必要を感じないので、麦茶にしたが結構重い。疲れているからだと思い、レジに並ぶと、たまたまレジ横に置かれている飲料を見た。そこには栄養ドリンクが売られていた。でも先輩から送られていた画像の栄養ドリンクはない。私は少し考えた後、一番安いものより二番目に安い栄養ドリンクをカゴに入れた。二番目にしたのは、一番安いのはお腹壊しそうで怖いなと思ったからだ。
夕食を食べて、風呂に入り、気絶するように寝る、その前に栄養ドリンクを飲んでみる。味は不味いとは言えないが美味しくとも言えない。少しは疲れが取れてればいいなと思いながら就寝し、朝を迎え、派遣の仕事に出勤した。疲れは変わらずあり、強い眩暈が起きたかと思うと、知らない天井を見ていた。
どうやら医者の言うところでは栄養失調になっていて入院らしい。とりあえず寝た。
#ノート小説部3日執筆 お題【栄養ドリンク】騎士恒例の飲み物(鼻血が出ます/BLっぽさはない)#おっさん聖女の婚約
「俺のお手製なら、飲むんだ……?」
俺の作った飲み物を渋い顔で見つめる男。色男はそんな顔ですらかっこよく見えるんだからすごい。俺がジークヴァルトくらいの年齢だった時はどうだったかな。
十年以上も昔の頃を思い出そうとして、やめた。だめだめ、そういうのは老け込んじゃう原因になるから!
「ヴァルト、今まで拒否し続けていたんだって?」
「……こんな得体の知れないもの、飲みたがる人間などいないだろう」
ジークヴァルトの言いたいことは分かる。これは騎士団に伝わる怪しい飲み物だ。いや、まあ……材料が材料だから嫌煙される感じで、実際は単なる栄養ドリンクである。
見た目は……あまり良くないな。材料のせいで。え? 材料? 多分聞かない方が良いと思う。
「でも、効くんだよ。疲労に」
「なぜ俺が!」
相当嫌らしい。珍しく俺に対して声を荒らげる相棒を見て、嬉しくなった。さて、どこまで受け入れてくれるのか楽しみだ。
俺は彼の手にコップを握らせながらさらっと言う。
「きみが疲れているんじゃないかと思って作ったんだ」
言い聞かせるような口調にしないのがコツだ。もちろん嘘ではない。この飲み物は「ラウル聖女特製の特別な飲み物」だ。騎士はだいたい、この飲み物が作れて一人前だからな。
俺だって悪習だと思うが、効果はてきめん。この飲み物が作れなければ、という先輩方の考えは分からなくもない。
「……お前が、作ったのか?」
「当たり前だろ。作れなきゃ、先輩騎士に可愛がってもらえなかったもん」
幸か不幸か、ジークヴァルトはこういう変な騎士の決まり事に巻き込まれる前に魔界の扉騒動が始まった。だから、彼は騎士のふざけた行事に疎いのだ。
こういうのを勢いよくこなすと、先輩からの反応が良い。気に入られておけば、自由に過ごすことができる。つまり、これは処世術の一つだった。
忖度しすぎて身を崩す残念な騎士がいたのは確かだが、元々良いとこの出身者だからな。そんなに風紀は乱れなかったってわけだ。
お上品で良いですこと! そんなわけだけど、これを飲ませたいのには理由がある。二つくらい。
一つ目は、単純に今日の戦闘が大変だったからだ。結構ジークヴァルトに無理をさせてしまった。だから、これを飲んで元気になってほしい。
ある種の労いってやつだ。
二つ目は、俺が作ったものならどこまで許容できるのかが気になったから。ジークヴァルトが頑なにこの飲み物を飲もうとしないと聞いた。
支給されるそれを見ると、小さく首を振って拒否するんだとさ。
断られる方の身にもなってみろ。せっかく用意したのに悲しくなっちゃうじゃないか。俺のひと言で飲めるようになるのなら、今後もそうしていけば良い。
ってことで、検証中なのだ。ジークヴァルトは俺のことを見つめてから自分の手元へ視線を落とし、それこそ何でもないかのように、すっとカップを口に運んだ。
さっきまでの拒絶する以外の選択肢はない、という態度はどこへやら。食後のコーヒーみたいな気軽さで、くいっと飲んでしまう。
「相棒の作ったものに、毒はないだろう。随分と独創的な味だが……」
飲めなくはない。と続けた彼の顔色は徐々に赤くなっていく。そんなに顔色が変わる飲み物だったっけか? 俺、何か間違えちゃったかな。内心でドキドキとしている俺の目の前で、残りの飲み物を飲み干していく。
え、大丈夫? 本当に大丈夫?
ドキドキ、というよりもハラハラする。血色が良すぎてもはや怖い。表情はいつも通りだけど、顔が真っ赤っか。実験的な考えは、どこかに飛んでった。
こうなると、ただただ彼が心配なだけだ。
「……大丈夫?」
「何がだ?」
無理して飲んだのだろう。ちょっと目が据わっている。彼は表情や顔色とは裏腹に、丁寧にコップとテーブルへと戻した。
「あ」
美丈夫の顔に、赤い一線が。鼻血だ。栄養ドリンクで鼻血って出るんだっけ!?
赤く染まった顔に、鼻血。どこからどう見ても、何かヤバい。良い男が台無しすぎる。
「ヴァルト、ちょっと、まって。あの、動かないでっ」
「何を慌てている?」
いや、訝しまれても困るから! 俺は大慌てで近くにあったタオルを彼に押しつける。あーもー、どうしてこんな状になるかな? あ、俺が原因か。ごめん。
今までこの飲み物を飲んだあと、ひっくり返ったりした人間は見ていない。ジークヴァルトだって、ひっくり返ってはいないが……いや、しかし鼻血である。顔面をぶつけたとか、強く叩きつけられたとかでもなく、普通にしていて鼻血。
「鼻血がね、出ちゃっててね」
「それはお前の反応を見ていれば分かる」
「おい!」
何だろう。どこかジークヴァルトは楽しそうだ。
「飲み物を飲んで鼻血を出したのは初めてだ」
「俺だって、そんなのに遭遇するのは初めてだよ!」
ああ、もう。様子を見る為にタオルを鼻から離す。鼻腔からたらりと落ちていく赤い雫を見て、再び布を当て直した。全然鼻血が止まりそうにない。しばらく駄目そうだ。
「ラウルの力が強すぎたのでは?」
「は?」
「どうやら俺は元気になりすぎたようだ」
「ヤバい、俺のベルンが壊れた」
ふっ、と笑みをこぼした相棒に、危機感を覚えた。どうしよう。困る。どうやったらまともに戻ってくれるんだろう。
動揺する俺をよそに、ジークヴァルトはとてつもないマイペースさを発揮している。どんどんタオルの色が変わっていくしどうすれば良いんだ、と頭を抱えたい気持ちになっていると、たまたま通りすがったらしいアエトスが「わあ、すごいことになってるね」と声をかけてきた。
「騎士の飲み物を与えたらこんなことになっちゃって」
「……普通に神聖魔法で癒してみたら治るんじゃないかと思うけれど」
「あっ」
俺の驚く声を聞いてくすくすと笑った彼は、ジークヴァルトがどうなるのかも分からぬ内に去っていった。
どうしてそんな簡単なことが思い浮かばなかったんだろうか。そんなことを思いながら癒しの詠唱を行えば、すぐに解決した。
何だったんだろう。この時間。
ジークヴァルトの鼻血で汚れたタオルを握りしめ、俺は深いため息を吐くのだった。
『不定形で不安定な栄養』 #ノート小説部3日執筆 お題「栄養ドリンク」 #みづいの スピンオフ
「おかえりー」
気の抜けた青年の声が出迎える。……ここは私一人の自宅なのだけれど。
「また勝手に上がり込んで……」
「勝手に、って言われても。俺はちゃんと合鍵使って入ったよ」
「合鍵を使えばいいというわけではありません。しかもうちの冷蔵庫まで漁ったんですか?」
ため息混じりに発した問いかけへの返事はなかった。しかし、彼の手中にある小さな瓶を見れば答えは明らかだ。
「仕事熱心なのはいいけど、栄養ドリンクやらエナジードリンクやらに頼るのはやめなよ」
しかもこれ不味いくせに高いし。すっかり空になった瓶を振りながら、青年――薬師川さんは呆れたように笑った。私は再びため息をつく。
「私が自分に対して何をしようと自己責任でしょう。薬師川さんが口を出す権利はありません」
「亜理紗さんを心配してるだけなんだけどなー」
「どうだか。あなたは自分の避難先を失いたくないだけでは?」
否定はしない。苦笑混じりの言葉が返ってくる。何が「否定はしない」だ、それ以外に理由なんてないくせに。
この青年が適当なことを宣うのはいつものこと。それなのに、今日はどうしようもなく気に障る。もしかしたら、自分で思っていた以上に疲弊しているのかもしれない。さっさと休息を取ろう。そのためには――。
「今日はもうお引き取りを。疲れているので」
「まあまあ、そう言うと思って、俺もちゃんと準備してきたんだよ?」
何を。聞き返すより早く、彼は台所へと歩いていった。そう時間が経たないうちに、丸型のお盆にいくつかお皿を乗せて戻ってくる。
「はいどーぞ。亜理紗さん、夕飯まだでしょ?」
「……は?」
「いや『は?』じゃなくて。疲れたときはまずご飯でしょー」
食べて食べて。ぐいぐい押しつけられるそれを反射的に受け取った。瞬間、ふわりと漂う出汁の匂いが鼻をくすぐる。
「苦手な食材とかあった? まぁあっても食べてもらうけど」
「い、いえ、特には……」
豆腐ステーキに野菜の味噌汁、焼き茄子と混ぜご飯。それなりにバランスが良さそうな食事だ。これを用意したのが彼――日頃から「面倒」を口癖としている青年――であるという事実に目を丸くする。
「何? 食べさせてあげようか?」
ふざけた発言は無視して、私は「薬師川さん」と呟いた。すると、彼は黙って首を傾げる。
「一体どういう風の吹き回しです。こんなに手間のかかることをするなんて」
「んー」
何とも形容しがたい唸り声を上げた青年は、直後くすりと笑う。
「医食同源、って言うでしょ?」
「理由になっていません」
「そうかなー。まぁ俺がやりたくてやってることだから、亜理紗さんは気にしなくていいよ」
曖昧な言葉で煙に巻こうとする薬師川さんをじっと見つめると、彼は笑みを深めた。ここで笑顔になる意味がわからない。
きっと、今の私は相当怪訝な顔をしていることだろう。しかし彼は指摘してこないまま、そっか、と声を発した。
「亜理紗さんが栄養ドリンク買ってくる度に俺がご飯作ればいいのか」
「……突然何を言っているんですか」
万事解決とばかりに大きく頷く青年を睨みつける。頭一つ分ほど上にある彼の顔が、わずかに近づいてきた。思わず身を引く。
「顔色悪いし、若干だけど肌荒れしてる。しばらくまともなもの食べてないでしょ」
「……」
図星だ。しかし素直に肯定するのも癪に思えて、私は沈黙を貫く。……頭上から吹き出すような笑い声が聞こえてくるまでは、の話だったが。
「あっはは、黙ってたってすぐバレるのにー」
「……はぁ。それで、私がまともに食事をしていないことはあなたの発言に関係あるとでも?」
「あるよ」
やけに明瞭な声が断言する。薬師川さんは今までの笑み――明るく、それでいてどこか軽薄な――を消し、改めて私を呼んだ。
「俺は、亜理紗さんに健康でいてほしいよ。逃げ場だとかそういうこと抜きにして、あなたが苦しむところは見たくない」
「……きょ、今日は珍しいことばかり言いますね」
まっすぐな視線が痛くて、私は誤魔化すように話題を変える。槍でも降るんですか、なんて空虚な笑い声を上げながら。しかし、その笑いもすぐに鎮圧された。青年の目が鋭くなる。
「ガラじゃないのはわかってる。でも俺がこんな行動に出るくらい、今の亜理紗さんは心配なんだよ」
「心配、なんて――」
必要ない。そう言い切る前に「黙って」と言葉を封じられた。言われるがままに口を閉ざし、薬師川さんの言い分に耳を傾ける。
「前に『立ち向かう状況が違っても戦友だ』って亜理紗さんが言ってたでしょ。俺はそれに倣って『戦友』が道半ばで倒れないように心配してるだけ」
これでも納得できない? 青年の言葉に首を振り、私は小さく息をついた。
「……わかりました。そういうことでしたら、遠慮なく」
いただきます。手を合わせて箸を取る。もくもくと食べ進めながら、料理が体内を満たしていくのを空想した。……これだけ美味しい料理が身体を構成していくのなら、それも悪くない。
#ノート小説部3日執筆 栄養ドリンク
「おはよーっす」
「おはようございます」
挨拶をすれば菅原さんはとんとんと目の下を叩いて見せた。
「なんです?」
聞けば、彼は一瞬顔をしかめ、ガオー! と手を開く。
「クマ! 目の!」
「ああ……最近寝不足で……」
菅原さんは呆れたように彼の髪をグシャッと握った。
「だめだろ、ちゃんと寝なきゃー」
「寝れないんですよう」
「バランスよく食べて! どうせ朝抜いてるんだろ?」
「まあ……昨日食べたかな……?」
菅原さんは顔を歪ませて何か言いたそうな顔をした。
「……こんど差し入れよっか、ほら、あの寝れる乳酸菌とかいうやつ」
「え、別にいいですよおー」
「まったく、手のかかる後輩だもんなあ……若いったって、健康には気をつけなきゃ」
やれやれと呆れたようにして、菅原さんは席についた。
そこで僕は気づく。机の下に並んだ小さな空き瓶。
「菅原さん……」
「んー?」
菅原さんはその小さな瓶をひとつ手に、錠剤を飲もうとしていた。
「それ、なんですか!」
「高血圧の薬」
「そーじゃなくて!」
「コレ? 栄養ドリンク飲まないと朝起きた気がしなくてなあ」
「どっちが『健康に気をつけなきゃ』ですか!?」
「俺はいいんだよ」
はあ……とため息をひとつ。
「どっちが健康か勝負しましょうか。今度の健康診断」
「お、いいよ。歳のハンデなんか目じゃないところ見せてやる」
ひと月後、そろって撃沈したことはいうまでもない。
#ノート小説部3日執筆 『時期のズレた贈り物』
久しぶりの休みの日。不在票を再配達してもらう日時指定を、こういう時に集中させているせいで、昼間から荷物が大量に届く。家にもう一人いると楽なのだろうと思うこの頃。
伝票を確認して、開けずに段ボールごと仕分けていく。
野菜は台所、化粧品は洗面所、ウォーターサーバーのカードリッジは……これも台所でいいかしら。
一つだけ、覚えがない箱があった。送り主は知らない名前。送り先を見ると『月雲(つくも)市 月雲区 留紅――』とある。
月雲なんて遠い都会に、知り合いは居ないと思うけど。
開封してみると、中身は箱入りの瓶ドリンク。いわゆる栄養ドリンクというやつだ。しかも、よくCMを見るものではなくゴールドの強いやつ。えぇと、8本入りの箱が8箱だから、64本もある。
その箱の上に封筒があった。中身は手紙だ。
どうやら、息子を保護している方からの手紙らしい。時候の挨拶から始まり、突然贈り物をしたことへの謝罪、息子の近況が書かれている。良かった、あの子はちゃんと元気みたいだ。
封筒をひっくり返すともう一つ、
『前略 母ちゃんへ お中元です。身体に気をつけてください。草々』
それだけ書かれたメッセージカードが一緒に入っていた。相変わらず言葉が少ない子だ。誰に似たんだか。
本当に、口数の少ない息子だった。
必要な事以外はあまり語らない、減らず口やワガママもほとんど無い子。
私はいつも遅くに帰ってくるのに、わざわざ『おやすみなさい』を言うまで起きていた子。
誕生日に何もしてあげられなかったのに、ただただ笑ってくれた子。
14回目の誕生日を祝う前に、実験に志願して、私の前からいなくなってしまった子。
楽しかった思い出はいくらでもあるはずなのに、思い起こすのはいつも『何もできなかった』記憶だけだ。
欲しがったらなんでも与えてあげよう。家に一人で寂しがるだろうからせめて、楽しく過ごせるようにしてあげよう。そう思って、何でも用意してきた。欲しいと言われれば出すつもりでおもちゃだって買ったし、流行っていたマンガだって揃えた。
結局あの子が欲しがったのは、分厚い問題集だけだった。勉強しろと言った覚えは全く無いのに。
もっと子供らしく、遊んでいてほしかったのに。
あまりにもあの子が何も強請(ねだ)らなかったから、押入れには今でも、当時流行っていたゲームが未開封で置いてある。なんなら、新しいものが出るたび買っている。私が遊ぶわけでもないのに。
いずれあの子が戻ってきたら、全部あげるつもり。でもあの子は、いつも通りに目を伏せて「いらないよ」と言うだけだろうか。
そもそも、戻ってくる保証はないけど。
ふと、メッセージカードの裏にもなにか書いてあることに気付いた。電話番号だった。
ためらう間もなく電話をかける。会えなくても、声が聴けるなら。
『はい、こちらリムディズ事務きょ――』
「洋平?」
しまった。つい早まって遮ってしまった。
『……ちょっと待ってて』
仕事中だったみたい。申し訳ないことしちゃった。そうよね、今日は平日ですもの。私の休みが不定期で、つい忘れちゃうわ。
しばらく、というほど待たなかった。
『……もしもし、母ちゃん。元気?』
ああ、やっぱりあの子だ。電話越しだし、さすがに声変わりしているけど、間違いない。
「えぇ、元気。贈り物が届いたから、お礼の電話をね」
『……そんなこと、しなくていいのに。やっぱ、律儀、だね』
話し始めのどもり方といい、妙にたどたどしい言い回しといい、変わっていないみたい。
「飲み物、ありがとうね。助かるわ」
『……そう?良かった。そろそろ、忙しい時期だろうし』
確かに、そろそろハロウィンにクリスマスと忙しくなる。彼なりに身を案じてくれたのだろう。
『……えっと』
ああ、あの子は長話が苦手だった。その上、会話を切るのも苦手だった。
まだ仕事中みたいだし、ここらで通話を終わらせてあげないと。名残惜しいけど、仕方ない。
「私も頑張るから、あなたも、ちゃんと食べてちゃんと寝て、頑張りなさいね」
激励と、労いと、あと言いたいことはいくらでもある。それを全て言うのは、あまりにも長くなり過ぎる。
『……うん、頑張るよ。ありがと』
少し声が明るくなった。昔どおりの照れ隠しだ。
「うん、じゃあ、また連絡するわね」
『じゃあ、ね。また』
それだけ言って、電話が切れた。
これからはたまに電話してあげよう。せめて、あの子の誕生日くらいは連絡しないと。
そう、あの子の誕生日まで、一週間を切っている。こちらからも、贈り物をしてあげなくちゃ。
十年以上、なんならもっと送れていないもの。ちゃんと選んであげないとね。 [参照]
#ノート小説部3日執筆 「嘆きの味」/お題「栄養ドリンク」 !注!このお話はフィクションです
もうこれで何日目の残業だろうか。
俺は、新卒で入社した印刷会社の営業として仕事をしていた。
その会社は工場が併設されており、2階はオフィスになっていた。
異変は入社して1週間ほど経ってから始まった。
俺は先輩とルート営業を行い、夕方……定時に近い頃に帰社した。
今日訪問した営業先の情報や、名刺、見積書の作成を行い、さて帰るか、と思ったときだった。
オフィスの奥に座っていた専務が言う。
「あ、それ終わったら下の工場手伝って。みんな残業だから」
(……?)
疑問には思ったが、俺は新社会人になって張り切っていた。
スーツのジャケットを椅子にかけると、工場へと降りていく。
「まぁ、仕事だしそういうこともあるのかな」
「お疲れ様ですー、お手伝いに来ましたー」
「あぁ、〇〇さん、こっちこっち」
工場で働いているパートのオバちゃん達に手招きされ、作業に取り掛かる。
手順を教えてもらい、封筒に二つ折りにした用紙を差し込んでいく。
それにしても作業量が多い。
簡単な作業ではあるが、作業机の上には30cm近い高さの紙の束がいくつもそびえていた。
途中、休憩を挟みながら、作業は深夜まで続いた。
終わる頃には、終電の時間をとうにすぎており、家には30分ほどかけて徒歩で帰るしかない。
するとオフィスに接している社長宅から社長が降りてきた。
「みんなお疲れさん。はいこれ少ないけど飲んでくれや」
差し出されたのは栄養ドリンクだった。
俺は一息に飲み干すと、社長に例を言い、タイムカードを切って帰途についたのだった。
しかし話はそれで終わらなかった。
残業は毎日行われ、毎週行われ、毎月行われた。
ときには土用も日曜も出勤することがあった。振替休日というものはなかった。
それでも俺は初めての勤労経験ということでとても力を入れていたので、苦ではなかった。
そんなある日、朝礼で社長が言った。
「そろそろ仕事も落ち着いてきたし、ミスのないように」
俺はそれを聞いて、より一層気を入れた。
それから何日かは残業のない日々が続いた。
俺は一人でもルート営業ができるようになっていて、訪問先も裁量で決められるようになっていた。
その日は電車で訪問先を回っていたので、昼食は公園でとることにした。
スマホを取り出して、食後のスケジュールの確認をする。
しかし妙なことに気づいた。
インターネットブラウザを開いて、「死にたい」「希死念慮」といった単語を検索していたのだった。
出掛けに社長から「今日もよろしく」と手渡された栄養ドリンクが手から滑り落ちた。
俺は初めて、心が壊れる音を聞いた気がした。
#ノート小説部3日執筆 栄養ドリンクは飲まなくていいよ/お題「栄養ドリンク」
「まっずいなぁ、コレ……」
どうしても欲しいものができて――
金が必要になったから、日雇い夜勤で働き始めた。
仕事は思った以上に肉体労働。
時計の針が天辺を回ったところで、初めて栄養ドリンクを飲んだ。
薬局のプライベートブランドらしいリポジトリやらアキハバラやらの親戚を、金属製の蓋を開けて一気に飲み下す。
舌に乗る味は始めは甘い。だが、喉を通り抜ける後味は科学的な苦さと甘さが残って複雑で、いまいち理解できなくてえづきそうになる。
せっかくだからと、少し高いヤツを買ったのになんだかな。
これなら、緑なモンスターの方が幾分マシだ。
「慣れてないと、安いのの高いのでも不味いよな」
「てことは、高いのはもっと不味いんですか?」
「うん、めっちゃマズいよ」
あまりのまずあじでゲーしていたら
したり顔の先輩が寄ってきた。
今度奢ってやると言いながら、その日は普通に働いて――
翌日、先輩は何本かそれっぽいドリンクを持ってきてくれた。
どうやら、奢りらしい。
やったぜ。
「で、持ってきたってわけよ」
「見た目から高そうだけど、安いのもありますね」
「マズいドリンクだけ飲んでも悲しいからな」
というわけで、まずは安い奴から飲むらしい。
奢りなので喜んで金属製の蓋をパキりと開ける。
飲んでみると、さらっと甘いが酷い後味もない。
むしろこれなら昨日のやつより美味い。
したり顔の先輩は、相変わらずしたり顔だ。
「モンエナより美味くないですか?」
「量が少ないし、あんま効かないけどな。でもどのプライベートブランドでも、一番安い奴は大抵不味くないぜ」
へぇ、良いことを聞いた。
まぁ、効かないならエナドリの方がいいけど。
そう思いながら、もう少し高い方の瓶を開ける。
量は半分くらいしかなく、喉の乾きは癒えそうにない。
でも口にしてみると、これがなんとも不味いこと。
一口目の濃さとまずさが段違いだ。
甘さは多少はあるような気がしないでもないが――
そういう話じゃなく、変なえぐみが最初に来るのは聞いていない。
飲み込んでみると、何故か後味が辛い。
お高い原料のうちのどれが原因かわからん。
でも、正直言わなくてもマズい。
ひどい味過ぎて、文句の一つも言いたくなる。
「本当にまっずいなぁ、コレ!!」
「真面目に高いヤツだから、しょうがないんだよ」
「にしても、限度がないですか」
「そもそも、医薬品扱いの栄養ドリンクは味で買ってもらう必要がないんだよ。効き目が良ければ味は二の次だから、元気を維持したいときは、医薬品部外品の美味いヤツ。元気を発揮したいときは、医薬品扱いの高いヤツを選べば外れナシってわけだ」
「じゃあ、逆に美味い栄養ドリンクの見分け方とかあるんですか」
「人工甘味料が入ってないヤツの方が後味が良い。でも、人工甘味料が好きなら、入ってるヤツの方が好きかもな。正直、値段含めて飲み比べるのがいい」
そういって、ドヤる先輩のお陰で五百円くらい得をしたのも今は昔。
気づけば、昼の仕事の時も栄養ドリンクを飲む機会は増えた。
エナドリがあまり健康にいいわけじゃないから、乗り換えた形になるが、栄養ドリンクを飲み続ける生活がそもそも健康に良くないことに気づいてからか、医薬品扱いの高い栄養ドリンクに頼らないようにいろいろと気遣っているつもりだ――
「にしても、まっずいなぁ、コレ……」
その日も時計の針が天辺を回ったところで、高い栄養ドリンクを飲んで、口直しにコンビニのシュークリームを飲み込むように齧り付く。
やわらかい生地を頬張り、カスタードクリームを口いっぱい放り込んだところで、乳脂肪分由来の甘さが高い栄養ドリンクの酷い後味を中和してくれるような気がする――
あれから、幾らか栄養ドリンクを飲み比べたものの、高級な栄養ドリンクは正直どれも五十歩百歩に不味いものばかりだ。
そんなことに、気づきたくはなかった。
もう名前も思い出せない先輩にドヤ顔されないように、転職を硬く心に誓いながら、俺は暗い天井を見上げた。
「譬?、翫ラ繝ェ繝ウ繧ッ、翼を授縺代k」 お題:栄養ドリンク #ノート小説部3日執筆
「富田、見ろよ!このニュース!」
会社の食堂で、同僚の岡が、鼻息荒く携帯の画面をこちらに押し付けるように見せてきた。そこにあったのは、フェイクニュースともとれるほど、奇妙な文章だった。
「栄養ドリンクで、翼が生える……?」
「凄えだろ!海外じゃ空を飛んでるやつもいるらしいぜ!」
ほら、これ!と彼が見せてきた動画には、確かに大きな翼で空を飛び回っている人間がいた。正直、頭が追いつかないし、はしゃぎ回る岡を静かにするために「かなり出来の良いフェイクニュースだろ」と否定することで、その日を乗り切ることにした。
次の朝、テレビを点けると映っていたのは、腕から白い何かを生やした岡が生放送の街頭インタビューを受けている映像だった。何故かタンクトップの岡には、脇から小指にかけて翼が形成されており、インタビュアーの前で羽ばたいて数m浮かぶ姿さえ見せていた。
私は、それを見て、文字通り開いた口が塞がらなかった。しばらく一言も発することなくテレビを見つめ続けていたが、インタビューが終わると同時に、スマホから着信音が鳴り響いた。画面には岡の名前が表示されており、私はそれに素早く反応した。
「もし……」
「もしもし!富田、見てたかテレビ!!」岡が携帯のスピーカーすら壊すような声で喋る。
「見てたよ……お前、どうやって翼なんか」
「昨日見せたニュースあるだろ?あの日、ネットであれから進展があって、生やす方法が発見されたんだ。凄いんだぜ、この体。ちゃんと空飛べる上に、全然疲れない。なんか体が軽くなったような気もするし」
「お前、それ本当に大丈夫なやつか?」
「大丈夫だろ、多分。まあ、方法だけ教えといてやるよ。」そう言って彼は電話を切ってしまった。
その後すぐ、岡から例の栄養ドリンクが買えるリンクと「7本一気に飲む」とだけメッセージが送られてきた。少しの葛藤の後、私はそれを注文した。
翼が生えてから、私の生活は一変した。満員電車と無縁の生活、何より無尽蔵の体力のおかげで、私達はどこへだって飛んでいけるようになったのだ。海、山、砂漠、どんな景色だって翼のおかげで見に行くことができる。人類は真の自由を手に入れたのだ。その流れは世界中に広がり、多くの人々が空を飛ぶようになった。
他人に強制させるつもりは無いが、翼が無いままの人間はこの恵みをどうして享受しないのか不思議でならない。翼を生やす過程で死んでしまう事故があるそうだが、そんな些細な障害を気にしない気概こそ新人類に必要なのだ。などと高層ビルの屋上で岡と栄養ドリンク片手に談笑していた時、ふと服を取りに帰ろうと思い立った。どうやら長い間家に帰っていないようで、着ていた服がかなり汚れていることに気がついたのだ。
岡に別れを告げて、直接マンションの7階の通路に降り立つ。久しぶり帰った部屋の床には、ドリンクの瓶が所狭しと転がっていた。これでは足の踏み場もないため、仕方なく瓶をどかしていく。その過程で汚れた右翼を洗うために洗面所に向かい、鏡の前に立ったとき、私は自分の姿に違和感を覚えた。
首から何かが生えている。首だけではない、胸も羽毛のようなもので覆われているのだ。「」は、「右手」の「指」は3本ではなく、もっと多かったはずだった。そう気がつくと同時に、呼吸と鼓動が早まり、全身から汗が吹き出る。私は咄嗟に下を向いた。自分の体ですらここまで変化しているのに、顔が無事である保証は無いと判断したからだ。私はそのまま目を瞑り、鏡を見ないように後ろを向いて洗面所から出ていった。
何とかリビングまでたどり着き崩れ落ちるように床に座り、大きく深呼吸をする。色々と考えたいことがあるのだが、頭に靄がかかったように思考が安定しない。私は一先ず、岡に電話をかけることにした。
「おう、どうした?服見つかったか?」岡はいつも通り気さくに電話に出た。
私は纏まらない思考を制御し、慎重に喋り始める。「あの、さ。体のことなんだけど。お前、自分の体が今どうなってるか分かるか?」
「どういうことだ?」
「家に帰って、鏡を見たんだ。そしたら、体に、羽毛が生えてんだよ。なんか指も少なくなってるし。お前は今どうなってる?」
「どうって…………普通だぜ?」彼はさらっと答える。
「普通って、つまりどう」
「お前と、一緒」
まだ指がまともに残っている左手から力が無くなり、携帯が滑り落ちそうになるのを必死に抑え、通話を続けようとする。しかし、言葉が出てこなかった。「大丈夫か?」と岡が聞いてきたが、それに返すこともできない。お互いが黙ったままの状況を嫌ったのか岡が喋り始めた。
「まあ、そういうときもあるだろ。俺も初めは不安だったけど、他の奴ら曰く『新人類に進化している過程』だからしょうがないんだってさ」
私は、心が押し潰されそうになった。一体これのどこが新人類なのか、指が無くなっていくことのどこが進化なのか、私達は取り返しのつかないところまで来てしまったのではないか、など様々な不安と後悔が頭を巡っていく。
「なあ岡、もう……やめにしないか」
私はそう彼に提案した。まだ戻れるかもしれないという希望と、自分が元に戻りたいというエゴから出た提案だった。それを聞いて、彼は大きくため息をつき、声を荒げて答えた。
「無理に……無理に決まってるだろ! お前だって、あの生活に戻れるのかよ! また惨めに、ボロ雑巾みたいになって働くのか? 体力も無くて、家と会社を往復することが全てだった、希望も無かったあの頃に!」
「でも……」
「やめるなら一人で降りろよ。じゃあな」
そう言って電話は切れてしまった。その後、私は、朝日が登るまでそこから動くことすらできなかった。私はこの日から、例の栄養ドリンクを飲むことをやめた。
その後、私の体は完全にとはいかないまでも、元に戻りつつある。「元に戻りたい」という同じ考えの人が世界中に多く存在していたのが不幸中の幸いだった。
そんなある日、新しく務めている会社先輩が、ある記事を見せてくれた。最近、世界中で新種の鳥が発見されており、どの鳥の血液にも栄養ドリンクに近い成分で構成されているというものだった。その記事にある写真の中に、なぜか既視感を覚える鳥がいた。その鳥は、どこかで見たことがあるような羽の色をしていたのだ。
私はそれを見て、岡に連絡をとってみることにした。あの日の謝罪と安否確認のためだ。しかし、何度電話をしてもメッセージを送っても、彼から連絡が来ることはなかった。
#ノート小説部3日執筆 「秋のはじめの準備、ですから」
前略。職場は暑いです。もう九月なんですけどね?このままじゃ仕事もままなりません。
喫煙所、内側は空調が効いてるんですけど、受付はぜんぜんなんですよね。しっぽを自動ドアに反応させ続ければ冷気が流れるんですが、なにぶん疲れるので。
そんなわけで、現在進行系で蒸し焼きモケーレ・ムベンベになっている私なのでした。
そんなへべれけムベンベでくたばっていると。
「もしも〜し、仁淀(によど)さ〜ん、仁淀 かなえさ〜ん?」
受付カウンターにへたり込んでいた私を呼ぶ声がした。利用者さんですかね。起き上がらないと。
「はい、はぁい。喫煙所のご利用ですかぁ?」
軽めに伸びてから立ち上がる。受付用の椅子、私が使うとちょっと低い。まあ、立っても背丈が足りないんですけど。
施設内の喫煙所は、使うものを受付に申請してから使うことになっている。カラオケの持ち込みみたいなもんだけど、内容が内容だけにちょっと物騒。まあ火気と薬品を扱うわけだから、仕方ないところはちょっとあるかも。
もそもそ立ち上がると、普段喫煙所に来ないような人(ヒトじゃないけど)がいた。
見上げるほどデカい身長、あっちこっちにカールした紫の長い髪。機器点検部の制服を羽織っている。
「点検に来ました、角谷(かどや)です。今大丈夫ですか?」
そういえば今日は点検日だった。忘れてた。
「はーい、大丈夫でぇす。お願いしまぁす」
ちゃんと返事はしないとね。
作業しているところを眺めてるのは、ちょっと面白い。ちょっとカバーを外せば、なんか知らない部品がうやうやあるから。
……ところで、なんで点検するんだっけ。点検告知の張り紙をもう一回見ておく。デカデカと機器点検部って書かれてるやつだったはず。
えーどれどれ。『秋口にかけて順次、施設内のエアコンを暖房に切り替えます!』
「えー、こんなに暑いのにぃ」
思わず出てしまった。思ったことを言う流れ、止めておくのを忘れてた。
それを聞いてたらしい、点検の人がちょっとこっち向いた。
「ね〜、まだ暑いですよね。もう秋なんですけどね」
そうですよねぇと返事をした。
暦の上では秋なんだよね。最近は季節感がガバガバで忘れていた。気温がヒトの平熱くらいなのは当たり前、なんならもっと高くなる。そんな日が続いていた。
最近は少し落ち着いたけど、それでも最高気温は30度くらい。まだまだ暑い。
せっかくだし、世間話に発展させたいな。でも会話のデッキがない。そう思っていると、あっちから話が振られた。
「秋になったら、イベントがありますよね。豊食祭とか、運動祭とか」
そんなのがあるんだ。今年から入った新人だから知らなかったや。
「ボクもこういうお祭りは初めてなのでね。楽しみですね」
あっちも新人さんだった。
「運動祭って何やるんですかねぇ?私、動くのは苦手なんですよねぇ」
元々動きは鈍い方。合成半獣(このいきもの)になってからはもっと鈍くなりましたが。身体検査で50m走をしましたが、そんじょそこらの小学生よりも遅い記録でしたから。
相手側から乾いた笑いが聞こえた。明らかにドン引きしてる時のヤツだ。
「まぁまぁ。ボクも苦手ですよ。伝令兵でしたけど、空飛んでただけなので、運動自体はからきしです」
そうなんですねぇ、と相槌を打った。
「まあ、速いだけが運動じゃありませんから。いろいろ種目あるらしいですよ?」
後でウチの先輩に聞いておこう。それで、参加できるものがあったらやっておきたい。お祭り系は楽しんでナンボって言うし。
……別に、人間だった頃にちゃんと楽しめなかったわけじゃない。楽しくなかったけど。
運動祭の話題はここまでにしとこう。なんか、私のズブさが露呈しただけな気がするし。
「そ〜だ、豊食祭ってどういうやつなんですかぁ?」
これは初めて聞いたから。学校とかだと聞かない行事だ。
「うんと、中庭の畑で作ってる野菜を収穫したり、それを使って、みんなでお料理したりするらしいですよ」
中庭の畑、こういうときに使うのか。週替りの管理当番が面倒くさかった思い出しかない。
「ボクの先輩が言ってたんですけど、食堂のごはんの何倍も美味しいらしいんですよね。気になるなぁ」
ここの職員がご飯の話題をするとき、高確率で食堂が引き合いに出される。たしかに、あんまり美味しくないかも。
「でも、食堂のごはんも美味しいですよね?」
そんな事言われても。
「うーん、私は微妙なんですよねぇ。味が薄いのでぇ」
「あー、やっぱり?」
「やっぱりぃ!?」
思わずオウム返しした。何がやっぱりなのか。
「みんな味が薄いって言うんですよね。ボクにはむしろ濃いくらいで……」
そっちか。私はてっきり『やっぱりみんな薄いと思ってるのか』の方だと。
「やっぱり、毎日美味しいごはん食べてると違うんですかね?」
「むしろ逆じゃないですかねぇ」
味覚刺激がないと“美味しい”とは思えない。ジャンクフードに慣れた現代人だとなおさら。
素材の味が分かるのは、その素材が美味しい場合だけだ。ここの食堂は、素材については相当こだわってるはずだし、その問題はない。
だから、問題があるなら私たちの舌の方だろうね。
「私たちは味覚がおかしくなってるだけですよぉ。角谷さんみたいなのが普通ですよぉ」
実際そうだと思うし。
「そういうもんですかね?」
「そういうもんですよぉ」
オウム返しをする。こういうのは、流れで言った方がいい。
世間話をしているうちに点検は終わったらしい。
「じゃ、これからスイッチ入れると暖房になるので」
笑顔でやたら酷なことを言われている。あっちも営業スマイルだろうけど。
「まあまあ、気温も下がってくる……はずなので」
たぶんそう。今年は残暑厳しくないといいな。
「うぉ〜……がんばりますぅ……」
家から扇風機持ってこようかな。でも喫煙所で風飛ばすのは良くないな。でも受付に置くだけだし。
「そーだ、最後まで冷房のところ、どこですかねぇ」
休憩時間とかに涼みに行きたいな。点検のお知らせにはここの点検日しか書いてないから、他のところは分からない。
「えっと最終日は……、食堂と監視室ですかね」
メモ帳を見ながら、角谷さんは答えた。監視室は監視長しかいないからさておき、食堂はありがたい。近いし。
そうだ。せっかくだし、今日のごはんは食堂で食べよう。日替わりなんだっけな〜。
#ノート小説部3日執筆 残暑
「どうしたの、リコネア」
セラが見れば、リコネアは日本語辞書と古語辞典を片手にうんうんうなっていた。
「今度のゼミ、『地球時代の書簡について』なんだけどね」
「あー」
新学期、始まってすぐの課題であるようだ。
「この時期なら『残暑お見舞い』かなって思うんだ」
「ザンショ?」
「ザンショは残暑。夏が終わっても暑さが残っていることよ」
「夏……」
この間体験した地球の「夏」を思い出し、セラは眉をひそめた。
「夏が終わってもまだ夏の気配が残ってるって素敵だよね」
「そうかなあ……」
時候の挨拶、結び方……資料をたどりながらリコネアはつぶやく。
「本当は立秋から白露までに出さなきゃいけないみたいだけど」
「もう、わけわかんないことばっかり……」
「季節感を表す言葉よ。こういうのが好きで日本文学やってるんだもん」
「気温差ないほうが体にいいって習ったけど。じゃ、オミマイは? 必殺技なの?」
リコネアはふふっと笑った。
「それは俗な用法ね。この場合、慰問などで訪ねることよ。実際にはお訪ねできないからお手紙でってこと」
「ふーん。電子メッセージじゃないのね?」
なるほどとセラはうなずいた。セラもメールが普及する前、紙に書いていたことは知っている。
「メールが普及してもしばらくはハガキ……簡易的な書簡を出すのが『粋』とされたみたいね」
「手で書くなんてめんどお〜」
「でも、いろんなイラストがあって、見てて楽しいよ」
ハガキには、青い海に白い砂浜、そこに赤いカニ。スイカとうちわ、金魚鉢。風鈴に花火。リコネアのいう、日本の夏らしいイラストだ。
「ね、これは? かわいい!」
セラが見つけたのは豚の形をした焼き物の絵だ。煙が一筋立ち上っている。
「ぶたさんの蚊取り線香ね。もっとも実際に使われることは稀になったようだけど、夏の形として理解されているみたい」
「カトリセンコウ、しってる。小さなムシを落としちゃうの」
「そうそう」
「このグルグルで目を回させるのかと思ってたわ」
「あははは」
リコネアは笑って、「私もそう思った!」と言った。
「そうだ、その絵ハガキ、私のコレクションなんだけどセラにあげよっか」
「えー……」
「あ、興味ない?」
「どうせならリコネアがザンショおみまい書いてよ。ゼミの課題になるんじゃない?」
はっとリコネアは気づいて顔を明るくした。
「いいよ! 書いて発表してセラに送るね! セラも返すんだよ!」
「え、わたしも!? 郵便代高いじゃない! 手渡しじゃダメ?」
「いいじゃん、地球美術史にも関わることでしょ? かわいい切手も貼ってあげる! 楽しみだなあ!」
#ノート小説部3日執筆 お題【残暑】ぬぐい合う(ほんのりBL)#おっさん聖女の婚約
「男の汗って、暑苦しいだけかと思ってたんだけど」
夏の暑さを引きずっているのか、中々気温が下がらない。魔界の扉の封印をしなければならないのに、魔獣を仕留めていかなければならないのに、暑さのせいで疲労感が強い。
俺がつらいんだから、きっと他のみんなもつらいんだろう。汗だくになった野郎どもに夏バテで苦しんでいる聖女。その光景を見ているだけでも、暑さが増す。
こういう時に、器用に魔法が使えるやつは良いよな。俺はうまく使いこなせないから、そういう人が作ってくれた氷の塊を近くに置いて涼を取っている。因みにこの氷を作ってくれたのは、俺の筆頭騎士ジークヴァルトである。
あの男、一体どうなっているんだろうか。できないことってないのかね。俺の近くで涼しい顔をしている相棒を見た。
あ、表情には出てきていないけど彼も暑いのか。ジークヴァルトの額に浮かんでいる汗を見つけて安心した。これで彼もむさくるしい男の仲間入りだ。
はあ、と熱い息を吐き出すと、ジークヴァルトがこちらに手を伸ばしてきた。次々と浮かび上がってくる汗をハンカチで拭いてくれる。そこまでお世話しなくても良いんだけど。
「ありがと」
ジークヴァルトは自分の汗はそのままに、俺の汗をぬぐう。俺はどういう感情でいれば良いんだ?
俺はそんなに面倒を見られなければ生きていけないような存在じゃないんだけどな。俺は別の意味で体温が上がっていく気がした。
その間も彼の肌に浮かんだ汗の粒は育っていく。ついに、その雫が耐えきれなくなり垂れ始める。あ、落ちそう。
「ヴァルト、俺のは良いから自分の汗ぬぐいなさいよ」
思わず、そう口にしていた。が、ジークヴァルトはなぜか頑なだった。
「俺は別に。それよりももう少し涼しくした方が良いか? といっても、氷を増やすくらいしかできないが」
「魔力の無駄遣いはしない方が――って言いたいところだけど、すぐに混戦になるからあまり魔力って使わないもんなあ」
混戦になると味方に攻撃が当たってしまう可能性がある為、神聖魔法か物理攻撃のみで戦うしかない。そうなれば、魔法の出番はないのだ。
だから、魔法が使える騎士たちは思う存分氷を作っているのか。全員汗だくだけど。俺も含めて効果があるように見えてないけど。
暑苦しいったらありゃしない。
「ラウル、ちゃんと水分を取った方が良い」
「ん」
俺の相棒は何て優秀なんだ。っていうか、きみは俺の母親か?
母親みたいに世話を焼いてくれる男から水を受け取り、一気に飲み干した。ジークヴァルトはそんな俺を見つめて満足そうに頷く。
「きみね、自分の世話もしなさいよ」
俺は顎を伝う彼の汗を指先で拭ってやりながら笑いかける。まったくもう、この年若い青年――と言うには、少し大人になったか――は相変わらず俺のことばかりだ。
ああ、また汗が。
ジークヴァルトが放置するそれを、今度は俺が拭ってやる番かな。ハンカチは持ってないけど。いや、ハンカチは持ってる。でも自分の汗を拭くのに使ってしまったから、他者に使うのはちょっと。
あー、彼なら気にしないかもな。むしろ喜んだりして。何てふざけたことを考える。
相変わらずジークヴァルトは俺の汗を拭っている。そんなに楽しいかい? 俺の世話を焼くのは。
「俺のベルン」
「……分かった」
彼は渋々ながら水を飲んだ。この休憩時間はいつ終わるか分からない。残暑って残酷だ。もうじき夏が終わるはずなのに。いや、終わっていても良いはずなのに。
終わっていても良い、と言えば、この行軍もだ。もっと早く決着をつけることができると思っていた。だが、効率よりも安全を重視しているせいで、中々終わらない。それもあと、少しで終わる――はずだ。
いや、まだまだ先は長いかもな。憂鬱な憶測を抱き、嫌な気分になる。
そこまで考えたところで、気づいてしまった。意外と自分が疲弊していることに。
ああ、暑いな。それが俺を弱らせている。行儀が悪いとは思ったが、ジークヴァルトが用意してくれた氷を抱きしめた。冷たすぎて頬がひりひりする。体勢をそのままにジークヴァルトを見上げると、彼は俺のことをじっと見つめていた。
やはり、汗を拭おうとはしない。彼の熱そうなフルプレートにそれが落ち、じわりと消えていく。その顔に、一切の憂いや絶望の気配は見られない。
「きみは、強いな」
「何を言いたいのか分からないが、俺が強くいられるのはラウルの存在があるからだ」
彼の視線はまっすぐだ。自分の言葉に疑問を抱いていないのがそれだけで分かる。ぽたり。再び顎から汗が落ちた。不思議と、むさくるしさや嫌悪感は感じなかった。むしろ――色気を感じるような。
「そうなの?」
「お前の存在さえあれば。聖女として、その力をこの世界の為に使おうというその心を尊敬している。お前を守りきることが俺の価値だ。俺は、お前を守る最後の砦だ。お前が聖女として立ち続ける限り、何も恐れることはない」
ジークヴァルトの言葉が俺の中に染み込んでいく。彼の暑さをものともしないその姿は俺への信仰心だけでできていた。
俺はくじけるわけにはいかないのだと、改めて気を引き締める。
「ヴァルト、きみのおかげで頭がすっきりしたよ。ありがとう」
「……? お前の役に立てたならこれ以上ない幸いだ」
ジークヴァルトが俺に対してどれだけ貢献してくれていることか。彼は理解していない。きっと、分かろうともしないんだろう。
ジークヴァルトの汗が垂れる。ああ、色っぽいな。再び指先で彼の汗をぬぐってやる。
「このまま、ずっとついてきてくれな」
「もちろんだ」
残暑は続くが、もう気にならなくなっていた。あ、嘘嘘。気になるけど、耐えられそうだった。ジークヴァルトが支えてくれている限り、俺はきっと大丈夫だ。そして、俺が大丈夫な限り、ジークヴァルトが俺のもとから去ることもない。
俺たちは互いの存在に支えられて生きている。汗をぬぐい合うように。
#ノート小説部3日執筆 「残暑」 ねっちゅうしょう
「もう9月なのにまだ暑いね」
「それ〜まじで勘弁して欲しいわ」
夕日は赤く僕たちを照らしている。それがとても暑くて、夏の日中みたいに汗がだくだくと流れる。
「なんで高校になったら水泳なくなるんだろうな」
そう言って幼馴染の涼くんは言う。それにはははと苦笑いしかできないのは僕たちの通っている学校にはプールがないからだ。
そもそも水泳できる場所がない。
「どうしてだろうね、わかんないや」
暑さでぼんやりする。学校の規則で、近くに住んでる僕と涼くんは徒歩通学だ。通学路は夕方になると強い陽射しが入るところで、二人で文句を言いながら帰ってたものだ。
「あっもう飲み物無くなった、香久耶《かぐや》飲み物持ってる?」
「あるけど少ないよ」
「あ〜〜〜まじかよ」
涼くんはその場でしゃがみ込んだ。額には汗が流れている。夕日のせいか、涼くんの顔が赤くなっているように見える。それにごくりと喉を鳴らしてしまうのは仕方ない。涼くんは男の僕から見てもかっこいいから。
「涼くん、熱中症? 大丈夫?」
「あ〜かも。香久耶はどう?」
「僕も、かなりきついかも」
今日は、体育が外であったから、ボトルに入れた飲み物の半分は飲んだと思う。帰るときにスポーツドリンクのペットボトルでも買えば良かったと僕は後悔しているので、きっと涼くんもそうだろう。
「この周りって、自販機なかったよな」
「うん、確かそうだったはず」
「あ〜〜〜くそ」
徒歩圏内と言ってもギリギリであって、あと1mでも家の位置がズレていれば自転車を使えたはずなのだ。
これに文句を言うのは夏に散々言ってたので今はもう言わない。
「涼くん立てそう?」
「無理かも。冷たい飲み物ガッと飲みてえ」
しゃがみ込んでた涼くんがもう完全に座ってしまった。この道は人がなかなか通らないといえ座り込んでしまうのは文句を言われるかもしれない。
僕は涼くんの鞄も肩にかけて、涼くんの肩を担いで日陰になるところで道から少し外れたところまで歩いた。涼くんは同じぐらいとはいえ、身長は涼くんの方が身長高いし、筋肉はついている。僕みたいなインドア派が持ち上げるのはかなり無理があったけど、なんとか持ち上げた。涼くんも意識はあるから、寄りかかってはいるけど、歩いてくれてはいる。
日陰に入ると、僕も涼くんも寝転んだ。道から外れた場所とはいえ、通れば見えるので、何をしてるのか見られるのは今考えると恥ずかしかったけど、とにかく暑かった。僕は顔を流れる汗をタオルでふく。タオルも、べちゃべちゃしてて気持ち悪いが、拭かないよりはマシだ。
「香久耶、タオル持ってたのかよ」
「涼くんは持ってなかったの?」
「俺は。制汗剤しか持ってなかった。タオル、忘れて……コンクリート暑すぎ……」
涼くんの声が小さくなっているのを見て、重度の熱中症かもと思った僕は、ボトルを差し出して、「飲んでもいいから」と涼くんに言った。
「……あ? これ、香久耶のボトルだろ、俺が飲んでもいいのかよ」
「涼くん、完全に熱中症だから、飲んでよ。僕はまだ大丈夫だから」
「そう、ありがたくいただくわ」
そう言って涼くんは少しの飲み物を飲んだ。喉が2回ほど動いて、「終わっちまった。すまん香久耶」
「いいよ涼くん、これも食べよう」
差し出したのは、塩分のタブレットだ。お母さんに持って行くように言われてたのが功を奏した。
「これ、何?」
「塩分のタブレットだよ。ほら、熱中症には水分と塩分取らなきゃって言うでしょ」
「あ〜そうだったな」
「僕も食べよう。食べないよりましだし」
包装を破って、タブレットを口に含んで、これって噛んじゃダメなんだっけ?っと思いながら、コロコロ、口の中で転がしてたら、涼くんと目があった。涼くんはタブレットを食べてないみたいだ。包装も破った方が良かったかなと思って、貸すようにと手で催促したら、手を握られた。
すっとメガネが外されて、唇が重なって、涼くんの熱い舌が口に入ってきて、それでタブレットを取られた。
カッと顔が赤くなるのを感じて呼びかけようとするも「りょっりょっりょっりょ」という感じで、呼びかけられない。
涼くんはそんな僕を笑ってた。熱中症が軽くなったのか、汗は少なくなってた。
「涼くん!あんな、あん、あんなこと、してたら、ダメだよ!」
「あんなことって?」
「あんなことってキキキッキ」
「さるになってるぞ、香久耶」
「キキキ、キス!、しちゃダメだよ!」
僕が顔を真っ赤にしながら言ったら、涼くんは冷静な声で言った。
「なんで?」
「こっこんなの、不純、だよ!」
「どこが?」
「も〜〜〜!!!!!キスは好きな人同士じゃないとダメだよ」
「香久耶は俺のこと嫌いなの?」
「きらっ………いじゃないけどぉ……涼くん、いつもこんなことしてるの?」
「そんなことね〜だろ、俺をどんなキス魔だと思ってんだ」
「えっじゃあ」
ぼやけていた視界がクリアになったと同時に涼くんの顔が目と鼻の先にあって、後に下がった。
「お前が好きだからしたんだろ」
そう言ったしゃがんでこちらを見ている。涼くんは暑そうに顔を真っ赤にしている。
「熱中症のせいじゃない?」
「そうかもな」
「じゃあ、これからは熱中症にならないでね」
それを聞くとしゃがんでいた涼くんが立ち上がってこちらに向かってきて僕を見下ろした。
「頭が暑さでいかれてるとか、赤い顔のお前が可愛いとかじゃなく、俺を優先してくれたお前のそんな優しいとこが好きなんだよ」
もう僕の頭は暑さでぐらぐらだ。涼くんがどんなことを言っているかは分かるが理解するのを拒否してる。
「だからと言って今すぐ付き合えとか言うつもりはないからって香久耶!」
涼くんが大きな声を出して額に手を当ててきた。若干冷たい。
「熱か、香久耶のお母さん呼ぼうか」
「いや、ただ暑いだけだし、そんなに酷くないからお母さん呼ばなくていいよ。それに、」
「それに?」
「暑いのは涼くんのせいだから」
涼くんはふっと笑うと僕の鞄を肩にかけ、僕に手を差し伸べて、引き上げてくれた。
「意識してくれるの嬉しい」
にこっと涼くんは笑った。
「僕も嬉しいかも」
つられて僕も笑う。
「じゃあ、付き合うか?」
「流石に今は……」
「さいて〜!俺の心弄ぶつもり!?」
両手をグーにして顔の近くに持って行くポーズをしてぶりっ子みたいにしているが、その目には全然僕を非難するような感情は含まれてない。
「ちゃんと考えたら応えるよ」
「早くしろよ、男子校生だから」
「男子校生関係ある? 僕も男子校生だけど」
「ある! 好きなやつと両思いならイチャイチャしたい!」
「それ、普通の感情じゃない?」
「普通じゃない、男子校生だから三倍はある」
「わかったよ、早く答えを出すけどその前にさ、」
涼くんの肩をポンポンと叩きこちらを向いた瞬間に唇を頬に当てる。
「ちゃんと好きって言ってね」
涼くんは、頬に手を当てて、顔が赤くなってた。
「お前も本当に意地悪だよな」
#ノート小説部3日執筆 お題「残暑」 タイトル『ツクツクボウシの知らせ』 #GL #百合
暑さを避け木陰に座っていると、秋が近づいてきているというのを知らせるツクツクボウシの声が耳に響くように届く。
山のすそ野にある集落ならば尚の事、その一抹の寂しさを纏った鳴き声は愁いを帯びて耳に届いていた。道すがら小さな商店で買った水色が涼やかなソーダ味のアイスを真ん中で割り、片方を一緒に涼んでいる子へと渡す。
「……もう夏も終わりじゃね」
アイスを受け取りながら彼女がそうどこか木々に木霊するセミの声と同じように一抹の寂しさを含ませて呟く。その声に、はぁ……と小さく溜息を吐くと、アイスに思い切りかぶりついた。
「そうは言うても、まだまだ暑いけん。まだ夏は終わっちょらん。まだ終わらん」
一気にアイスを食べ終わり一息吐くと、彼女の言葉にそうささやかな反論をしてみる。
彼女はこの夏が終わると都会へと引っ越していくことが決まっていた。
「そうじゃといいなぁ」
私の言葉に彼女は酷く遠い目をして、蜃気楼で歪み舗装もされていない道を見る。
この山あいにある小さな集落には子供が少ない。
だから必然的にみんな仲間の様な、親友の様な、家族の様なそんな付き合い方になっていく。その中の一人が欠けてしまうのは、大切な何かを失ってしまうのと同義だった。
「ほうじゃ! きょーちゃんだけウチに住めばいいんよ! ウチからおばちゃんに掛け合ってあげる!」
名案を思い付いたとでも言う様にそういえば、彼女、きょーちゃんはかけた眼鏡の向こうでどこか眩しそうな瞳を私に向けて微笑んだ。
そしてその後、視線をまたカラカラに乾いている道へと向け、溶け始めているアイスを下から上へとゆっくりと舐めて嚥下していく。その仕草に少しばかりドキリとし、私も視線を道路へと向けた。
人一人、車一台も通らない田舎の舗装さえされていない道。この道を進めば集落に辿り着き、そこには人の営みが確かにある。
だけど、今この場所には何もなくて、ただカラカラに乾いている土の道と、雑草、山の中へと続く木立、そして私達しかいない。
「……ほれじゃぁ本末転倒じゃ」
暫くして、ようやくアイスを食べ終わったきょーちゃんがさっきの微笑みとは違う、楽しそうに、だけどどこか諦めの入った笑みを私に向けるとそう呟く。
きょーちゃんが都会に行くのは、なにも親の都合だけではなかった。
「ウチがいかんと、両親が悲しむけん」
その言葉に含まれている意味に、私は下唇を噛み泣きそうになるのをグッと我慢する。
「それにほら、まだ結果はわからんち。先生も希望はある言うとったけ」
いつものように優しくきょーちゃんの手が私の髪に触れ、労わるように撫でてくれる。そんな気休めのような言葉、今の私にはただ残酷で辛いだけだった。
「……っ、でもっ」
「ええんよ。ウチが自分で決めたんじゃ。サチはここで待っちょって」
ふふっと笑い、きょーちゃんは私の髪を撫でていた手を頬へと移動させ私の目元をその細くて白い指で軽く擦る。
成功確率がとても低い賭け。
それに賭けるしかないという状況が彼女にとってどれほど辛い物なのか、不安や恐怖、その他様々な複雑な感情に苛まれているかなんて私には全てを知る事なんてできなかったけど、それでも、私が抱えるこの寂しさや不安、恐怖よりもよほど強くて深いものだという事だけはわかる。
そんな中でこの決断をした彼女は凄く強いと思うし、泣き崩れた両親を説き伏せたのも彼女の凄さだって私は良く知っていた。
「大丈夫、ちゃんと帰ってくるけん。ウチ、勝負運だけは強いんよ。サチも良く知っとるじゃろ?」
私の頬に流れる液体をその白い指で何度も拭いながら、眼鏡のフレームの向こう側から私を真っ直ぐな瞳で見つめ彼女は悪戯っぽく笑う。
「……学期末テストのヤマ全部当てたっちゃ」
「ほうよー。ウチのお陰で赤点免れたじゃろ」
きょーちゃんの勝負運の強さと勘の鋭さを思い出してそういえば、彼女はくすくすと笑い、もう一度私の頭を優しく撫でてくれた。
そんなきょーちゃんに私も笑い返し、今度は自分の指で頬を伝う雫を拭う。きょーちゃんとは違う、黒く日焼けしてごつごつしている指。
いつだってきょーちゃんは私の指を綺麗だって言ってくれるけど、私の指が綺麗だなんて自分では思えない。
綺麗、という形容詞が似合うのは、きょーちゃんの白くて細い指の事だ。その存在も含めて。
「そろそろ帰ろっか」
「……残暑じゃゆーても、暑いけんもうちょっとここにおらん?」
夕方を告げるひぐらしの鳴き声が更に大きくなった事で、きょーちゃんがそう言い歩き出そうとした手を思わず掴んでそんな見え見えの引き留め方をする。
そんな私に少しだけ小首を傾げて見せ、きょーちゃんはそっと私の手を握り返してきた。
その細くて綺麗な指を、ごつくて醜い私の指へと絡める様に握り返し、そっとその細い体を寄せてきた。
「サチはしょーがないなぁ」
くすくすと笑い、少しだけね、ときょーちゃんは囁くと私の肩にその頭を持たれさせる。
「……きょーちゃん、ウチ、」
「しーっ」
私が言いかけた言葉をきょーちゃんは私の唇に指をあてて黙らせると、そのままゆっくりと彼女の唇が私の唇に重なった。
途端、山の中にわんわんと響いていたツクツクボウシの声も、そしていまだ残る暑さも私の周りから消え、ただ彼女の柔らかい唇の感触と、爽やかな金木製のコロンの香りが鼻孔をくすぐる。
永遠というものがあるのならば、この瞬間を時間の檻に閉じ込めてしまいたい、だなんてらしくもなくロマンティックな事を考えてしまう。だけど、その永遠はすぐに失せ、彼女は体を離すと眼鏡越しにじっと私を見た後、繋いでいる腕を緩く引っ張った。
「……サチ。待っちょって。必ず帰ってくるけん、約束」
時間が戻り、わんわんと木々にツクツクボウシの声が反響している中で彼女はそう言い、そして私の手を一度ぎゅっと握った後、するりと離した。
その手を捕まえようと手を伸ばすけれど、指先が軽く触れただけで彼女はカラカラに乾いた道を歩いて集落へと背筋を伸ばして歩いて行く。私を振り返りもせずに。
木陰に一人取り残され、暑さの含まれた風が頬を伝う生緩い雫を拭い去って行った。
また何度目かのツクツクボウシの鳴く季節が廻って来た。
畑仕事を終えて、一息吐こうと木陰で休む。雑草の上に腰を下ろし持ってきている水筒から冷たいお茶を飲み、その心地よさにはぁっと息を吐く。
夏は確実に終わりへと近づいているのに、相変わらず残暑が厳しい。
だけど耳に届くツクツクボウシの声は確実に夏の終わりを告げていて……。
「……もう夏も終わりじゃね」
涼やかな声がそう後ろから聞こえ、そして頬にひやりとしたアイスの袋が押し当てられる。その声と押し付けられたアイスの袋に私は目を見開いて、後ろを振り返った。
そして私は――。
#ノート小説部3日執筆 お題:【残暑】
※甲子園三連覇とかこわい話をしていますが、フィクションとしてお楽しみください。
------
『Summer.』
「お」
部室を訪れると、よく見知った――しかしこうして会うのは久方ぶりのような――顔に出会う。
彼はついこの間まで、この野球部のエースとして活躍していた天才投手であり、捕手(ぼく)の相棒でもあった。同じ学年なのだから顔を合わせることもあろうと思うかもしれないが、我が校はそこそこ大きい学校である。クラスが離れていれば教室も遠く、その気が無ければそうそう出会うこともない。部活を引退する前は、僕が向こうのクラスへ行ったり、逆もあったが、このひと月ほどはぱったりとそれがなくなっていた。
あの日――甲子園の決勝の舞台に立てずに、僕たちの夏が終わった、そのときから。
「忘れ物ですか?」
「ああ」
彼は淡々と、いつもの調子でそう返した。僕は僕で、置いたままになっていた私物を回収する作業に取り掛かる。着替えやタオル、貸すために持ってきてそのままになっていた漫画。そういったものを全てロッカーから取り出してしまうと、引退するのだなあという実感が湧いてきた。三年間、野球漬けの生活をしていたのだから当然なのだが、放課後の予定が急にまっさらになるのは、変な心地だった。
ちらりと、彼を盗み見る。黙々と荷物を鞄に放り込んでいる、彼の肩は相変わらず細かった。入学時から技術は頭ひとつ抜きんでていたものの、その細さが不安になって、皆でこぞって弁当や菓子を押し付けていたのが昨日のことのようだ。生意気な彼は当初先輩すらも突っぱねていたが、だんだん縦社会に順応して食べるようになったのだった。
「ちょっと痩せたんじゃないですか。ちゃんと食べてます?」
「食べてる。お前は俺の母親か」
「違いますゥー。ついでに女房役も引退させてもらいましたァー」
お互い別々の方を向いて、背中越しに会話した。
――僕たちは入部してから二年間、夏の甲子園で優勝を経験していた。一年目は、先輩たちの優勝をベンチで見ていた。二年目は、先輩たちと一緒に優勝を掴んだ。彼はもう、エースとしてマウンドに立っていた。
三年目、僕たちの最後の夏。あと一点。たった一点の差を埋められずに、僕たちは負けた。準決勝敗退。三連覇の偉業は果せなかった。賞賛も野次も、どちらも耳には入ってこなかった。ただ、これで終わってしまったんだ、という事実だけを、否応無く噛み締めていたから。
野球は点を取らなければ勝てないゲームだ。投手が抑えても、得点できなければしようがない。――マウンドに立った彼と相対していたから、分かるのだ。あの日、彼の肩にどれだけの重いものが圧し掛かっていたのか。期待された三連覇。天才投手と呼ばれる彼の一挙手一投足が注目されていた。彼は、全てに応えようとしていた。我儘なくせに、変なところで真面目だった。
「おい、まだか」
一瞬、何を言われたのか理解できなかった。気が付けば、彼は部室の入り口に凭れ掛かっていて、去る気配が無い。
「いや、もうすぐ終わ……っていうか、もしかして僕を待ってんですか?」
「他に誰がいるんだよ」
確かに――と変に納得して、頭と手が連動して動かないような心地になりながら、荷物をしまい終えて立ち上がる。そうして、ようやく彼の顔を見た。よく見知ったままの顔だ。なんとなく、視線だけをそっと逸らした。
「お待たせしました」
「ん」
一緒に帰ろう、とはどちらも言わなかった。なんとなく連れ立って部室を離れ、お互いの家の方向とも全然違う――よく部活の皆でアイスを買いに行ったコンビニの方へ向かう道を歩いた。八月も過ぎたというのに、気温は高いままだ。街路樹の下には乾いた蝉の死骸が転がっていて、夏の終わりを再確認させられるようだった。
コンビニに着いて中へ入ると、涼しい空気が出迎えてくれる。適当に店の中をうろついただけで、いろんなことを思い出した。物思いに耽っていると、会計を終えた彼が出口で待っていた。
「やる」
差し出されたのはレモン味のかき氷――僕が好きでよく食べていたものだった。好みを覚えているなんて意外だと思いながら受け取って、少しコンビニを離れた橋の上で食べた。彼はいつも通り、パイン味を食べていた。
「君が奢ってくれる日が来るなんて」
「……ま、最後くらいな」
最後。当たり前のように出てきたその言葉が、不意に横っ面を叩いたようだった。夏は終わって、部活を引退して、その先には卒業が待っていて――僕と彼とは、別の人生がある。何も今更、驚くようなことじゃない。彼とこんな風に、並んでかき氷を食べるのは、きっと今年が最後だった。口をついて、言葉が転がり出た。
「ごめん」
「なにが」
「いや……ごめん」
何かが込み上げてきそうになったので、氷を頬張って誤魔化す。それは口の中でみるみる溶けていって、顔が熱くなっているのを感じた。努めて、彼の方は見ないようにした。
僕たち、あんまり仲良くなかったな、と思う。顔を合わせりゃ文句ばかり。くだらない喧嘩は数えきれない。部活から離れたら、会う用事のひとつも思いつけないのに、一丁前に後悔ばかりがあった。どこかで一本、打てていたら。もっと上手くリードできていたら。この可愛げのない相棒を、勝たせてやれたかもしれなかった。
――勝ちたかった。皆と、君と一緒に、勝ちたかったんだ。
橋の上を、風が吹き抜ける。夏の匂いは、もうしない。彼はちびちびとかき氷を何口か食べてから、言った。
「ドラフトで指名来たら、断るなよ」
「は」
突然話題が変わって、口から素っ頓狂な声が出てきた。あまりの驚きでつい彼の方を見てしまう。
「言っておかないと、逃げそうだからな」
意地の悪い笑みと挑発的な言葉に、反射的にムキになって返す。
「は? 逃げないが? っていうか、指名来るって前提が無理なんですけど」
「来るよ」
いつになく真剣に、彼は言い切った。彼には絶対に指名が来ると思う。彼の才能と活躍がそれに値することは、僕が一番よく知っている。僕はというと、不幸にも天才と同じ年に入部してバッテリーを組まされた、哀れな一般人だ。必死にならなきゃ、追いつけなくて。置いていかれるのは癪だから、必死に、その背を追い続けた。
少しくらいは、追い付けたのだろうか。君のすぐ斜め後ろくらいには、立てたのだろうか。
「打席で俺の強さを痛感するといい。三球三振で仕留めてやる」
「うわ腹立つ。ぜってぇ九回裏ツーアウトから逆転ホームランしてやるからな」
一瞬の沈黙ののち、どちらからともなく、笑いが零れた。胸の中のわだかまりが、ゆっくりと溶けてなくなっていくような心地がした。
夏は、終わった。この三年間に終止符を打って、歩き出す。秋めく風は、この夏を過去に追いやっていくだろう。
僕たちは、仲良くなかった。だけど、こんなに互いの考えていることが分かる人は、もう二度と現れないかもしれない。早足で少しだけ前を行く君の背中は、きっとこう語っている。どうにも面映ゆいので、答え合わせはしないでおくけれど。
卒業して、同じチームになっても、違うチームになっても、また。
――また、一緒に野球をしよう。
【#ノート小説部3日執筆 】地球で最後の着付け教室(お題:残暑)
「こんにちはぁ……」
教室に使われている、先生の自宅敷地の西側に建つ離れ。そこに人の気配はない。こもったムッとした空気に、わたしの声が心細気に響き、消えた。
玄関口からのびる廊下の右手には、掃き出し窓。母屋との間にある小さな庭が見える。その左手には畳敷きの教室。突き当りには、勝手口がある。
廊下を中ほどまで進んだとき、勝手口の向こうから、木のきしむ音を聞いた。いつもは木の枝の影が見える、勝手口のちいさなすりガラスの窓。そこに、枝ではない、何かの影がある。
「せんせぇ……」
わたしは着付け道具を入れた風呂敷包みをぎゅっと握った。
――この日が来た、ただそれだけ。
言い聞かせて、わたしは教室のスペースに入って窓を開け、外の空気を入れる。金木犀が香る。
「先生、10月といっても、まだ暑いですね。この時期でも、残暑って言っていいんでしょうか」
虚空に話しかけながら、風呂敷をほどく。
着付けの際に、着物を汚れから守るために敷く衣装敷を広げ、その上に、肌襦袢、長襦袢、腰紐、クリップ……使うものを並べていく。使う順に、手に取りやすいように。教えられた通りに。
それが終わったら、たとう紙を開けて、着物を取り出す。若々しいピンクに、桜の柄があしらわれたもの。
「今日からは袷(あわせ)の季節、ですよね。季節外れの柄だけど、やっとこれ、着られます」
着物には裏地のついた袷と、それがない単衣(ひとえ)があり、10月から5月いっぱいまでは袷の、6月と9月は単衣の季節。7月、8月は薄物、これは透け感のある絽(ろ)や紗(しゃ)といった生地で仕立てられた着物のことだ。
わたしが持っているのは、この桜柄の袷一枚だけだから、夏の間は、先生の単衣や薄物を借りて練習をした。薄物は、袷とは着付けの感覚が異なっていて、わたしにはすこし難しかった。
「来年の夏なんて来ないかもしれないけれど、せっかく習っているのだもの。覚えておいて損はないわよ」
先生は、わたしの後ろに回り、腰紐に親指を入れて、「ぐっぐっ」と左右に伸ばした。腰回りの皺が、みるみる整えられていく。
「ほら、きれいになった」
きれいだな、と思った。紗という素材の透け感が。先生好みの紺色の紗の着物と、薄いグレーの夏用の帯の取り合わせが。こういうきりっとした雰囲気を「粋」と表現することも、透けた織物で涼を感じさせることも、きっとここに通わなかったら知らないままだったろう。
そんなことを思い出しながら、次に手を伸ばしたのは、小ぶりなたとう紙。そこには、朱色の生地に蝶が刺繍された帯が包まれている。この帯をくれたのは、同じ教室に通うハヤマさんだった。
「じゃあ、今日、着物、着られないんですか……」
あれは、教室での初日。わたしは途方に暮れた。帯を持っていなかったからだ。
母が唯一遺した、嫁入り道具だとかいう桜柄の着物。それを纏うことは、長い間のわたしの夢だった。成長し、期間工の仕事でお金をためて、資格も取って、やっと念願だった着付け教室の門を叩いた。事前にネット通販で肌襦袢、長襦袢などはひと通り揃えたものの、帯のことはすっぽりと頭から抜け落ちていたのだった。
「でも、まずは着物を着る練習だから、帯はおいおい、ね」
「せんせっ、わたし、ちょっと用事が」
すでに着物を着終えていたハヤマさんが教室を飛び出していき、持ってきてくれたのが、この帯だった。
「わたしにはもう若すぎてねえ」
「まぁ、着物の柄にもぴったり!」
先生が手を叩いて喜び、生徒のひとりで、ふだんは無口なスギタさんが「着物とか帯って意外と年齢選ぶ柄あるから。今のうちに着とくといい」とボソッと言った。
「ありがとうございます。でも……」
「いいのよぉ、スギタさんが言う通り、こういうのは、若いうちしか似合わないから。いっぱい着るといいわ」
みんな上品で、いい人たちだった。
今はひとりの教室で鏡に向かい、足袋、肌襦袢、裾よけ、長襦袢、そして着物……と順繰りに身に着けている。
桜柄の着物は、てろりとした質感の正絹で滑りやすく、初心者にはやや手に余る。だから、腰紐を締めたら、じっくりと手で皺を伸ばし、体に沿わせてやる。わたしは痩せぎすだけれど、細い中にも凹凸がある。そのことを、着付けを習いはじめて知った。補正のために腰回りにタオルを当てていても、腰の反り、お尻の曲線がわかる。これを感じる時間が、わたしは好きだった。上手くいくと、正絹がぴたりと肌に吸い付くような感覚がある。
――贅沢だな。
自分の体にこんなふうに気持ちを向けたことなんて、なかった。何かを纏うことが心地よい、そんな感覚も知らなかった。先生やハヤマさんやスギタさんは、ずっとこんな感覚を知っていたのかな。うらやましいな、と思った。
みんな、どうしているんだろう。
やっと帯をいわゆる「お太鼓」の形で結べるようになったころ、あの彗星が接近して、世の中は荒れに荒れた。衝突の予測が外れて思ったより終わりは長引き、諦めがじっとりと社会を落ち着けて、またみんなここに集まるようになった。
けれど……。
ハヤマさんは、「昨日、旦那がねえ、お風呂をわかしてくれたのよ。ガスが止まってから、久しぶり。ドラム缶で、五右衛門風呂」とうれしそうに言った翌週から来なくなった。
スギタさんは、いつも通り、マネキンに向かって振袖の着付けを学んだあと、「今日までです。今まで、ありがとうございました」と、正座をして、お辞儀をした。下げた頭の先で三角形を作るスギタさんの指先はとてもきれいで、ああ、お辞儀ってこうやってするんだ、とわたしは思った。
今は静まり返った教室で、わたしは帯を手に取る。最初の頃は、上手く締められなくて、何回やっても結んだ帯が「どすん」と落ちてしまった。
「時代劇で、帯をほどいていくとクルクル回って、『あ~れ~』なんてシーンがあるじゃない?」
ハヤマさんがそれを見て、クスクス笑いながら言ったものだった。
「あんな風にはならないのよねえ。こうやって、落ちちゃうんだから」
「帯だけほどいても、その下には長襦袢に肌襦袢、補正もたぁくさん。簡単には脱げないっ」
先生はうんしょっと力を入れて、わたしの帯を締め直してくれた。その感覚を思い出しながら、今、わたしは帯をぎゅうっと引き締める。
「もう落ちません、帯」
わたしは帯締めを結び、ポンっと帯を叩いた。
鏡には、季節外れの桜の着物に、蝶の帯を締めたわたしが映っている。今までで、いちばんきれいに装えた、と思う。
わたしは教室の窓を閉め、夕闇にのまれつつある廊下を進む。
そして、勝手口のドアノブに手をかけた。それはひんやりと冷たく、先ほどまでの残暑の気配は微塵もない。回したくない、と思う。
でも、きっと先生は教室の日を選んで、こうしたはずだ。何より、先生にこの姿を見せたい、とも思う。
世界には、美しいものがたくさんある。正絹。紗。季節のものを纏う喜び。帯が余っているからとくれる人。お辞儀。全部、この教室で知ったこと。
だから。わたしは、勝手口の扉を開ける。
「先生、見てください」
実はビックマックはラップで頼めるんです。
齧るとホワイトビネガーが効いた酸味のある味わいと、牛肉の少しパサついたパティと、主張しないパンに合わせて広がるビックマックの悪い所である箱型容器ではなく、他のハンバーガーのようにラップで包んでもらうには、頼んだレジで「ラップでお願いします」と言えばいいんです。
大丈夫です。
研修初日のスタッフ以外には通じるし、通じない場合は、近くにいる研修担当のスタッフ以外には通じます。
ビックマックはラップにさえ包まれていれば、端からレタスがこぼれ落ちる煩わしさなんて無視して、あっさりとした特有の旨味に集中できるんです。
別に直火焼きのパティじゃないし、肉汁なんてカケラもないし、パンはちょっといいやつだけど、夜マックは200円して、どうにもコストに見合っているのかわからなくなるけど、プロセスチーズと酸味のあるソースと、ピクルスと牛肉の味わいが混じると、シェイクシャックやバーキンの味に慣れた舌もなんだかんだ満足してくれるんです。
残りの一口まで、形崩れすることなく渾然一体のハンバーガーを味わうことができる。
ハンバーグではなく、ハンバーガーを食べることができるんです。
そのことを、最近CMに出ていないドナルドに熱意を持って伝えると、彼は少し寂しそうな表情を浮かべながらも、何処か満足げに、まだ雲の高い夕暮れの空を見上げるんです。
「ドナルドのことは、皆、ニコニコ動画で見てくれるからさ。寂しくはないんだ」
そういって、遠くを見つめる彼のことを、僕らはあとどれだけ憶えていられるでしょうか。
ニコニコ動画は復旧したのち、とんと話題になる人は減ってしまいました。
皆に忘れられることが一つの死の形だというならーーたまには、マクドナルドのマスコットであった彼に会ってみるのもいいかもしれません。
今ドナルドは、都会にある大型の店舗で、たまに見ることができるそうです。
#ノート小説部3日執筆
お題「マスコット」
Misskeyノート小説部のアカウントをFedibirdをお借りして運営することになりました。#ノート小説部3日執筆 などのハッシュタグ企画や、そこで投稿された作品のリポスト(リトゥート?)をこちらで行い、Fediverseにおけるノート小説の振興を図っていきたい所存です。
主宰:小林素顔 https://misskey.io/@sugakobaxxoo

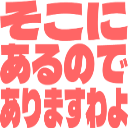



 :blobotoki:
:blobotoki:
 受付中
受付中
 東京
東京





 @葉桜神社同盟
@葉桜神社同盟




