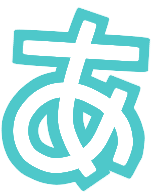#ノート小説部3日執筆 『へびのこ日常報告 喫茶店』
ここは蟒蛇塚(うわばみづか)。大蛇が管理し監視する合成半獣の居住区。
※合成半獣 人間と動物を合成した人工生命
隣町のように万年雨が降るわけでもなければ、川の向かいの町のようにずっと夜というわけでもない。合成半獣が住む地区としては極めて“普通の気候”の街だ。
――で、俺はその街の次期地主。ようは次の監視人。世襲制だからしょうがないとはいえ、荷が重い。
いつ代替わりしてもいいように、今のうちに近所との交流を深めるのが今の仕事だ。
とまあ長々話したが、普通の街で普通に生きて、普通にご近所付き合いするだけだ。
俺自身、なんだかんだ話すのは好きだし、近所をうろうろするだけでそれなりの仕事になるのはありがたい。
……ただの散歩が“仕事”になるのは、ちょっと嫌ではあるけどさ。
そんな訳で、ホントにただの散歩で、近所の喫茶店に来た。日当たりの良い路地に面したテラス席にはチラチラお客さんが見える。ほとんど顔なじみだが、今日は特に用事はない。
「いらっしゃい――おや坊っちゃん、お疲れ様で」
店に入るなり、店主がカウンターの向こうから顔を覗かせた。
「こんちわ、今日はおやつに来ただけだよ」
店に上がる前に、尻尾を軽く拭く。エチケットってやつだ。
ふと見ると、アスファルトの上を引きずって歩いているせいで、腹板にちょっと傷が見える。
※腹板(ふくばん) 蛇において、お腹側の鱗を指す
傷も深くないし、血が出てないから大したものじゃないだろう。無視しておく。ここに付き添いがいたら確実にどやされるだろうけど。
カウンターの端、一番人通りが少ない席に陣取る。俺は尻尾が長くてデカいから、できる限り邪魔にならないようにしなくちゃ。
おしゃれな文字だけのメニューを読んで、美味そうな響きのものを選ぶ。できれば大きいのがいいが、小さいのも美味しいから好きだ。
「ルイおじさん、この“イチゴとラズベリーのチョコサンデー”と、あとブレンドコーヒーお願い」
待っている間は優雅なもんだ。豆を挽く音、サイフォンを熱する火の光、立ちのぼるコーヒーの香り……。
これを味わうためだけに、ここにやってきた。
家の中ではこうはいかない。コーヒーの作法に煩い妹と、そもそもコーヒーの香りが嫌いな許婿がいるからだ。文句を聞き流すことができれば、苦労しないんだろうな。
ここ数年でようやく、穏やかな時間を味わう余裕ができた。血生臭い路地裏から足を洗ったと思ったら、頼った保護施設が襲撃に遭ったり、思い返せば散々だ。
「お待たせいたしました、ブレンドコーヒーでございます。坊っちゃんは、砂糖とミルクは必要でしたかな?」
“坊っちゃん”て呼ばれるの、なんか特権階級みたいで歯痒くて、好きじゃない。俺には気品とかそういうの無いから、なおさら。
「両方お願いするよ。砂糖は多めがいいな」
「かしこまりました」
いちいち気にしてもしょうがない。それに、こういうのは一度気にするとずっと気になるもんだ。とっとと忘れるに限る。
ここのブレンドは美味しいから好きだ。良い香りだし、酸っぱくない。
いつもこんな調子で大量の砂糖とミルクを入れるから、妹から小言を言われる。別にブラックも飲めるし嫌いじゃないけど、それを他人に強要するのはいただけない。好きに飲ませてくれないかな。
ふと耳を澄ませば、他のお客さんの話し声、店内BGM。情報中毒の舎弟を連れてきたら喜びそうなロケーションだ。もっとも、アイツは喫茶店の静かな雰囲気は苦手らしいけど。
カウンターの内側では、店主がサンデーを作っている。円柱形のカップの中に、シリアルフレークやクリームを順番に手際良く盛っている。
「お待たせいたしました。チョコサンデーでございます」
「わーいありがと――うわでっけぇ」
思わず口走ってしまった。
注文したときは気付かなかったが、思った以上に大きい。カップの二倍くらいまでチョコアイスやらプリンやら乗っている。この盛り方だと“パフェ”を名乗るべきじゃないのか。
「いただきます」
さっそく一口。ラズベリーのソースがかかったチョコアイスから。ほどよくシャリシャリのアイスの甘みに、甘酸っぱいソースがアクセントになっている。
横に鎮座したプリンは固めで、ほんのりビターだ。
少し下にスプーンを進めれば、溜まったソースとチョコクリームが見える。その下にはシリアルフレークやゼリーらしきものも見える。
「うまい」
クドくない絶妙な加減の甘さがちょうどいい。それをこの物量、物理法則に軽く喧嘩を売っていそうなバランスの盛り具合で出してくる。職人芸も極まるとここまでくるんだろう。
これで本職がパティシエじゃないあたりが驚愕ものだ。
「ところで坊っちゃん。ラズベリーはけっこう酸っぱいですけれど、大丈夫なのですか?」
昔の俺は酸っぱいものが苦手だったからだろう。
「舌が肥えたのさ。それに、美味けりゃ何でも食うよ」
甘くても酸っぱくても苦くても、それが美味いならなんでも食べる。とにかくなんでも吸収していくのが大事だ。
「なるほど、大きくなりましたねぇ」
なぜかしみじみされている。
――
「――ご馳走さま」
サンデーを食べきって、しばらくは何をするでもなく、コーヒーを飲みながら店内を見回す。
窓辺でパソコンを打ってる人、広いテーブルに書類を広げて書き込んでる人、複数人で談笑する子たちもいる。
まぁ厳密には“ヒト”ではないが、人型生命体なんだから助数詞は“人”でいいだろう。これをニンゲンの眼の前でやると良くないが、どうせこの街にはいないので問題無い。
15時に近くなってきて、お客さんも多くなってきたらしい。
居座る理由も無いし、そろそろ席を立つことにしよう。
「お会計お願いしまーす」
小声で言いながら、呼び鈴を鳴らす。こういう所で声出して呼ぶのは、なんか違う気がする。
「ありがとうございました」
「ごちそうさま。また来るよ」
お礼を言って、店を後にする。扉を一歩出れば、夏の風がじんわりやってくる。
「どれ、腹ごなしに散歩でもするか」
晩飯までに腹を空かせておかないと。とすると、歩く方向は決まってくる。
今日は天気が良いし、日暮れまで歩くことにしようかな。
#ノート小説部3日執筆 お題【喫茶店】
ある意味、「鬼は外」したピーナッツ←
#Noトラブル!Noライフ! の登場人物(https://misskey.design/notes/9vdjzqki5l)に対してモブ視点(セクハラ込み)で書いています
「節分の視線」
自分には行きつけの喫茶店がある。
峠道の途中にあり、何故こんな場所にあるのかと疑問に思うが、喧騒を離れた場所に佇む空間はとても居心地が良いので大して気になることでもない。
そして何より、その空間に立つ店主の雰囲気が好ましかった。
好ましい、などという言葉では到底この感情を表現するのに間に合わない。正直に言ってしまえば、彼の姿を見る度に性的な興奮が湧き上がりそうなのを持てる忍耐を総動員して抑えている。
彼がただ立っている、それだけでもだ。
自分の性的趣向が変化したのかも思ったが、別に他の同性を視てもこんな気持ちが湧き上がることはない。逆を言えば、店主の性別が女性であっても同じ気持ちになる自信はあった。
つまるところ、性別など些末な問題で目の前の人間にとてつもなく惹かれているという事実こそ真なのである。
今日は店内にいるのは自分ただ一人。いつもであればカウンター席を陣取る大柄な男がいるのだが。あの大柄な男がいるからいつまで経っても一番遠いテーブル席を選んでしまう。
いや、それも言い訳か、と小さくため息をついた。こんな下心を抱えて近寄るなどできないという内なる自分がいつも止めに入る。それに近寄ったら考えていることが漏れ出してしまうのでは、という考えが働くのも事実だった。
遠くから眺めていられればそれでいい。欲張ったらこの居場所を失いかねないからだ。
注文を聞かれ、まずはコーヒーを頼む。これもいつも通りだ。提供の為にカウンターの向こうへ行く彼の後ろ姿をこれでもかと眺める。
いつも細身のズボン履いているので脚のラインがよくわかる。引き締まった足首から張ったふくらはぎがあり、膝でもう一度引き締まり、太腿も張っている。
形のいい尻に細い腰、エプロンの紐が巻き付き、姿勢の良い背中へと繋がっている。そのまま視線を上げるとすらりとのびた首にかかるくるりと巻いた後れ毛が、きっちりとした彼の隙のようでいて愛らしささえ感じる。
結い上げた黒髪を団子状に纏め、そこにはいつも髪飾りを着けているのだが。
「…………」
今日のは一味違った。いつも目がある動物モチーフを着けているのだが、何故か今日は顔や手足が付いてるキャラクターっぽいピーナッツ。動く度に目がゆらゆら動き、ぶら下がっている手足も揺れている。
どこか、人を不安にさせる顔立ちしたピーナッツだった。彼の後頭部に目を向ければ常にその不穏な視線とぶつかる。まるで自分の視線を咎められているようで落ち着かない。
コーヒーを飲み干してからももう少し滞在していようかと思ったが、ピーナッツの視線はそれを許してくれない気がする。
支払いを申し出、会計の際にようやく店主と向き合えた瞬間、言いようのない安心感を感じた。思わず思ったことが口をついて出る。
「……いつも髪飾りが特徴的だと思ってますが……なんでピーナッツで……?」
「……あぁ、今日は節分なので。うちは豆撒きするとき大豆じゃなくて落花生を用いますから」
「……なるほど?」
落花生にしてもなんでそんな不穏な表情のやつを選んだんだ、とは聞けず、挨拶もそこそこに店を出るしかなかった。 [参照]
#ノート小説部3日執筆 「薄焼き卵のオムライス」一行だけ、本当にちょっとだけNSFWな部分があります。一応注意
オムライスが食べたい。それも薄焼き卵で巻いた、ケチャップで味付けされたものを。
野暮用を済ませた私は、出先で唐突にそんな欲求を感じた。そして同時に、一人眉を顰めた。
丁度昼飯の時間ではあるので、腹が空くのは道理だ。しかし問題は、『薄焼き卵のオムライス』という点。
というのも、今私がいるのはまさに都会の一角。この辺りでオムライスを出す店は洋食店から、(二十代半ばの男である)私一人では入り辛いキラキラな店まで幾つかある。だがそこで頂けるのは、総じて『ふわふわ卵』――タンポポオムライス、とも呼ばれるタイプ。勿論アレも素晴らしいものだが、今求めているのは違う。薄く延ばした卵がケチャップライスを包み込み、その旨味を引き立てる。言うなれば、卵がライスの『従』に徹しているタイプである。だが、このタイプは昔から食されてきた家庭の味。少なくとも、ビジネスビル立ち込めるこのエリアで、それを提供する場所など――
あった。ビルに隠れるようにして佇む古びた喫茶店。その食品サンプルの中に、確かに求めていたオムライスの姿が。
恐らく何十年、下手をすれば戦後ぐらいから営業してきたのだろう。営業中の看板が無ければ、とっくに閉めた店だと思っていただろう。
私は木製の扉に手を掛け、ゆっくりと開いた。カランコロンという小気味いいチャイムの音が響く。
視界の先に広がっていたのは、素晴らしいまでの『レトロ喫茶』の景色だった。華美な装飾とは無縁の薄暗い店内には、何処かで聞いた事のある洋楽が流れている。店内には薄っすらと煙草の匂いが漂っており、カウンターとテーブルには灰皿が置かれていた。古びた本棚には週刊誌とスポーツ新聞、私の親世代が読んでいたであろう漫画。
「ああ、いらっしゃい。お好きな席にどうぞ」
テーブルを拭いていた店主が顔を上げた。歳の頃は七十を超えていそうだが、腰も曲がっておらず、至って健康体。この手の喫茶店は、偶に心配になるほど老いた店主が切り盛りしていることもあるが、この店に関しては安心して見ていられそうだ。
私はカウンター席に座ると、年期の入ったメニュー表に目を通した。「オムライス 550円」の文字を確認すると、すぐに店主を呼んだ。ついでに300円らしいコーヒーも付けた。
料理が来るまでの待ち時間。今の時代、スマホという最強の暇つぶしがある。だが、こんな風情のある喫茶店でスマホだけしか目に入れないのは勿体ない。
私はもう一度店内を見渡した後、本棚からスポーツ新聞を手に取って広げた。週末だけあって、裏面には競馬の特集が組まれていた。そういえば、一時期競馬をよく見ていた。馬券を買った事もあったが、禄に当たらなかった。ペラペラとめくっていくと、中頃でいきなり乳房が丸出しの女の人が出てきて、思わず声を出しそうになった。私以外に客はいないが、スポーツ新聞を人前で広げるとこれが怖い。
私はいそいそと新聞を戻すと、カウンターの向こうで料理に取り掛かる店主を見た。二人入るのがやっとという手狭なキッチンで、店主は手際よくオムライスを作っていく。老人とは思えぬ軽快な手さばきでフライパンを振り、サラダ油でコーティングされた米を炒めている。その後も洗練された動作で調理を進める店主の一挙手一投足に、気が付けば私は目が離せなくなっていた。
そうして眺めること十分ほど――待ちに待った一品が、目の前に差し出された。波を描くようにケチャップを掛けられた薄焼き卵。この下に隠れているのは、ケチャップライス、それから――刻まれた玉ねぎと、鶏肉。
スプーンを入れると、押し込められていた熱が湯気となって飛び出し、同時にケチャップと玉ねぎの香りが鼻腔を刺激する。空の胃袋が『早く食べろ』と鳴いた。
スプーンに乗せたオムライスを口に入れる。その瞬間――口内に広がったのは、幾つもの味。ケチャップの甘味に、鶏肉の旨味。そして、玉ねぎの甘味。
細かく刻まれた玉ねぎは、見た目の上では目立つ存在ではない。しかし、実際に咀嚼してみると、ザクザクとした食感と特有の甘さがハッキリと主張する。その玉ねぎによって引き立つのが、鶏肉。元来玉ねぎと肉類は相性抜群なのだが、肉が主役でないオムライスでそれを実感するとは思わなかった。食感からして胸肉だろうが、驚くほどしっとりしている。
何より凄いのが、これだけの存在感を放つ両者を相手に、ライスが邪魔されていないことだ。心なしかパラパラしたライスは、トマトの甘味たっぷりのケチャップを身に纏い、噛むほどに舌を喜ばせる。これこそ、薄焼き卵のオムライスの魅力だ。包む卵が控えめだからこそ、中のライスと具一つ一つを集中して味わえる。無論、卵も目立たないのではなく、最初に舌に触れる、いわば旨味の尖兵としての役割を果たす。そしてライスに触れた後も、オムライス全体の味をまろやかに調和してくれるのだ。
名残惜しささえ感じながら飲み込むと、幾つもの美味が総体となって食道を下って行き、良質な映画のスタッフロールのような余韻をもたらした。
一つ幸福のため息を吐くと、それ以降は無言で食らいついた。話すどころか、息をすることすら面倒だ。本当に美味いものを口にすると覚えるこの感覚を、都会のレトロ喫茶で感じていた。
米粒一つすら残さず、完食。間違いなく、今まで食べた中で最高のオムライスだった。
食後のタイミングで運ばれたアイスコーヒーを口にしながら、ふと疑問が湧いた。
これだけ美味いなら、もっと人がいてもいいだろうに。
だが同時に、こうも思った。
私のような少数が知っている方が、こういう店は良いかもしれない。
昨今は若い世代にもレトロ喫茶が人気で、こうした店は一度話題に出れば客が押し寄せるだろう。しかし、売れる、知られるというのは必ずしも良い面だけじゃない。見たところこの店は、年老いた店主が一人で回している。となれば当然、行列など出来ればすぐにキャパオーバーになるだろう。それで身体を壊してしまえば元も子もない。
ここはこのままでいい。アーティストがメジャーになるのを嫌う心理と同じかもしれないが、そう思わずにいられなかった。
会計を済まし、「ありがとうございました」と頭を下げる店主に、「ごちそうさまでした」と会釈を返した。
暫く歩いてから振り返ると、古い喫茶店はビルの林に隠れてしまった。狐や狸が見せた幻だったとさえ思えたが――私の下と胃は、その味を確かに覚えていた。
#ノート小説部3日執筆 喫茶店
もう30年も前の話だ。放課後の女子校に呟きが落ちた。
「カフェやりたいなー」
智子はうんと腕を伸ばした。同級生の桜が呆れたように横目で見た。バブルが崩壊してこのかた、カフェが流行している。東京では小さなカフェに大行列ができるそうだ。喫茶チェーンも着々とこの田舎にまで流行を広げてきている。
「よくない? 路地裏の寂れたカフェ。サイフォンで、手作りケーキとか出すの」
「……カフェは面倒だよ」
「そりゃ人が入らなきゃ経営できないけど」
「喫茶店にしときなよ」
「なんで?」
「営業許可が違うから」
桜はあっさりと答えた。法律で決まっているのだと。
「そうなの?」
「カフェは飲食店で大体なんでも出せる。喫茶店は加熱調理のみ可でアルコール不可。喫茶店の方が簡単に取れる」
「へー」
「ケーキとか作るのはもっと大変。菓子製造許可もいる」
「うわ、マジでか」
智子はうわあと天井を仰いだ。それは本当に面倒そうだ。文化祭で食品を出すのも多くの決まりがあったのだから。
「だから昔、純喫茶が流行ったんじゃない?」
「あー、そういう……」
智子はうなずきながらも首を傾げた。
「『純』?」
「お酒を出さない喫茶店のこと」
「じゃあ、お酒を出す喫茶は不純喫茶? ……違う意味に聞こえるね。風営法的な」
「あまり間違ってないかな。特殊喫茶っていう接待付きの喫茶店があったから」
「接待……ああ、なるほど。考えることは昔も今も変わらないなあ」
「そう。まあ、食品衛生法に適合する店舗がないとダメだから、カフェは難しいと思う」
「わかった、今は諦めよう。……なんで桜、そんな詳しいの?」
「さあ?」
それから30年。バブルの時代は遠い昔になった頃、路地裏にある喫茶店の扉が開いた。
「こんにちはー」
「はい、こんにちは」
「智子さんも桜さんも元気で」
「お客さんが多いからね。まだ老けてられないの」
「はは、そりゃよかった」
客は迷うことなくカウンターに腰掛ける。
「いつもの?」
「うん。コーヒーとケーキ。今日は何?」
「ガトーショコラ」
「じゃあそれを」
サイフォンに火が入る。沸騰すると一度火から離し、ロートにコーヒー粉を入れる。再び火にかけるとお湯が上がってきた。智子がそっと混ぜてやる。火を消すと、できたコーヒーが落ちるので、カップに注いでやる。ガトーショコラが皿に乗せられた。
「この店でこの様子を見るのが好きで」
「あら、あなた桜目当てじゃなかったっけ?」
「智子さんも桜さんも好きですよ。チェーン店が多い中、こういう個性的な店はいいですね」
「あらあ、上手に言えたわね。クリーム増やしてあげる」
「やったあ。智子さん大好き!」
なお2021年に食品衛生法が改正され、喫茶店とカフェの区別はなくなった。
#ノート小説部3日執筆 にゃんぷっぷーと飼い主とその彼女の話です
※一次創作『子々孫々まで祟りたい』のキャラ奥武蔵と狭山咲の事を知ってないとよくわからないかもしれません、すみません
金曜日の夜、オタくんが言ったにゃ。
「日曜にさ、咲さんと喫茶店で会うんだけど、にゃんぷっぷーも来てくれない?」
「とうとう一人で行くのが怖くなったのにゃ?」
オタくんはまともにできた初めての彼女が咲さんで、いつも捨てられないか怯えてるにゃ。
「ちがくて! にゃんぷっぷーを紹介したいの!」
「でも、元ぬいぐるみのにゃぷが喋ったら咲さんはびっくりするにゃ」
だからにゃぷは、だいたいおうちにいるのにゃ。でも、オタくんは「大丈夫」って言ったにゃ。
「咲さんは怨霊とか化け狸とか知ってる人だから、ちゃんと説明すれば平気。喫茶店も、個室ある所選んだし」
そういう訳で、にゃぷは日曜日にオタくんのバッグに入って喫茶店まで行ったにゃ。
アイスコーヒーとオレンジジュースを頼んで咲さんを待ってると、しばらくして、ノースリーブにロングスカートのお姉さんが来たにゃ。
「こんにちは! 奥さん、今日にゃんぷっぷーちゃん見せてくれるんですよね」
奥、はオタくんの名字にゃ。
「あ、その、もうここにいます……」
オタくんは、テーブルの上のにゃぷを指さしたにゃ。にゃぷはてむてむ跳ねて、咲さんの近くに行ってあいさつしたにゃ。
「こんにちはにゃ、はじめましてにゃ!」
「喋った!?」
咲さんは目をまんまるにしたにゃ。オタくんは言い訳するみたいに言ったにゃ。
「なんかその……コインランドリーににゃぷぬいを間違って入れて回しちゃったら、生きたにゃんぷっぷーになってまして……」
「にゃぷはかわいがられたかったから、かわいがってくれるオタくんのところに来たのにゃ」
「そんなんでこんなことなるんです!?」
「まあ世の中には、怨霊も化け狸もいるので……」
「にゃぷはにゃぷにゃ。咲さんも飲み物頼むといいにゃ」
咲さんは戸惑ってたけど、「え、えっと、じゃあ……」とメニューを開いたにゃ。
「アイスティーでいいかな」
咲さんは店員さんを呼ぶボタンを押したにゃ。店員さんが来て注文取るまでは、にゃぷは大人しくしてて、店員さんがいなくなってから喋ったにゃ。
「自己紹介するにゃ。にゃぷはかわいがられるのと、オタくんを応援するのと、オタくんを褒めるのがお仕事のにゃんぷっぷーにゃ」
「いつもは奥さんのお家にいるの?」
「お家にゃ。だいたいMisskeyにいるにゃ」
「だいぶミス廃なんですよ」
オタくんはにゃぷを指さして苦笑したにゃ。
「にゃぷちゃん、ご飯は食べるの?」
「食べるにゃ。朝ごはんと夜ご飯はオタくんと同じのを食べて、お昼は猫のカリカリ食べてるにゃ、猫だから」
にゃぷが喋ってたら店員さんが入ってきて、びっくりしてたけど、オタくんは「すいません、AIで喋るぬいぐるみの試作品なんです!」と言い訳したにゃ。AIって万能にゃ。
「じゃあ、にゃぷちゃん、今おやつ食べたりする?」
「食べたいにゃ! 甘いの好きにゃ!」
「じゃあ、好きなのひとつ奢ってあげる」
「ぷにゃ! 本当にゃ!?」
にゃぷは欲望のままにパフェを頼んだにゃ。にゃぷはにゃぷ用のスプーンを持ってきてなかったけど、咲さんはにゃぷにパフェをひとさじずつ食べさせてくれたにゃ。いちごとバニラアイス、生クリームと缶詰みかん、チョコソース、どれもたまらないにゃ!
「甘いにゃー! おいしいにゃ!」
咲さんは笑って、オタくんに話しかけたにゃ。
「奥さん、こんなかわいい子が家にいたら、もう毎日たまんないでしょ?」
「いやー、ははは、実は、たまんないです」
オタくんは照れくさそうに笑ったにゃ。
「……私も、この子はかわいいですよ」
咲さんは、紙ナプキンでにゃぷの口を拭いてくれたにゃ。咲さん、オタくんの言う通りに優しい人にゃ!
「……まあ、この子なら千歳さんみたいには見なくてすむかな」
咲さんは、にゃぷをなでなでしてくれたにゃ。にゃぷは咲さんが大好きになったにゃ。
「にゃぷ、咲さんのこと大好きにゃ、だからオタくんとずっと仲良くしててほしいにゃ!」
「そっかぁ……」
咲さんはにゃぷをもう一度なでて、それからオタくんに言ったにゃ。
「……私、別に奥さんなら、結婚前提でもいいですからね?」
「え!?」
「ぷにゃ!?」
「まあ、結婚前提なら話し合うこといろいろありますけど、奥さんはどうですか?」
「え、えっと……」
オタくんはびっくりして、なんにも考えられないみたいにゃ。しばらくして、オタくんはなんとか言ったにゃ。
「その……僕も結婚前提だと、嬉しいですけど……」
「じゃ、決まりですね」
咲さんはニコッとしたにゃ。なんてことにゃ、オタくんの生涯の伴侶が決まる場面に立ち会ってしまったにゃ!
「私、にゃんぷっぷーちゃんならかわいがれそうですから。三人で、やっていきましょう」
「は、はい……」
オタくんはまだ信じられないみたいな顔だったにゃ。
にゃぷは、にゃぷをかわいがってくれる人が増えて、とっても嬉しかったにゃ。二人で、たくさんにゃぷをかわいがってほしいと思ったにゃ。
#ノート小説部3日執筆 お題「喫茶店」お話思い浮かばなくてエッセイにしてしまった……。
散歩のゴールを喫茶店にした話
私は通院しており、血液検査をする機会があった。CKという値が低く、運動不足を指摘された。血でそんなことがわかるのか、と感心しつつ、出不精であることを反省し、健康のために散歩を始めることにした。
最初は毎日、家の近所を回ってコツコツと歩いていた。住宅街の細かいところなんて案外知らないものだ。宛もなくフラフラと彷徨ったあと、帰巣本能を頼りに道に迷いつつ家に帰る。まあまあ楽しかった。
しかし、ある日から散歩が続かなくなった。その理由を考えたとき、私は単調な道を歩くことに飽きてしまっていたことに気がついた。そこで、目的地を決めて歩くことを試してみることにした。
目的地といっても、これがまた思いつかないもので、とりあえず電車に乗る。一時間くらいか熟考して、歩いたあと休めるように、最終的な目的地を喫茶店に決めた。電車を降りる。
サンドイッチ屋さんを見つけた。美味しそうだが、これから喫茶店に行くのだ。また今度、機会があれば買いに行こう。とある建物の前に変なモニュメントを見つけた。狛犬のように、両端に鎮座しているが、何なのかわからなかった。ふんどし専門店を見つけた。こんなお店があるのか。
30分フラフラと散歩した頃だろうか。城という喫茶店を見つけた。城、でありますか。名前に興味を持ち、ここを目的地として入ることにした。
城と言うには控えめすぎる扉を開くと、馬に乗った騎士のステンドグラスが目に入った。城を守る騎士に会釈し、地下へ続く階段を降りていく。すると城の内装が描かれた大きなステンドグラスが目に入った。ここは本当に城であった。
純喫茶のクラシカルな雰囲気、そこに綺麗なステンドグラスが並んで、特別な空間が出来上がっている。私は端っこの席についた。店員さんからメニューを渡される。ブレンドコーヒーとチョコレートケーキを頼んだ。
すぐに注文したものが用意された。昼前の空いている時間だったからだろうか。ブレンドコーヒーを飲んでみる。程よい苦みと酸味。ああ、食レポの技術がないのが悔しい。チョコレートケーキを口に入れる。クリームはしっかり固め。甘さ控えめ。コーヒーの邪魔をしない。ほっと一息つく。
ソファの背ににもたれかかる。ギシギシ音がなり、年季が入っているのを感じた。散歩の道のりを振り返る。サンドイッチ屋さん、建物の前に置かれた変わったモニュメント、ふんどし専門店、最後に城という喫茶店。ここは変わった街だ。この喫茶店で過ごす時間は、ただの休憩ではなくなった。特別な体験を振り返る場所になった。
これからも散歩のゴールを喫茶店にしようと思った。コーヒーとケーキと素敵な空間が、単調な散歩に豊かさをくれる。みなさんも散歩のゴールを喫茶店にしてみてはどうだろうか。いや、喫茶店でなくてもいい。どこか休めるところで、知らない街での体験を振り返ってみて欲しい。きっと素敵な思い出に変わるだろう。
#ノート小説部3日執筆 「モーニング」お題:喫茶店
なめらかな金の瘡蓋、もしくは深い夜空に一筋、星の軌道をそのままにしたような金継ぎが施された夜空色のコーヒーカップから香る珈琲の芳しさは私をほっとさせた。
「どうぞ」
最近ここに働きはじめたらしい青年――巽君が、続けてトーストとゆで卵のセットを差し出す。実にスタンダードなモーニングセットだ。私は添えられたイチゴジャムをトーストに塗りたくりながら、さて相方はいつ来るのやらと窓をちらりと見やった。
夏の始まりとは思えないような目映さである。午前の早い時間だというのに気温は三十度近い。
「マスターは今日はお休みなのか?」
「いえ、朝から買い出しに。こんな暑さだとは思いもしなくて……週明けからかき氷を始めようって言っていたんですけど、前倒しを」
「なるほど」
巽君の返答に頷き、ジャムをたっぷりと塗ったトーストをかじる。丁度良い焼き加減のトーストと甘酸っぱいイチゴジャムの良い案配が口の中に広がり、私の身体はまた一段階、目を覚ました。
「暑いので僕が行きましょうかと行ったんですが」
「まあ季節の始め、夏でいちばんめの氷だ。挨拶することもあろうさ」
「そうですかね、氷でしょう?」
「氷でもだ。そういうものだよ」
巽君は首を傾げたが、あのマスターの素性を知らずとも何かしらを察しているらしく曖昧に頷いた。――と。
「おはよう! クリームソーダひとつ!」
「は、はいっ」
待ち人のお出ましである。賑やかを人間の形にすればこうなるのだろうと思わせるような明るさで、彼女はドアを開き開口一番注文を通した。私は小さくため息をつきながら、珈琲を一口飲む。
「猛暑だろうが君は元気そうだね」
「いやー、暑い、暑い! 日焼け止めもお手上げですよ、この暑さは!」
相方は私の隣にどかりと座りながら、持っていたウチワではたはたと己を煽る。あまりのそよ風を感じながら、ふん、と鼻で笑うと彼女の目の前にクリームソーダが置かれた。背の高いグラスに、ケミカルなグリーンが満たされている。その中ではフツ、フツと小さな泡がかつ消えかつ結びて、それが一種の秩序のように思えた。そしてそのケミカルグリーンの海上にひとつ、惑星のようなアイスクリームがぶかりと浮いている。水面に面しているところからゆるくクリームが溶け始め、混ざり始めていた。
「さて、この私を呼び出したのには理由があるのだろう。ミノウラくん」
「まあ待ってください、待ってください。今ちょっと……忙しいんです」
相方――ミノウラくんは真剣な顔で目の前のクリームソーダを睨みつけている。私はゆっくりと瞬きをさせ、珈琲をもう一口飲む。柔く微笑んでいた巽君が、口を開いた。
「おかわりありますので」
「ありがとう」
ミノウラくんの持つ銀色の細いスプーンが、ミルク色の惑星をつつくたびにそれはケミカルグリーンの海に沈んでは浮かぶ。ついにその地表が削り取られ、ミノウラくんの口に運ばれた。
んー! と感極まったかのような声を聞き流しつつ、私は皿の端でコツコツとゆで卵の殻にヒビをいれる。
「ミノウラさん、モーニングはいかがですか?」
「小倉あん」
「かしこまりました」
巽くんはトースターに食パンを放り込み、慣れた手つきで小倉あんを小鉢によそう。
「理由としては」
スプーンでクリームソーダの海をくるりと混ぜながら、ミノウラくんは切り出す。それを飲みきるまで何も言わないだろうと高をくくっていた私は、うたた寝を叩き起こされた学生のような反応の鈍さで彼女を見た。すると彼女は、私を見て可笑しそうに笑った。
「君が聞いてきたんじゃないか!」
「……続けてくれたまえよ」
カウンターの向こうでチン、という軽やかな音が聞こえる。私に促され、ミノウラくんは渋い顔をさせて口を開いた。
「まずは家の冷房が壊れた。この時期にだよ! あれほど可愛がっていたというのにあの冷房は恩知らずもいいところだね」
「はあ、まあ運が悪かったのだね、君が」
「それと――」
ミノウラくんの目の前に、焼きたてのトーストとゆで卵が置かれる。その傍らには小倉あんが添えられていた。
「おまたせしました」
「それと?」
「お待ちくださいよ、今トーストがやってきた。あんを塗らなければ……」
彼女の手がバターナイフを握る。私がふむ、と息を吐けば巽君が申し訳なさそうに、笑んだ。
バターナイフがぐり、ぐり、とトースターに小倉あんを塗っていく。まるで漆喰を塗る職人のような真剣さで、ミノウラくんは小倉あんトーストを作っていった。一面に塗りたくられたのを満足げに見つめたあと、ざくりと一口……。
「やあ、暑いな」
マスターが帰ってきた。その肩にクーラーボックスをしょって、額の汗を拭っている。
「おかえりなさい。お水を出しますので」
「ああ、ありがとう」
「まふたー!」
「口の者を胃に仕舞ってから喋りたまえよミノウラくん」
マスターは私と彼女のやりとりににこにこしつつ、カウンターに戻った。大きな冷凍庫の戸を開け、買ってきたばかりの氷塊を入れる。
「やあ、今年初めてのかき氷を食べるお客さんがいて良かったよ。さもなくば僕と巽くんで独り占めをしてしまうところだった」
備品を押し込めた棚を漁りながら、マスターは嬉しそうに笑う。
「それでねえ、ミチヲくん。おい、聞いていますか」
ミノウラくんの声を聞き流しつつ、私は巽君が並べだした色とりどりのシロップを眺めつつ、彼に珈琲のおかわりを頼んだ。全ての輪郭をぼかしてしまいそうな陽光が窓から差し込んでいる。その光を受けて私の手にあるマグカップを彩る金継ぎはきらきらと輝いていた。 #ノート小説部3日執筆
#ノート小説部3日執筆 ガーリックトーストが食べたいのじゃねぇ お題/喫茶店
◆◇◆
真夜中の喧騒を眺めながら、窓際のカフェテーブルに座って読書をしていた自分は、手元の腕時計に目を落とすと、日を跨いで随分時間が経ったことを知った。
ナイトジャズと仕掛け時計のリズムが響く店内には、静寂とは呼べないまでもざわざわとした賑わいが溢れており、むしろ何かに打ち込むためには、この場所はうってつけな環境であった。
手元の文庫本に目を向けようとしたとき、ふと気が付くと随分と腹が減っていることに気づいた。
そういえば入店した際に注文した、アイスコーヒー一杯で、随分と居座ってしまったこと事実を思い出し、少し申し訳なく思いながらも、メニューを手に取る。
ナポレオンやパフェなんて小洒落たメニューが腑に落ちず、一瞬、固まってしまったとき――目に留まったのは「厚切りガーリックトースト」の文字であった。
迷わずそれを注文する。
ウェイトレスが、無感情に注文を受け、カウンターの向こう側で、マスターが調理を始める。待ち時間など、ページを読み進めれば、苦にもならないものだ。
ただ、刻々と過ぎる時間を楽しんでいれば、ほどなくしてウェイトレスが厚切りのガーリックトーストを皿にのせて運んできた。
ガーリックトースト――
音の響きだけで、食欲がそそられる代物だ。
見た目は、家ではお目にかかれないトーストだが、黄金色の焼き色にきらめき、触れるだけでサクッと音を立てそうな雰囲気が漂う。
何より漂ってくるのは、火入れされた焦げ目の苦みすら感じさせる小麦の香気。 そして、しっかりとした食欲をそそる、トーストへとしみ込んだガーリックバターの食欲をそそる香ばしくコクのある香り――
もう我慢できずに一口、手で持って齧りつく。
すると、トーストされた表面のカリカリとした食感が口いっぱいに広がり、柔らかくて自然な小麦の甘みが後に続く。そして、表面をコーティングしているガーリックバターの重く濃厚なニンニクな旨味が、顔をのぞかせる。
ならば――遠慮なく咀嚼しなればならない。
トーストの旨味は、噛んでこそ、じっくり味わってこそ味わい深く広がっていく。ニンニクの香ばしい風味は一層膨れ上がり、バターのコクと、刻々と変わる食感がそれを受け止め、その味の重厚さに反して、すっと胃へと収まっていく。
もう一口、ゆっくりと味わうようにガーリックトーストを齧る。
贅沢なほどの厚みが、今は嬉しい。
カリカリに焦げた耳を齧り、サクサクと音を立てるトーストは決して単調な料理ではない。バターがしみ込んだ、しっとりとした表面、もっちりと歯を受け止める中身、これらが一体になる瞬間をゆっくりと咀嚼していく。
◆◇◆
そうして、一片のガーリックトーストに夢中になっていると――
「サービスですからどうぞ――」
と、無愛想なウェイトレスが一杯のミネストローネを持ってやってきた。
ありがとう、と軽く会釈をしてカップへと目を向ける。
カップの中で揺れるのは、冷房の効いた店内で嬉しい、暖かいトマトスープ。
甘酸っぱく深みのある香りが鼻腔を擽れば、これがコンソメや野菜の上手さが溶け込んだものであることが分かる。
残り半分となっていた、ガーリックトーストを尻目にスプーンを手に取って一口。
その瞬間、舌の上に広がったのは、よく煮込まれ酸味と甘みが絶妙に調和したトマトの、まろやかで優しい味わいだった。
もう一口、具材と共に掬い、口へと運ぶ。
ニンジンの甘みがトマトの酸味を引き立て、玉ねぎの甘みと旨味がスープ全体を引き締める。
最近まで高かったキャベツがふんだんに使われているのも嬉しい。
葉物野菜特有の煮込んでも原型残るしゃきしゃきとした食感の内側に、スープの旨味をしっかり吸い込んで、主役を張れる御馳走になっている。
そうして、野菜の優しい甘みを味わっていると――自分の中で無性に強い旨味が恋しくなってくる。ならばと、一度カップを置き、ガーリックトーストを手に取って、がっと豪快に頬張る。
これは、正解だった。
パンの甘みとバターの塩味が、野菜の旨味で引き立って、より深いハーモニーを奏ながら、カリカリ、モチモチ、ジュワッという食感の変化が、まるで交響曲のように口の中で展開され、もくもくとトーストにかじりついているうちに、気づけばガーリックトーストは、余すことなく胃に収まっていた。
なんとも儚いが、満足感のある一皿だった。
最後にミネストローネを、目をつぶって、すすり音を立てながら啜る。いまだに喉に感じる熱さの中で、すでに原型のないジャガイモが、舌の上でほろりと崩れた。
なんだ、お前だったのか、このスープにまろやかさを加えてくれたのは。
そう思いながら、ふと店内に目を向けると、なんだかトーストを片手に談笑したり、スマートフォンを弄る人が増えているように感じる。
なんだ、考えることは皆同じか。
少しの共感を覚えつつ、再び掌の中の文庫本を開く――この尊い時間は、日が昇るまでは続くことだろう。
#ノート小説部3日執筆 でノート小説を書くにあたっての相談や質問ができる「Misskey.ioノート小説部」のDiscordサーバーも以下のリンクにご用意してあります。作品の批評や雑談のできるテキストチャットや、お題を自薦いただける会議部屋などもございます。わたくし小林素顔がサーバー管理者なのでお聞きになりたいことがございましたらお気軽にご参加くださいね!
https://discord.com/invite/ReZJvrqG92 [参照]
#ノート小説部3日執筆 第13回のお題は「喫茶店」に決まりました! 今回は7月7日(日)の24時間の間での公開を目標としましょう。作品はノートの3000文字に収まるように、ハッシュタグの#ノート小説部3日執筆 のタグを忘れずに! [参照]
#ノート小説部3日執筆 「ローバーに願いを」 お題:七夕
2020年、マーズ2020計画により火星に送られた探査車(ローバー)、パーサヴィアランスを知っているだろうか。
不屈の名を持つそれは長期稼働に耐えるだけの動力システムを持ち、火星に願いをかけた人々の名を彫り込んだプレートを背負い、地表探査の傍ら火星の大気から人間の生存に適した空気を生み出す実験を続け、今日の火星移住計画の礎となったと言っても過言ではない存在だ。
そして、火星の各地に全天型のドームが建てられて本格的な移住が盛んになった今でも、ドーム外のどこかを走り回っているのだという。
「で? お前がパーサヴィアランス(パーシィちゃん)ラブなのは知ってるけど、それと七夕は関係なくね?」
ショッピングモールの中心に置かれた七夕飾りのコーナーでカラフルな短冊に即物的な願いごとを書きながら、ジロウはルイの蘊蓄を聞き流した。
二人は旧くからの友人で、近年は仕事の都合で疎遠になりがちだったのだが、偶然邂逅を果たしたため「せっかくだから」とモール上階のアミューズメント施設で高校生に戻ったかのように汗を流し、遅い昼食でも摂ろうとレストランフロアに来たところで件の七夕飾りを発見してジロウがそれに飛びついたところである。
カネにがめつく、しかしながら夢は一攫千金で左団扇といういささかロマンティストなジロウと、宇宙をこよなく愛し、しかしながら宇宙人やアブダクションなどの超常現象には懐疑的というリアリストなルイは一見相反する性格のように見えるが、謎の噛み合わせの良さを見せる言わば凸凹コンビなのだった。
で、本来は子供のお客様向けだろう短冊にデカデカと「 」と書いたジロウがルイにも短冊を勧めたところ、固辞と冒頭の蘊蓄が返ってきたというわけである。
」と書いたジロウがルイにも短冊を勧めたところ、固辞と冒頭の蘊蓄が返ってきたというわけである。
「お前にも叶ってほしい夢とかあるっしょ? 火星に行きたいーとか」
「確かにそれは俺の悲願だが、願いをかけるとしても遊び呆けて神の怒りを買ったリア充(織姫と彦星)相手になんぞごめんだね。だったら今も勤勉に探索してるパーシィちゃんに託したい」
火星移民はいまはまだ狭き門で、一定条件を満たした上で結構な倍率の抽選に当選しなくてはならない。
そしてルイは今年ようやくその「条件」を満たし応募資格を得たところなのだった。
パーサヴィアランスが火星に打ち上げられるにあたって「名前を刻んだプレートを火星に持っていくキャンペーン」なる企画を立ち上げた時、ルイはまだ年端もいかない子供で、当然のことながら自力で応募することはできなかったので、親に頼み込んで誕生日プレゼント代わりにその企画に応募してもらったのだという。
それくらいルイの火星好き、パーサヴィアランス好きは筋金入りで、以来、いつかは火星に渡ってパーシィちゃんと直接対面するというのが彼の夢、もとい目標なのだった。
「お前ってそういうとこ妙にお堅いっていうか、ロマンティストなんだかリアリストなんだかわかんないとこあるよな」
「『金くれ』なんて夢のない願いを短冊に書くお前にだけは言われたくないが」
茶化すように言うジロウをルイは睥睨したが、いつものことなのでジロウは臆した風もなく軽く肩をすくめただけだった。
「まー、短冊に書くだけならタダだし? じゃあ素直じゃないルイのために俺ちゃんが書いといてあげようかね……『パーシィちゃんがルイの火星行きを叶えてくれますように』っと」
そして笹のいちばん高いところにそれを吊るした。
「おい、勝手に人の名前を書くな、それからパーシィちゃんとか書くな、書くならちゃんとパーサヴィアランスと書け」
「訂正したきゃ自分で短冊外して書き直しな〜」
この二人、性格のみならず身長も凸凹で、長身のジロウはルイの手が届かないことをわかって敢えて短冊の吊るし場所として高いところを選んだのだった。
ルイはぐぬぬ、と呻き声を発さん勢いで臍を噛んだが、ここで騒いで周囲の耳目を集めるよりはそのままにしておいてただの紙切れ(短冊)が他の多くの短冊(願い)に紛れるに任せた方がいいと判断する。
「……満足したならいい加減メシに行こう、俺はひとまず腹を満たすって願いを叶えたいね」
「俺も俺も! じゃー適当に空いてる店探すかー『美味くて安い店がちょうど席空いてますよーに』!」
「お前はホント即物的だなぁ」
こうして二人は七夕飾りのエリアを後にした。
その後間もなく、ルイは念願叶って火星行きの抽選に見事当選を果たすのだが、それはローバーへの想いが通じたからなのか、牽牛と織女が叶えてくれたからなのかは知る由もないことである。
おわり
大遅刻、申し訳ありません【#ノート小説部3日執筆 】※人の病気、死について言及があります『インターネットの銀河の果てに、彦星は』
2024年6月26日。ICQが終わった。
明日も出勤日である事実から目をそらしつつ、就寝前にスマホをいじっていたわたしは、懐かしいメッセンジャーアプリの名前を見かけたのだった。
「ICQ、まだあったんだ」
検索してみると、1996年のスタートから、運営会社を変えながら運営され、アプリもあったそうだ。「へえ~」と思いながらブラウザを閉じようとしたとき、「〇×商店街に七夕飾りが~~」というニュースが目に入って、突然、記憶がよみがえった。
「あ! そうだ! 彦星!」
およそ25年前、ICQに「自称・彦星」が現れたのだ。
***
時は1998年か1999年あたり。インターネット回線はダイヤルアップ接続であり、夜中のテレホーダイタイム(一定料金でインターネットがつなぎ放題!)が待ち遠しかったころ。
ある日、「ICQって知っとる? これあったらな、いつでも連絡できるんやに」と、遠くの大学に進学した友人のイチに教えられて、わたしはそのツールを知り、ほどなくして夢中になった。
何しろ遠くにいる友人と、テキストだけとはいえ、電話代を気にすることなくリアルタイムでやり取りできるのだ。メッセージが届くと、「アッオー!」と、独特の通知音がする。鶏の鳴き声のようなその音を聞くと、ワクワクした。
わたしはもうすこしこのワクワクの頻度を増やしたいと思い、「ホワイトページ」と呼ばれるICQでの交流相手を探せるページや、ICQ利用者が集まる掲示板をのぞくようになった。
そこで見つけたのが、奇妙な書き込みだった。「当方、彦星! 七夕に会える織姫を探しております。7月7日の7時に連絡を」。あからさまな出会い目的だが、その堂々とした姿勢にかえって好感をもったわたしは、7月7日にメッセージを送ってみた。「『ICQ便利帳』の掲示板でIDを見かけて連絡してみました」。
どんながっついた返事がくるかと身構えたものの、「アッオー」の音声とともに届いた返事は、「こんばんは! あそこを見てくれたんですか。ありがとうございます」といった常識的なものだった。
彦星は穏やかで、住んでいる場所など、繊細な個人情報を聞くことはなかった。ICQを使い始めたきっかけから、お互い大学生であることを明かし、見た映画の話や文学の話をし……。記憶は曖昧だが、次の年の7月7日にもメッセージのやり取りをしたような、気がする。
わたしは懐かしいあのICQのインターフェイスを見ようとノートパソコンを立ち上げ、検索をして……意外なところで彦星と再会した。
それは、パソコン雑誌のアーカイブだった。「今話題のICQって!?」という記事で、利用者何人かがインタビューに応じている。そのひとり、太田原凱彦の談。
「恥ずかしいですけど、彼女ができたらな、と思ってICQを使っています。注目してもらえるかなと思って、『彦星です、7月7日に連絡して』なんていって。でも連絡をくれた子は、みんな人として面白くて。天文学者目指している子とか、今アメリカにいますって子とか。7月7日だけじゃ話し足りなくて、毎晩『アッオー!』を楽しみにしてます。織姫とは出会えていないけど、世界が広がって、ICQには感謝です」
彦星、いい奴だな。わたしとは年に一回しか連絡を取らなかったけど!
あらに彦星のことが知りたくなったわたしは、検索窓に太田原凱彦と打ち込んでみた。が、めぼしい情報はない。たしかイチとわたしはその後、Skypeに移行した。Skypeは2004年に誕生……。2004年……mixiだ! わたしは数年ぶりに、mixiにアクセスした。
「太田原凱彦」では出てこない。記憶を掘り起こすうち、あるやり取りを思い出した。
名前がガイって読めるから、友達とのチャットでGUY××って書かれたことあるよ。××は、本名につく漢字ね……。内緒だけど(笑)「GUY彦」の検索結果、1件。
そこには、彦星の足跡があった。
「2006年10月16日 嫌になりますね~
就職活動で死ぬほど苦労したけど、給料は上がらず。
今日もまた終電」
彦星は、どうも地方のメーカーの子会社に就職したようだった。
「2007年1月1日 暗い話です
お久しぶりです。実は、会社を休職していました。ある日、朝、布団から起き上がれなくなって」
「2008年5月1日 ゴールデンウィーク!
ご無沙汰しています。非正規雇用で工場で働き始めました。タイトルに反して……ゴールデンウィーク関係なく、シフト入ってます(笑)」
「2008年12月7日 無題
雇い止めです。リーマンショック。どうすりゃいいの?」
「2009年1月10日 なんとか
ICQって覚えてますか? あれで知り合った人と、偶然このmixiで再会して。東京の小さな会社で働くことになりそうです」
最後の更新は、2010年9月。「1年ぶり? 東京で働いています。最近はTwitterにいることが多いです。IDはGUY_hiko××~~です。
彦星の足跡は、わたしたちの世代が歩んできた典型だった。彦星はどうなったのだろう。多少ドキドキしながら、わたしはXではなくあえてTwilogにアクセスし、数日かけて足跡をくまなく追いかけた。
東京に出てからの彦星は、平穏な暮らしをしていたようだった。おはよう、出勤、ほかてら、ほかえり、ファストフードの新商品を食べた。
そういった暮らしの間に、次第にロードバイクの話題や山登りの話題。どうも同行者は毎回、Twitterで知り合った人らしかった。さすが彦星、社交的だ。
2020年4月から5月は、コロナへの不安。2021年4月に、「実は、農業やることになりました」と報告がある。なんでも後継者不足の農業の担い手に、氷河期世代を……というプロジェクトがあり、そこにTwitterのフォロワーが関わっていて声をかけられたらしい。
2021年の数少ないツイートは、夏の炎天下の田んぼの草むしりや、黄金色の稲穂の画像、そこにときたま、「下痢が治らない」「今日も病院」といった内容。そして2023年5月の投稿を見て、指が冷たくなる。「いろいろ考えて、Mastodonへ移行します。病状の報告も、そちらで」。
リンクを踏み、否応なく目に飛び込んできた最新の投稿は――。
「兄・太田原凱彦は、2024年4月24日に逝去しました。生前のご厚誼に深く感謝いたします。当人からメッセージを預かっております。
みんな、ありがとう!わたしはノートパソコンを閉じた。くしくも7月7日。ベランダに出てろくに星も見えない夜空を見上げ、わたしは彦星と、そしてわたしたちの25年に思いを馳せた。
人生いろいろあった。
でも、節目節目でネットで知り合った人に助けられてきたよ。
お団子エルボーちゃんなんてさ、ICQからの付き合いでしょ? 信じらんないよね。
俺は幸せだったよ。みんなと山行って、自転車乗って、思い出がいっぱいあるよ。
もっとやりたいこと、たくさんあった。織姫にも出会えなかったし。
このネタ、古い付き合いじゃないとわかんないか、エルボーちゃんに聞いてね!
ありがとう、ちょっと先にあっちで待ってるよ!
#ノート小説部3日執筆 お題:七夕。彼女と青年の話。もやはシリーズだなこれ。知ってたけど
夏は年々訪れが早くなり、梅雨も駆け足で真夏日が続く。風が吹いても暑く、街中では貴重な木陰や日影にばかり人が多い。
そんな中、さらさらと涼し気な音が彼女と青年の足を止めた。音の方へ目をやると、商店街の大型店の店先に大きな笹が飾ってあって、葉が風に揺れる音だった。
「あー……七夕かあ」
そんな時期かとばかりに青年がのんびりと呟いた。こうも暑苦しくてはとうに七夕など過ぎたのかと勘違いしそうになるが、まだ七月に入ったばかりで夏本番ですらない。
笹飾りには色とりどりの短冊がくくられて風に揺れている。飾りの横には机が用意してあって、短冊と筆記用具があるところを見ると自由に短冊を書いてもいいようだった。
「お嬢、短冊書いてかない?」
「あなた願い事なんてあるの」
「なくても、年中行事じゃん。いいじゃんよ」
「……私は、いい。書いてくればいいわ」
彼女は頑なに短冊を書くことを拒んで、ふいと顔を背けてしまった。
「じゃあさ、お嬢、そこで待っててよ。どっか行かないでよ?」
「うん」
青年は拒絶する彼女に念を押して笹飾りのある店先に走った。学校の机のような小さな机上には律儀に五色の短冊が箱に入っていて何種類かの色のペンが置かれていた。
「へえ……五色の短冊なんてまた律儀なんだか……」
妙に感心したように青年は呟いて、短冊の色を選ぶのに少し迷った。
緑、赤、黄、白、黒の短冊は色のついたものがよく減っていて、一番残り数が多いのは黒い短冊だった。
「でも、どう考えたってこうじゃん?」
青年は独り言を呟いて黒い短冊を手に取ると、銀色のキャップのペンを取ってさらりと見た目に似合わない達筆な字を書くと、笹飾りにくくって彼女の元へと戻った。
「お待たせ」
「雨は結構ああいうこと、好きよね」
「まあ、好きかな。願い事が叶うとか別に信じちゃいないけど、なにもしないよりはいいかなと思ってさ」
「黒い短冊だった」
ぽつりと彼女は呟く。
「なんだ、お嬢。見てんじゃん」
「黒は命の水よ。どうして」
彼女は青年の向こうでさっき彼がくくったばかりの短冊が揺れる笹飾りを見て言う。
「水がないと木は枯れて生きていけないんだって」
ほんのりとばつが悪い気持ちで青年は答えた。さすがに短冊に何と書いたのかまで言う気はないが、そこまで白状してしまえば半分言ったも同然だった。
色とりどりの短冊がかかる笹飾りの中で、黒い短冊はひときわ目立つ。緑、赤、黄の短冊に時々白が混ざっていて、黒の短冊は青年の書いたものだけのようだった。きっと青年の短冊以外に色に願いが込められたものなどない。無作為に、好きな色を手に取ったのだろう。用意された五色にもう意味を知るものなど居ないのだろう。
木は燃えて火を生む緑。燃えた後灰になり土に還る赤。土を掘って鉱物を得る黄。鉱物の表面に凝固して水を生む白。木を養う水の黒。
「お嬢がさあ! 俺を置いてどっか行っちゃったら困るからさあ!」
冗談めかして青年が笑ってけれど、彼女はひとつも表情を変えなかった。
しかも、青年の言葉など聞いていないかのようにさっさと歩き始めて、彼は慌てて小さな背中を追った。
「ねえ、お嬢。聞いてる? いま俺、お嬢が俺を置いてったら困るって言ったんだけど?」
「本気じゃない言葉は聞いてない」
青年を見もしないで、前を向いたまま彼女は静かに答えた。そんな冗談を言っても彼女は少しも気にかけないことは知っているけれど。
「少しは本気なんだけどな」
「知らない」
なにが彼女の機嫌を損ねたのか図り切れないまま青年は肩を落として彼女の隣を歩く。
いつも隣を歩いている青年にはわかる。彼女に触れても許される時と許されない時。いまはそれが許されていないから、いつものように繋ぐ手を伸ばせない。薄い膜のような拒絶。
たかが七夕飾りなどで彼女が機嫌を損ねる理由が青年には思い当たらない。七夕飾りなどもう何百年と見てきて、時には短冊を書いたことだってあったのに。梅雨時期のような気紛れであればいいけれどと青年はそっと溜息をつく。
「お嬢がさ、居ないと生きていけないなんて本気で思ってないよ。眷属だから、本気で契約を解除されたら消えるかもしれないけど、わかんないし。ひとりだって、そのうち慣れるんじゃない? だから、俺がお嬢が居ないと生きていけないなんて思ってないけどさ」
「じゃあ、なに? 私はあなたの命の水なんかじゃない」
そんなことで機嫌を損ねていたのかと青年はもう一度溜息をつく。少女の内心は複雑だ。
「お嬢は、ひとりになったら寂しくない? 俺はひとりになっても生きていけると思うけど、お嬢が居ないと寂しくて苦しくなると思うから」
ほんの気紛れにしか笑わない彼女を少しでも見たいと願った。
商店街の人通りもまばらな昼間に、青年は歩く足を止めた。ひとりで居た時間は青年にもあった。けれど、その時間を彼女の隣にいる時間がとうに追い越してしまって、ひとりきりをどうしていたか忘れた。それを多分、孤独と言うのだ。
立ち止まって俯いてしまうと、泣きはしないのに泣きそうな気持ちになってしまう。
「たぶん、私も寂しい」
どこにも行けない手が彼女に握られて、青年は驚いて顔を上げた。笑うより珍しく、彼女は少し眉を下げて困っているらしい顔をしている。
「だって、一緒に居てくれるんでしょう」
一緒に居てとは言わない彼女を青年は不器用だと思う。頼りなく握る手なんて振り払えてしまうのに、青年はぎゅと握り返す。
「居るよ。それでさあ、俺はずっとお嬢と居るけど、もうちょっとお嬢が笑ってくれたら俺は嬉しいの」
願いなど結局は口にしないと伝わらない。行動にしなければ叶わない。願うだけではなにも起きない。一歩踏み出すきっかけにしか過ぎないと知っていた。
「だからさ、お嬢、笑ってよ」
「……いきなり笑ってって言われても困るわ」
彼女は笑うよりもずっと珍しい困り顔で青年をゆるりと抱いて頭を撫でた。青年には彼女が撫でてくれる手がとても心地いい。
「雨、降るといいなあ」
「そうね。うれし涙ね。でも雨はいいのよ。だって、あなたの願いは私が叶えるもの」
くすりと背伸びした彼女は青年の耳元で悪戯に笑う。青年は彼女に囚われたまま、つられてふにゃりと笑ってその腕に懐いた。
「優しいな、お嬢」
さっきまで機嫌が悪かったのに、青年が立ち止まってしまうと一緒に立ち止まって手を伸べてくれる。彼女はいつもそうで、青年はそれを優しさだと初めて気付いた。願いなど短冊にしたためなくても、星に願わなくてもいい。言葉にしてしまえば簡単なのだ。もっと、言葉にしても叶わないような願いが心に浮かんだら、また短冊にしたためてもいいかもしれないと青年は笑う。
#ノート小説部3日執筆 お題:七夕 『催涙雨』
「笹の葉さらさらって歌あんじゃん」
「あるなぁ」
「あの〝笹の葉さらさらノキバに揺れる〟の〝ノキバ〟ってなに?」
唐突にそんなことを問われて面食らってしまう。質問した本人は真剣そのもので、あまり茶化せない空気だ。
「俺、子どもの頃からずっと気になってたんだよな。〝ノギワ〟とか〝ノギマ〟って歌ってたんだよ」
「なんやゲームの呪文みたいやな」
よくわからないが、きっと炎とか爆発とか起きたりするのだろう。『たなばたさま』という曲名だから、もしかしたら水の魔法かもしれない。
そんなくだらないことが頭をよぎったが、この年上の男はどこまでも真面目な顔をしている。
「そうなってくると〝キンギンスナゴ〟ってなんだ。〝キンギンツナゴ〟じゃないのか」
また新たな疑問が生まれたらしい。彼のスマートフォンには、その『たなばたさま』の歌詞が表示されている。
「なんでまた、そんなこと気になったん」
この週末は確かに七夕だが、それにしたって唐突である。すると、久秀さんは眉間に皺を寄せたまま唸る。
「いや、同じ事務所の南雲くんとこの姫にさ、一緒に七夕すしようって誘われて」
南雲さんはオレも共演したことがある。久秀さんと同じぐらいの身長があり、筋肉質で、少し強面の俳優だ。そんな南雲さんの五歳になる娘さんが久秀さんのことをいたく気に入っているようで、似顔絵を送ったりデートをしたりしているらしい。
「はぁ、そんなら断れんなぁ」
「だろ? それで一緒にお歌も歌おうってなったから、プロとしてはちゃんとしたくて、こうして歌詞を調べてるってわけ」
久秀さんの生歌を間近で聴ける、そのお姫様が羨ましい。オレだって一緒になにか歌いたいが、さすがに五歳児に嫉妬は見苦しいので、適当に頷いた。
「そしたら、俺のなかにあるのと、実際とじゃ歌詞が違うからさ、ビックリしたんだよ」
それが〝ノキバ〟と〝スナゴ〟らしい。
久秀さんの見ている歌詞は、すべてひらがなだ。これでは、イメージもしにくいだろう。
「あー、うんと、まず〝ノキバ〟なんやけど」
オレがそう切り出すと、久秀さんは目を丸くしたのち、嬉しそうにニコニコし始めた。確実に後でからかわれるのだろうが、この際なので彼の好きにさせようと思う。彼の意識が自分に向いてほしいのは事実なのだから。
「〝ノキバ〟は漢字で書くと〝軒端〟になんねん。ようは、軒の端、軒先のこと。せやから、笹の葉がさらさらと軒先で揺れてるよ、って言いたいんやな」
「へぇ……。軒端」
軒端、と手帳に書き記しながら説明すると、久秀さんは言葉を繰り返す。
「そんで〝キンギンスナゴ〟やけども。〝キンギン〟はそのまま〝金と銀〟で〝スナゴ〟は〝砂子〟のこと。色紙とか屏風に吹き付ける金箔の粉のことやな。つまり、お星さまが金とか銀とか砂子みたいにキラキラしてるってこと」
「……お前、よく知ってるなぁ」
すこしばかり驚いたようで、久秀さんは感心したように頷いた。
「ちなみに〝ごしきのたんざく〟はそのまま五色の短冊のこと。もともとは中国の五行説っていう、なんかそういうのからくるんやけど、色とりどりとかそういう意味があるんやって」
「ほんとによく知ってるなぁ。逆になんで知ってるのか気になるんだけど」
「ほら、うちのパパとママがそういう日本の行事好きやから」
日本好きの両親は、オレが子どもの頃からそういった行事をずっとやってきた。そのたびに、行事の歴史を話してくれていた。七夕はもともとは中国の『七夕の節句』からくるものであること、日本にあった『棚機』という行事がそれを結びついて今の『七夕』という行事になったことを丁寧に教えてくれたのである。
それを自然と覚えていたので、他の人よりちょっとだけ詳しいのである。
「いいご両親だな」
「まぁ……節分に全力を出しすぎて、オレに一生のトラウマを植え付けたこと以外は悪いひとたちやないと思う」
あの無駄に時間と金をかかった節分は、一生忘れることができないだろう。わざわざ特殊メイクまで施して、当時六歳のオレを怖がらせようとしたのだ。両親ともに迫真の演技で迫ってくるものだから、まだまだ幼いオレが勝てるはずもなく、まんまと返り討ちにあったのだ。それから、オレは節分と化け物が苦手になってしまった。
閑話休題。久秀さんはオレの説明を自分の手帳に書いている。
他になにかトリビアはあるかと聞かれたので、七夕の当日に降る雨を『催涙雨』と言い、織姫と彦星が会えなかった悲しみの雨だったり、逆に会えてうれし泣きの雨であるとか様々な説があることや、七夕の前日に降る雨を『洗車雨』と言って、彦星が牛車を洗車するときの雨である、ということを伝えると、とうとう久秀さんは腕を組んで「すごいな」とぽつりとこぼした。
「なんつーか、ご両親もすごいけど、それを覚えてるお前もすごいよ。分かりやすく説明できる、ってことはちゃんと理解してるってことだし」
「自分じゃよくわからんけど。……褒められるのはちょっと嬉しい」
すごいすごいと久秀さんは頭を撫でてくれる。褒められるのはイヤじゃない。素直に嬉しい。が、それよりも、彼の意識が今はオレに向いていることが嬉しくてたまらない。
ワガママが通るのなら、オレだって久秀さんと七夕をすごしたいと思う。七夕まつりに行きたいし、小さい七夕飾りを買って、短冊を吊るしたいと思う。
しかしお互いスケジュールがかみ合わない。久秀さんは仕事のあと南雲さんのところに行くだろうし、オレは七夕コンサートがある。
スケジュールを併せることが難しい職業柄、それはどうしようもないことなのだろう。なので、こうして今一緒にいる時間を大切にしたいと思っている。
「七夕に一緒にいられないのは残念だけどさ、今、ラスティと同じ時間を共有できているのは嬉しいよ」
まるでオレの心を読んだかのように久秀さんは言う。ぱちっと目が合って、優しく微笑んでくれた。
「……七夕の日、雨らしいで」
「あー、そんなイジワルなこと言うのか? しょうがないやつだな」
オレのささやかな抵抗に、久秀さんは困ったように笑う。
「当日会えないけど、空の下じゃ繋がってるだろ。俺は短冊にお前のことを書くし、七夕の歌もお前のこと考えながら歌う。つまり四捨五入したら、お前と七夕を過ごしてることになるだろ」
「どういう数式やねん」
なにをどうしたらそうなるのか、甚だ疑問ではあるが、オレを慰めようとしてくれているのは伝わってきた。久秀さんはまた、よしよしと頭を撫でてくれる。
「当日一緒に過ごせない分、今日はずっと一緒にいような」
催涙雨は、会えない悲しみの雨か、こうして一緒に過ごせることを喜んでいる雨か。
外でさっきから降っている雨ははたしてどちらなのだろう。
#ノート小説部3日執筆 お題【七夕】
「あなたがそう願うなら」
「……ちょっと出かけるが、買い出しなどの用はあるか?」
「……いや、特にはないかな」
急に声をかけられ、驚きつつも室賀はそう応える。休日にわざわざ出かけるなんて珍しい事もあるな、とは思ったが、言及することなく再び視線を手元の本に戻した。
しばらくして眞壁が外出したであろうドアの開閉音がする。
少し間を置き、眞壁の出ていったドアを見つめ、なんだかんだと生活を共にしている事に考えを巡らせる。彼の中で『居候』が『同居』に変わってもいいものか、その思考も悩ましかった。
果たして眞壁がどう思っているのか。口に出してこないので彼の考えていることは全くわからない。早く出ていって欲しいと思っているのだろうか、それとも言及してこないことに甘えてこのままの状態を続けてもいいのだろうか。
(新しい生活基盤ができるまでは置いてくれ、と言った手前、新しい住居も探さないといけないんだけど……)
正直、前のボロアパートくらい安い家賃の賃貸は無い。上京前に見つかったのが奇跡みたいなものだ。
(……住居探しも何もしてないと思われてもアレだし……眞壁にそれとなく言ってみるかなぁ)
その際の反応で、なんとなく考えが読めればいい、という希望もある。
本に集中できず考えもまとまらず、いつの間にか室賀はソファでうたた寝をしてしまった。
「……おい、本が」
「!」
また急に声をかけられ、うっかり寝落ちてしまっていた室賀は驚きに身体が跳ねあがる。反射的に手を開き、辛うじて持っていた本が手から滑り降りた。それは近くに立っていた眞壁の足に突き刺さる。
「……いっ!」
「……ま、眞壁!?」
思いの外、自分の近くにいた眞壁との距離感とその彼の足の上にまぁまぁ重量のある本を落としてしまった両方に驚き、室賀は彼の名を反射的に呼んだ。
「……お前の足の上に本が落ちそうだと、注意しようとしたらまさかそれが俺の方に来るとは……」
「……わ、悪い……」
本を拾う為に屈むと、視界の端に何やらカラフルな色が入り込んできた。それは小さな竹の枝にこれまたかわいらしいサイズの七夕飾りが下がっている。ただ、そのかわいらしいものを持つのがこれほどまでに似合わない男が目の前にいる。
「……眞壁、これ……どうしたんだ?」
「……所用の帰り、商店街の馴染みの店に顔を出したら、家に飾ればいいと渡されて……、断る理由もないし、そのまま持ち帰ってきただけだ」
「へぇ…、そうか、もうすぐ七夕かぁ」
地元は1ヶ月遅れだから意識してなかったな、と室賀は言い、眞壁からその七夕飾りを受け取った。それを適当に見つけたガラス瓶に挿すとテーブルに置く。
「せっかくなら、願い事の短冊も付けるべきだろ」
「うちに短冊になるような色紙なんかないぞ」
「……まぁ、字が書ければなんでもいいさ」
室賀は剥がされた6月のカレンダーを持ってくると、器用に切り分け、即席の短冊を拵える。
「……はいよ、眞壁の」
「……」
受け取ったカレンダーの裏紙を少し見つめ、眞壁はマジックで紙いっぱいに字を書いた。まだ書いていない室賀は、その短冊を見て思わず呟く。
「……さすが、眞壁。豪快にしかもでかでかと『世界平和』を書くとは……。こうなったらおれは宇宙の平和を願うべきか」
「そこで張り合ってどうする」
律儀に紙に穴を開け、紐を通して短冊を笹に取り付けながら言うと、室賀も短冊に『世界平和』と書いていた。
「いいと思うよ、世界平和。一人で願うより、どうせなら二人で同じ事を願った方がいい気がするしな」
多分な、と笑いながら室賀も笹に短冊を取り付ける。テーブルの真ん中にできた小さな七夕飾りを2人は満足そうに眺めた。眞壁の表情は全く変わっていないので、満足しているかは定かではないが、きっとそうだろうと室賀は思う。
今の『平和』が続く事を密かに願い続けるしかない。
この均衡が崩れれば、共にいられないのだから。
#ノート小説部3日執筆 お題「七夕」
タイトル「思いを見上げて」
スーパーの前に笹竹があるのが見えた。色とりどりの短冊がすでに飾られている。
「ねえ、ねえ」
「何?」
「短冊、書いていこうよ」
あんま願うことなんて無いんだけど、付き合ってやるか。
「いいよ」
テーブルに置かれた短冊とマジックを手に取る。さて、何を書くか。
「ねえ、ねえ」
「何?」
「短冊は、色によって込める気持ちが違うって聞いたんだけど、本当だと思う?」
は? 迷信か何かだろ。
「何それ、そんなのあるの。色で何が違うんだ?」
「青は学業向上とかを願う気持ち、白は決まり事を守る気持ち、黄色は人を大切に思う気持ち、赤はご先祖様や親に感謝する気持ち、緑は徳を積む気持ち」
「はあ、よくわからんな」
緑の徳を積む気持ちってなんだよ。
「どうでもいい。俺は緑が好きだから緑チョイスするわ」
「へへ、らしいね。私は黄色にしよ」
黄色は人を大切に思う気持ち。お前こそ、らしいわ。
* * *
放課後、神社でたむろしているときだった。賽銭箱の隣に机が置かれ、短冊を書くスペースが出来ているのが見えた。
「なあ、あれ書いていかね?」
「うおー、いいね」
短冊を取ろうとして気がついた。
「ピンクしか余ってなくて笑う」
「男子高校生が使っていい色とは思えん」
「俺ピンク好きだからラッキー」
「お前が好きなのはアイドルのりりかちゃんで、イメージカラーがピンクなだけだろ」
「バレたか」
リュックにりりかちゃんの缶バッジ、誰だってわかるわ。
「はー願い事決まったか?」
「俺まだ」
「お小遣いアップ」
「みんなの願いが叶いますように、はぁと♡」
「きっしょ」
「彼女欲しいー。夏祭りデートしてぇー」
「そりゃ叶いそうにねえな」
「俺らずっと彼女いない同盟の仲間だろー?」
「学校爆発しますように」
「草」
みんなふざけつつも短冊に願い事を書いている。俺は何書こうかな。提案しといてなんだが、案外思いつかないもんだな。
「決めたわ。お前らとズッ友でいれますように、ほぉし☆」
「くっさ」
* * *
職場で七夕を飾ることになった。エントランスに置くそうだ。
「SDGsと絡めて願い事を書いて欲しい、ですか」
「ああ。金曜日の午前中までに提出しなさい」
「わかりました」
SDGsの活動に否定はしないし、会社としてもSDGsに絡めて理念を掲げている。アピールしたいのはわかるけど……。すぐに思いつかない。
お昼、同期の友達と相談しながら書くことにした。
「お、温暖化が、地球温暖化がこれ以上進みませんように、とか?」
「んー……。安直だけどそういうのしか思いつかないよね」
「難しすぎる」
「っていうか、SDGsってさ、昔から言われてたことを改めてかっこよく言い直しただけじゃない?」
「それ以上は言ってはいけない」
少し沈黙が流れる。
「私は、そうだな、みんなが平和に暮らせる世の中になりますように、にしよ」
「こんな壮大なこと叶えてくれるかな」
「わかんない。少なくとも私たちは会社の命令で書いているだけ」
「願いってさ、要するに他力本願だよね」
「それな。SDGsと絡めて書くことじゃないわ」
はー。二人同時にため息をついた。
* * *
「あれが、デネブ、アルタイル、ベガ」
どっかで聞いたことがあるような歌詞を口ずさむ。
「夏の大三角形か」
新聞を読んでいた父さんが反応する。
「父さん、星に詳しいの?」
「少しな。お前のじいさんが望遠鏡をもっててな。倉庫においてあるんじゃないか?」
「ほんと?」
「ああ。手入れしてないから使えるか知らんが」
「ちょっと見てくるわー」
倉庫へ向かう。
「ふふふん、ふふふふん、夏の大三角、覚えて空を見る」
曲だけで覚えて空を見る。檻姫様と彦星様、見てみるか。
「おお、これか」
「ホコリだらけだな、使えそうか?」
「箱に入ってたから、ぱっと見は綺麗だよ?」
「今度の日曜日、車で高台に連れてってやろう」
「わーい、やったー!」
フッフー! 心の中で曲の続きを歌う。楽しげなひとつ隣の君~。ちょっと待った。この曲失恋ソングか。
「縁起でもないなー。デネブ、アルタイル、ベガ、どれが織姫でどれが彦星か知らないけど、絶対見つけてやろう」
* * *
「くそあち」
33℃か。温度計見るんじゃなかった。余計熱く感じる。
「そうめん頂いたからお昼はそうめんにしようか」
母ちゃんがキッチンから声をかけてくる。
「……何でそうめんなん」
「何でって?」
「何でわざわざそうめんなんて贈るんだよ」
「七夕の行事食だからでしょ」
「行事食ぅ? 何それ」
「一月はおせちにお雑煮、二月は福豆、三月はちらし寿司、五月はかしわ餅、七月はそうめん、土用のうしの日はうなぎね、八月はお盆で、これもそうめんだったかしら、九月は十五夜でおだんご、十二月は年越しそば」
母ちゃんの長いうんちくを聞く。そういえば季節ごとに食べるものあったな。
「七夕にそうめんのイメージないわ。夏だから食うって感じ」
「それもそうねー」
そうめんか。ネットで色々と調べる。
「七月七日ってそうめんの日らしいぞ」
「まあ、そうなの。面白いわね。そういえば七夕の日、お昼にご町内会で流しそうめんやるのよ。行ってみる?」
「いいね、友達連れてくるわ」
「ふふ、楽しみねー」
後に知ることになる。炎天下でそうめんを食う苦しみを。
* * *
七夕。東を向いて見上げる。一番明るいのが、こと座のベガ。ベガの右下にあるのが、わし座のアルタイル。ベガの左下にあるのが、はくちょう座のデネブ。
ベガが織姫、アルタイルが彦星。この星の間に天の川が通る。
笹の葉に色とりどりの短冊が括り付けられ、稲穂のように垂れ下がる。夜風に当たり、さらさらと音を鳴らす。
みんな、七夕は何をして過ごすだろうか。夏の大三角形、星は見えるだろうか。短冊に込めた願いはどうなるだろうか。織姫と彦星は会えるだろうか。
思いを見上げて目を細める。
みんな、七夕に何を思うのだろうか。
思いを見上げて目を閉じた。
#ノート小説部3日執筆 『七夕労働争議』
「七夕」とは、毎年7月7日に行われる中国神話にちなんだお祭りである。日本では短冊に願いを書いて笹に付けるのが一般的であるが、その願いは果たして織姫と彦星と呼ばれている牛飼いと機織りの娘に届いているのだろうか。そして彼らはその願いを見て何を思うのだろうか。これはそんな七夕のお話。
●
今年も七夕がやって来た。年に一度しか会えない牛飼いと機織りの娘はこの日を待ちわびていたが、最近はとある事情に悩まされていた。
「お待たせ、全部集めてきたよ」
そう言いながら機織り娘の元にやって来たのは牛飼いである。彼はとても大きな袋を持っており、到着するとそれを機織りの娘の前に置く。
「お疲れ様。今年も大量ね」
そう言って機織りの娘が袋を開けると、中から大量の短冊が零れ出てきた。この日に掲げられた願い事の短冊だった。人々が思い思いに書いた願い事が短冊が何千枚と袋には入っていた。
「みんな好き勝手書いてくれるねぇ…」
牛飼いは呆れるように言いながら座り込むと、短冊をひとつずつ確認していく。そして実現できる内容と、そうでない内容の短冊を分けていった。機織りの娘も同じように短冊を分け始める。2人の元に集まった願い事なので、2人が処理しなくてはならなかった。そしてこれが最近の2人の悩みでもあった。この仕事の所為で2人の時間が著しく減っていたからだ。
「あー面倒になってくる…どうして今日しかこの仕事できないのかな」
牛飼いは短冊を分けながら愚痴を零す。機織りの娘も口には出さなかったが同じ気持ちだった。
「そもそも叶えられる願いだけを書いてくれればこんな事しなくていいのに…なんだ世界の支配者になりたいって?」
牛飼いは叶えられない願いを見て呆れた顔をしながらそれを振り分ける。
「ねぇ、私たちだけが働くのはなんだか不公平な気がしない?」
機織りの娘が不意にそんな事を言うと、牛飼いの手が止まった。
「そうだね。こうなったら天帝様に直訴しよう! 今から労働組合を作って改善を要求する!!」
牛飼いは唐突に労働組合の設立を宣言すると仕事を放り出して機織りの娘を伴って天帝の元へと向かうのだった。
●
「それで、お前たちは労働組合を作ったと…」
天帝は呆れながら眉間にしわを寄せる。突然2人がやって来たかと思ったら労働の改善を要求されたので、流石の天帝にも理解が追い付かなかった。
「そうです! 今日は私たちが年に一度だけ会える大切な日。それが労働によって台無しになっているのは不当だと考えます!」
「私も同感です。去年は仕事だけで1日が終わってしまい、自分たちの時間を過ごせなかったんです!」
牛飼いと機織りの娘が窮状を訴える。天帝も言われてみれば最近2人が落ち込んでいる姿を見る事が増えたと感じていたので、現状の改善が必要ではないかと考え始めた。
「お前たちの言い分も一理ある…では次回に向けて改善策を練るとしようか」
「それでは遅いです! 今からでもできる改善をお願いします!!」
天帝は来年からの改善を提案するが、牛飼いは今日からの改善を要求する。
「いきなり言われてすぐできる訳が…いや、できるな」
天帝は無茶振りだと言おうとしたが、できる事を思いついたのか言葉を変える。
「要はお前たちの労働負担が減ればいいのだろう? その短冊を今すぐ持って来るがいい」
天帝の言葉に2人は大喜びだった。そしてすぐに短冊を取りに戻り、急いでまた天帝の元に戻ってきた。
「ふむ、確かに願い事が多いな」
初めて見る短冊の量に天帝も2人の言い分が分かってきた。
「それで、これらの願い事はどうすれば良いでしょうか?」
牛飼いが尋ねると、天帝は短冊の入った袋を持ち上げた。
「今から我の力で全ての願いを叶えよう!」
そう言って天帝は力を溜める。それを見て牛飼いは慌ててそれを止めようとした。
「お待ちください! それをするととんでもない願いまで叶えてしまい地上に混乱が起こります!!」
牛飼いは先ほど見た叶えられない願いの事を思い出して天帝を止める。
「む、そうか…。ならばこれでどうだ?」
天帝は袋を置くと今度は床に火を起こし始めた。
「初めから願いは無かった事にしてしまおう。それならば余計な混乱も起こるまい」
天帝はそう言って袋を投げ込もうとするが、今度はそれを機織りの娘が止めた。
「やめてください! 純粋な子供たちの願いすら無かったことにするのですか?」
「む、それも可哀そうだな…」
そう言われて天帝は袋を床に置く。機織りの娘はそれを見て安堵した。
「そうなるともう策が無いぞ。どうする?」
天帝に言われて2人は考え込む。
「そもそもどうしてこの日に願いを書くようになったんだろうか?」
牛飼いの疑問に天帝は何かを閃いたのか、突然地上を見下ろし始めた。
「天帝様?」
機織りの娘が尋ねるが、天帝は黙って地上を見下ろしていた。
「どうやら根本的な解決が必要かもしれんな」
天帝はそう言って地上に向けて手をかざす。
すると突然天候が悪化して大嵐が発生したかと思うと、たちまち地上を飲み込んでいった。
「最近の人間は我ら神を信じぬ。そんな不信信者どもの願いなど聞く必要はない。むしろ罰するべきであろう」
天帝の言葉で大嵐はさらに勢いを増し、人間が作り出した都市を悉く飲み込んでいった。
突然の事で2人は茫然と天帝が地上を破壊する様を見ている事しかできなかった。
やがて大嵐は世界中を飲み込み、地上のすべてを破壊しつくした。そして嵐が収まると、地上には人間の痕跡は殆ど無くなっていた。
「よし、これでおまえたちの仕事が減っただろう。我も最近の人間の所業には呆れていたからな。これでお互いゆっくりできよう」
天帝は満足したのかスッキリした顔でその場を後にする。残された2人は天帝の力に恐れを成したのかしばらく立ち尽くしていた。
こうして牛飼いと機織りの娘が起こした労働争議で人類は再び石器時代へと戻る事になるのだった。
了
『年一くらいがちょうどいい』またスピンオフでゴメンネ! #僕らの壊せない三角 #ノート小説部3日執筆 お題:七夕
───七夕、か。
織姫と彦星が高い空の上で年に一度だけ出逢える日。この日に、願い事を短冊に書いて竹笹に飾ると叶うらしい。私はハーフだけど生まれも育ちも日本だから馴染み深い祝祭だ。
そういえば、どうして願い事が叶うのか、どうして笹に飾るのかはよく知らないな。出逢えたら彼等の気分が良くなってついでに叶えてやろうとなるんだろうか。雨で天の川が出なかったら叶わないんだろうか。そもそも彼等って神様なんだっけ。
……でも、さぁ。
年に一度でも会える日があるなら、良いじゃねえか。
私は……私の好きな人とは、もう、会えないかもしれない。
「……インカー、インカー。ねえ、書かないの?」
鋭い視線が責めるようにこちらを見ていて、ハッと我に返った。クリス、いや、リノが苛立たしげにペンで机を叩いている。
(スッスは、そんな顔したことない)
心臓に氷を流し込まれたみたいにキュッと痛い。
目の前の男は、自分の好きな人の体を持っているのに、明らかに違う人間だった。
一年前、私の好きな人だったクリスは、リノに巻き込まれて二人とも意識不明に陥る事故……事件?を起こした。そこからクリスだけが意識を取り戻した……と思ったら、中身はリノになっていた。
入れ替わったんだと本人は言ってる。
私は正直、半信半疑だ。
少なくとも本来のリノは、私に友人以上の興味は一切無かったと思う。あいつの世界はクリスだけだった。なのに、入れ替わったと主張するクリスの中のリノは、私に手を出してきた。『クリスの彼女』なんだから当然だろうというような態度で、私を手に入れた。
もしかしたら、リノが意識不明のままだと知ったクリスが、最愛の人の喪失に耐えきれず、リノを演じているのかもしれないと思う。リノの意識さえ戻れば、いつものスッスに戻るのかもしれない。
植物状態の人間の意識が戻るのなんて奇跡だと言うけれど。
それこそ神頼みでもしないと……。
『スッスが元気になりますように』
短冊にはそう書いた。神様はどう捉えるだろう。クリスは元気じゃないか、と思われて終わりかもしれない。
……正直、私は、クリスがこれからリノとして生きていくのだとしても仕方ないと諦めているし、それならそれで付き合っていこうとも思っている。事故のショックで記憶を失って、人が変わってしまった恋人を、見捨てるのも違う気がするからだ。
だけど、このクリスは、スッスじゃない。
クリスッス! とにこやかに元気よく自己紹介してきた人懐こい奴じゃない。
「……ふうん、ま、お前はそう書くよね」
リノは私の手元を見て薄ら笑いを浮かべていた。
「リノはなんて書いたんだ?」
「僕のクリスの目が覚めますように」
「僕のって……」
「僕の体の中にいるんだから、僕のだろ。別に所有権を主張してる訳じゃない。僕はあいつのものだけど、あいつはお前のだし」
「その理屈で言うとお前も私のってことになるけど……」
「心まで全て支配したと思うなんて傲慢だな、インカーは」
「いや、そもそも私のモンだなんて思ってねーよ」
「……。ま、いーや。クリスが起きてきたら決着つくことだし。どうせどっちも俺の!とか言うんだろうけど」
「あー、スッスなら言いそうだなァ」
「だから、さぁ」
リノが私の腕をぐいと引っ張り、祭りの喧騒へと誘う。私は慌てて借りていたペンをペン立てに戻して駆け寄った。大きな手が私の肩を抱いて、その心地よさにスッスを思い出して、自然と顔が歪む。
思い出してって、何だよ、私……私の好きな人は……大切な、人は。
「……さっさとあいつ、起こそうね。僕も医者になるの頑張るし、神頼みでも何でもするから」
「……そうだな」
リノは、私とクリスの目の前で自殺しようとした奴だ。医者になって『リノ』の治療が成功したとして、クリスに体を返したらきっとまた何のためらいもなく死のうとするんだろう。
嫌、だ。
リノを喪ったクリスを見るのも嫌だし、私自身も……お前が死ぬのは、もう、耐えられない。
一年間ずっと、お前を見てきた。スッスの頃のような甘さが抜け落ちたお前は、強烈な存在感で皆を魅了すると同時に寄せ付けない。
恋人の私だけはお前を受け入れたいと思うけれど、怖い、と思ってしまうことも多々ある。でもそれを口にしたが最後、お前は二度と戻ってこない気がする。お前はリノの体と心中することだって少しは考えているんだろう。それの方が、もっと怖かった。
リノ。
お前が、好きだ。
手負いの獣のように人を睨み、
それでも私を振り切れないお前が好きだ。
お前を幸せにしてやりたい。
お前の幸せに私は要らない。
お前の幸せを願ってるから。
「なぁ! スッスが起きたら、お前らまた一緒に暮らすだろ。年一くらいで遊びに行ってもいいか?」
「は? 何言ってんの? 僕要らねえだろ!」
七夕の祭りは賑やかで、私達の声も張り上げないと聞こえない。私達は笑って楽しんでいるけど、口調はまるで喧嘩してるみたいだなと思う。こんなにお互いがお互いのことを想っているのに。
「要るし。私はお前も好きなんだよ。七夕の日くらい素直に好きって言わせろ」
「馬鹿?」
「そうだよ、馬鹿だよ、言われなくても分(わ)ーってる」
「救いようがねぇな……」
頭に優しいキスが降ってくる。これがスッスのしたことなら、どれほど私の心は救われただろう。
見たいとゴネた誰かさんのために借りて着付けてもらった紫の浴衣。その袖をギュッと握って、私は何とか笑顔を維持した。
年に一日くらいが、ちょうどいいのかもしれないな。
誰かを素直に純粋に好きでいられる時間は、きっとそう長くはない。
一緒に居れば居るほど、情とか欲とかで訳分かんなくなる。
私達は、弱いから。
おかしくなる前に、引き離して。
神様。
どうか短冊に書いたことだけ、叶えてください。
私の本当の願いは、叶わなくて良い。
リノとスッスが幸せであれば、私はきっと満ち足りるのです。
#ノート小説部3日執筆 素麵とフライドチキンが食べたいのじゃね。/お題:七夕
七夕の日。
随分遅い時間なのに、淡い夕焼けが残る空模様は、徐々に深い青に染まりつつある。
そんな中、家に帰ると、鶏肉の香ばしい香りが漂っていた。
「どうしたの?」
「あ、お帰り――ケンタッキー、買ってきたよ!」
台所から、はきはきとした声と共に、レンジの完了音が響く。
そんなことより、湧き上がった疑問に答えてほしい。
「それは分かるんだけど、朝、素麺を茹でるっていってなかった?」
「まぁまぁ、いいでしょ~、もうすぐご飯できるから、着替えて待っててね!」
にっこりと微笑みながらそう言われ――
エプロン姿の彼に丸め込まれるままに、手を洗い、着替えて食卓に向かう。
テーブルの上には、素麺と、フライドチキン。
白い陶器の大皿に盛られた素麺が涼し気に並び
熱々のフライドチキンから香気が立ち昇る。
ちょっと、アンバランス。
でもいいか、栄養バランスはよさそう。
「「いただきます」」
刻み葱と生姜が盛られた小さなつゆ鉢に、素麺を浸して一口。
今年初めての素麺は、まるで織物のように繊細な食感。
小麦粉を引き延ばしただけなのに――
そのするするとした、食感の美味しさを今年もまた思い出す。
唇に振れた瞬間から、冷たさが伝わる心地よさ。
少し甘いカツオだしのつゆと絡まるだけで、小麦の風味が際立つ。
もくもぐと、奥歯で咀嚼すれば
最初はしっかりとした弾力が感じられるが、すぐに柔らかく崩れて口の中で分かたれていく。
今度は薬味を良く絡めて、もう一口。
葱のしゃきしゃきとした歯ごたえに、たれの旨み。
生姜の辛みがアクセントになって、ひんやりとした涼しさが、いくらでも胃に入る。
そう、これは素麵なのだから、噛む必要なんてない。
喉に流し込むように、するすると飲み込むように食べるのが嬉しい。
これだけで胃をいっぱいにしてもいいくらい――
夏に疲れた体に、元気をくれるもの。
「それはそれとして――」
そういって、目を向けた先にあったのは計6ピースのフライドチキン。
あと、ちょっと太目のポテトフライと、クリスピーチキンが一人一個もあるなんて。
「あ、君が好きなの取っていいよ」
「ちょっと、買いすぎじゃない?」
「それは、創業記念パック、今日までだったから――大丈夫、残った分は全部食べるから!」
まぁいいけど――
ため息をつき、レンジでチンされて、熱を持ったのフライドチキンに向き合う。
何をとってもいいっていうなら、ナプキン越しにドラムスティックを手に取る。
揚げたてに戻った衣は、黄金色に輝いていて――我慢できずに一口、感じる。
口の中に広がるのは、ジューシーな酉肉の柔らかさ。
そして、ケンタッキーのスパイシーに味付けに負けないもも肉の味と食感が広がる。
ブラックペッパー、生姜、オールスパイス、ニンニクーータイムにセージ、ささやかななチリパウダー。
噛めば噛むほど肉汁が広がり、衣と肉から重層的な旨味が染み出る。
ケンタッキーの美味しさは、言葉にはできない。
それでも、ただ美味しいだけじゃない――
たくさんのスパイスが、深い味わいを産み出すのが嬉しい。
だから、飽きずに骨まで夢中で齧りつく。
骨にこびりついた、軟骨や肉のカケラまで、胃に収めて――
少し乱暴な食べ方だけど、綺麗に骨を掃除することすら楽しい。
ちょっとナプキンで手と口を拭いて、もう一度、素麺を啜る。
肉の油が、さっぱりとした出汁で洗い流されていくような味のコントラスト。
咥内にのこったスパイスも、全て素麵の滑らかさが胃に連れ言ってくれる。
だが、主食なのに、箸休めとはこれいかに――
よくわからないから、ウイングを手に取り一口かじる。
すると口の中にあふれるのは、肉の繊維がちぎれる食感。
そして、油の少ないながら、しっとりとした鶏肉の味。
どの部位の肉だって、スパイスの美味しさは変わらない。
寧ろ、味がさっぱりしている胸肉だからこそ、たくさんのスパイスの味わいがよくわかる。
からっと揚げられて、衣をまとっているのに――
何故かはっきりと何処が手羽か、わかってしまうから、面白い。
軟骨を綺麗に外し、骨に着いた肉を、むしゃむしゃと齧っていく。
ウイングは食べ方を知っていれば、とってもきれいに食べられるから嬉しい。
それにしても――どうして、骨に着いた肉は
こんなにも美味しいのか――
余すところなく食べきると――
ちょうど彼も二個面のフライドチキンに手が伸びるところだった。
「そうだ、サイとか、もらってもいい……」
「好きなの取ったし、好きなの取りな」
「よかったぁ。これ大好きなんだよね!」
そんな会話を挟みながら、彼はおいしそうに厚みのある肉を齧る。
特有のクリスピーな食感と、重厚な味わい。
サイの肉はジューシーで柔らかく、しっかりとした鶏肉の風味と共に、肉汁と衣の香ばしさが絶妙に交じり合うもの。
それを横目に、柔らかなクリスピーチキンを齧りつつ、再び素麵を啜り上げる。
するすると胃に収まるのが嬉しい素麺だけど、一夏のお供には少しシンプル過ぎる。
ちょっと贅沢な気分だけど――
今年の夏も、いいスタートを切れそう。
「きっと、今日の主役も許してくれるよ」
察して、笑顔になった彼を足で小突く。
これから夏が始まるそんな気分。
そうだ、織姫様、彦星様。
一年に一度しか会えないんだから、今日はフレンチでも食べにいったら?
Misskeyノート小説部のアカウントをFedibirdをお借りして運営することになりました。#ノート小説部3日執筆 などのハッシュタグ企画や、そこで投稿された作品のリポスト(リトゥート?)をこちらで行い、Fediverseにおけるノート小説の振興を図っていきたい所存です。
主宰:小林素顔 https://misskey.io/@sugakobaxxoo



 @葉桜神社同盟
@葉桜神社同盟

 がくじゅつてきあかげ
がくじゅつてきあかげ