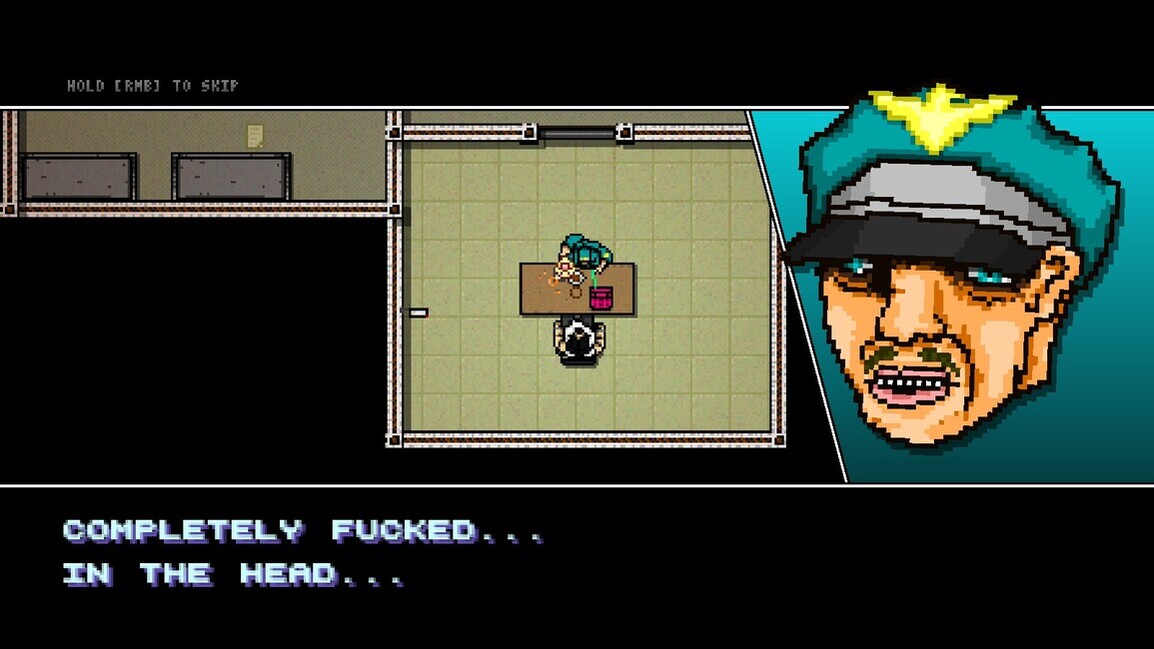
1ヶ月ほど前に気が狂って予約した赤ワイン(我らが栄えあるヤマガタランド産)が届いたんだが、よく考えると私の拠点にはコルク抜きなどといった高尚な代物はない
前から折に触れて実感してきたことですし、今日改めて認識したんですが
鉄火場になるとアドレナリン駆動でイキイキしだすタイプのヒト、事務屋に向いてないです(自白)(自己紹介)(不特定多数に向ける意図はない)
ノー アイムシングルコア マルチタスクヤメテ オー脳
静寂という名の嗜好品
冬が来るのがすこし遅い、国南の土地も今朝からぐっと冷えこんだ。
ベッドから抜け出すのが苦痛なのは確かだが、身支度を整えて外に出てしまえば気分がいい。すっきりとした空気が心地よく、部屋の鍵と読みさしの本、朝食の代金だけをコートのポケットにつっこんで街路をゆく。
観光街からも貿易港からもはずれた、運河沿いのカフェのテラス席に腰を落ち着けた。惜しみなくバターがつかわれたつややかなクロワッサンと、ボウルいっぱいのカフェオレはいつ目の前にしても口角があがる。
ときおり、出勤するのであろう地元住人が銀杏の落ち葉を踏みしめて駅の方角に歩いていく。焼きたてのクロワッサンを噛みしめる音と似て心地いい。
店内のラジオも漏れ聞こえず、ぜいたくな静けさがここにはあった。ペーパーバックを開き、読書に集中しはじめる。
何ページが読みすすめたところで、隣のテーブルに客がついた。
礼儀正しいフランス語で熱いコーヒーとクロワッサンを注文したので、地元の人間だと思った。この地域には、公用語のつぎにフランス語を喋れる人間が多い。
「僕のフランス語、通じるんだなあ」
彼はごく小さい声でつぶやいた。日本語だった。
反射的に紙面から顔を上げてしまった。
黒縁の眼鏡をかけた、壮年の日本人男性とばっちり目が合う。彼も私を見て、ルーツが同じであることを見てとったのか、相好をくずした。
「Bonjour Monsieur,C'est Beau Matin」
あなたいま日本語喋りましたよね、と思いながら「ボンジュー」と腑抜けた発音で返答する。
そうして、ずいぶんと日本的な会釈を交わした。
それから互いに黙ってすごした。とくに気づまりではなかったが、彼が有名なトランペットプレイヤーであることを察してから、目から文章を滑った。観光街のほうで公演でもあったのだろう。
ペーパーバックを閉じ、ぬるくなったカフェオレを舐めながら、ぼんやりと朝の風景を喫する。
いつだったか、彼を追うドキュメンタリ番組に見入ってしまったことがある。深夜帯の放送で、過剰な演出やナレーションがなく、聴こえる音楽は彼と彼のバンドが鳴らすジャズだけだった。
「僕なんか撮って面白いですかねえ」とほがらかに笑い、年齢に似つかわしくないじゃれ方で年下のプレイヤーとふざけたおす様と対照的に、トランペットを構える彼の立ち姿は凛々しかった。機知に富んだ男だった。それが音に現れていた。
彼のライブに足を運んだり、レコードを買ったりしたわけではないが、それ以来なんとなく好ましく思っている。ということを伝えたい気もするが、機を逃して何も言わずに枯葉の黄色を眺めている。
「静寂は嗜好品ですね」
やはり独り言のように彼は言った。眼鏡をはずしてテーブルに置き、いまだに湯気がたつコーヒーに口をつけている。
「あなたのような職業の方が仰るなら、そうなのでしょう」
おや、というかんじで彼は眉を持ちあげてみせた。西洋的な所作だ。
「ここはいいところだ」
味わったすえに発された響きを帯びていた。
彼はきわめて丁寧にカップをおろし、眼鏡をかけなおして立ち上がった。支払いを済ませて戻ってくると「すてきな海辺を知りませんか」と問われる。
「それなら……」
道筋を説明しながら、彼が提げたブラウンのケースをそれとなく見やった。金管楽器は冷えているとよい音が出ないのではないだろうか。
「ありがとう」
そう言って差し出された右手を握り返して思った。
彼がトランペットを吹くために海辺を探しているというのは、ぶしつけな想像だと。
近接航空支援を要請したい。今現在この端末が発しているGPS座標あてに
眠る前にこれだけは(Xリンク)
殺人アルパカをシェアします(なんてことを……)(すいませんねえ)
- GTC (GabaTalkCounts) (Since 2024/10/08~)
- 16
Press G for GabaGaba Talking
Press R to Remain Silent
Fav魔
この記述はフィクションです



